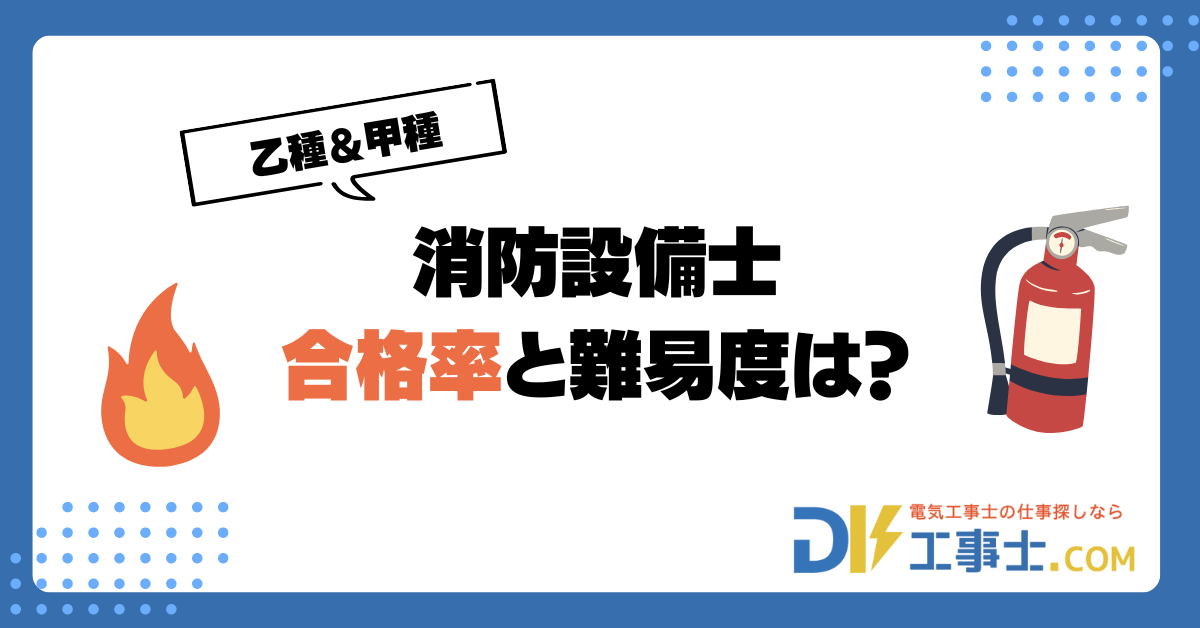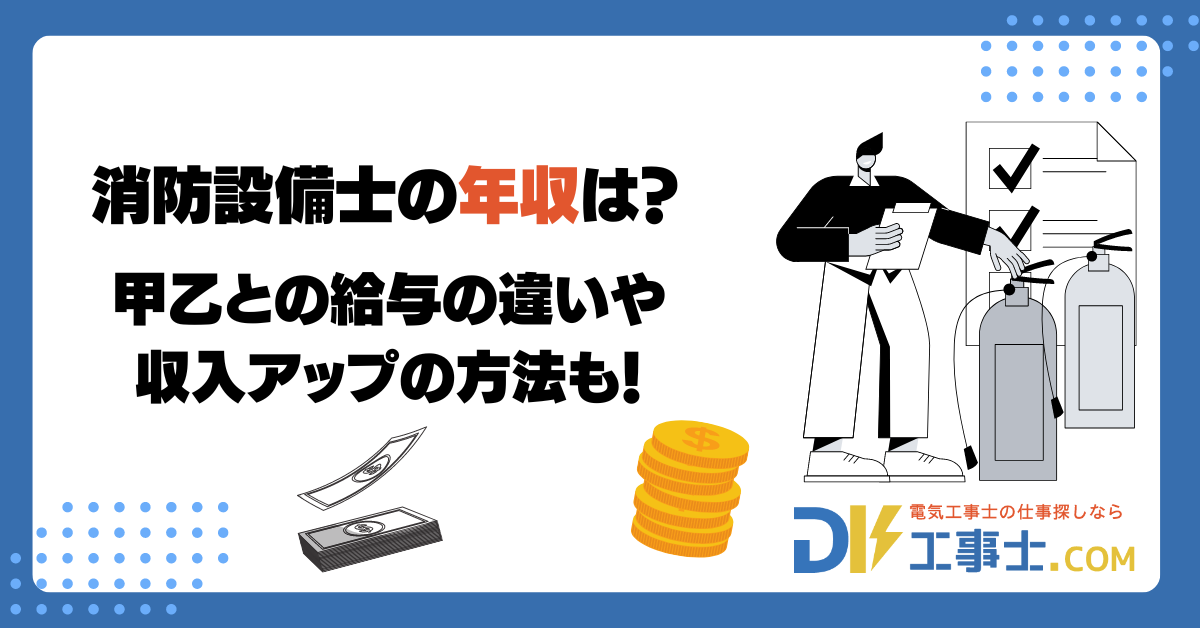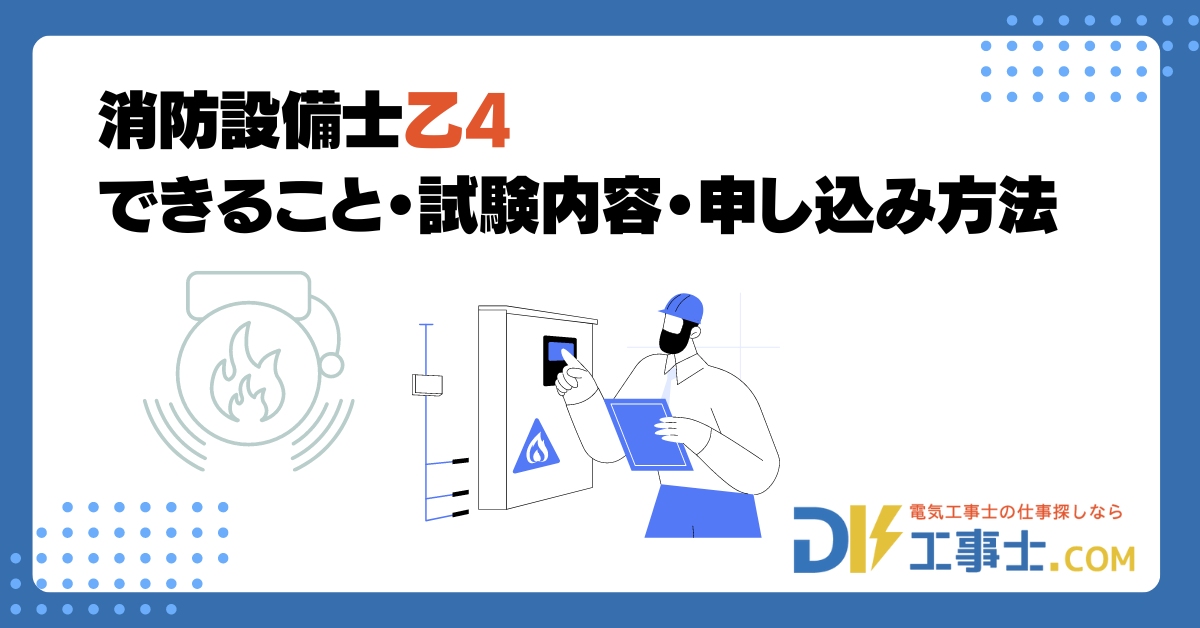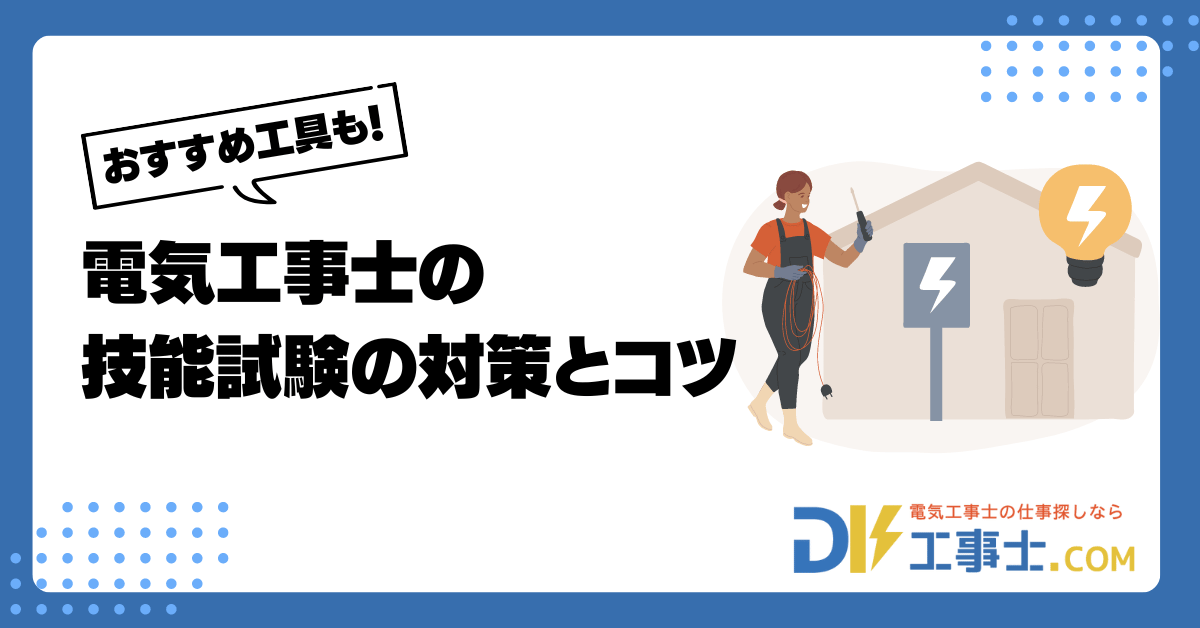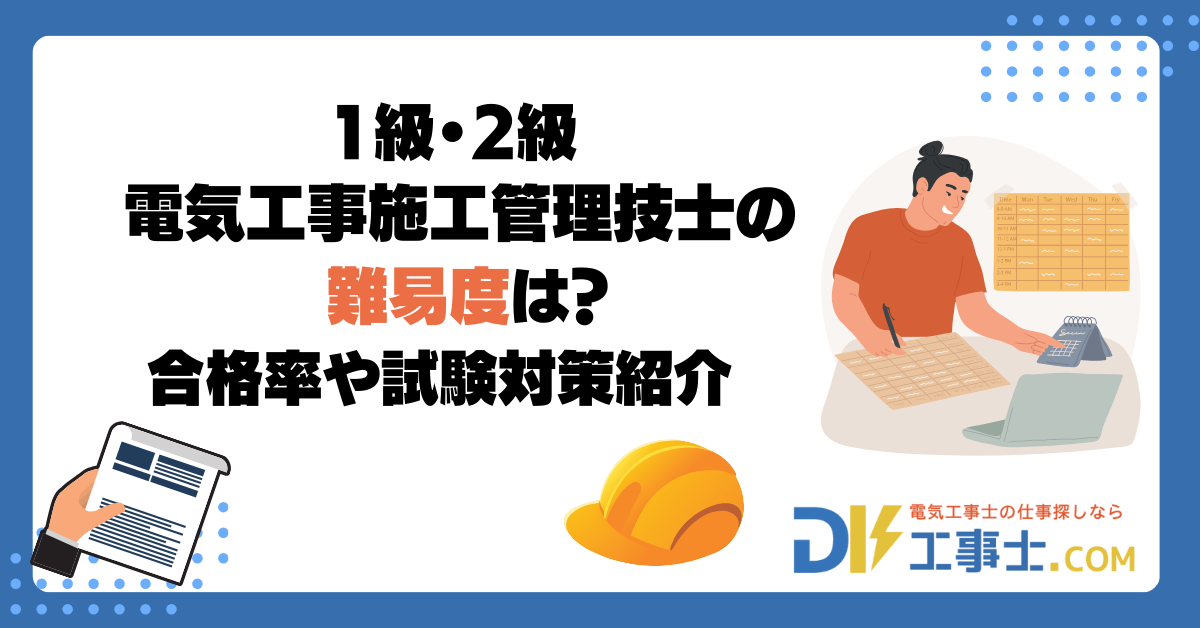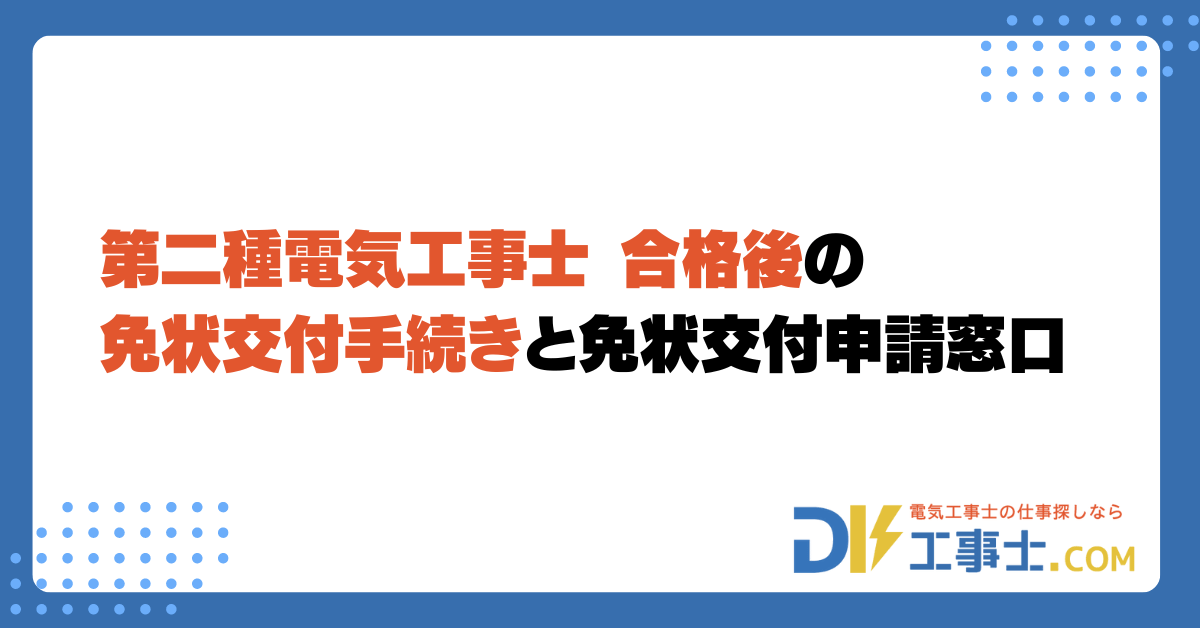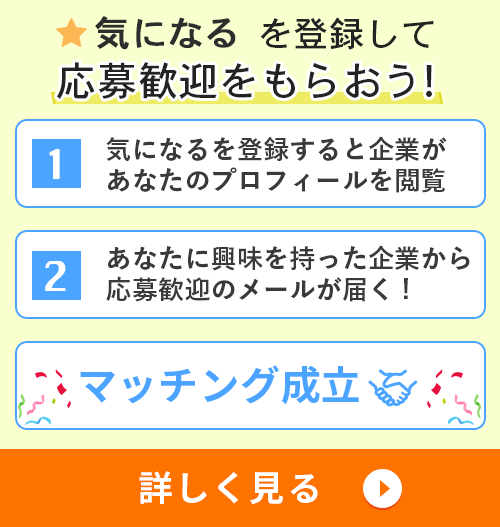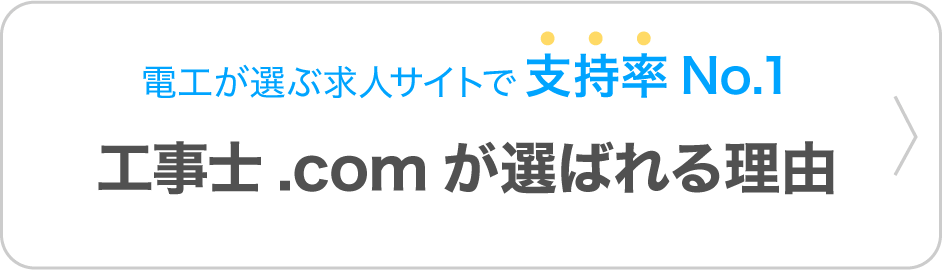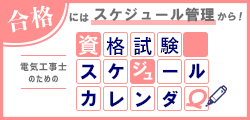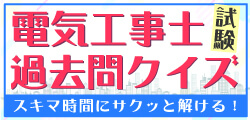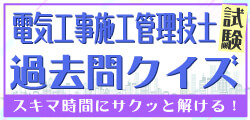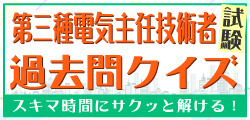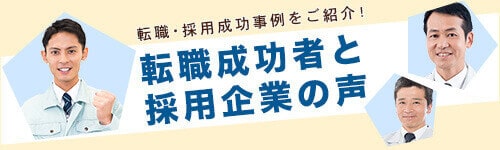消防設備士乙6とは?仕事内容や合格のコツ・申込み方法など幅広く解説
消防設備士
最終更新日:
消防設備士の乙種6類は、『消火器』に特化した資格です。
今回は、消防設備士の乙種6類ができることや、資格試験の情報、試験対策から求人情報まで幅広く紹介します。
消火器は消防設備の中でも圧倒的な設置数を誇るので、 乙種6類の資格を持った方の活躍の場は非常に多いと言えるでしょう。
今後、消防設備関係の仕事をしたいと思っている方には特にオススメしたい資格なので、是非参考にしてみてください。
※下記からは乙種6類を『乙6』と省略させて頂きます。
消防設備士乙6とは?
消防設備士の資格は、消防法によって定められている国家資格です。その中でも乙6は、 『消火器』を扱うことができる資格に当たります。
資格を取得した後は、消防設備会社やその下請け会社、ビルメンテナンスの会社などで活かすことができ、活躍の場は広いです。
消火器などの消防設備に関わる仕事は、建物がある限りなくならないため、安定性があります。
とはいえ、消火器だけを専門に扱っている会社は少なく、基本的に複数の消防設備を扱っている会社が多いです。
そのため、消防設備の業界で頑張っていこうと考えているならば、乙6だけでなく、他の消防設備の資格もあると更に活躍の場が広がります。
消防設備士には「甲種」と「乙種」があり、甲種は1類〜5類、乙種は1類〜7類まであり、工事及び点検・整備の対象設備によって資格の区分が変わります。
■甲種
工事と整備(点検も含む)を行うことができる
■乙種
整備のみを行うことができる
| 分類 | 甲種 | 乙種 | 工事及び整備(点検を含む)の対象設備 |
|---|---|---|---|
| 1類 | ● | ● | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備等 |
| 2類 | ● | ● | 泡消火設備等 |
| 3類 | ● | ● | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備等 |
| 4類 | ● | ● | 自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備 |
| 5類 | ● | ● | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
| 6類 | ● | 消火器 | |
| 7類 | ● | 漏電火災報知器 |
どの消防設備士の資格を取るかを決める際、参考にしてください。
消防設備士乙6の資格試験まとめ
消防設備士乙6を受ける方のために、試験情報をまとめました。
受験資格
乙6の試験には受験資格などの制限はなく、学歴・職歴・年齢を問わず、 どなたでも受験可能です。
消防設備士の資格には甲種と乙種がありますが、乙種の場合は1類から7類までのすべての資格において、 受験する際に必要な条件や制限はありません。
■甲種
受験資格あり(国家資格・学歴または経験などが必要)
■乙種
受験資格なし(学歴・職歴・年齢・性別問わず、どなたでも受験可能)
乙6の資格試験には受験資格が無いことから、学生や大人まで幅広い層が受験しています。
消防設備士の仕事は設備の点検や整備などが多く、重いものを運んだり屋外で作業したりすることは少ないと言われています。比較的、力仕事も少ないため、最近では女性の消防設備士も増加傾向にあるようです。
出題形式
消防設備士の試験では、筆記試験と実技試験の両方を受験します。
筆記試験の問題はマークシート方式で、 4つの選択肢の中から問題に合った解答を選びます。
『基礎的知識』『消防関係法令』『構造・機能・及び工事・整備の方法』 の3科目で構成されており、全部で30問の問題が出題されます。
実技試験の問題は、鑑別試験(かんべつしけん)といって、消火器の写真やイラストなどを見ながら、記述式で解答する問題などが出題されます。
消火器の操作方法や作業手順など、より実際の業務に近い問題が出題されるので、実技試験と呼ばれています。
試験中は実物の消火器を触ったり、点検したりするような作業はありませんので、 特別に身構えておく必要はありません。
出題される内容
| 試験科目(乙種6類) | 出題数 | ||
|---|---|---|---|
| 筆記 | 基礎的知識 | 機械に関する部分 | 5 |
| 電気に関する部分 | ― | ||
| 消防関係法令 | 共通部分 | 6 | |
| 6類に関する部分 | 4 | ||
| 構造・機能・及び工事・整備の方法 | 機械に関する部分 | 9 | |
| 電気に関する部分 | ― | ||
| 規格に関する部分 | 6 | ||
| 合計 | 30 | ||
| 実技 | 鑑別等 | 5 | |
| 製図 | ― | ||
消防設備士は筆記試験と実技試験の両方に受かって合格です。試験時間は1時間45分で、その間に筆記試験と実技試験の両方を行います。
合格基準は、筆記試験では科目ごとで40%以上かつ全体で60%以上の合格点が必要です。 実技試験では、60%以上の合格点が必要になります。
合格率・難易度
消防設備士乙6の過去5年間(2019年~2023年)の平均合格率は39.6%です。
■消防設備士 乙種6類の合格率
| 年度 | 合格率 | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|
| 平均 | 39.6% | 23,616 | 9,328 |
| 2023年度 | 38.1% | 25,136 | 9,567 |
| 2022年度 | 38.8% | 25,023 | 9,712 |
| 2021年度 | 39.9% | 25,634 | 10,240 |
| 2020年度 | 42.7% | 20,955 | 8,944 |
| 2019年度 | 38.3% | 21,333 | 8,176 |
その他の国家資格と比べると難易度の高い資格ではありませんが、受験者の半分以上は試験に落ちている資格です。
難易度の高い資格ではないからと油断していると不合格になってしまう可能性が十分にあるため、しっかりと対策を行うようにしましょう。
乙6試験の難易度・合格率については「消防設備士乙種6類の合格率は約40%!難易度を他資格と比較」でも詳しくまとめていますので、是非そちらも併せてご覧ください。
その他の消防設備士試験の難易度・合格率は、「消防設備士の難易度・合格率は?試験の難所を解説!」を参考にしてください。
免除制度
消防設備士乙6を受ける際、科目免除制度というものがあります。
科目免除とは、消防設備士(乙6以外)の資格や、技術士(機械部門)等の資格を持っていれば、試験の一部を免除できるといった制度です。
また消防団員として5年以上勤務し、消防学校で所定の教育を修了している場合にも、 試験の一部を免除することができます。
※なお、試験が一部免除になった場合は、試験時間も短縮になるので注意してください。
乙種6類の科目免除については下記の表をご参照ください。
■ 乙種6類の科目免除表
(※乙種6類以外の保有資格がある場合)
| 保有資格 | 6類での免除科目 | |
|---|---|---|
| 消防関係法令 (共通部分のみ) |
基礎的知識 | |
| 甲1 | ● | |
| 甲2 | ● | |
| 甲3 | ● | |
| 甲4 | ● | |
| 甲5 | ● | ● |
| 乙1 | ● | |
| 乙2 | ● | |
| 乙3 | ● | |
| 乙4 | ● | |
| 乙5 | ● | ● |
| 乙7 | ● | |
※ 乙6以外の消防設備士の資格保有者:消防関係法令の共通部分が免除可能
※ 甲5・乙5の資格保有者:消防関係法令の共通部分の免除に加え基礎的知識も免除可能
※ 試験時間の短縮に関しては下記のように変更になります。
消防関係法令の共通部分が免除=(通常)1時間45分⇒1時間30分
消防関係法令の共通部分の免除に加え、基礎的知識も免除=(通常)1時間45分⇒1時間15分
※ その他の情報
▼技術士(機械部門)の資格をお持ちの方
基礎的知識及び、構造・機能・及び工事・整備の方法を免除することができます。
▼電気工事士または電気主任技術者の資格をお持ちの方
基礎的知識及び、構造・機能・及び工事・整備のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除になります。
▼消防団員として5年以上勤務し、消防学校で所定の教育を修了している方
基礎的知識及び、実技試験のすべてを免除することができます。
また、消防設備士の科目免除にはメリットとデメリットがあるといわれています。科目免除を受けるかどうかは、以下の内容を参考にしてください。
■科目免除のメリット
- 勉強する範囲を少なくできる。
- 勉強にかける時間を短縮できる。
- 試験に必要な範囲を絞って勉強できるため、より知識が深まる。
■科目免除のデメリット
- 部分的な免除があっても、科目ごとに40%以上の正解率を取らなければならないため、結果的に負担が増える。
(例えば、消防関係法令の『共通部分』のみが免除される場合、残りの『法令種別』だけで40%以上の正解率を取らなければいけない。) - 免除となる部分には、基礎的な知識が多く含まれており、得点を稼ぎやすいので、免除するのはもったいない。
消防設備士乙6試験の注意点
実際に試験を受ける際に見落としがちな情報をまとめました。
試験日程・申込方法に注意
消防設備士の試験は、都道府県ごとに、試験日程・試験回数が異なります。 詳しい試験日程や試験会場を知りたい方は、消防試験研究センターの公式サイトをご参照ください。
消防設備士の試験では、居住地以外の都道府県でも受験することが可能です。その場合は、受験を希望している都道府県の各センターへ受験申請をする必要があります。
例えば、『居住地は東京だけど試験の日程が合わないから、神奈川県で受験したい』といった場合は、 神奈川県の試験センターへ受験申請してください。
受験費用は4,400円
消防設備士乙6種の受験費用は4,400円です。(2024年度時点)
■消防設備士の受験費用
- 甲種 6,600円
- 乙種:4,400円
※ 受験費用は改定されています。市販のテキストの中には、改定前の旧料金が記載されているものもありますのでご注意ください。
試験の申請は『書面申請』と『電子申請』の2パターン
消防設備士の試験の申請方法は、『書面申請』と『電子申請』の2つの方法があります。
■書面申請の方法
書面申請では受験願書が必要になります。 願書は消防試験研究センターの各支部及び、関係機関の窓口で無料配布しています。
受験申請に必要な書類(受験願書・郵便振替払込受付証明書など)を揃えた後、 受付期間内に消防試験研究センターの各支部へ提出してください。 受験票は試験実施日の1週間~10日前ごろまでに郵送される予定です。 (詳しくは消防試験研究センターの各支部へお問い合わせください)
■電子申請の方法
電子申請は、インターネットから消防試験研究センターのHPにアクセスして申請する方法です。
まず、消防試験研究センターのHPの【電子申請はこちらから】にアクセスし、必要事項を入力します。 申請手続き終了後、受験費用の振り込みを行います。
(クレジット・コンビニ払い等選択可)その後、消防設備研究センターのHPから受験票をダウンロードし、 受験票へ顔写真を添付します。試験当日は、顔写真付きの受験票を持参してください。(詳しくは消防試験研究センターの各支部へお問い合わせください)
消防設備士の資格を取ったら講習を忘れずに!
消防設備士の資格の取得後は、新しい知識や技術の習得などの為に、 定期的に講習を受ける必要があります。忘れずに行きましょう。
■受講対象者
消防設備士の免状を交付されている方
■受講期間
(1)免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内
(2)(1)の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内
消防設備士乙6の試験対策
消防設備士乙6の合格率を少しでも上げられるよう、試験対策のコツを紹介します。
筆記試験対策のコツ
筆記試験対策のコツは以下の3つです。
- 消防関係法令から取り組み、基礎知識をしっかり押さえる。
- 過去問を繰り返し解き、出題傾向を把握する。
- 覚えるべき項目を重点的に暗記する。
筆記試験の問題はマークシート方式で、 4つの選択肢の中から問題に合った解答を選びます。
『基礎的知識』『消防関係法令』『構造・機能・及び工事・整備の方法』 の3科目で構成されており、全部で30問の問題が出題されます。
この筆記試験に合格していないと、実技試験は採点すらされないため、 資格を取得するには筆記試験のクリアが第一条件です。
勉強する科目の順番は、知識ゼロから勉強を始めるのであれば、まずは消防関係法令から取り掛かる事をオススメします。 消防関係法令には消防設備士として働く上での基礎知識がたくさん詰まっているからです。
勉強方法としては、過去問を繰り返し解いて、暗記をたくさんすることが一番の対策ではないかと踏んでいます。 ネット上などで公開されている問題は数がそれほど多くないので、問題集を用意したりスマホアプリ等を有効活用したりすると良いでしょう。
筆記試験の勉強時間や勉強する上でのポイントをまとめた記事もあるのでそちらも併せてご参考ください。
実技試験対策のコツ
実技試験対策のコツは以下の3つです。
- 消火器の写真やイラストを見て、操作方法や手順を記述できるようにする。
- 記述式の問題が出題されるため、正確な記述練習を行う。
- 問題数が少ないため、部分点を狙い、正確に答えるよう心がける。
実技試験の問題は、鑑別試験(かんべつしけん)といって、消火器の写真やイラストなどを見ながら、記述式で解答する問題などが出題されます。
4択で解答する筆記試験に比べると、実技試験は記述式で解答するので、 より正確な解答を求められています。
実技試験には部分点などもありますが、問題数が少なく1問当たりの配点も高くなるので、 筆記試験よりも実技試験の方が、少し難易度が高いと言えそうです。
実技試験の勉強方法や、試験を受ける上でのポイントを詳しく紹介している記事もあるため、併せてご参考ください。
消防設備士乙6を活かせる求人情報
建物には必ず消防設備が設置されるため、全国各地に消防設備士乙6を活かして働ける企業がたくさんあります。
参考として、実際の求人情報の事例を3つ紹介します。
■消防設備士を活かせる求人情報3つ
| A社(宮崎県) | B社(東京都) | C社(栃木県) | |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 自動火災報知設備・消火器・非常放送設備などの消防用設備の施工やメンテナンスを行っていただきます。 | 建物内の消防設備の保守点検作業。点検時に不具合箇所を見つけた際は改修・修繕を行います。 | 防災設備(火災報知器、消火器、消火栓、スプリンクラー等)の定期点検。設置工事を行うこともあります。 |
| 給与 | 170,000円〜200,000円 (他、各種手当あり) |
209,000円~338,000円 (他、各種手当あり) |
190,000円〜240,000円 (他、各種手当あり) |
| 特徴 | ●消防設備士 あれば尚可 ●資格取得支援制度あり |
●大手グループ企業 ●消防設備士乙6の資格手当あり |
●乙種消防設備士 あれば尚可 ●消防設備士の資格手当あり |
出典:工事士.com
消防設備士乙6を持っていれば、転職の際の選考や入社の際の条件面で優遇されたり、入社後も資格手当が支給されたりする場合があります。
また、中には資格取得支援制度を設けている企業もあるため、まずは未経験で転職活動し、入社後に資格を取得するのも良いでしょう。
どのような企業で働けるか、あなたの地域の求人情報もぜひ覗いてみてください。
よくある質問
消防設備乙6について調べている人によくある質問をまとめました。
消防設備士乙6の勉強におすすめのテキストは?
消防設備士乙6の勉強には、「基礎知識から応用までをわかりやすく説明しているもの」、「イラストや図表が豊富で視覚的に理解しやすいもの」、「過去問がたくさん収録されているもの」などを選ぶと良いでしょう。
消防設備士乙6の実技試験は難しい?
消防設備士乙6の実技試験は、記述式で、具体的な操作手順や構造について詳しく記述する必要があるため、難易度が高いと感じる人もいます。
しかし、過去問を繰り返し解くといった練習を行うことで、十分に対策可能です。
ちなみに、消防設備士乙6の過去5年間(2019年~2023年)の平均合格率は39.6%となっています。
消防設備士乙6の合格発表はいつですか?
通常、消防設備士試験の結果発表日は、試験のおよそ1ヶ月後です。
試験日程および合格発表は消防試験研究センターのホームページから確認できます。
消防設備士の資格はどの順番で取ればいいの?
まずは乙種6類(消火器)など比較的取得しやすい資格から始めるのが一般的です。
その後、業務内容やキャリアプランに応じて、他の乙種や甲種を取得するのが良いでしょう。
他の乙種は例えば、乙1(屋内消火栓設備)や乙4(自動火災報知設備)などです。また、甲種資格を取得すれば、設置工事や広範囲な管理業務が可能になります。
詳しくは「消防設備士|どの種類を取ればいいのか迷わずわかる!」をご覧ください。
まとめ
今回は「消防設備士乙6」の概要や試験情報について紹介しました。
消防設備士乙6の資格は、消火器に特化しており、消防設備の基礎を学ぶのに最適です。
また、消火器の設置・整備を通じて多くの現場で活躍できるため、安定した需要があります。
これから受験される方は、試験対策をしっかりと行い、資格取得を目指しましょう。
皆さんの合格を願っています!
消防設備士の求人を探す
消防設備士のおすすめ求人

株式会社レスキューサービス
【レスキューサービススタッフ】マンション・ビルトラブルの救世主!/資格経験不問<直行直帰OK◎>/正..

株式会社マトイテック
\年3回の賞与・10年以上増収増益/消防設備の点検や工事★資格不問・未経験も大歓迎◎社宅&資格手当有..

株式会社昌栄電設
《地域密着で出張&夜勤ナシ》和光市~日高市の現場に直行OK!集合住宅の電気工事<資格・経験不問>/正..

株式会社マトイ防災
\連続・増収増益/早期昇進・昇給のチャンスも!将来も無くならない、消防設備の保守点検<資格経験不問>..

共栄防災株式会社
《出張ナシ・官公庁取引アリ》消防設備のメンテナンス/資格経験不問【月給は職能に応じてベースアップ★】..
消防設備士の求人一覧
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする