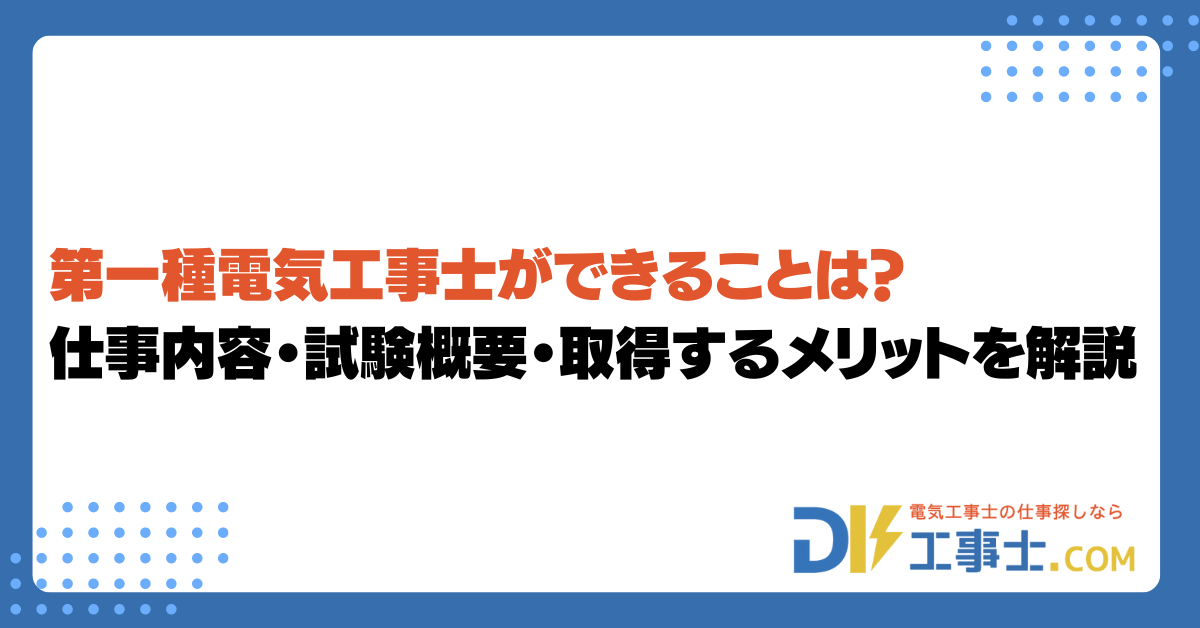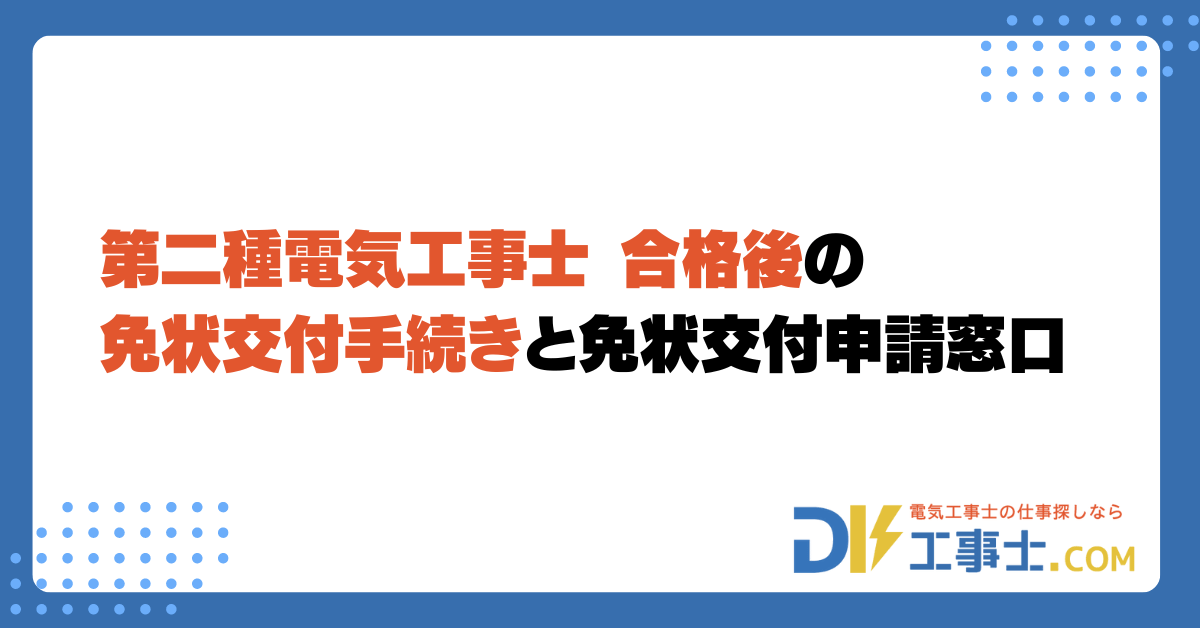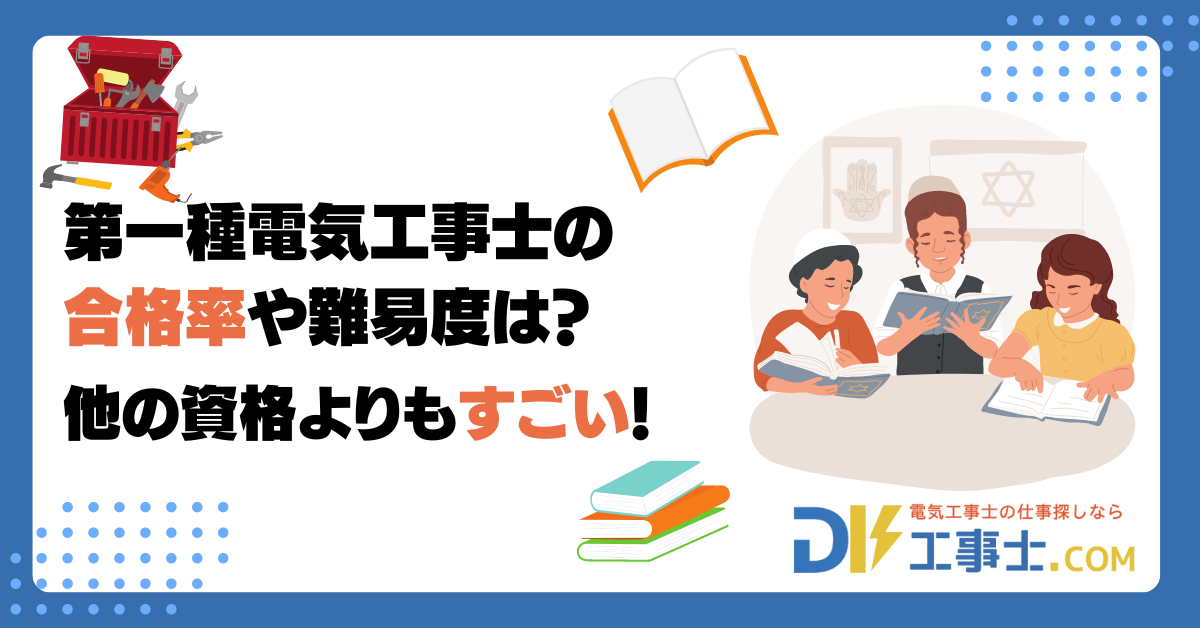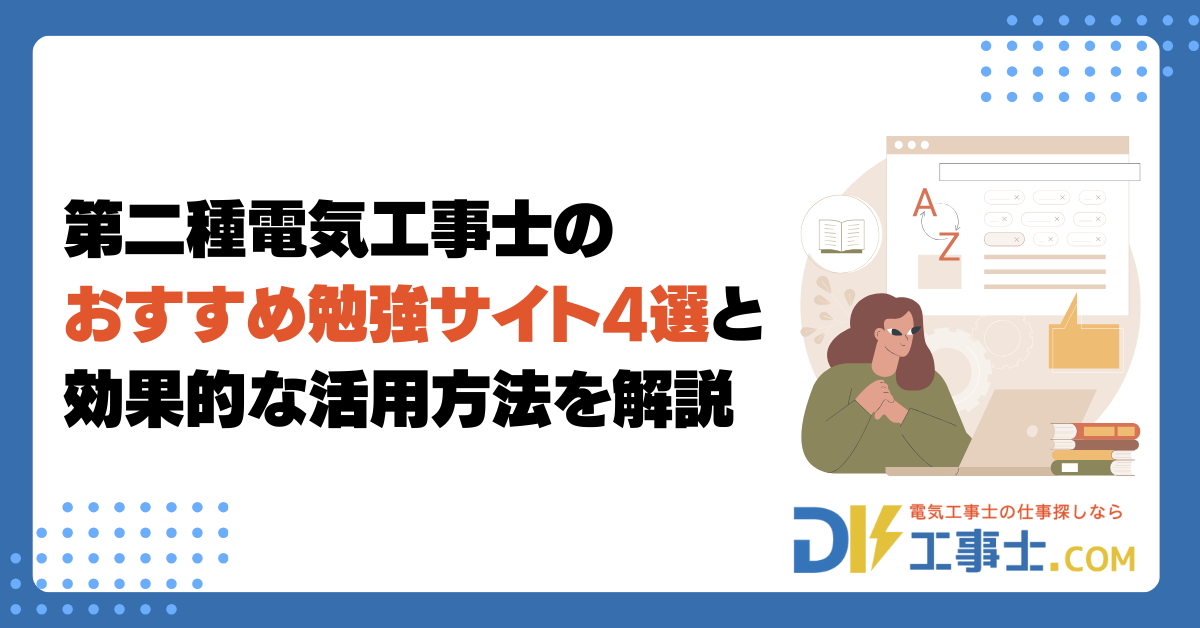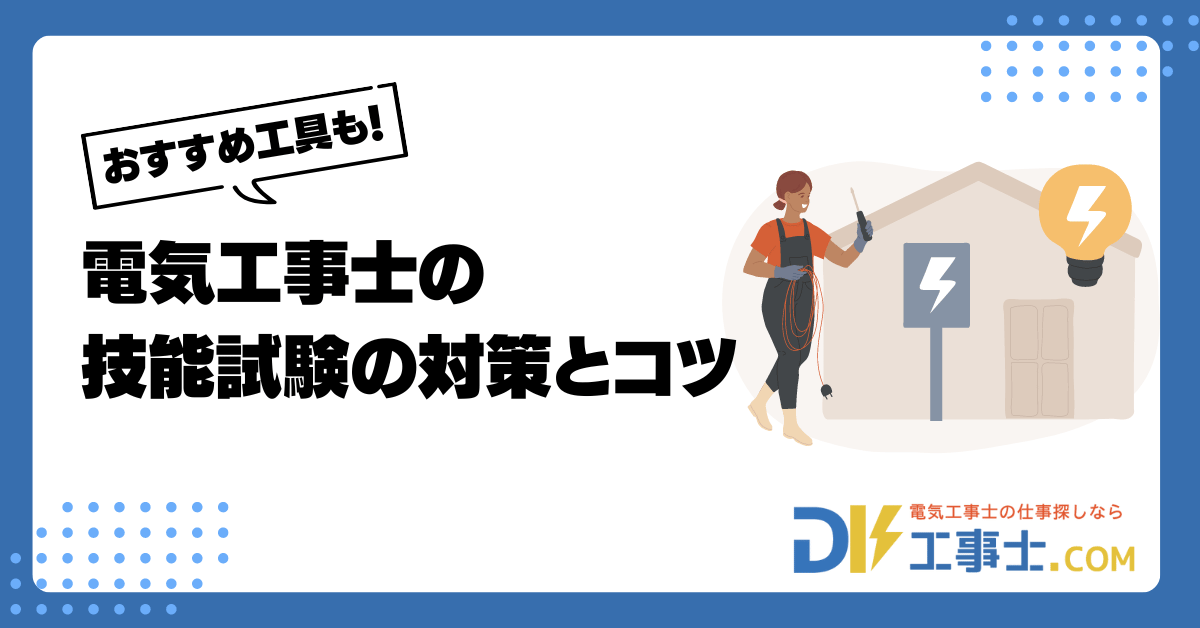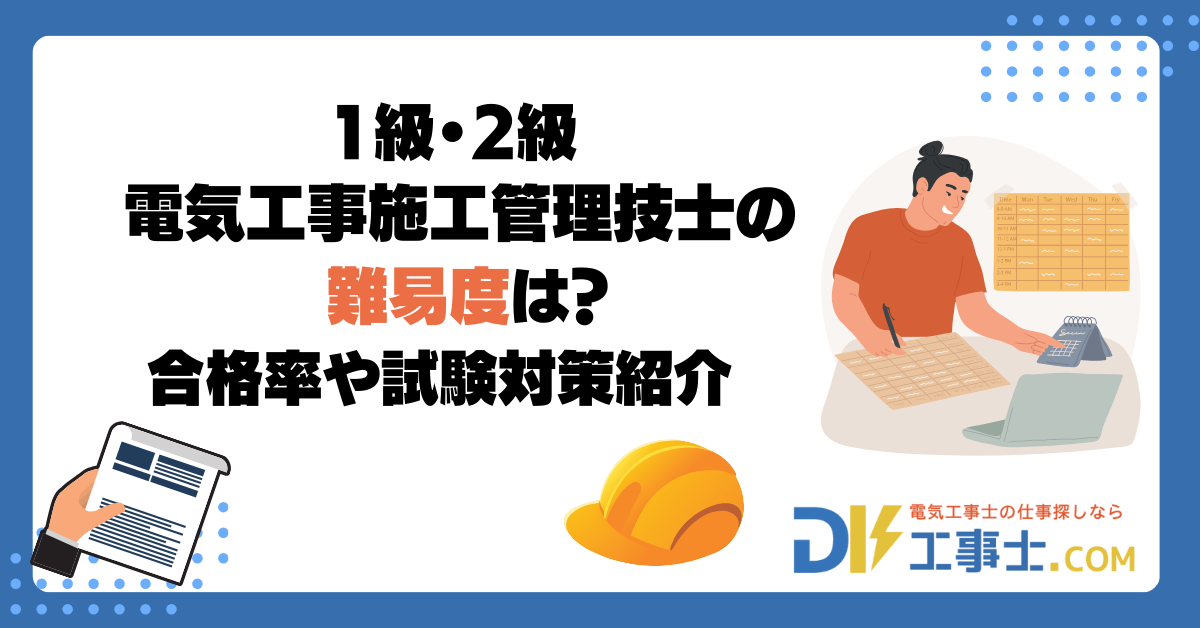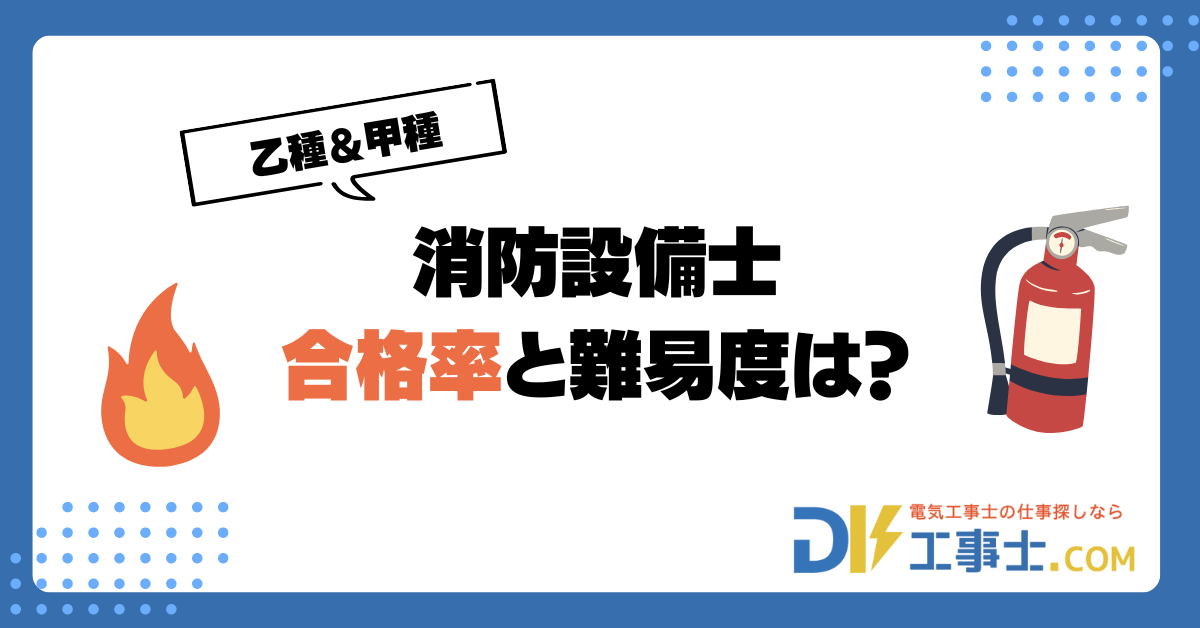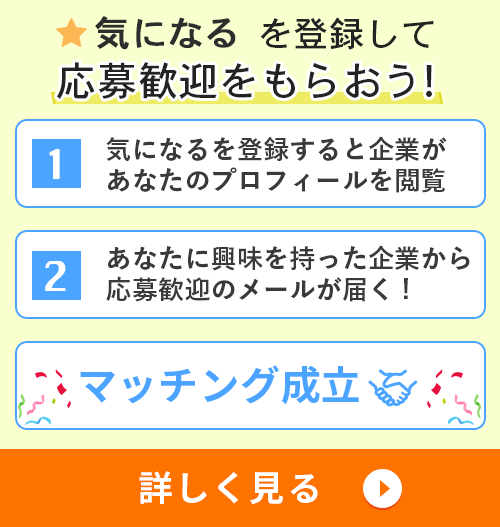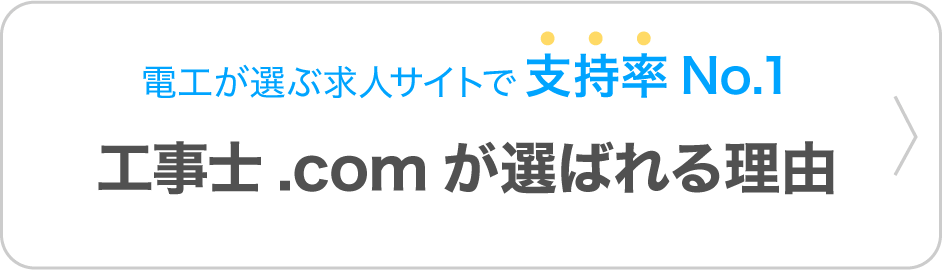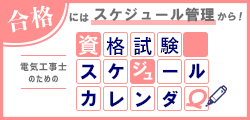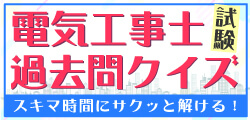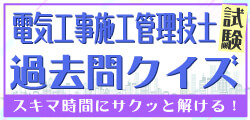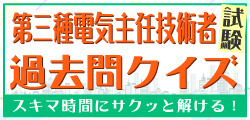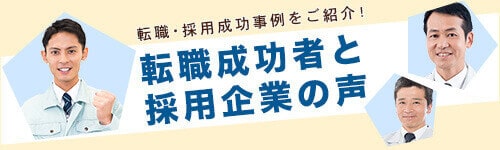第一種電気工事士の受験資格|免状取得には実務経験3年以上が必要
電気工事士の資格・試験最終更新日:
第一種電気工事士に受験資格はありませんが、免状交付の条件として3年以上の実務経験が必要です。
第一種電気工事士は、電気工事業界でのキャリアアップを目指す技術者にとって非常に重要な資格です。
しかし、第一種電気工事士の受験資格や実務経験の要件について詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、第一種電気工事士の受験資格や必要な実務経験、試験の概要について詳しく解説します。
資格取得を目指す方にとって、役立つ情報を提供しますので、ぜひ参考にしてください。
第一種電気工事士の受験資格は?

第一種電気工事士の試験を受けるためには、特別な条件や受験資格はありません。
年齢、学歴、職歴に関係なく、誰でも受験することができます。
ただし、合格後の資格免状交付には条件があるため、試験に合格しただけでは免状の交付は受けられません。
第一種電気工事士の免状交付には3年以上の実務経験が必要!
第一種電気工事士の免状交付には、試験の合格に加えて3年以上の実務経験が必要です。
2022年4月1日以降、試験合格者に必要な実務経験の期間が5年以上から3年以上に短縮されました。
なお、3年以上の実務経験については「連続して3年」ではなく「合計して3年」であれば問題ありません。
また、試験合格前の期間も含めることができます。
例えば、第二種電気工事士としての実務経験が3年以上ある状態で、第一種電気工事士試験に合格した場合は、すぐに免状の交付申請が可能です。
実務経験として認められるのは、以下のような電気工事です。
■ 第一種電気工事士の免状交付時に実務経験として認められる工事
- 第二種電気工事士として行う一般用 電気工作物等に係る電気工事
- 認定電気工事従事者として行う最大電力500kW未満の自家用電気工作物の低圧部分に係る電気工事
- 最大電力500kW 以上の自家用電気工作物に係る電気工事
- 第二種電気工事士養成施設において教員として担当する実習
ちなみに、「電気主任技術者の免状取得者」や「高圧電気工事技術試験合格者」も、一定の実務経験を積んでいれば免状交付を受けられますが、それぞれ実務経験の年数が異なりますのでご注意ください。
■第一種電気工事士 条件ごとに必要な実務経験年数
| 第一種電気工事士 免状交付の条件 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 電気主任技術者の免状取得者 | 5年以上 |
| 高圧電気工事技術試験の合格者 | 3年以上 |
参考:第一種電気工事士免状の取得方法(一般財団法人 電気技術者試験センター)
また、免状交付申請は居住する都道府県の知事が担当します。
申請には、実務経験を証明する書類や試験結果通知書などが必要です。
詳しい手続きや必要書類については、各都道府県の電気工事士免状担当窓口に確認してください。
第二種電気工事士の条件との違い
以下の表のとおり、第一種電気工事士と第二種電気工事士の受験資格や免状交付条件には違いがあります。
■ 第一種・第二種電気工事士 受験資格と免状交付条件の違い
| 条件・要件 | 第一種電気工事士 | 第二種電気工事士 |
|---|---|---|
| 受験資格 | なし(年齢・学歴・職歴不問) | なし(年齢・学歴・職歴不問) |
| 免状交付条件 | 試験合格後、3年以上の実務経験 | 試験合格のみ |
第一種電気工事士の免状交付には3年以上の実務経験が必要です。
一方で第二種電気工事士は、試験に合格すれば、すぐに免状交付申請が可能です。
第一種電気工事士と第二種電気工事士のその他の違いについては、「電気工事士「1種」と「2種」の違いは?仕事内容や難易度を解説!」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
免状交付に必要な実務経験の積み方

第一種電気工事士の免状取得に必要な実務経験は、実際どのように積んでいけばよいのでしょうか。
第一種電気工事士の受験者の多くは、まずは第二種電気工事士の免状を取得し、第二種電気工事士として3年以上の実務経験を積んでいます。
具体的には、住宅や小規模な商業施設などの一般電気工作物に関する工事に従事することが多いです。
したがって、第一種電気工事士としてキャリアを積みたい方は、まずは第二種電気工事士の資格取得を目指すのが効率的でしょう。
また、認定電気工事従事者として最大電力500kW未満の自家用電気工作物に関する工事に携わることも、第一種電気工事士に必要な実務経験の対象となります。さらに、工場やビルなどの大規模施設での高圧電気工事に携わることや、第二種電気工事士養成施設での指導も実務経験としてカウントされます。
このように、現場での経験を積み重ねることで、より専門的な知識と技術の取得と共に、第一種電気工事士の免状取得に必要な実務経験も満たすことができます。
なお、電気工事士の求人の中には、未経験者を歓迎しているものも数多くあります。
第一種電気工事士に必要な実務経験が足りない方は、このような企業に入社して経験を積んでいきましょう。
注意!実務経験にならない工事5点

先述したとおり、第一種電気工事士の免状交付には一定の実務経験が必要です。
しかし、電気工事の業務の中には実務経験にカウントされないものもあります。
以下に、その代表的な例を紹介します。
■ 免状交付に必要な「実務経験」に含まれない工事
- 軽微な工事
- 特種電気工事
- 5万V以上で使用する架空電線路の工事
- 保安通信設備の工事
- 違反工事
■軽微な工事とは
電球の交換やコンセントのカバー取り付けなど、資格がなくてもできる簡単な作業
■特種電気工事とは
最大電力500kW未満の需要設備のネオン工事や非常用予備発電装置工事
※詳しくは「特種電気工事資格者|認定証を取得する為の申請方法・講習内容」にてご確認ください。
上記の業務に従事していても第一種電気工事士の免状は取得できないため注意してください。
第一種電気工事士の資格概要

第一種電気工事士の資格は、電気工事業界でのキャリアアップに必須の資格です。
この資格を取得することで、ビルや工場などの大規模な電気工事に従事できるようになるため、第二種電気工事士として働くよりも仕事の幅が広がります。
第一種電気工事士の試験の概要は下記のとおりです。
■ 第一種電気工事士 試験の基本情報
| 項目 | 学科試験 | 技能試験 |
|---|---|---|
| 問題数 | 50問 | 1問 |
| 出題内容 | 電気工事の基本知識 | 電気工事の基本作業 |
| 試験時間 | 2時間30分 | 60分 |
| 合格基準 | 60%以上 | 欠陥なし |
第一種電気工事士の資格試験の詳細は、下記記事で詳しく解説しています。
第一種電気工事士の合格率・難易度
第一種電気工事士の過去5年間平均合格率は、学科試験が55.9%、技能試験が63.8%です。
■第一種電気工事士 学科試験合格率
| 年度 | 合格率 | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|
| 平均 | 55.9% | 35,731 | 19,963 |
| 2023年度 | 61.6% | 33,035 | 20,361 |
| 2022年度 | 58.2% | 37,247 | 21,686 |
| 2021年度 | 53.5% | 40,244 | 21,542 |
| 2020年度 | 52.0% | 30,520 | 15,876 |
| 2019年度 | 54.1% | 37,610 | 20,350 |
※参考:第一種電気工事士試験(一般財団法人 電気技術者試験センター)
■第一種電気工事士 技能試験合格率
| 年度 | 合格率 | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|
| 平均 | 63.8% | 24,690 | 15,747 |
| 2023年度 | 60.6% | 26,143 | 15,834 |
| 2022年度 | 62.7% | 26,578 | 16,672 |
| 2021年度 | 67.0% | 25,751 | 17,260 |
| 2020年度 | 64.1% | 21,162 | 13,558 |
| 2019年度 | 64.7% | 23,816 | 15,410 |
※参考:第一種電気工事士試験(一般財団法人 電気技術者試験センター)
ちなみに、第二種電気工事士の過去5年間平均合格率は、学科試験が60.5%、技能試験が70.8%です。
この数字からも分かるとおり、第二種電気工事士と比べて第一種電気工事士の資格試験の難易度は高いです。
第一種電気工事士の資格試験の合格率や難易度についての詳細は、「【実はすごい】第一種電気工事士の合格率・難易度を他資格と比較して解説」にてご確認ください。
【2024年最新版】第一種電気工事士の試験日まとめ
2024年度の第一種電気工事士試験の申し込みから試験日までのスケジュールは以下の通りです。試験に合格するために、申し込みから試験当日までの計画をしっかりと立てておきましょう。
■ 2024年度 第一種電気工事士試験スケジュール
| 日程 | 上期(申込終了) | 下期 |
|---|---|---|
| 申込期間 | 2024年2月9日(金)~3月8日(金) | 2024年7月29日(月)~8月15日(木) |
| 学科試験日 (筆記方式) | なし | 2024年10月6日(日) |
| 学科試験日 (CBT方式) | 2024年4月1日(月)~5月9日(木) | 2024年9月2日(月)~9月19日(木) |
| 技能試験日 | 2024年7月6日(土) | 2024年11月24日(日) |
※学科試験免除の対象者は、受験申し込み完了後に証明書類を提出する必要があります。
なお、免状交付申請は、技能試験の合格発表以降となります。
申請時に必要な書類等もありますので、技能試験終了後から余裕を持って準備しておくと良いでしょう。
第一種電気工事士の試験スケジュールや、申し込み方法、免状交付申請方法などについては下記記事で詳しく解説しています。
第一種電気工事士の試験対策は?
第一種電気工事士の学科試験では、過去問を繰り返し解くことが効果的です。
過去問を行うことで、試験問題の傾向を把握し、頻出問題を重点的に学習することができ、効率的に点数を上げることができます。
電気工事士の求人サイト「工事士.com」が運営する「電気工事士試験問題クイズ」では、過去15年間の過去問をクイズ形式で学ぶことができます。
スマホからでも気軽に利用できますので、通勤時や休憩時などのスキマ時間の試験勉強としてぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
また、技能試験の準備では、複線図の書き方をマスターすることが重要です。
複線図を正確に描くことで、配線ミスを防ぎ、作業効率を高めることができます。また、公表されている候補問題を繰り返し行い、実技試験の流れに慣れておくことが大切です。
第一種電気工事士試験のより具体的な勉強法については、下記記事で解説しています。
よくある質問
第一種電気工事士の資格取得を目指す方々から寄せられる質問をまとめました。
以下の質問と回答を参考にして、第一種電気工事士の資格取得を目指してください。
第一種電気工事士が従事できる工事の範囲は?
第一種電気工事士は、自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備の電気工事が可能です。
また、一般用電気工作物、つまり一般住宅や小規模な店舗、事業所などの低圧(600V以下)で受電する場所の配線や電気使用設備等の電気工事も担当できます。
ただし、特定の工事(ネオン工事や非常用予備発電装置工事)を行うには、さらに特種電気工事資格者認定証が必要です。
実務経験が足りない場合はどうすればいい?
第一種電気工事士の免状交付に必要な実務経験を満たしていない場合には、第一種電気工事士の免状を取得することができません。
第一種電気工事士の合格前でも後でも構いませんが、必要な実務経験を満たせる会社に所属し、3年以上の実務経験を積むようにしましょう。
実務経験にはアルバイトも含まれる?
アルバイトが実務経験として含まれるか否かについては、一概には言えません。
勤務時間や業務内容により、判断が異なるからです。
免状交付時に必要な実務経験証明書は、雇用主からの証明が必要となるため、まずは雇用主に相談してみることをおすすめします。
まとめ
今回は、第一種電気工事士の受験資格や免状交付に必要な実務経験について詳しく解説しました。
- 第一種電気工事士は、試験には受験資格がないが、合格後の免状交付には3年以上の実務経験が必要。
- 免状交付の条件である3年以上の実務経験は、試験合格前の期間も含めることができる。
- 実務経験の積み方としては、まずは第二種電気工事士の資格を取得し、第二種電気工事士として経験を積むのが一般的。
- 軽微な工事や特殊電気工事、高電圧の架空電線路の工事、保安通信設備の工事、違反工事は実務経験として認められない。
第一種電気工事士の免状は、試験に合格するだけでは取得できません。
必要な実務経験を満たす必要があるため、現場で経験を積みながら資格の取得を目指しましょう。
この記事を参考に、第一種電気工事士の資格取得を目指して、計画的に準備を進めてください。

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
第一種電気工事士の求人を探す
第一種電気工事士のおすすめ求人

株式会社オフシス
\年休122日&残業月10h/健康的に働ける環境で、手に職をつけられる◎【資格・経験不問/計装工事】..

日研電気株式会社
年休120日超◎賞与2回+決算賞与◎残業月5h◎研修制度◆二種電工&経験必須/公共施設等の電気工事/..

株式会社甲友電気設備
【電気設備工事】神戸市内メイン*住宅・ビル・学校など幅広い場所で活躍!/直行直帰OK<資格経験不問>..

サンコーエレック株式会社
賞与年3回★公共施設・商業施設等の電気工事【二種電工必須・経験不問】一種電工や職長経験ある方は優遇◎..

新栄電気工事株式会社
【照明工事】首都高メイン★資格経験不問/年休121日/皆勤手当2万円《1週間のリフレッシュ休暇あり》..
第一種電気工事士の求人一覧
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする