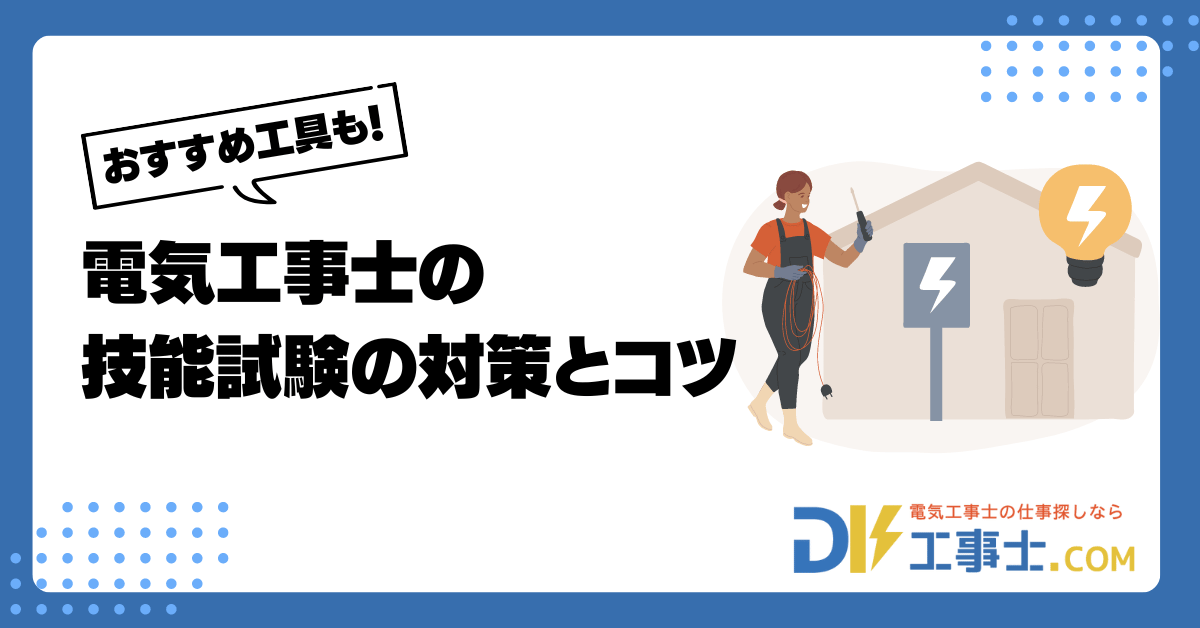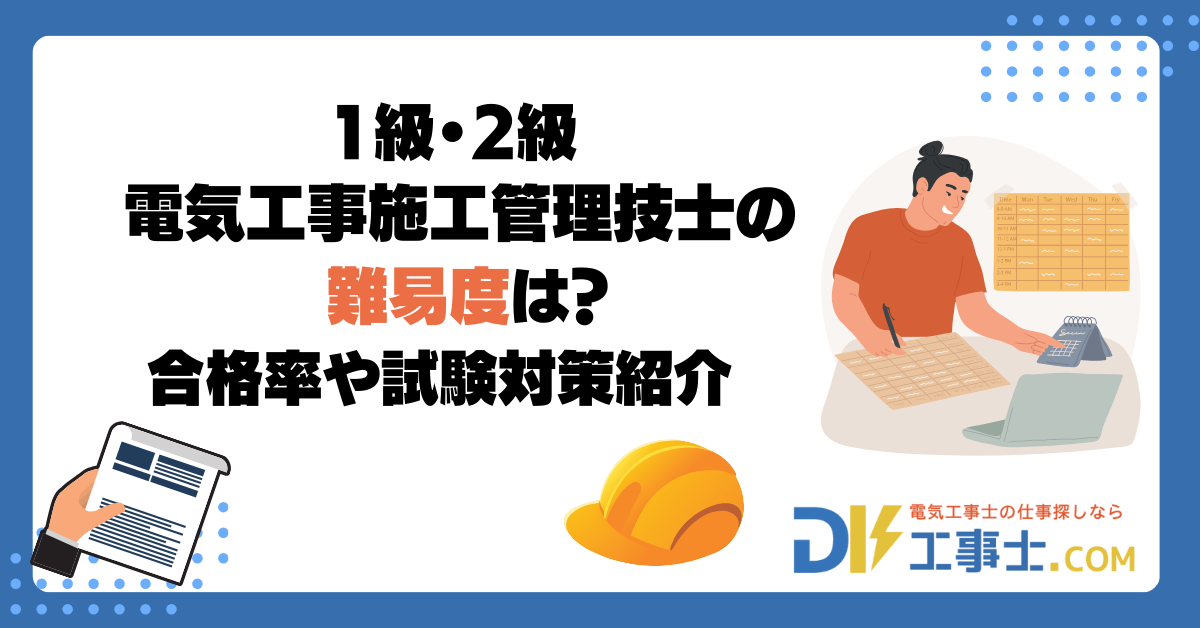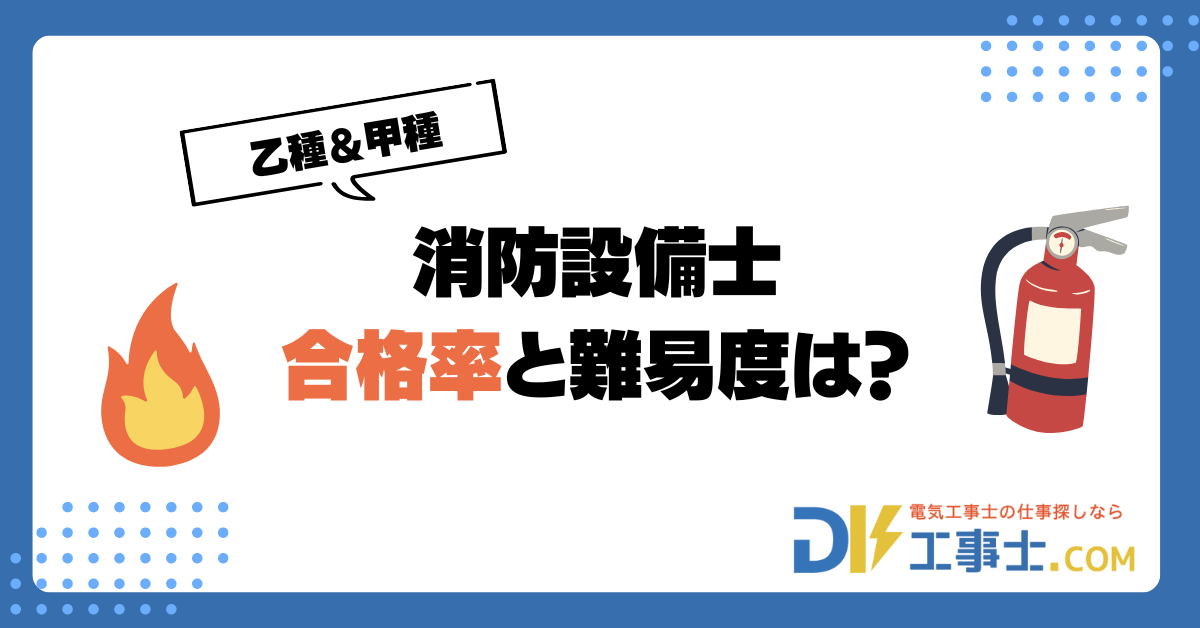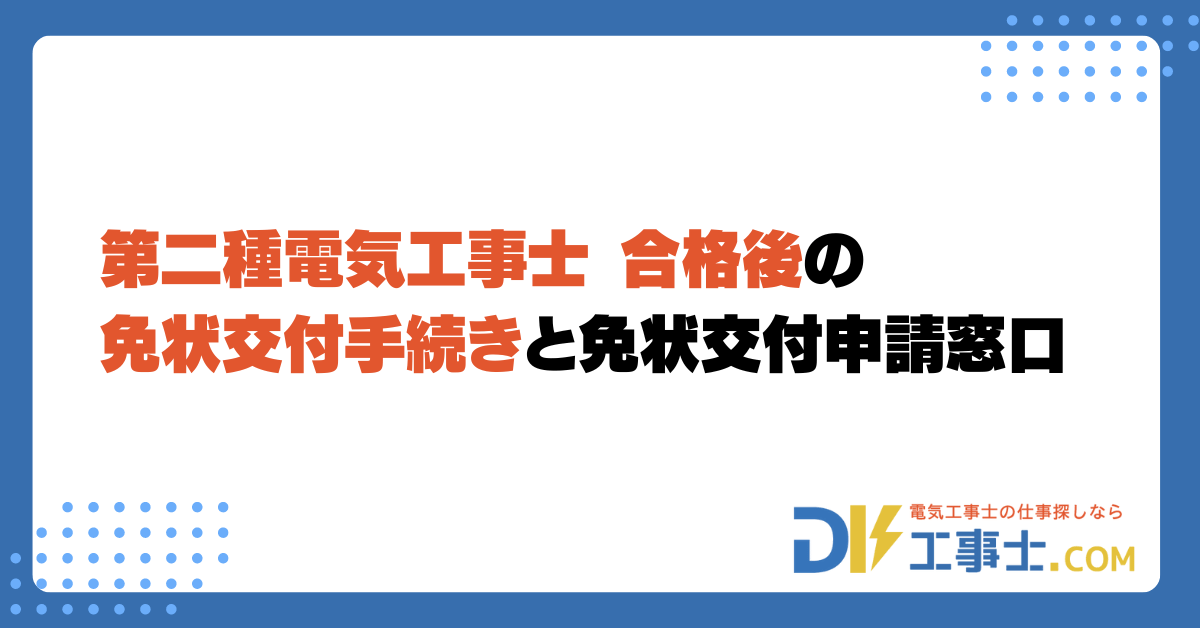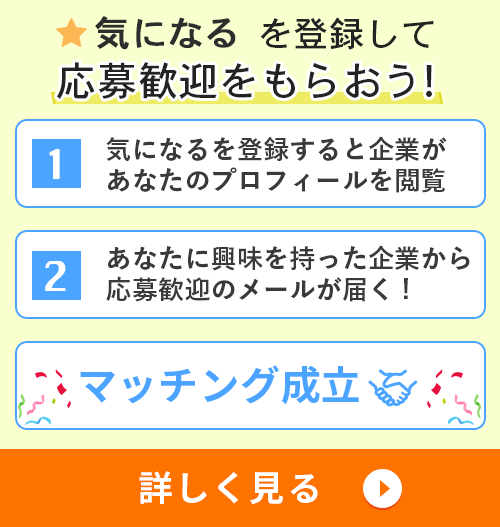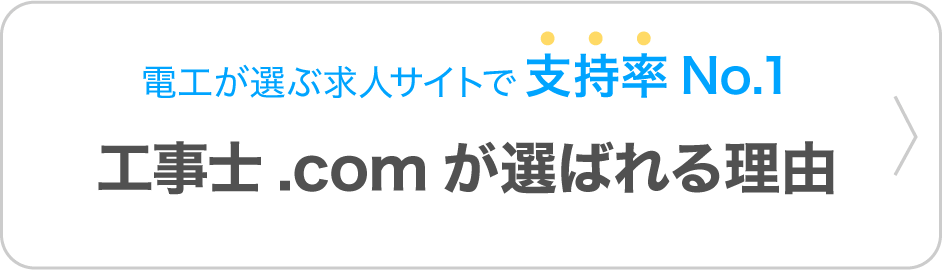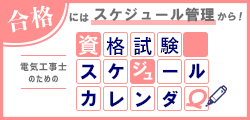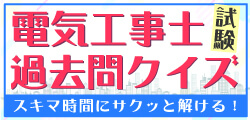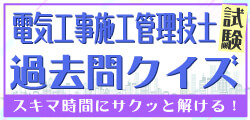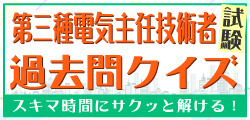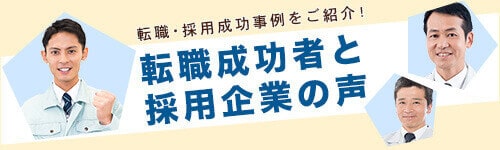電験三種の勉強時間をアンケート調査『文系出身者の目安は600時間~800時間程度』
電気主任技術者(電験)最終更新日:
電気工学系・理系出身者である方とそうでない方で違いはありますが、電験三種の合格に必要な勉強時間は少なくとも400時間〜多くて800時間ほどです。
この記事を読むことで具体的な勉強時間の目安、勉強スケジュールの組み方、電験三種の勉強方法などがまるっとクリアになるでしょう。
電験三種の試験について悩んでいる方の力になれれば幸いです。
合格者にアンケート「電験三種の勉強時間は?」
電験三種に合格するにはどのくらい勉強すれば良いのでしょうか?
実際に電験三種の試験に合格した方たちへのアンケートを基にして、合格までにかかった「総勉強時間」「科目別勉強時間」を説明していきたいと思います。
電験三種合格者の総勉強時間
アンケートの結果、電験三種に合格するまでにかかる総勉強時間の目安は以下のとおりです。
■電験三種の総勉強時間に関するアンケート結果
| 学歴 | 年齢 | 勉強期間 | 総勉強時間 |
|---|---|---|---|
| 電気工学系の卒業生 | 20代前半 | 1年半~2年 | 400時間~600時間 |
| 電気工学科以外の理系卒業生 | 50代 | 1年半~2年 | 400時間~600時間 |
| 電気工学科以外の理系卒業生 | 40代 | 2年~2年半 | 400時間~600時間 |
| 電気工学系・理系以外の卒業生 | 20代前半 | 3年~4年 | 600時間~800時間 |
合格率がわずか十数%と、難易度が高いことで有名な電験三種の試験ですが、合格するにはやはりそれ相応の勉強時間が必要になってくることが分かります。
また、特に注目するべき点として、電気工学系・理系出身者である方とそうでない方で勉強期間と総勉強時間が変わってくることがあげられます。
電験三種の勉強時間は電気工学系・理系出身者で400時間~600時間、それ以外の方で600時間~800時間ほどでした。
電験三種の試験は、「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目で構成されています。
■電験三種の試験科目
| 試験科目 | 出題範囲 |
|---|---|
| 理論 | 電気理論、電子理論、電気計測、および電子計測に関するもの |
| 電力 | 発電所・変電所の設計および運転、送電線路(屋内配線を含む)の設計および運用、並びに電気材料に関するもの |
| 機械 | 電気機器・パワーエレクトロニクス・電動機器応用・照明・電熱電気化学・電気加工・自動制御・メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝達・処理に関するもの |
| 法規 | 電気法規(保安に関するものに限る)および電気施設管理に関するもの |
その4科目の中で「理論」は【電気理論、電子理論、電気計測、および電子計測に関するもの】が出題範囲になっており、4科目の全ての基本となる知識を含んでいるのが特徴です。
4科目全ての基本となる「理論」ですが、理論の試験では、直流回路や電磁力・静電気など、中学や高校の理科で勉強する知識や、計算式を使って答える数学の知識が必要になります。


そのため、電験三種の勉強量は、中学・高校レベルの「数学・理科」の理解度で勉強量が変わるということです。
学校の授業で習ったオームの法則やフレミングの法則などを覚えていますか?
もし「全然覚えていない」という場合は、まず中学・高校の数学・理科の復習から取り組むことから始まるので、その分勉強時間を多く見積もっておくと良いでしょう。
電験三種合格者の科目別勉強時間
続いては、電験三種の勉強時間を科目別に詳しく見ていきたいと思います。
科目別勉強時間に関するアンケート結果は以下のとおりです。
■電験三種の勉強時間(科目別)
| 学歴 | 理論 | 電力 | 機械 | 法規 |
|---|---|---|---|---|
| 電気工学系の卒業生 (20代前半) |
~100時間 | 100時間~200時間 | 100時間~200時間 | ~100時間 |
| 電気工学科以外の理系卒業生 (50代) |
~100時間 | 100時間~200時間 | 100時間~200時間 | ~100時間 |
| 電気工学科以外の理系卒業生 (40代) |
~100時間 | 100時間~200時間 | 100時間~200時間 | 200時間~300時間 |
| 電気工学系・理系以外の卒業生 (20代前半) |
100時間~200時間 | 200時間~300時間 | 200時間~300時間 | 300時間~ |
個人差はありますが、各科目毎に100時間~300時間ほど必要となるようです。
各科目ごとにしっかりと準備しましょう。
電験三種の勉強スケジュールの立て方
電験三種に合格するまでの全体的な勉強時間が分かったところで、具体的な勉強スケジュールの立て方について説明していきます。
「何から勉強していけばいいのか分からない」という方は参考にしてみてください。
勉強スケジュールの参考例
電験三種の勉強を進める上で1番大切なのは、毎日少しずつでいいのでコツコツ勉強することです。
電験三種の試験範囲はとても広いので、短期間で全て頭に叩き込むというのは難しいでしょう。
例えば、実際に試験に合格した方のアンケート結果から、合格までに「600時間」必要だと仮定すると、次のような勉強スケジュールが作成できます。
■勉強スケジュール例
【平日1時間×5日+休日2時間×2日×4週間=36時間/月】⇒【36時間/月×1年5ヶ月=612時間】
平日1時間と休日2時間を毎日続けていけば1年5ヶ月、つまり約1年半ほどで合格できる計算になります。
「600時間」と聞くと気が遠くなってしまうかもしれませんが「平日1時間と休日2時間」なら案外出来そうに感じませんか?
このように、自分のライフスタイルに合わせて、長期スパンで計画的に勉強を進めていくことが大切です。
科目別合格制度を活用したスケジュール
電験三種の試験には科目別合格制度という制度があり、4科目のどれかに合格した場合は申請により次回からその科目を免除することが可能です。
この科目別合格制度を活用すれば、【科目別に絞って勉強する方法】が可能です。
電験三種の試験は上期と下期の年2回実施されているため、「次の上期は2科目合格を目指して、下期で残りの2科目を合格する」といったスケジューリングができます。
4科目全てをまんべんなく勉強し1度に全科目に合格する、となると勉強量や範囲も膨大で難しいと思う方も多いと思います。
そんな方は是非この【科目別に絞って勉強する方法】で1科目ずつ合格していく方法を試してみるのもありかもしれません。
なお、科目別合格制度には回数制限が設けられており、最初に合格した試験以降、最大で連続5回までと決まっています。
そのため、最初に合格した試験から5回以内には4科目全て合格できるようにスケジューリングすると良いでしょう。
電験三種のおすすめ勉強方法
ここからは、電験三種のおすすめ勉強方法を詳しく解説していきます。
勉強時間を最大限に活用するテクニック
勉強時間を最大限に活用するテクニックとしておすすめなのが「スキマ時間の有効活用」です。
電験三種に限らず、皆さん1度は耳にしたことがある「スキマ時間の勉強」。
通勤・通学中やお昼の休憩時間など、普段の生活の中で余っている時間を有効活用できれば、より効率的に勉強を進めることができます。
特に最近では、資格の勉強ができるアプリや電子で読める参考書など、スマホがあればできる勉強が多いです。電験三種の勉強であれば、スキマ時間に過去問を沢山解くのも良いでしょう。
平日など忙しい時はスキマ時間を利用して過去問を解いて、休日などガッツリ勉強できるときに知識を入れていく勉強方法もアリですね。
電験三種の過去問を手軽に体験してみたいという方は「第三種電気主任技術者(電験三種)の過去問クイズ無料」をご覧ください。
各科目(理論、電力、機械、法規)の勉強法
続いては、各科目(理論、電力、機械、法規)それぞれの勉強法について解説していきます。
■理論
「理論」はとにかく全科目の基礎の部分に当たるとても重要な科目です。
その中でも特に、【直流回路・交流回路・電磁力・静電気などに関係する原理や法則】は必ず覚えましょう。
電験三種の試験はこの原理や法則を応用した問題や考え方がとても多く出題されます。
基礎の部分を理解し覚えることでその後の勉強にも関係するのでしっかりとマスターしましょう。
出題される問題としては、計算問題や正誤判定問題、穴埋め問題などさまざまなパターンがあるので、過去問を沢山解いて問題に慣れておくことが必要です。
■電力
電力では、【発電・変電・送電・配電のそれぞれの仕組みや、設備の違い】などを重点的に覚えましょう。
例えば、試験では下記のような問題が出題されます。
■例題
0.01kgのウラン235が核分裂するときに0.09%の質量欠損が生じるとする。これにより発生するエネルギーと同じだけの熱を得るのに必要な重油の量【I】の値として、最も近いものを次の(1)~(5)から選べ。重油発熱量は43000kj/Iとする。
【選択肢】
(1)950 (2)1900 (3)9500 (4)19000 (5)38000
【正解】
(4)19000
電気工事士や発電所などの仕事に関わっていたことのある方にとっては、身近に感じる部分が多いでしょう。
電気技術者試験センターが公開している過去問等をみると、電力は理論に比べて計算問題は少なく、正誤判定問題や穴埋め問題が比較的多い傾向です。
過去に出題された問題を分析すると、毎年似たような問題が出題されているので、過去問を中心に勉強すると良いでしょう。
■機械
機械についてはズバリ【直流機・変圧器・誘導機・同期機の四機】をマスターすることが重要です。
機械の科目は「電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御、メカトロニクス並びに電力システム」など、機械の仕組みに関するより専門的で深い知識が必要になります。
例えば、試験では下記のような問題が出題されます。
■例題
貯水池に集められた雨水を、毎分300㎥の排水量で全揚程10mを揚水して河川に排水する。このとき100kwの電動機を用いた同一仕様のポンプを用いるとすると、必要なポンプの台数は何台か。ただしポンプの効率は80%、設計製作上の余裕係数は1.1とし、複数台のポンプは排水を均等に分担するものとする。
【選択肢】
(1)1 (2)2 (3)6 (4)7 (5)9
【正解】
(4)7
工業高校などの機械科を卒業した方などからは「理解しやすかった」という話を聞きますが、機械についてあまり馴染みのない方も多いと思います。
そんな方に特に抑えて欲しいポイントが【直流機・変圧器・誘導機・同期機の四機】に関する内容です。
この「四機」は試験問題の約70%を占めているので、ここだけは必ずマスターするように勉強しましょう。
■法規
法規の勉強方法について、大切なポイントは【先に計算問題の練習をしておくこと】です。
「あれ?法規なんだから暗記じゃないの?」と思うかもしれませんが、計算問題・正誤判定問題・穴埋め問題がまんべんなく出題されます。
また、電気事業法・電気工事法などの法律や、電気設備の設置基準、電気施設管理などの数多くの法律や基準を覚えなければいけません。
例えば、試験では下記のような問題が出題されます。
■例題
次の文章は「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空電線路の電線の断線、支持物の倒壊等による危険を防止するために必要な場合に行う、高圧保安工事に関する記述の一部である。
a. 電線はケーブルである場合を除き、引張強さ( ア )【kN】以上のもの又は直径5【㎜】以上の( イ )であること。
b. 木柱の( ウ )荷重に対する安全率は、1.5以上であること。
c. 径間は、電線に引張強さ( ア )【kN】以上のもの又は直径5【㎜】以上の( イ )を使用し、支持物にB種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を使用する場合の径間は( エ )【m】以下であること。
上記の(ア)~(エ)に当てはまる語句として、正しい組み合わせは次のうちどれか。
<1>(ア)8.71(イ)硬銅線(ウ)垂直(エ)100
<2>(ア)8.01(イ)硬銅線(ウ)風圧(エ)150
<3>(ア)8.01(イ)高圧絶縁銅線(ウ)垂直(エ)400
<4>(ア)8.71(イ)高圧絶縁銅線(ウ)風圧(エ)150
<5>(ア)8.01(イ)硬銅線(ウ)風圧(エ)100
【正解】
<2>
覚える量が他の3科目に比べて特別に多いのが特徴です。
そのため、先に暗記を済ませてしまうと、試験までの期間でどうしても忘れてきてしまうことがあります。
よって、法規の場合は先に計算問題を練習しておいて、試験まで暗記を続けるという形の方が良いでしょう。
試験直前の勉強時間の最適な使い方
試験直前の勉強時間の最適な使い方は、「実際の試験に近い環境で慣れておくこと」です。
ここまでせっかく長い時間勉強してきたのに、時間に追われて慌てて解答したり、時間内に問題を解ききれなかったら元も子もないですよね。
だからこそ、試験直前は実際の試験と同様の時間で問題を解き、慣れておくことが大切です。
慌てず、落ち着いて勉強したことを発揮できるようにしましょう。
よくある質問
電験三種についてよくある質問に回答していきます。
電験三種はなぜ難しい?
電験三種が難しい理由は、試験範囲が広い上に、深い専門知識が必要だからです。
電験三種では、電気理論、電力、機械、法規の4科目にわたる広範な知識が必要です。それぞれの科目が専門的で深い内容を含んでおり、一つの科目だけでもかなりの勉強時間が必要となります。
特に電気理論や機械の分野では、電気回路や機械の原理を理解するために、高校レベル以上の数学や物理が必要です。
電験三種は、主に発電所や変電所、工場、ビルなどの受変電設備や電気設備を保守・管理することが仕事です。事故やトラブルのないよう安全に使用するためにも、保守・管理する側の人間には厳しい基準が求められます。
電験三種の具体的な難易度や、合格率について知りたい方は「電験三種の難易度・合格率」をご覧ください。
電験三種の申し込み方法は?
電験三種試験の申し込み方法はインターネット申し込みが基本となっています。
ただ、インターネットを利用できないなどのやむを得ない場合は郵送での申し込みも可能です。
電験三種試験の申し込み方法について詳しくは「電験三種試験日|申し込み手順を画像で解説!」をご覧ください。
まとめ
今回は、電験三種に合格するまでに必要な勉強時間や勉強方法について解説しました。
- 電験三種の合格までに必要な総勉強時間は平均600時間
- 科目の得意不得意などでその科目に必要となる勉強時間が変わる
- 科目別合格制度を利用できる
- 試験合格には効果的な勉強スケジュールでコツコツ勉強するのが大切
- スキマ時間や過去問を効率的に活用しよう
電験三種はとても難易度が高い国家資格で、勉強範囲や勉強量も膨大です。
自分に無理のない勉強スケジュールを組み、制度なども効果的に活用しましょう。
先を見て、計画的に勉強していくことが合格への近道です。
電験三種の求人を探す
電験三種のおすすめ求人

ROCKWOOL Japan合同会社
【年間休日120日以上】【社宅あり】断熱材製造工場設備のメンテナンス・改善業務◆二種電工&経験必須/..
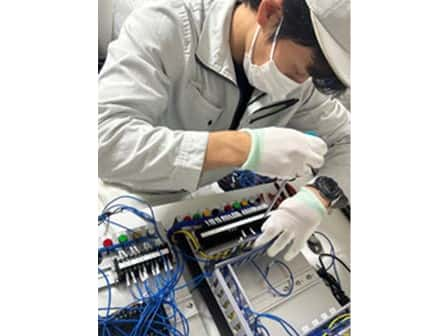
株式会社河北技研
【半導体製造装置の電気配線◇資格経験不問】天理市内の工場常駐\ものづくりに興味がある方歓迎//正社員

瀬川電気株式会社
《ビル・施設の電気保安点検など》経験次第で月給30万円以上も可★夜勤なし<電験三種必須・経験不問>/..

株式会社ボイス
《設備管理》現場は“神奈川県警察本部”というレアな場所!◇二種電工or二級ボイラー技士・経験必須/正..

有限会社加茂電設
★未経験でも月給26万円以上をお約束!【屋内メインの電気・空調工事】資格経験不問《資格取得支援あり》..
電験三種の求人一覧
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする
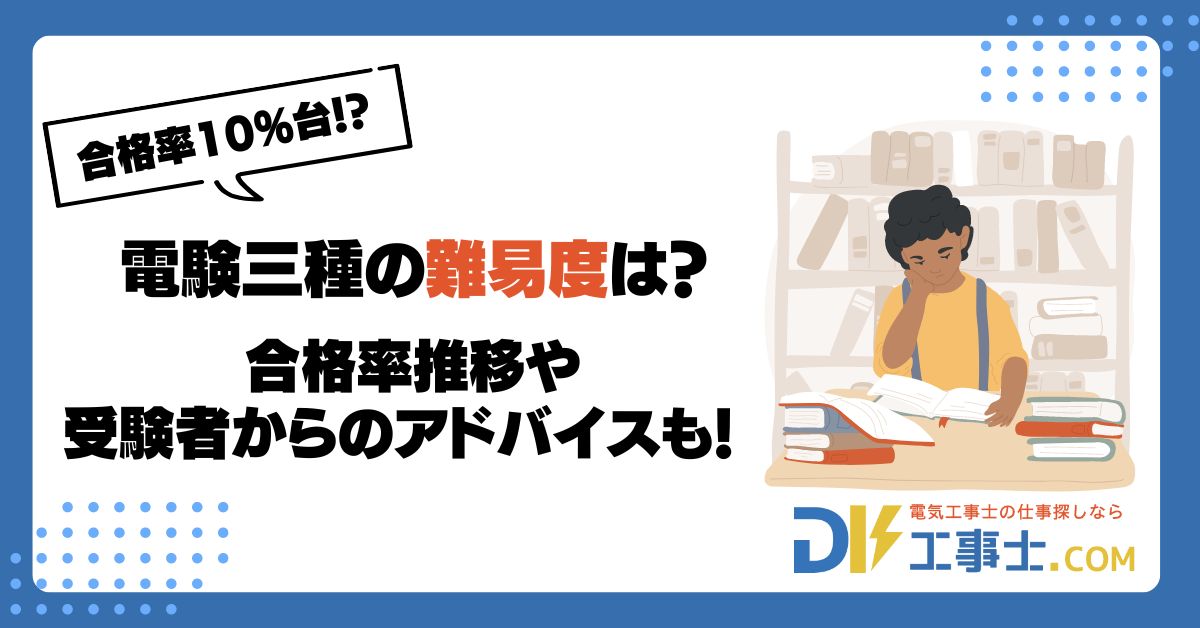
|
電験三種の難易度は高い!合格率推移や受験生の声&合格に向けた対策を紹介
資格
試験
対策
|
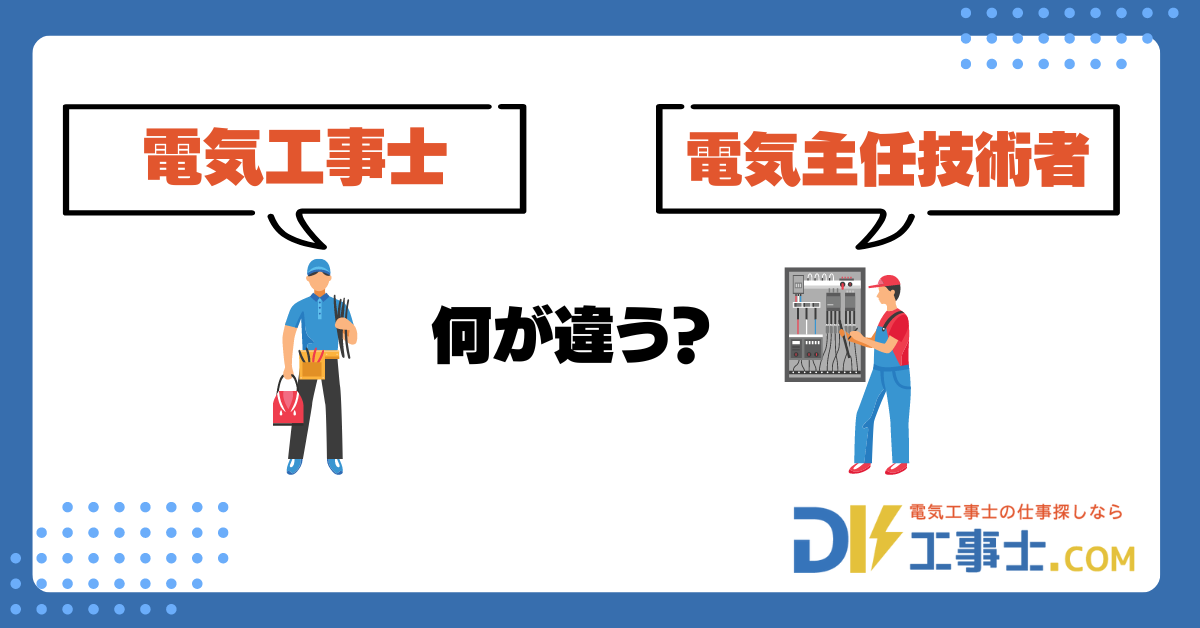
|
【電気工事士と電気主任技術者】仕事内容・難易度・試験内容・年収を比べてみた
電気工事士
第二種電気工事士
第一種電気工事士
資格
仕事内容
|
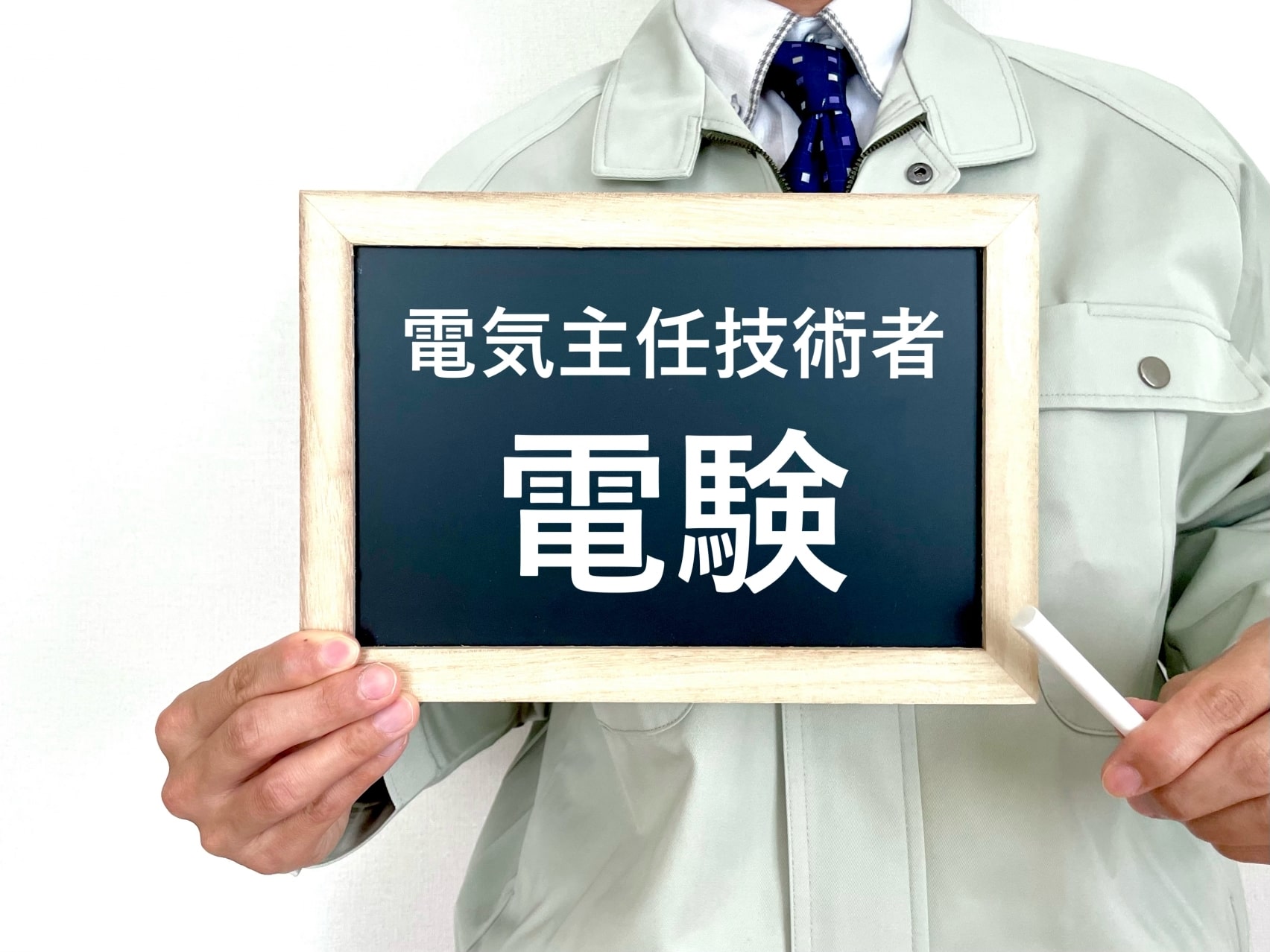
|
電験を取得する前に読んでほしい「電気主任技術者 やめとけ」と言われる理由
資格
待遇
転職・就職
職場環境
仕事内容
|

|
電験三種の年収は400万円~550万円!収入アップのコツや現場の声紹介
給与
転職・就職
活躍
職場環境
仕事内容
|

|
【2024年7月更新】令和6年度の電験三種試験日|申し込み手順を画像で解説!
資格
試験
対策
|