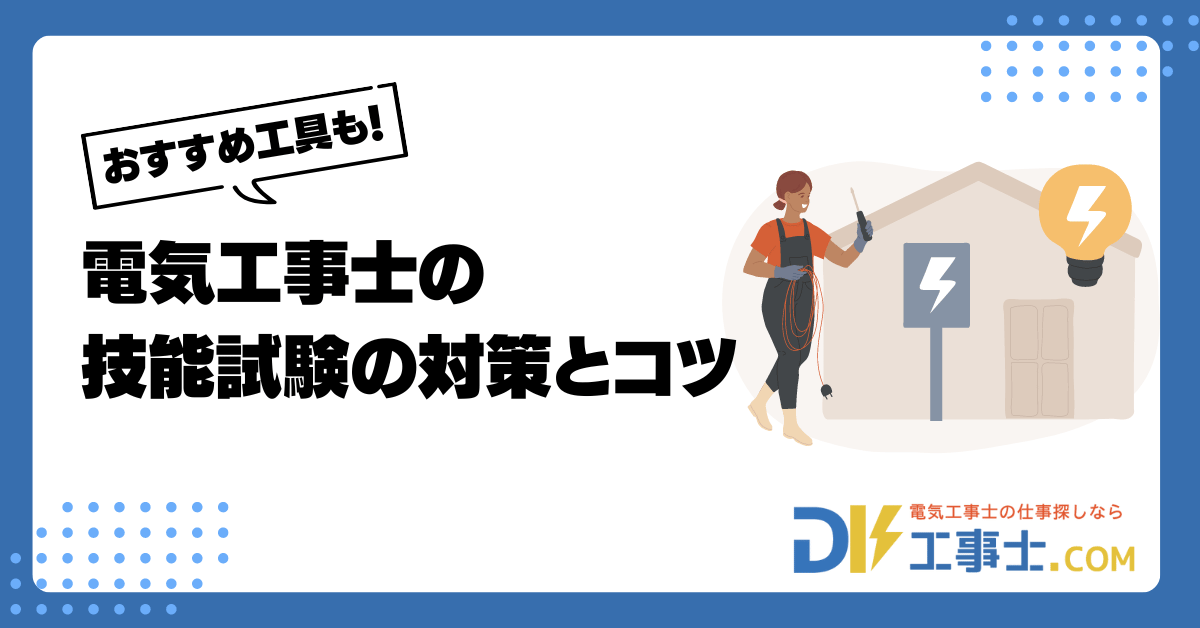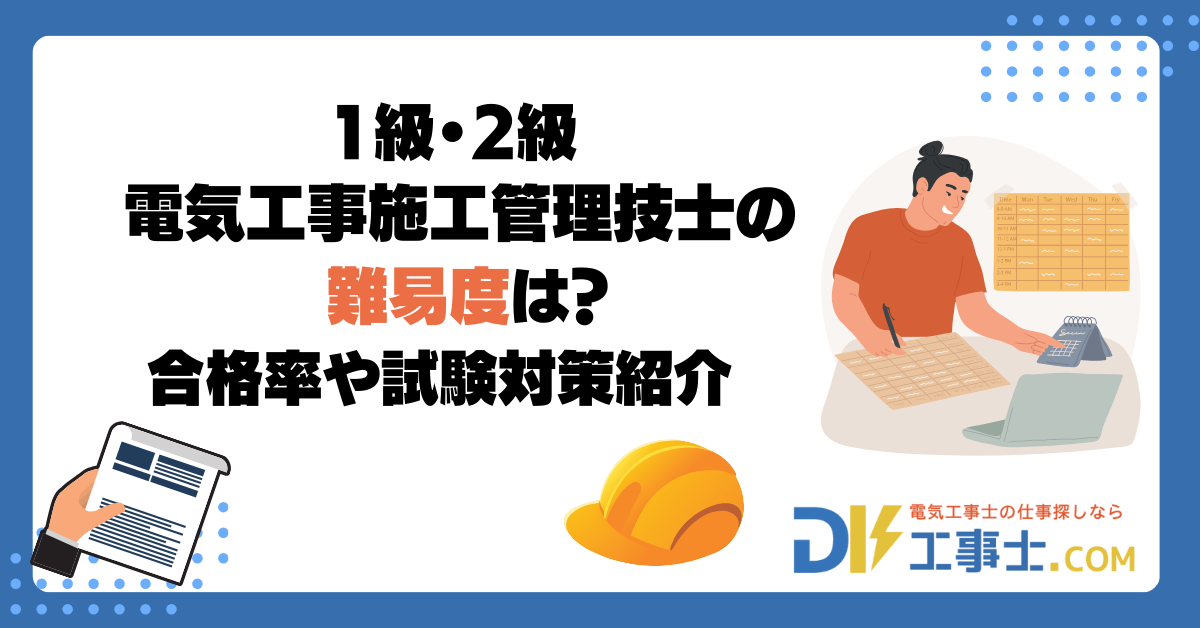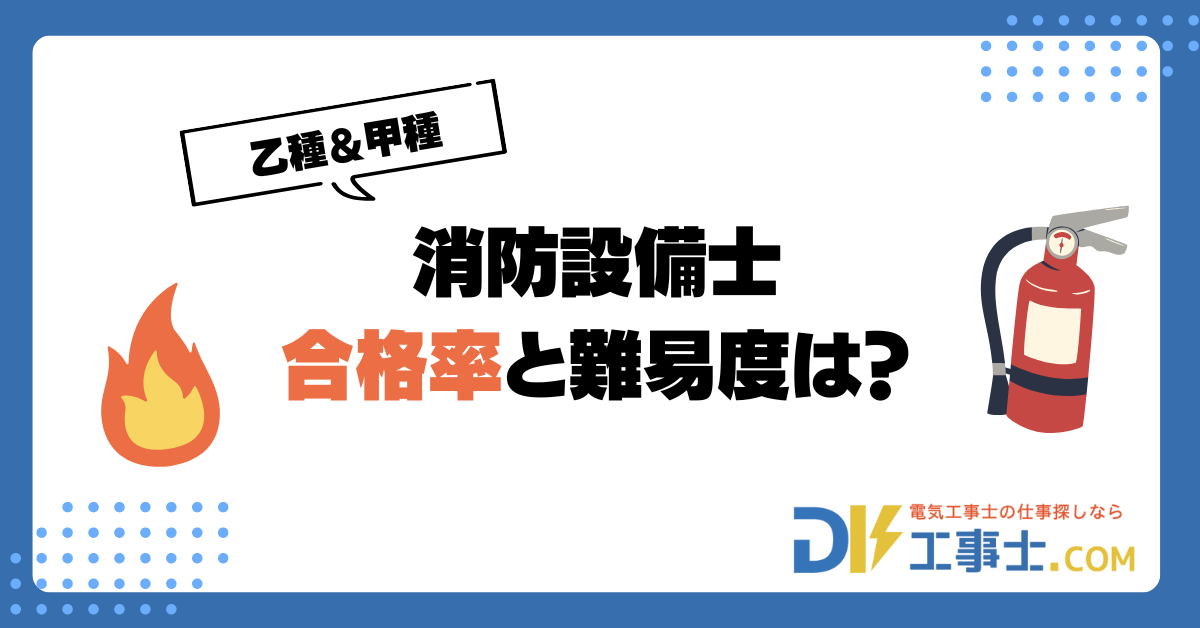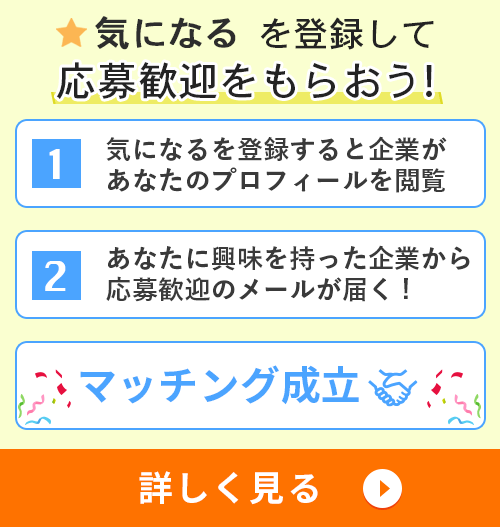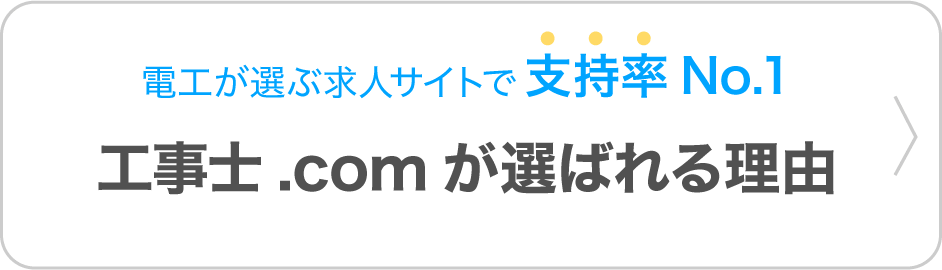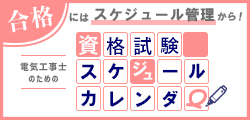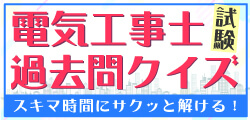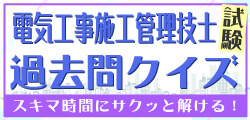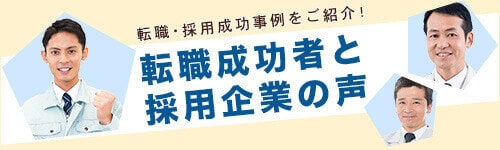DIYするなら第二種電気工事士の資格がおすすめ!取得のメリットや試験情報を解説
電気工事士の資格・試験最終更新日:
DIY好きなら、第二種電気工事士の資格取得を検討してみませんか。
第二種電気工事士の資格を取得することで、照明やコンセントの工事、エアコンの取り付けまで、家の電気周りのDIY作業のほとんどが自分で行えるようになります。
この記事では、DIYにおける第二種電気工事士の資格の価値や魅力を詳しく解説します。
第二種電気工事士の資格取得に向けた具体的な学習方法まで、実践的な情報をご紹介しますので、DIYでできる作業を増やしたいと考えている方はぜひ参考にしてください。
DIYする上で第二種電気工事士を取得するメリット
DIY好きなら、第二種電気工事士の資格取得をぜひ検討してみましょう。
第二種電気工事士の資格を取得することにより、照明やコンセントの工事、さらにはエアコンの取り付けまで、電気周りのさまざまな工事が自分でできるようになります。
DIYする上で第二種電気工事士を取得する具体的なメリットは下記のとおりです。
第二種電気工事士の資格取得のハードルはそれほど高くないため、DIYの世界をぐっと広げる強い味方になってくれるでしょう。
それでは、DIYにおいて第二種電気工事士の資格を取得するメリットを1つずつ詳しく解説していきます。
自分でできる作業が増える
第二種電気工事士の資格を取得すると、家の電気周りにおけるカスタイマイズの自由度がぐんと上がります
なぜなら、第二種電気工事士の資格があれば、電気工事の簡単な作業から本格的な工事までを自分の手で行えるようになるからです。
第二種電気工事士の資格があればできるDIY作業の一例は、下記のとおりです。
■第二種電気工事士の資格があればできる主なDIY作業
- コンセントやスイッチの移設・増設
- 照明器具の取り付け・交換
- エアコンの配線工事
- 屋内外の配線工事
なお、上記の各作業については、本記事内「第二種電気工事士を取得するとできるDIYの作業」で詳しく解説しています。
自宅の電気周りを自分の手で自由にアレンジできる楽しさは、DIY好きにとっては格別でしょう。
電気工事費用を節約できる
第二種電気工事士の資格があれば、電気工事の費用を大幅に節約できます。業者に依頼する場合の費用の多くが人件費のため、自分で工事すれば材料費だけで済むためです。
一般的な工事の費用相場を見てみましょう。
■一般的な工事の費用相場
- コンセントの新設:8,000円~14,000円程度
- 照明器具(シーリングライト)の取り付け:6,000円~10,000円程度
- スイッチの交換:5,000円~15,000円程度
- エアコンの取り付け工事:10,000円~20,000円程度
上記のような工事を自分で行う場合、材料費は数百円から数千円程度で済むことが多いです。
例えば、スイッチの交換なら材料費1個300円前後、シーリングライトであれば安いもので4,000円程度のものが主流です。
より自分好みの家を作れる
業者へ注文するのと比べ、より自分好みの家を作れるのも第二種電気工事士の資格を取得するメリットです。
第二種電気工事士を取得すれば業者に頼らず自分で工事できるため、試行錯誤しながら最適な位置にスイッチを増設したり、照明を設置できたりします。
■よくある電気工事のカスタマイズ例
- 雰囲気のある部屋にするため、間接照明やスポットライトを設置
- キッチン家電の使い勝手を考えたコンセントの配置
- スイッチを入れなくても作動する人感センサー付きライトの設置
- 趣味部屋用の電源設置
例えば、リビングの照明を間接照明に変えたけれど明るさが足りないと感じたら、すぐにスポットライトを追加できます。キッチンでもコンセントの位置が使いづらければ、家電の配置に合わせて増設が可能です。
このように、暮らしながら気づいた不便さをすぐに解消できるのが、DIYにおいて第二種電気工事士を取得することの大きな魅力です。自分の手で何度でも調整できるため、理想の住まいに近づけていく楽しさも味わえるでしょう。
好きなタイミングで作業できる
第二種電気工事士の資格を持っていれば、思い立ったときすぐに電気工事を始められます。
業者の予約や日程調整に縛られず、自分のペースで作業を進められるのがメリットです。
■資格があると便利な場面
- 突然の電気トラブルへの対応
- 休日を利用して計画的に工事ができる
- 夜間の作業も自由にできる
- 工事を少しずつ進められる
例えば、照明の配置を変えようと思い立ったら、その日のうちに作業を始められます。また、コンセントの増設も休日の空き時間を使って少しずつ進められるため、生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
また、工事の途中で計画を変更したくなった場合でも、気兼ねなく作業を中断できます。
自分のアイデアや暮らしのリズムに合わせて柔軟に進められる点は、DIY好きにとって大きな魅力です。
第二種電気工事士を取得するとできるDIYの作業
第二種電気工事士の資格があれば、一般住宅の電気工事のほとんどを自分で行えます。
具体的な作業は下記のとおりです。
では、それぞれの作業について詳しく見ていきましょう。
コンセントの交換・移設・増設

コンセントに関する作業は、第二種電気工事士の資格が役に立つ工事の一つです。古いコンセントの交換から新規設置まで、幅広い工事が可能になります。
■よくあるコンセント工事の例
- 壁付けコンセントの交換
- コンセントの増設工事
- USBポート付きコンセントへの変更
- アース付きコンセントへの交換
- 屋外用防水コンセントの設置
工事の手順も比較的シンプルです。
ただし、配線を接続する際は、作業後に必ずテスターで通電を確認しましょう。また、キッチンなど水回りのコンセント工事では、防水性能のある部材を選ぶことが重要です。
スイッチの交換・移設・増設

スイッチの工事は、住まいの利便性を高める重要なDIY作業です。第二種電気工事士の資格があれば、スイッチの交換から配置変更まで自由自在に行えます。
■取り付けられるスイッチの主な種類
- 通常の壁付けスイッチ
- 人感センサー付きスイッチ
- 調光機能付きスイッチ
- タイマースイッチ
- スマートスイッチ
スイッチは、照明やエアコンなど様々な機器の操作性を向上できるのが魅力です。例えば、階段の上下に人感センサー付きスイッチを設置すれば、手を触れずに照明をつけられます。部屋の入り口に複数のスイッチを設置して、便利な動線を作ることも可能です。
照明器具や引掛けシーリングの交換・移設・増設

第二種電気工事士の資格があれば、照明器具まわりの工事も可能です。器具の交換から配線を伴う移設まで、自分好みの照明を設置できます。
■主な取り付けられる照明の種類
- シーリングライト
- ペンダントライト
- ダウンライト
- スポットライト
- ブラケットライト
- 人感センサー付き照明
引掛けシーリングの場合、器具を回して外し、新しい照明を取り付けるだけの簡単な作業です。一方、ダウンライトは天井に穴を開け、配線を通して器具を設置します。
さらには、キッチンの作業灯として天井にライティングレールを設置したり、廊下に人感センサー付きのダウンライトを並べたりもできます。
暮らしに合わせて照明環境を整備できるのもメリットと言えるでしょう。
エアコンの設置

エアコンの設置も第二種電気工事士の資格があれば自分で行えます。ただし、エアコン設置工事は、電気工事の部分だけでなく配管工事の知識や経験も必要になるため、慎重に進めなければなりません。
■第二種電気工事士の資格でできる主なエアコン設置作業
- 200Vコンセントの設置工事
- 配線の引き込み工事
- アース線の取り付け
- ブレーカーの増設
- 既存エアコンの移設
エアコン工事の手順は複雑なため、初めての方は、配管工事のレンタル工具を借りたり、経験者にアドバイスをもらったりしながら進めるのがおすすめです。
屋内配線の施工
屋内配線の施工は、電気工事の基本となる大切な作業です。第二種電気工事士の資格があれば、分電盤からの配線引き込みや、既存配線の分岐工事なども自分で行えます。
■第二種電気工事士の資格でできる主な屋内配線作業
- VVFケーブルの新規配線
- 既存配線の分岐工事
- 配線の増設工事
- 配線の修理・交換
- 漏電対策の改修
- アース線の施工
配線工事では安全確保が最重要です。ケーブルの被覆を傷つけないよう丁寧に作業を進めましょう。また、将来のメンテナンスを考えて、配線図を残しておくのもおすすめです。
DIYの電気工事の範囲まとめ
DIYの電気工事は、資格の有無や種類によって作業できる範囲が異なります。誰でも取り付けられる照明器具もあれば、第二種電気工事士の資格が必要な配線工事もあります。さらには、第二種電気工事士の資格では行えない作業もあります。
ここでは、DIYで電気工事をする際の作業範囲について、詳しく説明していきます。
資格なしでできる工事
配線工事を伴わない簡単な電気工事であれば、電気工事士の資格がなくても行えます。電気工事の対象とならない工事は、電気工事士法で「軽微な工事」として定められています。
■資格なしでできるDIYの電気工事
- シーリングライトの取り付け・交換
- プラグ式の照明器具の取り付け
- 電球や蛍光灯の交換
- コンセントカバーの交換
- 延長コードの使用
- 電池式機器の設置
ただし、電気工事士の資格がない場合は以下の条件を守って工事しなければなりません。
- コードやプラグが最初から付いている製品であること
- 配線工事を必要としない取り付け作業であること
- 工具を使わない簡単な作業であること
例えば、天井の引掛けシーリングに照明を付けるだけなら資格は不要です。しかし、新しくコンセントを増やしたり、スイッチを交換したりする工事には電気工事士の資格が必要です。
■関連記事
電気工事の資格なしでできる工事については「資格なしでもできる”軽微な電気工事”って?無資格OKの範囲と罰則も解説」でも解説していますので、ぜひご覧ください。
第二種電気工事士の資格でできるDIYの電気工事
第二種電気工事士の資格があれば、一般住宅の電気工事のほとんどを自分で行えます。しかし、第二種電気工事士の資格でできるのは、法律で定められた600V以下の低圧電気工事に限ります。
■第二種電気工事士ができる工事の範囲
- 一般住宅での電気工事全般
- 小規模店舗の電気設備工事
- コンセントの設置・移設・交換
- 照明器具の取り付け・配線工事
- エアコンの配線・設置工事
- 分電盤の交換や増設
- 屋内外の配線工事
なお、第二種電気工事士の資格があっても、工事内容によっては専門業者に依頼した方が安全な場合もあります。自分のスキルを把握し、無理のない範囲で作業することが大切です。
■関連記事
第二種電気工事士が行える業務範囲については「【第二種電気工事士とは】できることは?仕事内容・メリット・試験内容を解説!」でも解説しています。
第二種電気工事士の資格ではできない工事
第二種電気工事士は、高圧電気を扱う工事や大規模な電気設備の工事はできません。これらの工事には、第一種電気工事士や認定電気工事従事者などの上位資格が必要になります。
■第二種電気工事士ができない工事の一例
- 太陽光発電システムの設置工事
- 自家用発電設備の設置工事
- マンションの共用部分の工事
- ネオン看板の設置工事
- 600Vを超える電圧を使用する設備
- 最大電力が500kW以上の需要設備
- 高圧受電している建物内の工事
法律で定められた範囲を超える工事を行うと違法となり、事故の危険性も高まります。自分の資格で対応できない工事は、必ず適切な資格を持つ専門家に依頼しましょう。
■関連記事
第二種電気工事士の試験概要
第二種電気工事士の試験は、学科試験と技能試験の2段階で実施されます。電気の基礎知識を問う筆記試験と、実際の工具を使う技能試験に合格できれば、第二種電気工事士の免状が交付されます。
第二種電気工事士は年2回の受験チャンスがあり、合格率は約60%と比較的高めです。受験資格は特になく、学歴や実務経験も不問なため、誰でもチャレンジできる国家資格として人気があります。
ここからは、試験の具体的な内容について詳しく見ていきましょう。
基本情報
第二種電気工事士試験は、学科試験(筆記・CBT)と技能試験の2段階で実施される国家資格です。
電気の基礎知識を問う学科試験と、実際の工事作業を行う技能試験に分かれており、難易度は電気系の資格の中では比較的低めとされています。
■第二種電気工事士の試験概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験の基本情報 |
受験資格:なし(誰でも受験可能) 実施回数:年2回(上期・下期) 受験料:9,300円(インターネット申込) 免状交付条件:なし |
| 学科試験の概要 |
試験時間:2時間 問題数:50問(四択式) 合格基準:60点以上 合格率:約60% |
| 技能試験の概要 |
試験時間:40分 課題数:1問(候補問題13問から出題) 採点基準:欠陥がないこと 合格率:約70% |
資格取得の流れ
第二種電気工事士は、申し込みから免状交付まで、一般的には約6ヶ月の期間を要し、学科試験と技能試験の2段階の試験に合格後、免状を申請できます。
■第二種電気工事士取得までの主な流れ
- 試験の申し込み
- 学科試験の受験(筆記またはCBT方式)
- 学科試験の合格発表(筆記:約1ヶ月後、CBT方式:2週間後)
- 技能試験の受験
- 技能試験の合格発表(約1ヶ月後)
- 免状交付申請
- 免状取得
第二種電気工事士は年2回の受験機会があるため、不合格の場合も次回チャレンジできます。また、学科試験に合格していれば、次回実施される試験で学科試験が免除されるため、ぜひ活用しましょう。
■関連記事
詳しい資格取得の流れについては、「電気工事士資格の取り方を解説!電気工事士になるにはまず何をする?」にてご確認ください。
試験日程
第二種電気工事士の試験は年2回実施されるため、上期と下期で受験機会があります。
■第二種電気工事士 2025年度の試験日程
| 2025年度 上期試験 | 2025年度 下期試験 | |
|---|---|---|
| 申込期間 | 3月17日(月)~4月7日(月) | 8月18日(月)~9月4日(木) |
| 学科試験(CBT) | 4月21日(月)~5月8日(木) | 9月19日(金)~10月6日(月) |
| 学科試験(筆記) | 5月25日(日) | 10月26日(日) |
| 技能試験 | 7月19日(土)または 7月20日(日) |
12月13日(土)または 12月14日(日) |
※参考:第二種電気工事士試験(一般財団法人 電気技術者試験センター)
よくある質問
DIYのために第二種電気工事士試験を受験しようと考えている方々によくある質問をご紹介します。
第二種電気工事士の資格は初心者でも取得できますか?
第二種電気工事士は未経験の方でも十分取得できる資格です。合格率は学科試験が約60%、技能試験が約70%と、他の国家資格と比べて比較的高めです。
独学でも合格を目指せますが、初心者なら約50〜150時間の学習時間が必要です。
また、技能試験では電工ナイフやペンチなどの工具を使う作業があります。そのため、事前に練習用の工具を揃え、作業に慣れておくことをおすすめします。
第二種電気工事士の資格は女性でも取得できますか?
第二種電気工事士は、もちろん女性でも取得できる資格です。実際に、電気工事の現場で活躍する女性も年々増えています。
また、第二種電気工事士試験の女性の受験者も増加傾向にあります。技能試験では工具を使う作業がありますが、コツをつかめば体力的な問題もほとんどありません。
性別を気にせず、積極的にチャレンジしてみましょう。
まとめ
今回は、DIYにおける第二種電気工事士資格のメリットや試験の概要などについて詳しく解説しました。
- 第二種電気工事士の資格を取得すると、自分で電気工事ができるためDIYの幅が広がる
- DIYをする上で第二種電気工事士の資格を取得するメリットは、「自分でできる作業が増える」「電気工事費用を節約できる」「より自分好みの家を作れる」「好きなタイミングで作業できる」など
- 第二種電気工事士を取得するとできるDIYの主な作業は、「コンセントの交換・移設・増設」「スイッチの交換・移設・増設」「照明器具や引掛けシーリングの交換・移設・増設」など
- 第二種電気工事士の資格は受験資格がなく、試験の合格率も約60%と比較的高いため、初心者でも取得しやすい
第二種電気工事士は、DIY好きにとって強い味方となる資格です。自分のペースで作業でき、理想の住まいづくりを実現できます。また、電気工事の基本を学べるため、DIYを安全に行う上でも役立ちます。
興味のある方は、ぜひ第二種電気工事士試験にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
おすすめ求人

株式会社真翔
【工場での電気工事/資格経験不問】未経験でも月給25万円~/残業月平均3h/直行直帰OK★/正社員

有限会社羽鳥電気商会
【電気設備工事◎現場は多摩メイン】賞与6ヶ月分/残業ほぼナシ/各種手当アリ/資格経験不問★経験者優遇..

中村電設工業株式会社
《賞与実績は最大300万円》大手企業・官公庁との取引豊富◆電気工事士&現場代理人/二種電工・経験必須..

ENERCON Services Jap
【風力発電機の保守・メンテナンス/資格経験不問】#大手グローバル企業の日本法人#年間休日124日/正..

株式会社石電設
《集合住宅の電気工事/修繕・改修》年間休日121日◆大手一次請けで業績安定の安心環境【資格経験不問】..
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする

|
【第二種電気工事士とは?】できることや第一種との違い・資格取得メリットを解説
第二種電気工事士
資格
試験
対策
活躍
|
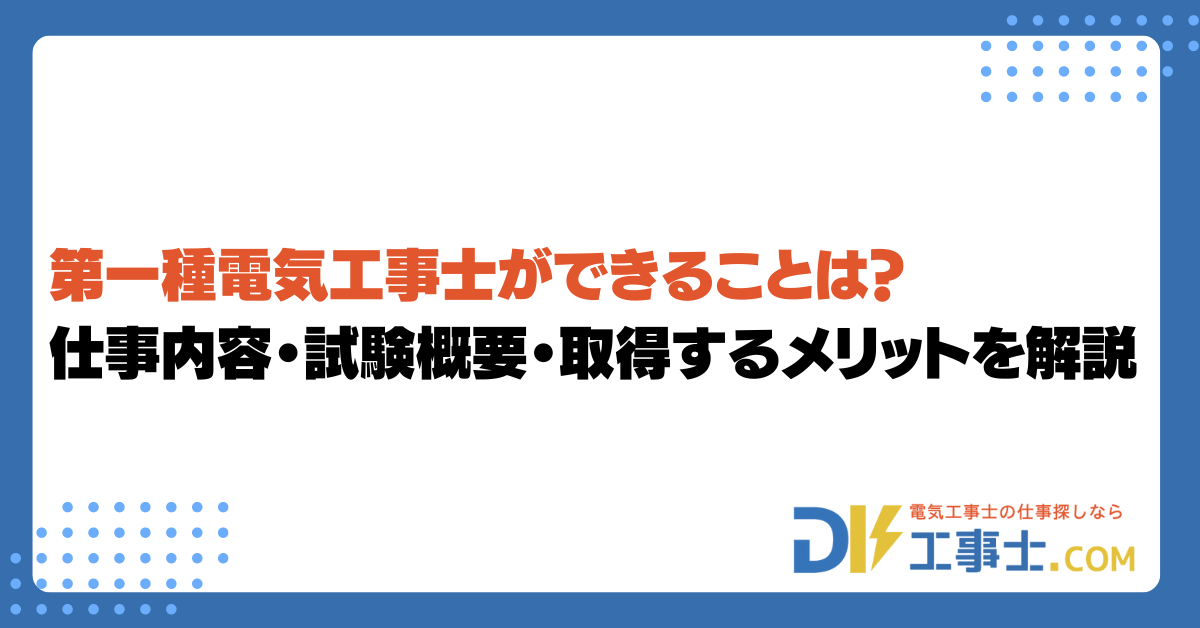
|
第一種電気工事士とは?仕事内容や第二種との違いから試験概要や勉強時間まで徹底解説
電気工事士
第一種電気工事士
資格
対策
仕事内容
|
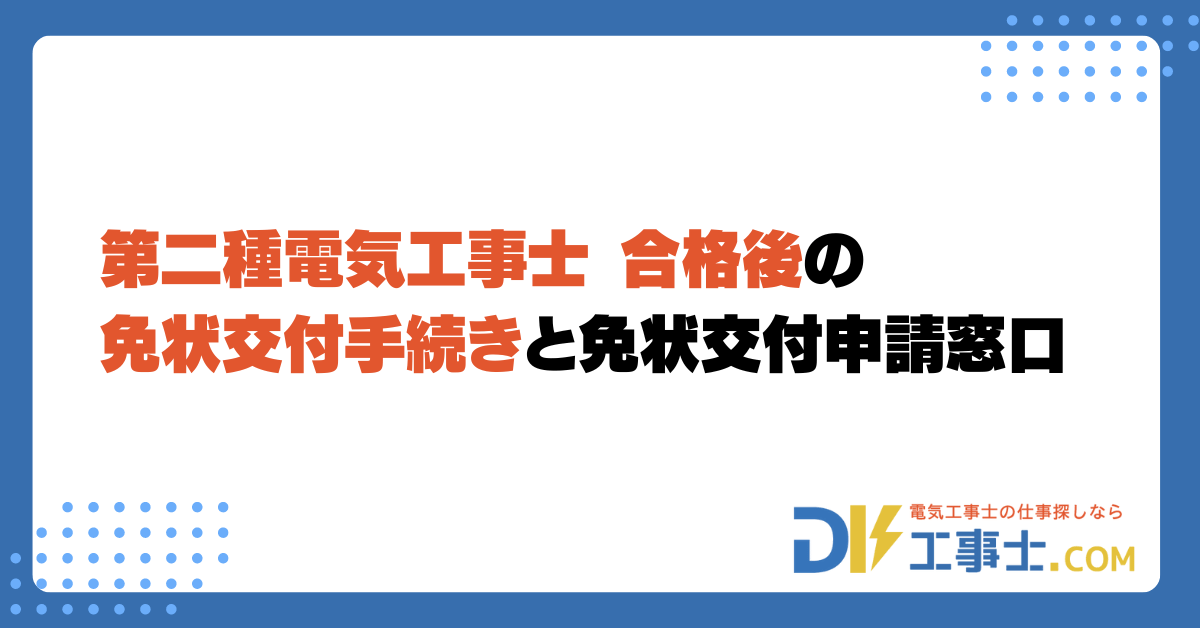
|
第二種電気工事士合格後の免状交付手続きを詳しく解説!申請期限や窓口情報まとめ
第二種電気工事士
資格
試験
|
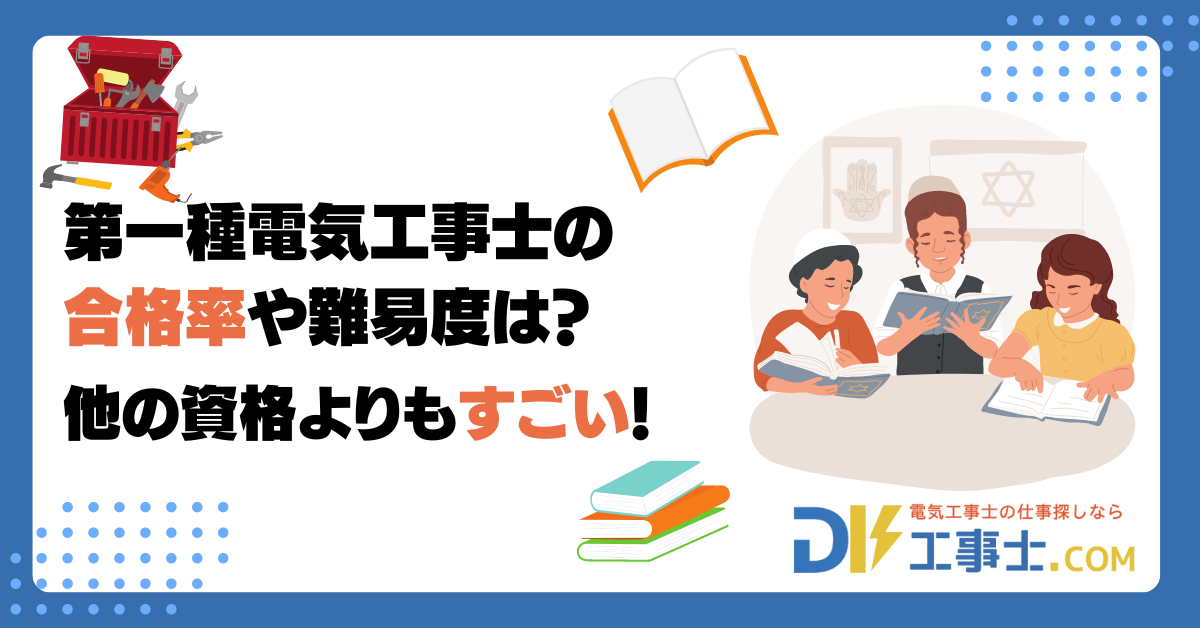
|
【実はすごい】第一種電気工事士の合格率は約56%!難易度を他資格と比較して解説
第一種電気工事士
資格
試験
|
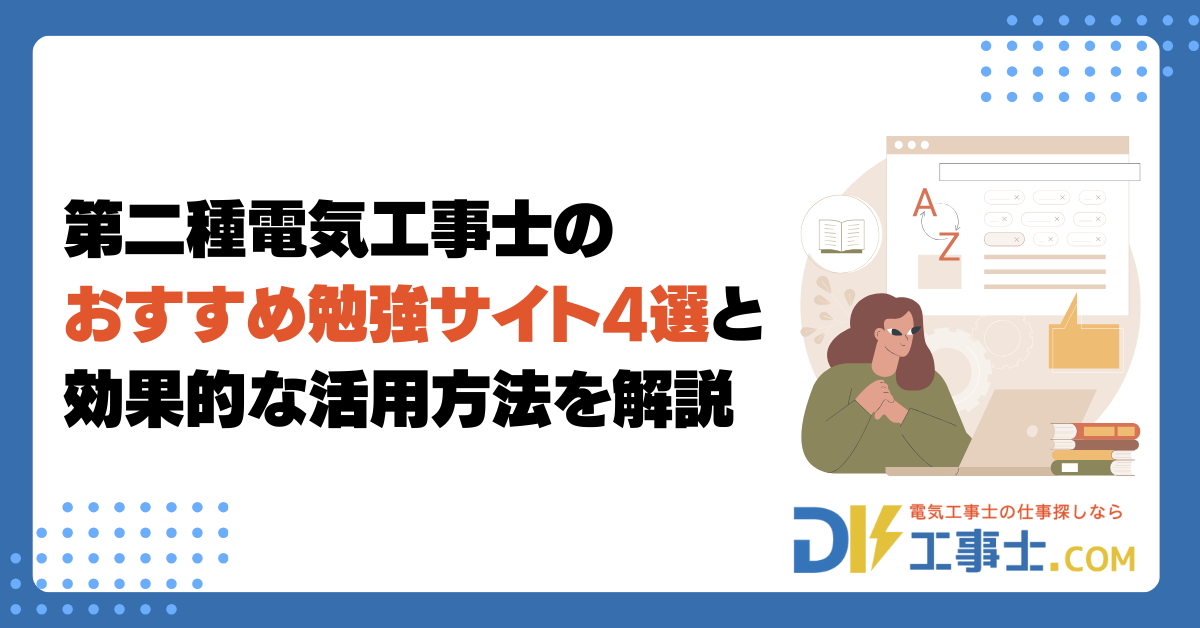
|
【無料】第二種電気工事士のおすすめ勉強サイト一覧!効果的な活用方法も解説
第二種電気工事士
試験
|