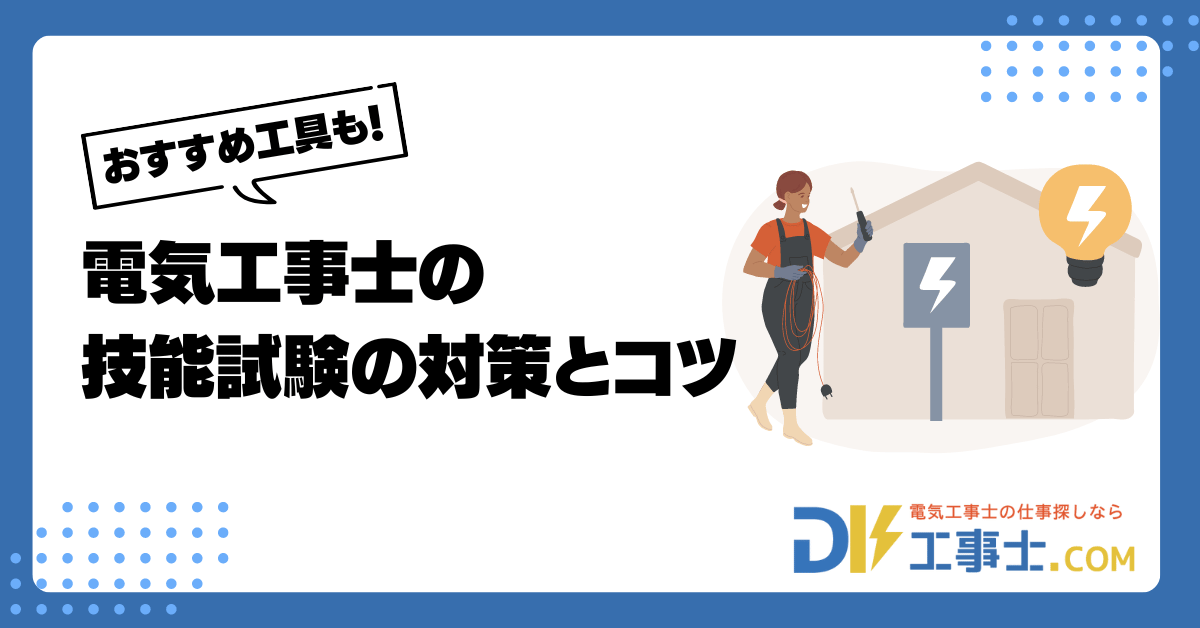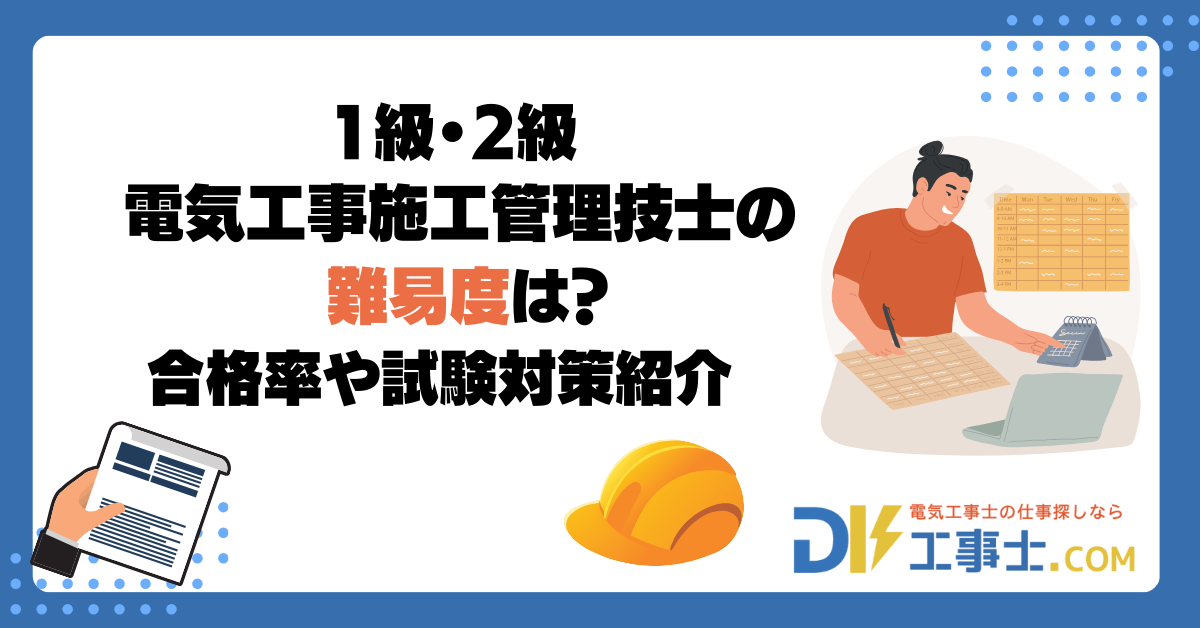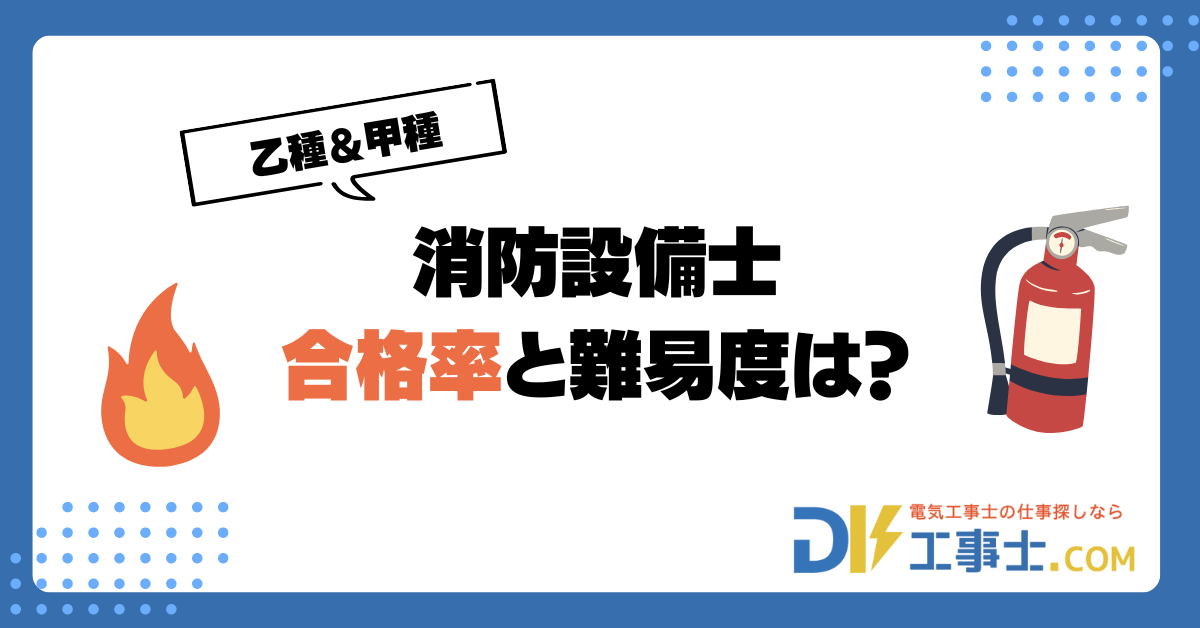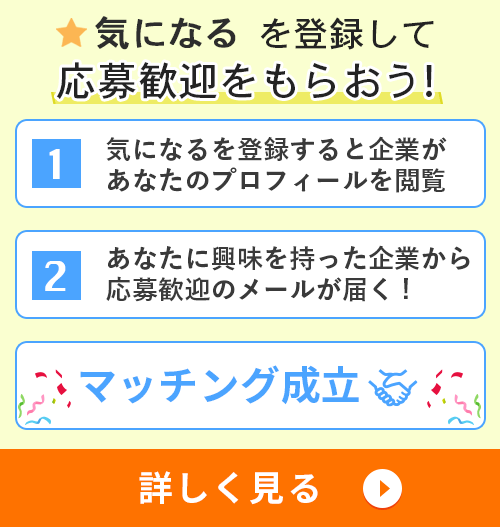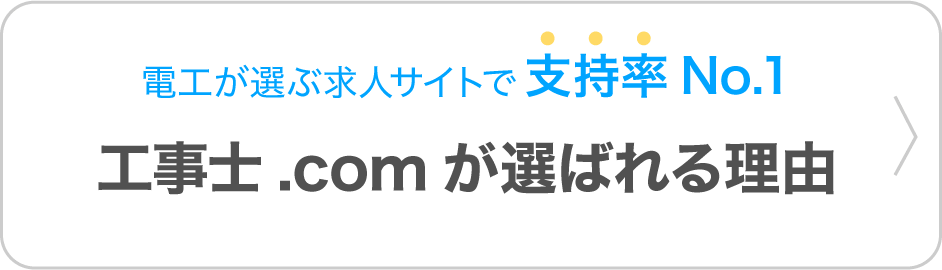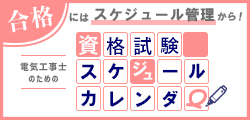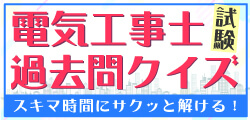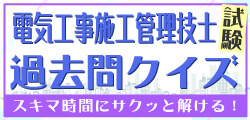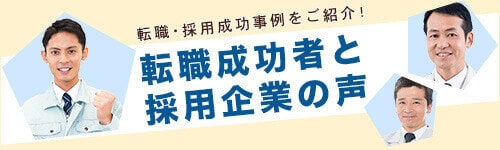第二種電気工事士の技能(実技)試験は練習なしでの合格は難しい!効率的な練習方法を紹介
電気工事士の資格・試験最終更新日:
第二種電気工事士の技能(実技)試験を練習なしで突破するのは、極めて困難です。
この試験では知識だけでなく、確かな技術力と制限時間内で作業を完了する段取り力が求められるためです。
本記事では、第二種電気工事士の技能(実技)試験が練習なしでは難しい理由や、合格までのステップなどについて解説します。
この記事を参考に技能(実技)試験への不安を解消し、計画的な対策で合格を目指しましょう。
■関連記事
■電気業界の求人なら工事士.com!!
- 電気業界に特化した求人が多数
- 資格が活きる仕事が見つかる
- 気になる企業から応募歓迎機能あり
第二種電気工事士技能(実技)試験は練習なしでの合格は難しい!5つの理由
第二種電気工事士の資格取得を目指す上で、多くの方が直面する課題が技能(実技)試験です。
結論から申し上げると、技能(実技)試験を練習なしで合格するのは非常に困難です。
なぜなら、技能(実技)試験は単に知識を問うものではなく、正確な技術と制限時間内での作業遂行能力が厳しく評価されるためです。
ここでは、第二種電気工事士の技能(実技)試験が練習なしでの合格は難しいとされている、5つの理由について解説します。
公表される候補問題が多い
第二種電気工事士の技能(実技)試験が練習なしでの合格が難しい理由には、公表される候補問題の多さにあります。
例年、事前に候補問題が13問公開されますが、試験当日までどの問題が出題されるかは分かりません。
これらの候補問題は、それぞれ独自の課題設定がされています。
例えば以下のような点が異なります。
■実技試験 候補問題の課題設定の一例
- スイッチの数や回路構成の複雑さ
- アウトレットボックスのような、施工に時間と手間を要する器具の有無
- 使用する電線の種類、指定寸法、接続方法
- 接地線の種類や接続箇所など、施工条件で指定される細かな指示
練習なしでは、各問題特有の課題を的確に把握しながら作業を進めることは難しいです。また、ぶっつけ本番では焦りから思わぬミスを招く可能性も高まります。
そのため、全パターンの問題に触れ、それぞれの特性を理解するための反復練習が必要です。
複線図を書く練習をしなければならない
複線図は、配線図(単線図)から実際の電線の接続を示す、いわば電気工事の設計図です。
したがって、「複線図」を作成する練習を怠ると、合格は遠のくと言っても過言ではありません。
複線図が不正確だと、以下のような致命的なミスに直結します。
■実技試験で複線図が不正確だった場合に起こりうるミス
- 誤接続:電線を間違った箇所に接続してしまう
- 配線ミス:回路が正しく動作しない配線をしてしまう
上記のミスは、どちらも一発で不合格になってしまいます。
学科試験で知識を習得しても、制限時間内に正確な複線図を描くスキルは、手を動かす練習でしか養われません。特に初めて見る問題や複雑な回路に対し、短時間で正確な複線図を描くには反復練習が重要になります。
■関連記事
複線図の書き方については、「【実例あり】複線図の書き方5ステップ!第二種電気工事士試験に受かるコツまで」で詳しく解説しています。
工具の基本的な作業を練習しなければならない
第二種電気工事士の技能(実技)試験では、工具で行える基本的な作業を練習しなければ合格するのは難しいでしょう。
例えば、以下のような基本的な工具作業は、適切な力加減や手順、高い精度が求められます。
■ 実技試験で使用する工具と基本作業
| 工具 | 主な作業内容 |
|---|---|
| ペンチ | 電線の切断・曲げ加工、器具への固定、輪作りなど |
| プラスドライバー | ネジ締め(コンセント・端子台・ランプレセプタクルなど) |
| マイナスドライバー | ネジ締め、器具の取り外し |
| 電工ナイフ | 電線の被覆剥き ※VVFストリッパーも同様 |
| 圧着工具 | リングスリーブの圧着(電線同士の接続) |
工具の扱いに不慣れだと作業に時間がかかるだけでなく、心線の損傷や被覆の剥き過ぎ、電線の圧着不良などのミスにつながる危険性もあります。
したがって、質の高い作業を行うためには、工具を使用した反復練習が欠かせません。
■関連記事
第二種電気工事士技能(実技)試験で使用する工具については「第二種電気工事士の【指定工具7点】+【1点】で技能試験(実技)を有利に進めよう!」で詳しく解説しています。
制限時間内に完成させる練習をしなければならない
40分という厳しい制限時間の中で作品を完成させなければならないという点も、第二種電気工事士の技能(実技)試験が練習なしで難しいとされている理由です。
40分の間に、以下の作業を終了させる必要があります。
■実技試験の制限時間内に行わなければならない作業
- 複線図の作成
- 材料の切断、ケーブルの被覆剥き
- 器具への取り付け、電線の結線
- 作品全体の最終確認
技能(実技)試験の練習をしていないと、各作業にかかる時間や効率的な手順が分からず、時間配分が全く掴めません。
また、試験特有の緊張感によって、手の震えや焦りから普段は起こりえないミスが発生しやすくなります。
その結果、作業が雑になったり、最悪の場合は未完成で時間切れになったりする可能性が高いです。
繰り返し練習することで作業の流れを体で覚え、ペース配分を掴めるようになると、合格へ近づくことができるでしょう。
1つでも欠陥があると不合格になってしまう
第二種電気工事士技能(実技)試験の合否判定は非常に厳しく、たった一つでも欠陥があれば即不合格になります。
そのため、練習なしで合格するのは、かなり至難の業と言えるでしょう。
合格するためには、事前に公表されている「欠陥の判断基準」をしっかりと確認し、それに該当しないよう一つ一つの作業を正確に行わなければなりません。
欠陥とされる項目には、以下のようなものがあります。
■実技試験の主な欠陥
- 誤接続・誤結線
- 電線の損傷(心線キズ、被覆の剥きすぎなど)
- リングスリーブの圧着不良(刻印ミス、圧着不足)
- 寸法の誤り(指定より短いなど)
- 器具の破損や取り付け不良
欠陥作品を作らないためには、各作業の正しい手順を熟知し、常に欠陥条件を意識しながら細心の注意を払う必要があります。
しかし、どれだけ注意していてもミスを犯す可能性はゼロではありません。練習を重ねることで、どのような点が欠陥につながりやすいかを覚えられるようになります。また、作業後の見直しやセルフチェックの習慣を身につけることで、欠陥なく作品を作ることができるでしょう。
■関連記事
「第二種電気工事士技能試験の欠陥とは?事例と対処法を写真付で分かりやすく解説!」では、第二種電気工事士技能(実技)試験の「欠陥」を1つずつ詳しく解説しています。
\ 合格前から求人情報をチェックしよう! /
※登録不要で求人を探せます
第二種電気工事士技能(実技)試験の合格に必要な目安
第二種電気工事士の実技試験に合格するためには、実技練習が欠かせません。
ここでは、第二種電気工事士技能(実技)試験合格に向けて一般的に必要とされる「練習時間」と「材料」の目安について解説します。
記事を参考に、自分に適した計画を立て、自信を持って技能(実技)試験に臨みましょう。
練習時間
第二種電気工事士の技能(実技)試験合格に必要な練習時間は、一般的に50時間から60時間程度が目安とされています。
ただし、個人の経験や手先の器用さ、学習の進捗度によって練習時間は大きく変動します。
■実技試験の練習時間の目安
- 電気工事未経験者や作業に不慣れな方
工具の扱いに慣れるところから始まり、各候補問題の作業手順を一つ一つ確実に習得していく必要があるため、目安よりも多くの時間が必要となる傾向がある - 電気工事経験者や手先が器用な方
基本的な工具の扱いや作業勘が既に備わっている場合、比較的短時間で合格レベルに到達することも可能
目標とすべきレベルは、「40分の制限時間に対し、どの候補問題が出題されても30分程度で欠陥なく作品を仕上げられる」状態です。30分の中には、作業開始前の複線図の作成時間(5分以内が目安)も含まれます。
毎日少しずつでも工具に触れて練習を継続することが、技術を習得し、自信を持って本番に臨むための確実な方法です。
材料量
技能(実技)試験対策においては、練習に適切な量の材料を準備することも重要です。
一般的には、材料セットは候補問題を最低2周できる量がおすすめと言われています。
なぜなら、最初の1周では全体の作業手順を覚え、2周目以降で時間内に作業を終わらせたり欠陥を出さずに完成させたりする練習が必要なためです。
練習の進め方と必要な材料量の目安は、以下のとおりです。
■実技試験 練習の進め方と必要な材料の目安
- 1周目の練習(基本の理解とスキルの上達)
・各候補問題の作業手順、電線の寸法、接続方法、注意点などを把握する
・工具の基本的な使い方に慣れ、一つ一つの作業を丁寧に行う - 2周目以降の練習(実践力の向上と時間短縮)
・実際の試験時間を意識し、40分以内に欠陥なく完成させることを目指す
・苦手な作業を重点的に繰り返し練習し、精度を高める
・ミスを減らし、候補問題ごとの作業順番を決めておく
なお、練習中には電線を切り間違えたり、器具を破損したりすることもあるため、2回分以上の材料があると安心でしょう。
また、なるべく材料を節約したい方は、一度使用した電線やケーブルを再利用して練習するのもおすすめです。
\ 合格前から求人情報をチェックしよう! /
※登録不要で求人を探せます
第二種電気工事士技能(実技)試験をなるべく練習なしで合格するためのポイント
第二種電気工事士技能(実技)試験の練習時間を最小限に抑えつつ、合格の可能性を高めるための2つの重要なポイントを解説します。
ポイントを意識することで、限られた時間の中でも効果的な対策が取れるでしょう。
学科試験勉強の時点で複線図をマスターしておく
技能(実技)試験の練習時間を短縮したいのなら、学科試験の段階で「複線図」をマスターしておくことが大事です。
なぜなら、複線図は実技試験における作業全体の設計図であり、正確に素早く描けなければ、その後の全ての作業に支障をきたすためです。
学科試験の範囲には複線図の基本的な知識が含まれていますが、単に理解するだけでなく、実際に手を動かしてスラスラと描けるレベルに到達することが重要です。
どの候補問題が出ても5分以内に正確な複線図を完成させられるスキルを学科のうちに身につけておけば、複線図の練習時間を省き、実技練習にのみ時間をかけられます。
スキマ時間に動画を視聴してイメージトレーニングしておく
実技練習の時間が取れない場合、スキマ時間を活用したイメージトレーニングが効果的です。
技能(実技)試験の実演動画を視聴し、頭の中で作業をシミュレーションしてみましょう。
実演動画を見ることで、以下の作業を視覚的に学べます。
■実技試験の実演動画で効果的に学べること
- 正確な作業手順
- 適切な工具の扱い方
- 注意すべきポイント
例えば、VVFストリッパーでの被覆剥き、ランプレセプタクルの輪作り、リングスリーブの圧着といった具体的な作業を映像で確認し、自分が作業している姿を思い浮かべます。
また、各候補問題の工程を何度も頭の中でリハーサルすることで、本番でのスムーズな作業が可能になるでしょう。
\ 合格前から求人情報をチェックしよう! /
※登録不要で求人を探せます
第二種電気工事士技能(実技)試験 合格までのステップ
第二種電気工事士の技能(実技)試験に合格するためには、やみくもに取り組むのではなく、段階的に練習していくことがおすすめです。
ここからは、技能(実技)試験の合格までに必要なステップを4つに分けてご紹介します。
各ステップを一つずつ着実にクリアしていくことが、合格へと繋がります。
1.工具と材料を揃える
技能(実技)試験対策の第一歩は、必要な工具と練習用材料を揃えることです。
指定工具であるペンチ、ドライバー、電工ナイフ、圧着工具などに加え、作業効率を上げるVVFストリッパーなども準備しましょう。
材料は、候補問題全13問を練習できるセットが市販されています。自分に合った工具を選び、練習に必要な材料を確保することが、第二種電気工事士実技試験の合格に向けた最初のステップになります。
■関連記事
工具や材料の揃え方については、「第二種電気工事士の【指定工具7点】+【1点】で技能試験(実技)を有利に進めよう!」で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
2.候補問題の複線図を覚える
次に、技能(実技)試験の設計図とも言える「複線図」の作成をマスターします。
電気技術者試験センターから公表される候補問題の単線図を見て、正確な複線図を素早く描けるように練習を重ねましょう。複線図の理解度と作成スキルが、その後の作業の正確性とスピードを大きく左右します。
各候補問題の複線図をしっかりと覚えることが、合格への重要なポイントです。
■関連記事
複線図の詳しい書き方については、「【実例あり】複線図の書き方5ステップ!第二種電気工事士試験に受かるコツまで」をご覧ください。
3.候補問題を1周練習する
いよいよ候補問題の作成練習に取り掛かります。
まずは全13問の候補問題を、時間を意識せずに一通り作成してみましょう。
この段階では、各問題の作業手順や注意点、工具の基本的な使い方を確実に身につけることが目的です。
実際に手を動かすことで、各作業の理解が深まり、課題を見つけられる可能性もあります。
■関連記事
練習するのに必要な工具や勉強方法については、「第二種電気工事士の技能試験(実技)とは?必要な工具や勉強方法と独学について解説!」にて解説しています。
4.欠陥条件を確認しながら何度も復習する
候補問題を一通り練習したら、次は欠陥条件を確認しながら何度も復習します。
電気技術者試験センターが公表している欠陥の判断基準を読み込み、どのような作業が欠陥になるのかを正確に把握しましょう。
また、過去に自分が犯したミスや欠陥が起きやすい工程を意識しながら、繰り返し練習することが合格への最終ステップです。
■関連記事
欠陥事例と対処法については、「第二種電気工事士技能試験の欠陥とは?事例と対処法を写真付で分かりやすく解説!」で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
\ 合格前から求人情報をチェックしよう! /
※登録不要で求人を探せます
よくある質問
第二種電気工事士の技能試験受験にあたり、よくある質問と回答をまとめました。
事前に不安を疑問を解消し、安心して試験対策に取り組めるように、詳しく解説していきます。
技能(実技)試験は毎年同じ問題が出題される?
第二種電気工事士の技能(実技)試験は、毎年同じ問題がそのまま出題されるわけではありません。
電気技術者試験センターから事前に13問の「候補問題」が公表され、試験当日はこの中から1問が選ばれて出題されます。どの候補問題が選ばれるかは試験会場によって異なるため、当日までわかりません。
しかし、候補問題自体はここ数年、大きな変更はなく、ほぼ同じ内容のものが繰り返し出題されています。
そのため、全ての候補問題をしっかりと練習し、それぞれの施工条件や作業手順をマスターしておくことが合格へとつながるでしょう。
技能(実技)試験に落ちたらどうなる?
万が一、技能(実技)試験に不合格となった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
第二種電気工事士試験は年に2回(上期・下期)実施されており、再受験が可能です。また、学科試験の合格は2年間有効で、その期間内は技能試験のみを受験できます。
しかし、まずは何が原因で技能試験に落ちたのかを冷静に分析することが大切です。反省点を踏まえて、次回の試験に向けて練習を再開しましょう。
■関連記事
再試験に挑む場合は、「第二種電気工事士の技能試験に落ちた原因は?よくある失敗や再試験への対策を解説!」を確認し、次回に向けた対策を考えましょう。
技能(実技)試験に合格するコツは?
第二種電気工事士技能(実技)試験に合格するためのコツは、事前の準備と練習を徹底することです。
まず、公表されている全13問の候補問題を2〜3周は練習し、各問題の複線図を正確に素早く描けるようにしましょう。
また、試験本番では時間配分も重要になるので、練習の段階から時間を計測し、40分以内に余裕を持って作業を終えられるようにペース配分を意識することも大切です。作業後には、必ず見直しを行い、細部まで確認する習慣をつけましょう。
\ 合格前から求人情報をチェックしよう! /
※登録不要で求人を探せます
まとめ
本記事では、第二種電気工事士の技能(実技)試験について、練習なしでの合格の難しさを中心に解説しました。
- 第二種電気工事士の技能(実技)試験は、練習なしでの合格は困難
- 第二種電気工事士の技能(実技)試験合格には、十分な勉強時間と、最低2周分の練習をするための材料が必要
- なるべく少なめの練習量で合格を目指したい場合は、学科試験勉強時に複線図をマスターし、動画でのイメージトレーニングを行うことが効果的
この記事を参考に、第二種電気工事士の技能(実技)試験に向けて、計画的な試験対策を行い合格をつかみ取りましょう。
■ 関連記事
■電気業界の求人なら工事士.com!!
- 電気業界に特化した求人が多数
- 資格が活きる仕事が見つかる
- 気になる企業から応募歓迎機能あり

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
おすすめ求人

大喜産業株式会社
\未経験歓迎/非常用発電機の点検・整備◆資格経験不問【賞与年3回】【残業月平均5h】【直行直帰OK】..

ジャパングリッド株式会社
《未経験者もWelcome★》OJTで徹底サポート◎特別高圧ケーブルのジョインター募集/資格経験不問..

株式会社サコテック
<大手の元請け中心◎プラント電気設備の施工管理/二種電工必須・経験不問>年休114日/残業月15h/..

株式会社翔栄電設
\残業月10hでメリハリ◎/ビル・住宅等の各種電気設備工事*資格経験不問<経験者優遇!月給30万~>..

有限会社小塚防災
【消防設備工事・保守点検】残業月20h/家族・住宅手当あり/女性も活躍できる環境◎<資格経験不問>/..
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする

|
【第二種電気工事士とは?】できることや第一種との違い・資格取得メリットを解説
第二種電気工事士
資格
試験
対策
活躍
|
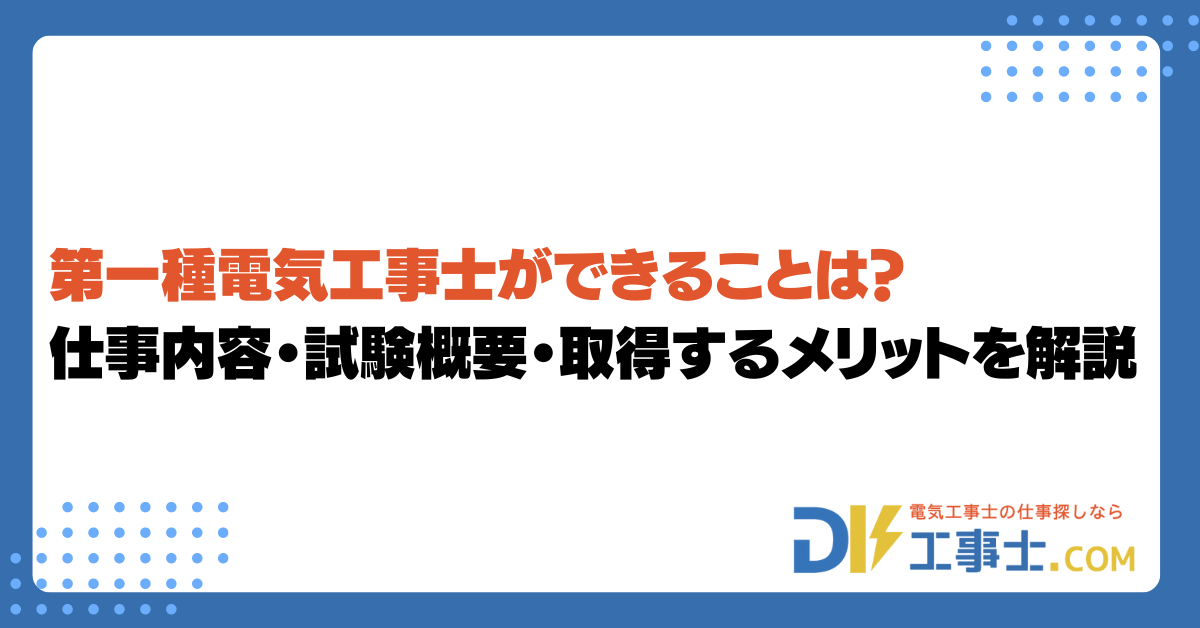
|
第一種電気工事士とは?仕事内容や第二種との違いから試験概要や勉強時間まで徹底解説
電気工事士
第一種電気工事士
資格
対策
仕事内容
|
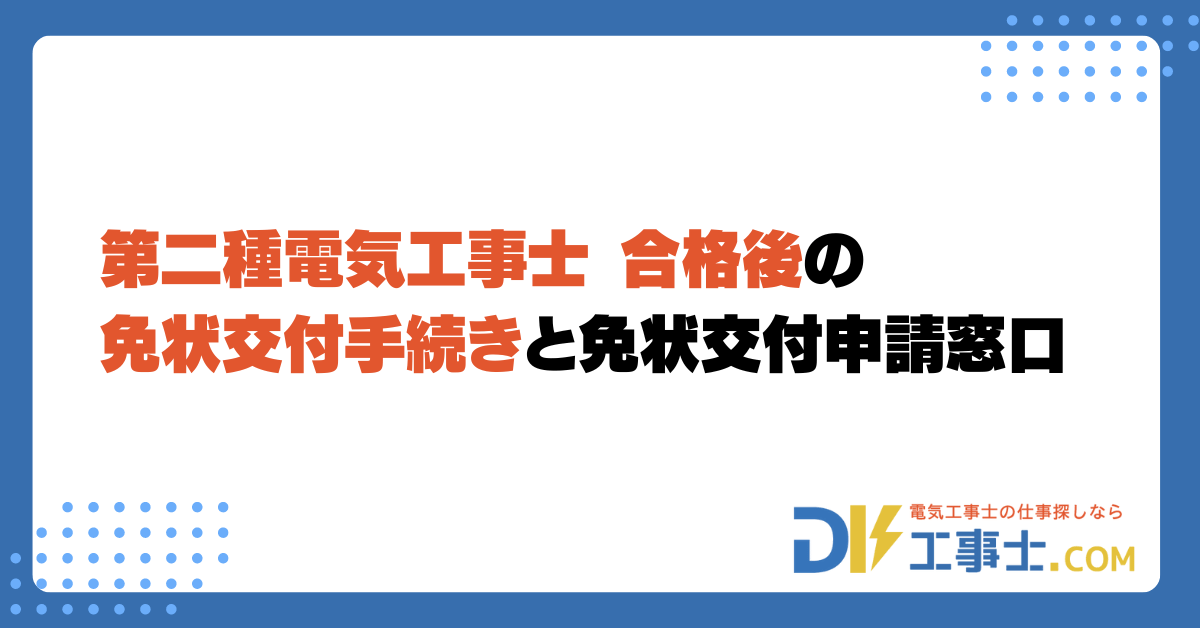
|
第二種電気工事士合格後の免状交付手続きを詳しく解説!申請期限や窓口情報まとめ
第二種電気工事士
資格
試験
|
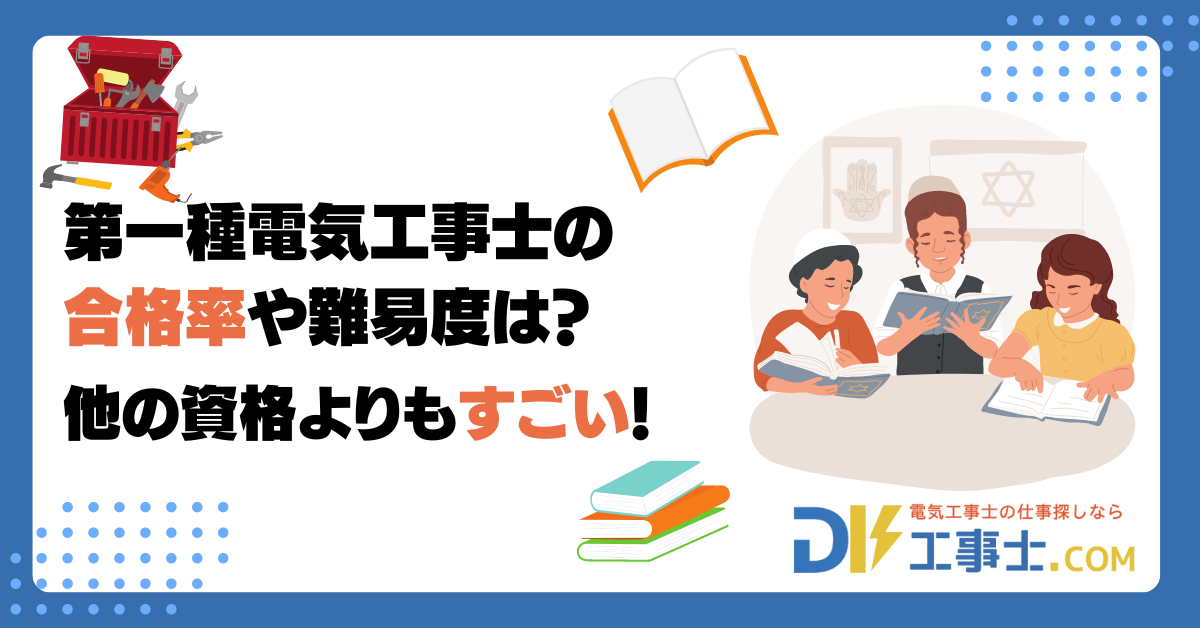
|
【実はすごい】第一種電気工事士の合格率は約56%!難易度を他資格と比較して解説
第一種電気工事士
資格
試験
|
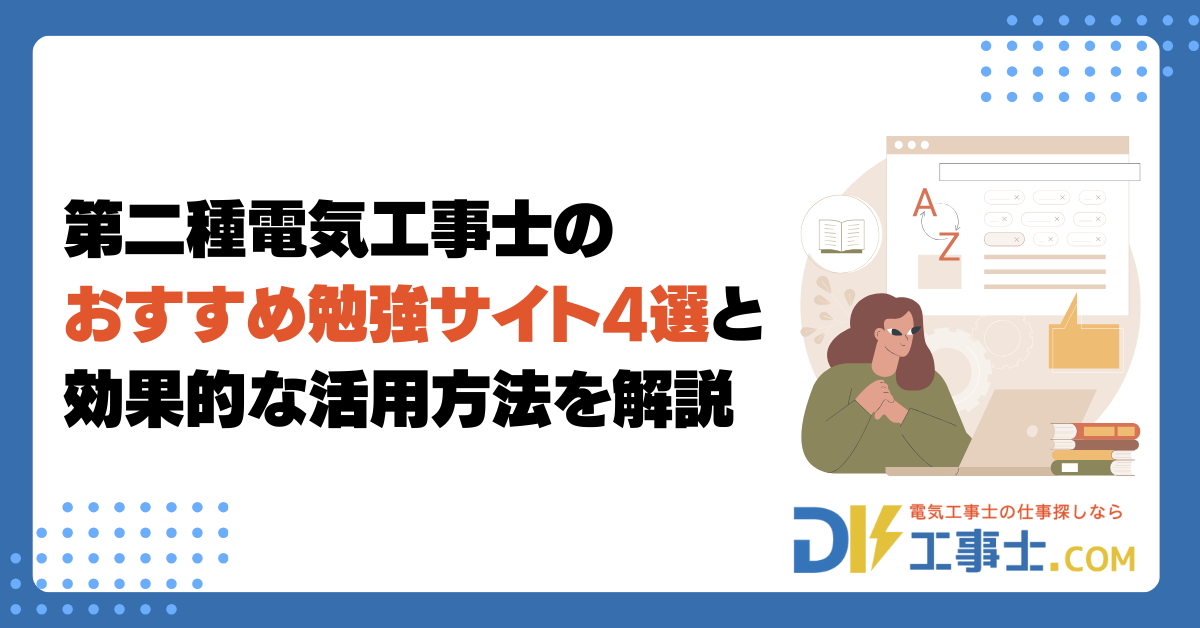
|
【無料】第二種電気工事士のおすすめ勉強サイト一覧!効果的な活用方法も解説
第二種電気工事士
試験
|