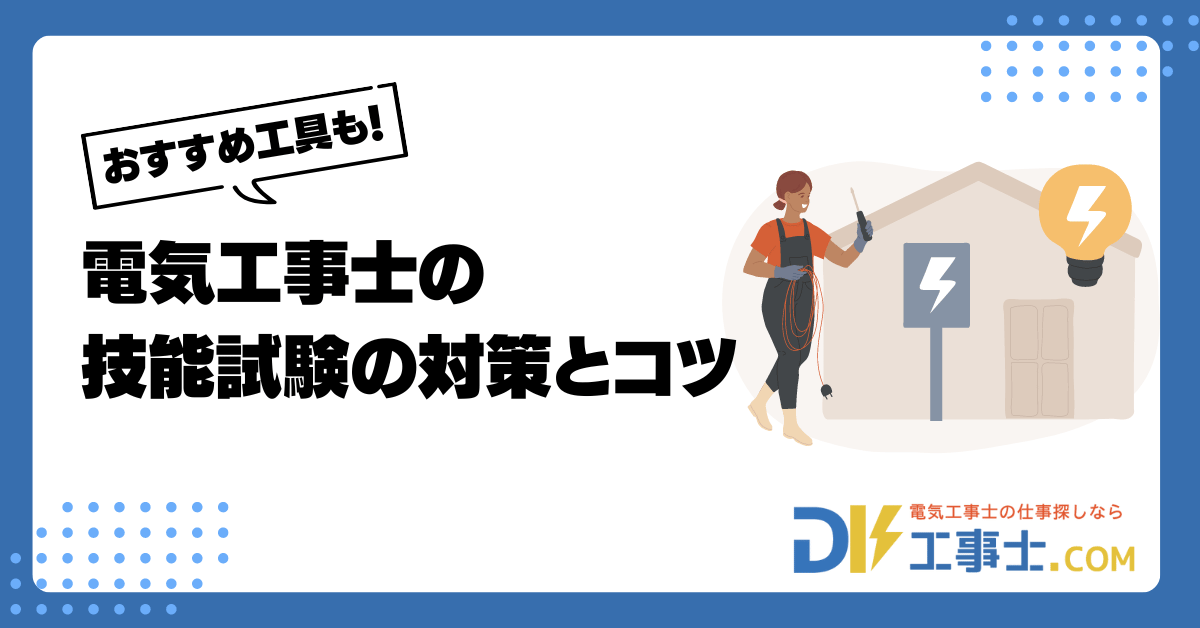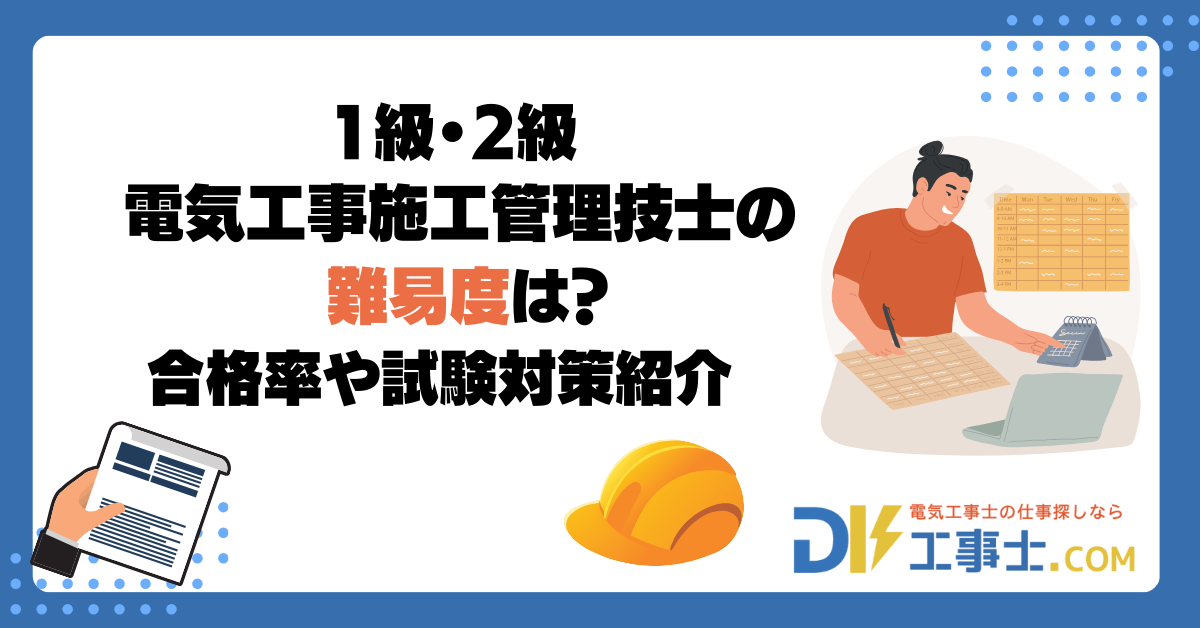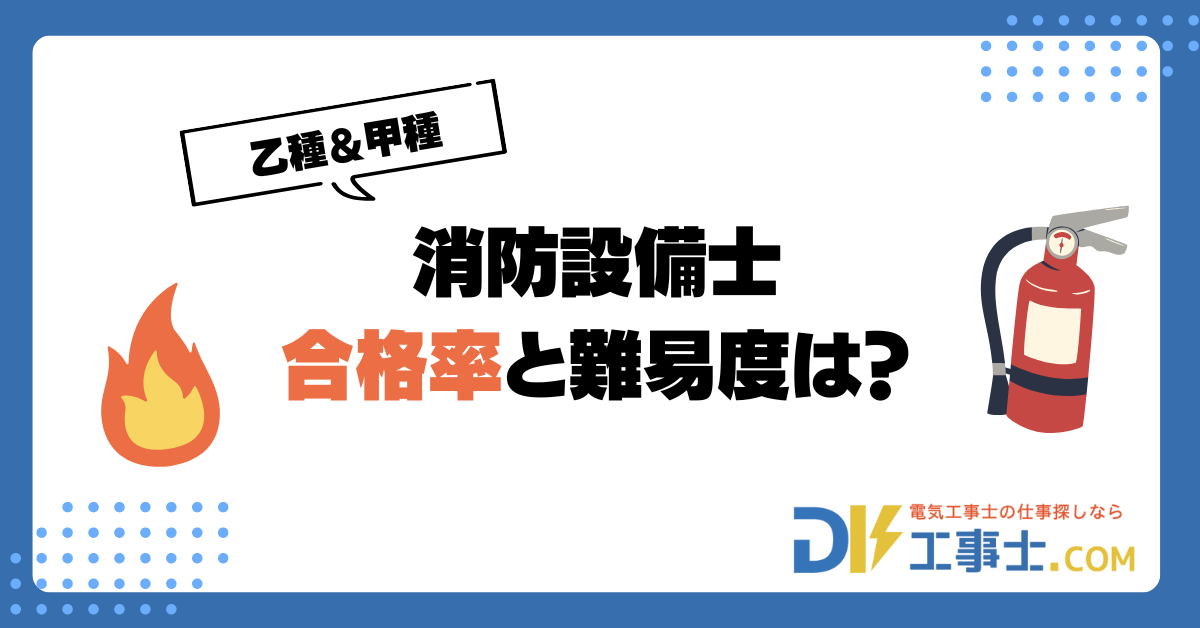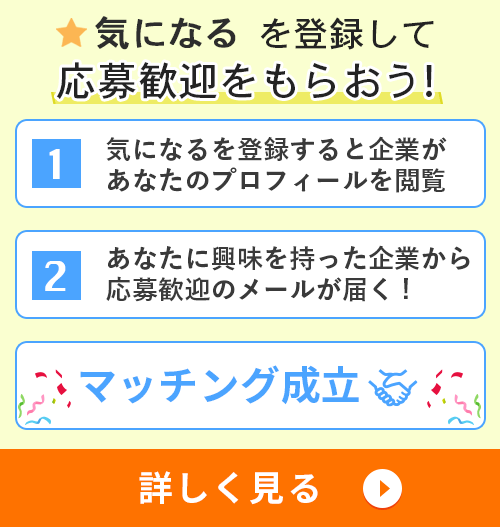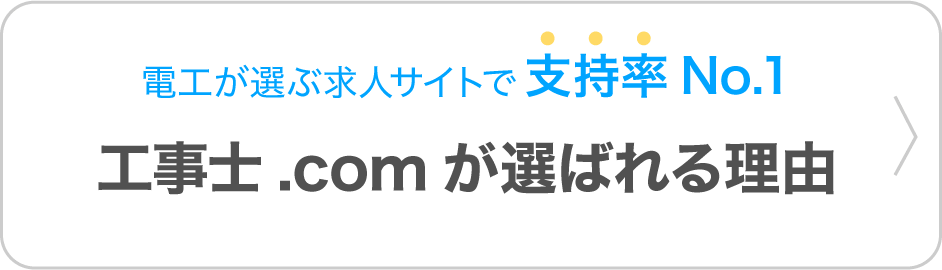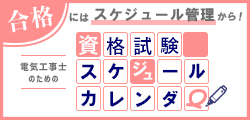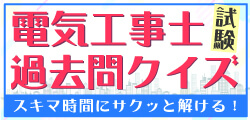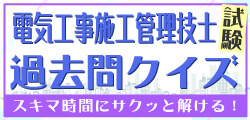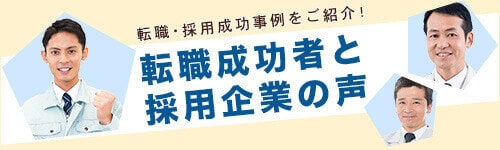低圧電気取扱業務特別教育と電気工事士の違いは?受講が必要な業務例やメリットを解説
電気工事士の資格・試験最終更新日:
電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育は、「国家資格」と「講習」という違いがあります。
電気工事士は、電気工事の欠陥による災害発生を防ぐために制定された「資格」であるのに対し、低圧電気取扱業務特別教育は、職場における労働者の安全と健康の確保のために受講しなければならない「講習」です。
低圧電気取扱業務特別教育とは、低圧の電気設備を取り扱う作業に対して行われる講習のことです。
そのため、低圧電気設備の工事を行う際には、電気工事士の資格を持っていても、低圧電気取扱業務特別教育を受講しないといけません。
本記事では、低圧電気取扱業務特別教育と電気工事士との違いや受講するメリットなどについて詳しく解説していきます。
特別教育の受講を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
■関連記事
低圧電気取扱業務特別教育とは?
低圧電気取扱業務特別教育とは、低圧の電気設備の作業を安全に行うために、法律で受講が義務付けられている講習です。
該当業務に従事する場合は、特別教育の受講が必要です。
では、低圧電気取扱業務特別教育の内容について詳しく見ていきましょう。
低圧電気取扱業務特別教育の概要
低圧電気取扱業務特別教育は、低圧の電気設備に関する作業を安全に行うために必要な講習です。
感電などの電気災害を防止するのが目的で、「労働安全衛生法」および「労働安全衛生規則」に基づき、企業は労働者に適切な教育を行うことが義務付けられています。
教育内容は「学科」と「実技」の2種類に分かれており、1つの講習で知識と技術の両方を習得できます。また、受講時の年齢や職歴の制限はなく、ご自身の仕事内容に応じて受講を決められます。もし該当する業務がある場合は、必ず受講しましょう。
「低圧」とは、交流で600V以下、直流で750V以下の電圧のことを指します。
受講が必要な業務例
低圧電気取扱業務特別教育は、低圧電気設備(交流:600V以下、直流:750V以下)を取り扱う業務を行う際に受講が必要です。
低圧電気取扱業務特別教育の受講が必要な業務の具体例は、下記のとおりです。
■ 特別教育の受講が必要な業務例
- 充電電路の敷設もしくは修理の業務
- 充電部分が露出している開閉器の操作の業務
例えば、電源が入った状態での配線に絶縁テープを巻く修理やブレーカーの入り切り操作を行う際などに、低圧電気取扱業務特別教育の受講が必要です。
電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育の違いは?
電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育は、「国家資格」と「講習」という違いがあります。
電気工事士は、電気工事を行うために必要な国家資格です。
一方、低圧電気取扱業務特別教育は、資格ではなく、低圧の電気設備を安全に扱うための講習です。
電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育の違いをまとめると、下表のとおりです。
■ 電気工事士と低圧電気取扱業務特別教育の違い
| 電気工事士 | 低圧電気取扱業務特別教育 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 国家資格 | 特別教育 |
| 業務範囲 | 電気工事全般 | 電気工事のうち、低圧電気設備の取り扱い |
| 役割 | 電気工事を行うための資格 | 感電事故を防ぐための安全講習 |
| 所管 | 経済産業省 | 厚生労働省 |
電気工事士は、電気工事の欠陥による災害発生を防ぐために制定された資格であるのに対し、低圧電気取扱業務特別教育は、職場における労働者の安全と健康の確保のために受講しなければならない講習です。
電気工事士は、「電気工事士法」により、電気工事に従事できる者の資格として定められています。
そのため、電気工事士の資格を取得すると電気設備の設置や修理などの工事を行えますが、安全教育はカバーされていません。
一方で低圧電気取扱業務特別教育は、「労働安全衛生法令」により、労働者の安全のために定められている教育制度です。
したがって、感電のリスクが高い特定の業務に携わる際は、電気工事士の資格とは別に、低圧電気取扱業務特別教育も受講する必要があります。
万が一、特別教育を受けずに該当業務を行った場合は、法律違反となり、罰則が適用される可能性がありますので気をつけましょう。
電気工事士が低圧電気取扱業務特別教育を受講するメリット
電気工事士が低圧電気取扱業務特別教育を受講するメリットは下記のとおりです。
業務範囲の拡大とキャリアップ
低圧電気取扱業務特別教育を受講すると、感電リスクを伴う充電電路の敷設や修理作業といった「低圧電気設備の工事」を行えるようになるため、業務の幅が広がります。
転職時の選択肢が増えるため、キャリアアップにも繋げやすくなるでしょう。
電気工事士は「電気設備の工事」を行うための資格です。そのため、低圧電気取扱業務特別教育を受けていなくても電気工事に携わることはできますが、低圧電気設備を取り扱うことはできません。
また、業務範囲が拡大することで、多くの現場に対応できる人材として評価されやすくなります。将来的なキャリアアップに加え、収入アップのチャンスも広がるでしょう。
企業の安全管理基準を満たせる
会社側は労働者の安全を守るために、特別教育を実施する法的義務があるため、低圧電気取扱業務特別教育を受講していると企業の安全管理基準を満たせるメリットがあります。
安全対策が不十分だと事故のリスクが高くなり、罰則を科せられると、企業にとっては大きな損失になってしまいます。
したがって、特別教育を受講していれば、企業内での価値も高くなり、より多くの業務を任されるようになるでしょう。
低圧電気取扱業務特別教育の受講費用はいくらかかる?
低圧電気取扱業務特別教育は、主に1日コースと2日間コースの2種類あります。
金額の相場は、1日コースは学科のみで約10,000円前後、2日間コースは学科と実技で約20,000円前後です。
低圧電気取扱業務特別教育の費用について、詳しく見てみましょう。
1日コースと2日間コースの違いと費用相場
低圧電気取扱業務特別教育は、主に「1日コース」と「2日間コース」があり、1日コースの費用は約10,000円前後、2日間コースの費用は約20,000円前後です。
コースごとの違いや費用相場は、下表のとおりです。
■ 低圧電気取扱業務特別教育の受講費用相場
| コース | 内容(一例) | 費用相場 |
|---|---|---|
| 1日コース | 学科のみ、実技のみ、学科+実技1時間など | 約10,000円前後 |
| 2日間コース | 学科+実技7時間 | 約20,000円前後 |
※参考:講習会一覧(一般社団法人 安全衛生マネジメント協会)、講習会のご案内(関東電気保安協会)
基本的に、学科講習は、実技講習は約7時間程度です。したがって、学科講習と実技(7時間以上)講習の両方を受講する場合は、2日間コースで行われることが多いです。
なお、実技講習は内容によって受講時間が異なります。
実技講習では、上記のどちらか1つの講習を受講する必要があります。ご自身の業務範囲に合った内容を選択しましょう。
地域別の費用例(東京・大阪など)
低圧電気取扱業務特別教育の受講費用は、地域によって若干異なります。
主要都市における費用例をまとめると、下表のとおりです。
■ 地域別の低圧電気取扱業務特別教育の受講費用相場
| 地域 | 費用 | 講習内容 |
|---|---|---|
| 東京 | 23,980円(税込) | 学科+実技7時間(2日間) |
| 大阪 | 13,200円(税込) | 学科+実技1時間(2日間) |
| 愛知 | 22,500~25,000円(税込) | 学科+実技(2日間) |
| 福岡 | 10,670円(税込) | 学科+実技(1日間) |
※参考:講習会のご案内(関東電気保安協会)、低圧電気取扱者 安全衛生特別教育(関西電気保安協会)、低圧電気取扱業務特別教育(公益社団法人 愛知労働基準協会)、安全衛生講習(一般社団法人 福岡経営者労働福祉協会)
低圧電気取扱業務特別教育の講習においては、費用の中にテキスト代が含まれている場合と、テキストを別途購入する必要があります。各機関の料金をよく確認し、総額でどれくらいかかるのかを事前に把握しておくとよいでしょう。
講習内容や日程は各開催機関によって異なるため、受講を検討される際は公式ホームページで最新情報をご確認ください。
助成金や会社負担を利用して受講費用を抑える方法
低圧電気取扱業務特別教育の受講費用を抑えるには、「助成金を利用する」方法と「会社負担を利用する」方法があります。
低圧電気取扱業務特別教育の受講には、厚生労働省が提供している「人材開発支援助成金」を利用できます。
また、勤めている会社によっては、会社負担でも特別教育を受けられますが、受講の必要性を具体的に説明する必要があります。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
助成金の申請条件と手続きの流れ
低圧電気取扱業務特別教育を受講する際には、一定の条件を満たしていれば、厚生労働省が提供している「人材開発支援助成金」を申請できます。
人材開発支援助成金とは、企業が従業員の能力向上を目的とした訓練や講習にかかる費用の一部を助成する制度です。
ただし、助成金制度を利用するためには企業が一定の条件を満たしていないといけません。
申請するための条件は下記のとおりになります。
■ 助成金の受給対象となる事業主の条件
- 資本金もしくは出資総額が3億円以下、または常時雇用の労働者300人以下の建設事業主
- 建設の事業として、雇用保険料率(18.5/1,000)の適用を受ける事業主である
- 事業主からの業務命令で、建設労働者が受講する
- 受講者が雇用保険の被保険者である
- 所定労働時間内に受講させ、その場合に支払われる賃金の額以上の賃金を支払っている
- 雇用管理責任者を選任している
なお、助成金の手続きは、基本的に下記のような流れで進めていきます。
■ 助成金の手続きの流れ
- 申請前の受給資格の確認
- 講習会の申し込み
- 計画届の提出
- 講習を受講
- 必要書類を送付
- 所轄の労働局、ハローワーク等へ助成金申請
- 助成金の受給
訓練後は期限内に労働局へ申請書類の提出を行います。申請期限を過ぎてしまうと、助成金が受給できなくなるため、早めの提出が必要です。制度の内容や要件は変更される可能性があるため、最新の情報を確認するようにしましょう。
会社負担で受講する際の事例とポイント
低圧電気取扱業務特別教育を会社負担で受講するためには、業務上の必要性を明確に説明することが重要です。
例えば、低圧電気設備の点検業務を任されているにも関わらず、特別教育を受けていないとスムーズに業務を進められず、作業効率が下がってしまいます。
このような業務への支障を具体的に会社側に説明すると、費用を負担してもらえる可能性が高くなります。
また、低圧電気の取り扱いには、低圧電気取扱業務特別教育の受講が法律で義務付けられている点も強調すべきポイントです。特別教育を受講することで感電事故などのリスクを軽減でき、作業中の安全確保にも繋がります。
業務への支障をきたすだけでなく、法令遵守や安全対策などの明確な理由を説明すると会社側にも受講の必要性が伝わりやすくなります。従業員のスキルアップと会社の安全管理という両面でメリットがあるため、今後の研修申請もしやすくなるでしょう。
低圧電気取扱業務特別教育の受講内容
低圧電気取扱業務特別教育の講習には、学科講習と実技講習があります。
また実技については、実際に従事する業務内容によって学ぶべき内容は異なります。
低圧電気取扱業務特別教育の受講内容について、詳しく見ていきましょう。
学科の受講内容
低圧電気取扱業務特別教育の学科講習では、電気関係の基礎知識や安全対策、関連する法律について学ぶことができます。
具体的な講習内容は、下記の通りです。
■ 学科講習の受講内容
- 低圧電気に関する基礎知識
- 低圧の電気設備に関する基礎知識
- 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
- 低圧の活線作業および活線近接作業の方法
- 関連法令
※参考:低圧電気取扱業務特別教育
すべての学科科目を受講するには、7時間以上の講習を受講する必要があります。
実技の受講内容
実技講習では、実際の作業を通じて低圧電気を安全に取り扱うための技術を習得できます。
業務内容によって、2種類の実技講習が用意されています。
■ 実技講習の受講内容
| 講習内容 | 講習時間 |
|---|---|
| 充電電路の敷設もしくは修理の業務 | 7時間以上 |
| 充電部分が露出している開閉器の操作の業務 | 1時間以上 |
※参考:低圧電気取扱業務特別教育
実務に活かすためには、自分が実際に行う業務内容に合わせて講習を選ぶことが重要です。
例えば、開閉器の操作のみを行う場合は、学科(7時間)と実技(1時間)で十分でしょう。
一方、低圧電気設備の敷設や修理を行う予定がある場合は、7時間以上の実技講習が必要です。業務内容に合わせた選択は、時間の節約にも繋がり、効率よく勉強を進められます。
また、現場経験が少ない方は、実技が充実した講習を選ぶことをおすすめします。講習によっては、実際に使う工具の使い方まで詳しく教えてもらえたり、具体的な質問に答えてもらえたりするため、実務に直結するスキルを身につけられるでしょう。
修了証を紛失した場合の再発行手続き
低圧電気取扱業務特別教育の修了証を紛失した場合は、特別教育を受講した機関で修了証の再発行ができます。
ただし、修了証の再発行には手数料を支払う必要があります。受講した機関によって金額は異なるため、再発行の前に事前に確認しておきましょう。
再発行に必要な書類と手数料
低圧電気取扱業務特別教育修了証の再発行に必要な書類は、各機関によって異なります。
特に必要書類として多いのは「再交付申請書」や「本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」です。
ご自身の申請機関のホームページなどで、事前に確認しておきましょう。
また、手数料に関しても受講した機関によって若干異なります。
手数料の相場は、およそ1,000円〜2,000円ですが、正確な金額は受講した機関のWebサイトや窓口で確認しましょう。
再発行ができないケースと対策
低圧電気取扱業務特別教育修了証の再発行は、受講した機関のみでしか行えないため、受講先が分からないと再発行が困難になってしまいます。
また、教育機関の記録保存期間が過ぎてしまうと、必要な記録が残っていない場合があります。
もし受講先がわからない場合は、下記の対処法を試してみましょう。
■ 受講先が分からない場合の対処法
- 勤務先の同僚に確認をして、受講した教育機関を特定する
- 受講先が判明したら、教育機関へ問い合わせを行う
なお、記録の保存期間は、法令で3年間と決められています。※参考:労働安全衛生法における特別教育の概要(厚生労働省)
保存期間が3年以上過ぎていた場合は、再発行ができませんので気をつけましょう。
よくある質問
ここからは、低圧電気取扱業務特別教育に関するご質問にお答えします。
受講に必要な条件や資格はあるの?
低圧電気取扱業務特別教育の受講に特別な資格や事前の条件はありません。
低圧電気取扱業務特別教育は、主に低圧電気の作業を行う方が対象となります。また、企業側が労働安全衛生法に基づいて従業員に受講を義務付けるケースもあります。
テストや試験はあるの?
低圧電気取扱業務特別教育には、テストや試験はありません。
講習を受講して、全カリキュラムを修了すれば修了証が交付されます。講習を受講することで法的に必要な教育を修了したと認められます。
資格を失効することはある?有効期限は?
低圧電気取扱業務特別教育の修了証には有効期限はなく、一度受講すれば、資格が失効することはありません。
ただし、長期間業務から離れていたり、法改正があった場合には、最新の知識や安全対策を学ぶために再受講が推奨されます。
また、企業によっては安全管理のために定期的な再教育を義務付けている場合もあります。受講前に、職場のルールを確認しておきましょう。
まとめ
本記事では、低圧電気取扱業務特別教育についてや、電気工事士との関係性について解説しました。
- 低圧電気取扱業務特別教育とは、低圧の電気設備に関する作業を安全に行うための講習
- 電気工事士は安全管理に対応していないため、安全対策として電気工事士資格とは別に低圧電気取扱業務特別教育の受講が必要
- 助成金や会社負担を利用すれば、低圧電気取扱業務特別教育の受講費用を抑えることができる
- 低圧電気取扱業務特別教育修了証の再発行は、受講した機関でのみ再発行できる
電気工事士の資格を保有していても、該当する業務を行う場合は、低圧電気取扱業務特別教育の受講が法律で義務付けられています。特別教育を受講すると、行える業務の範囲が広がります。多くの現場で対応できる人材と評価されれば、キャリアップにも繋げやすくなるでしょう。
電気工事士の資格をお持ちで、業務の範囲を広げてキャリアアップを目指したい方は、低圧電気取扱業務特別教育の受講を検討してみてはいかかでしょうか。
■ 関連記事
申請や認定講習のみで取得できる電気工事系資格については下記記事で詳しく解説しています。

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
おすすめ求人

株式会社大電通
<未経験OK><残業月10h>電気通信設備工事・電気工事/資格経験不問【NTT関連の取引多数】/正社..

株式会社プログレス
《引越費用支援&借上社宅あり》電気工事・電気通信工事スタッフ/資格経験不問*残業月10h*/正社員

KS電設株式会社
【最大15万円の入社祝金 or 社宅でサポート】電気・計装工事の施工や施工管理/経験資格不問/正社員

髙橋電気工業株式会社
電気設備工事の施工管理(経験3年以上の有資格者)■電気工事士(資格経験不問)も同時募集中!/正社員・..

柏崎協電株式会社
残業月3h◆引込線工事で地域のライフラインを守る!資格経験不問<育成環境が充実><講習費用支援あり>..
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする

|
【第二種電気工事士とは?】できることや第一種との違い・資格取得メリットを解説
第二種電気工事士
資格
試験
対策
活躍
|
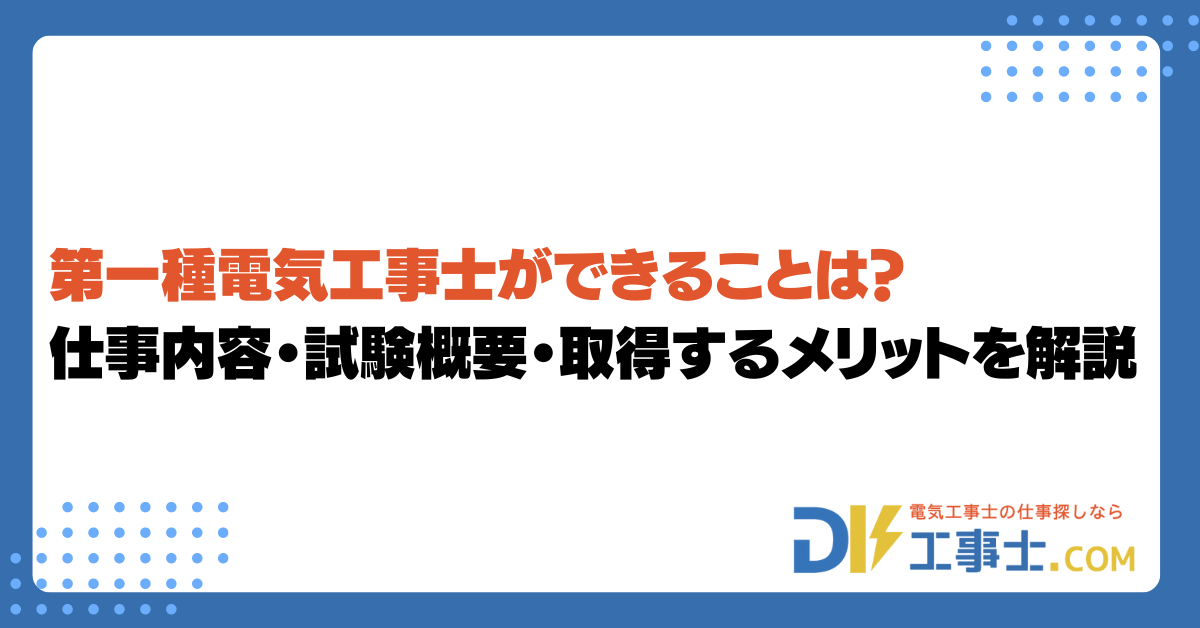
|
第一種電気工事士とは?仕事内容や第二種との違いから試験概要や勉強時間まで徹底解説
電気工事士
第一種電気工事士
資格
対策
仕事内容
|
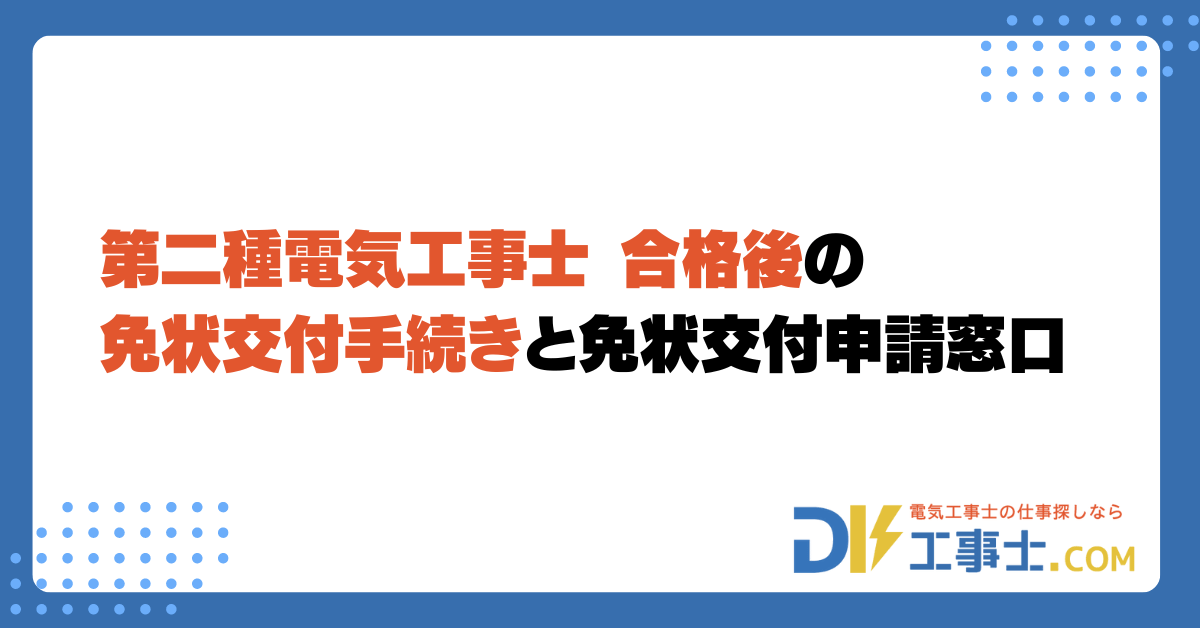
|
第二種電気工事士合格後の免状交付手続きを詳しく解説!申請期限や窓口情報まとめ
第二種電気工事士
資格
試験
|
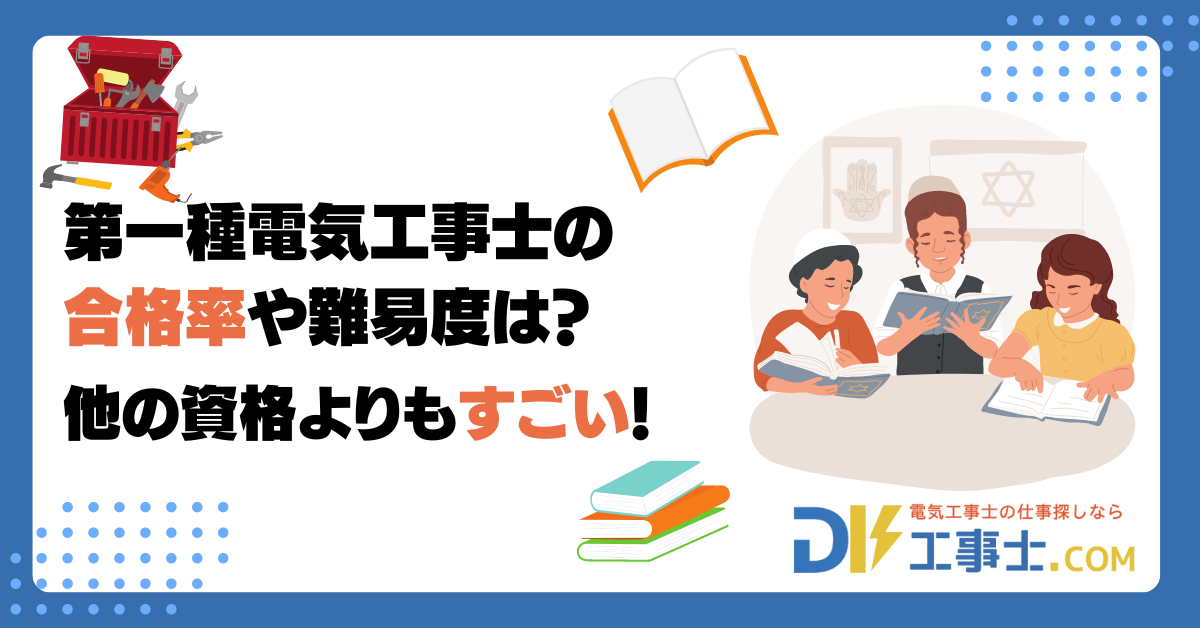
|
【実はすごい】第一種電気工事士の合格率は約56%!難易度を他資格と比較して解説
第一種電気工事士
資格
試験
|
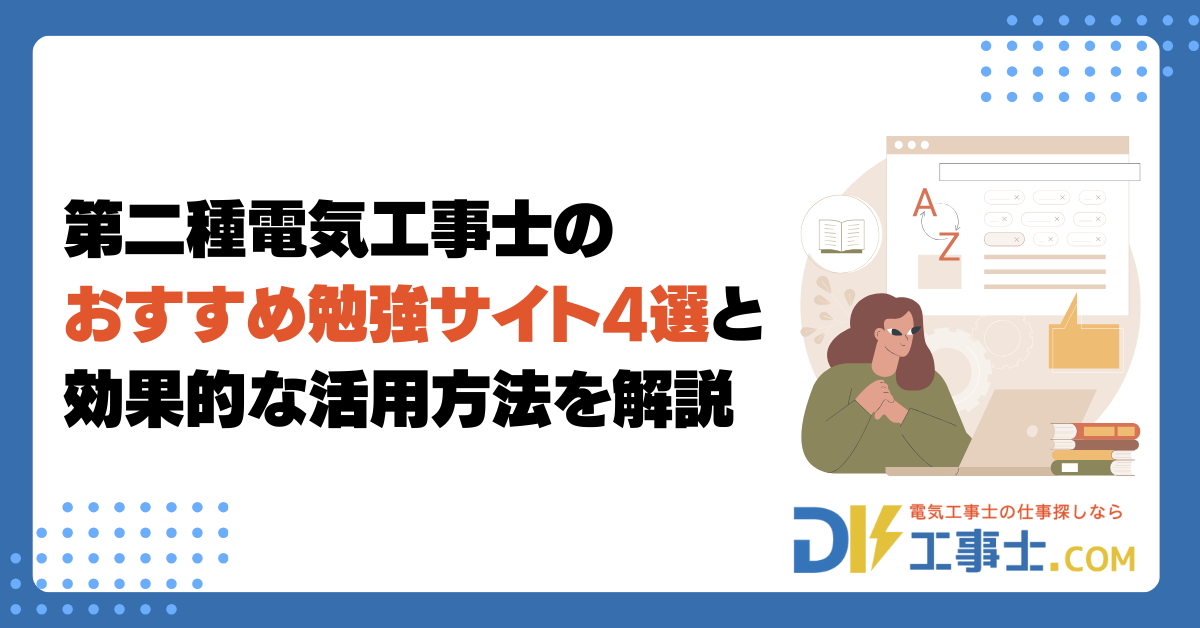
|
【無料】第二種電気工事士のおすすめ勉強サイト一覧!効果的な活用方法も解説
第二種電気工事士
試験
|