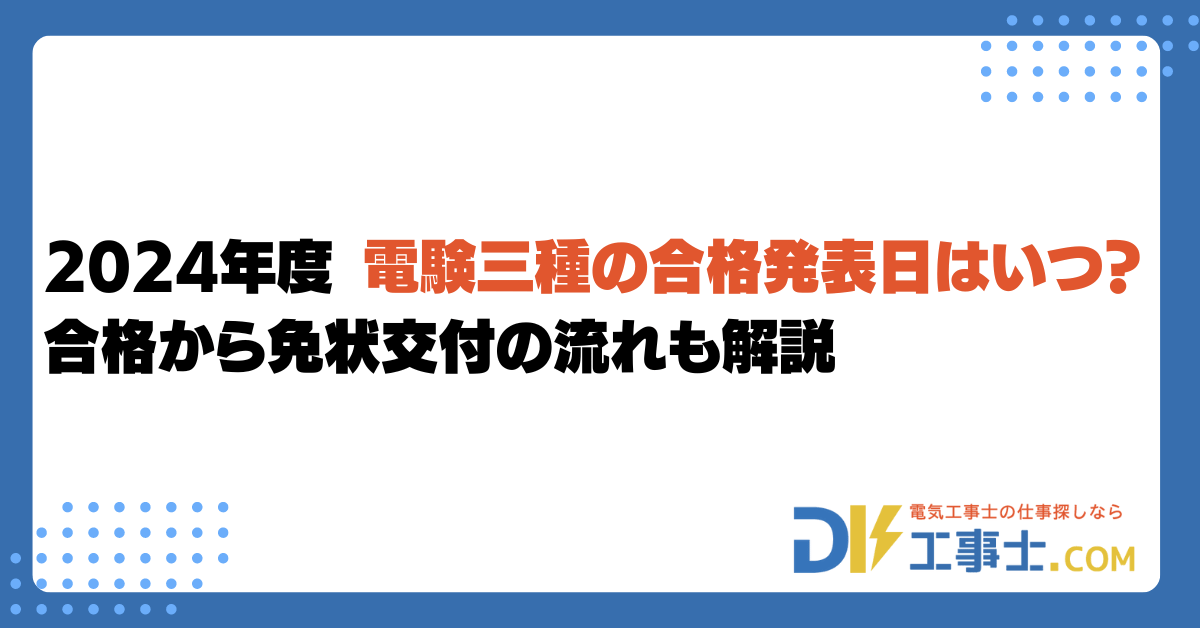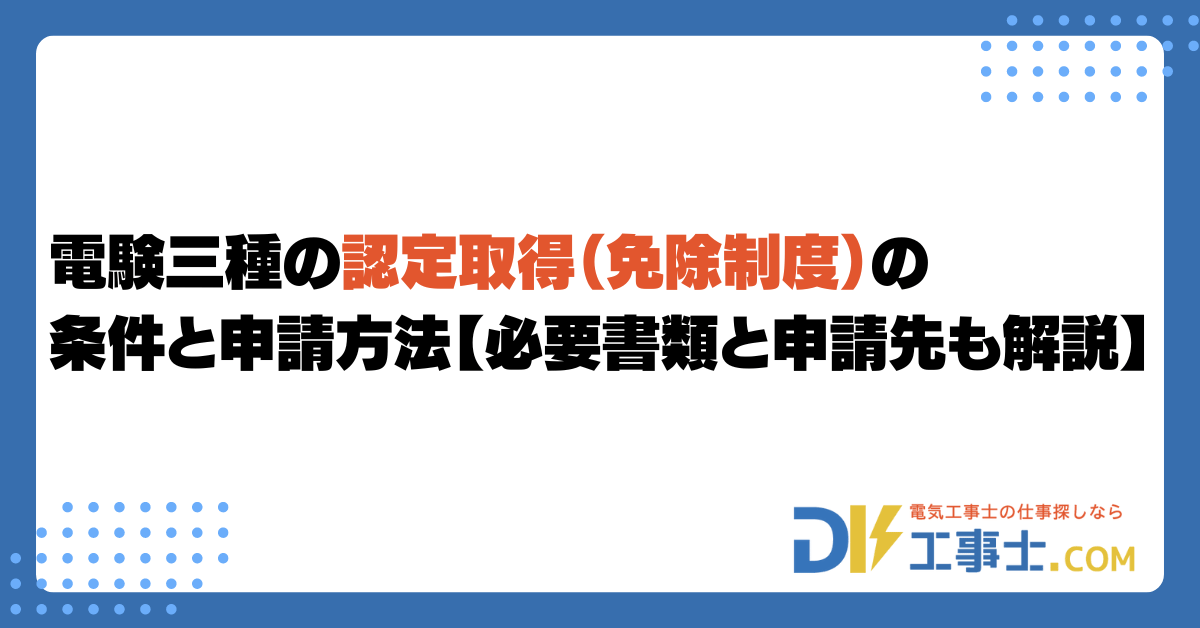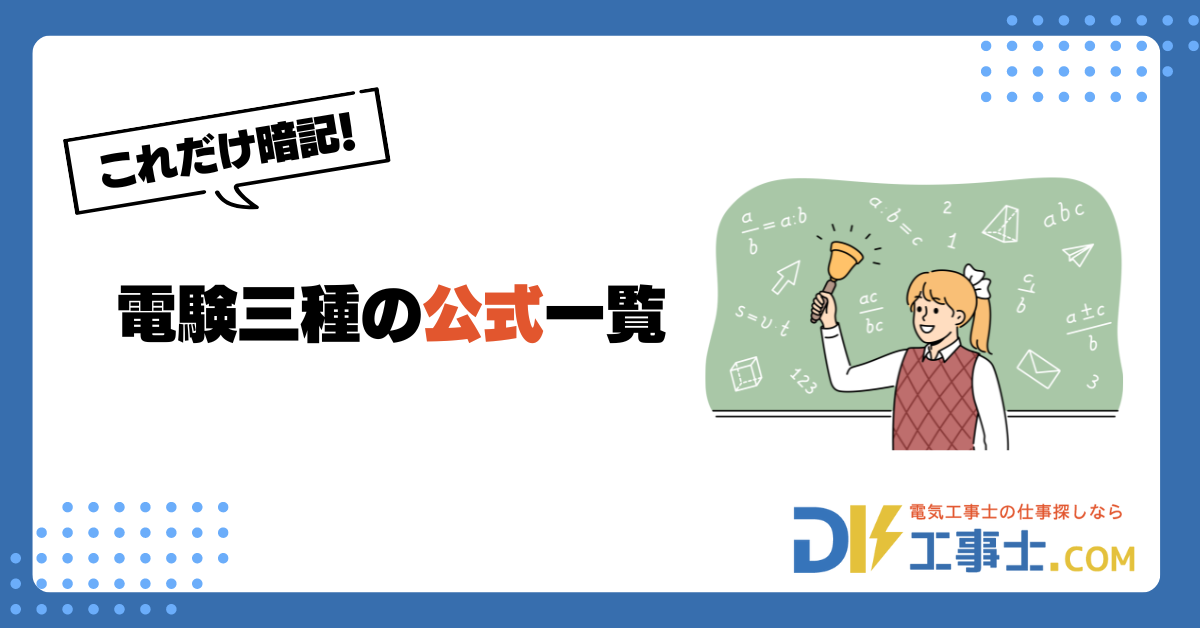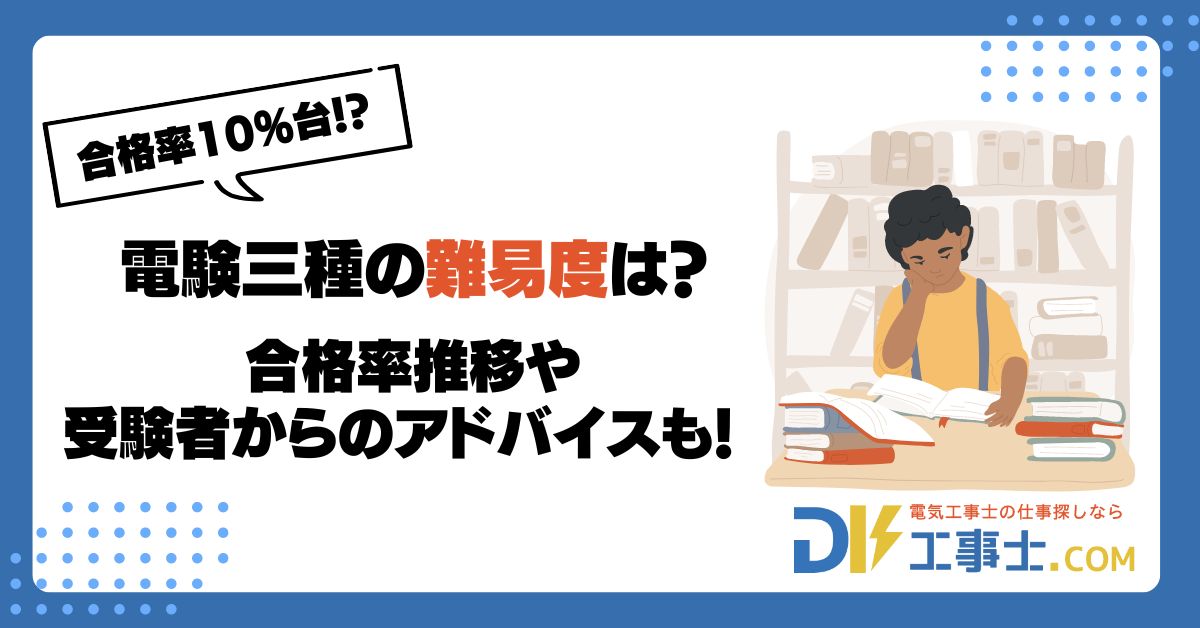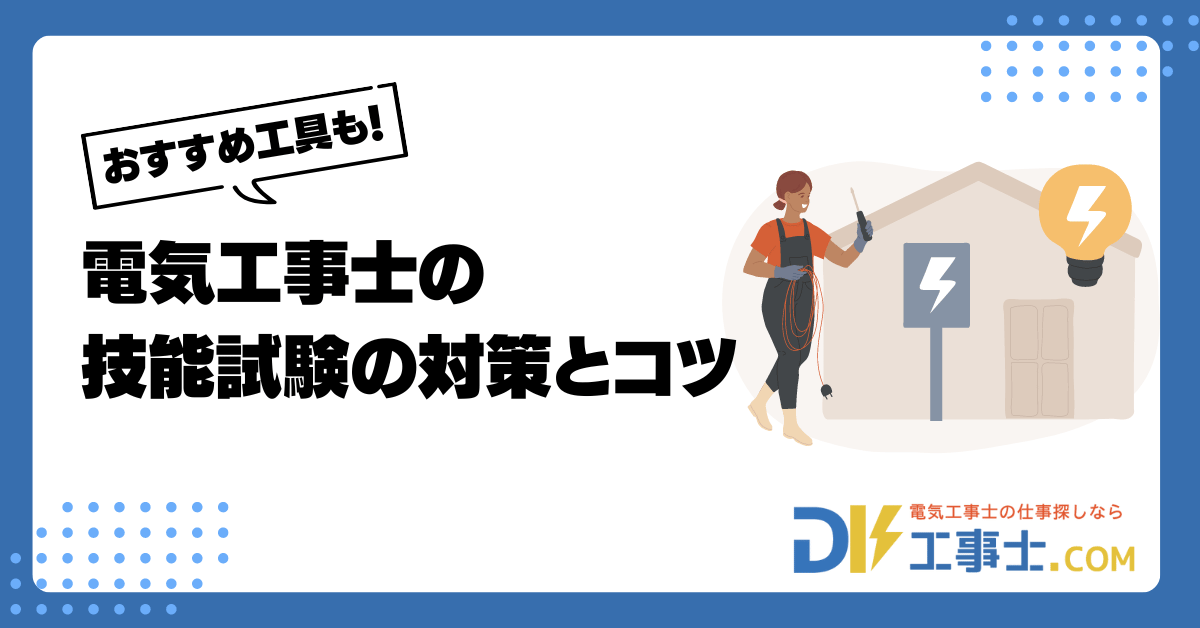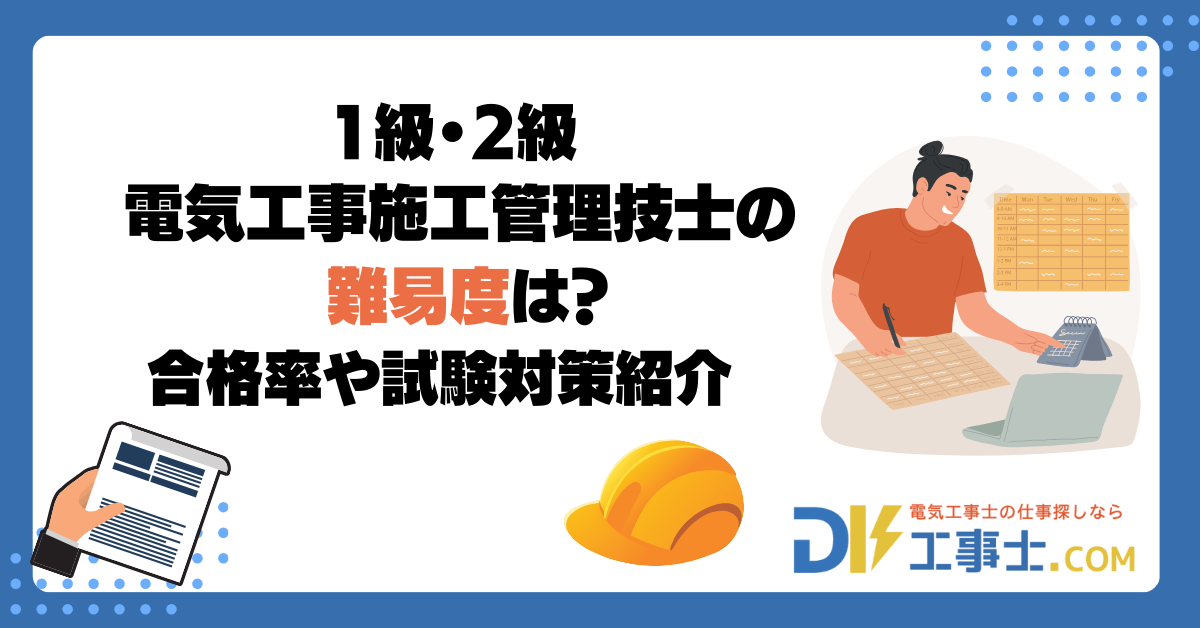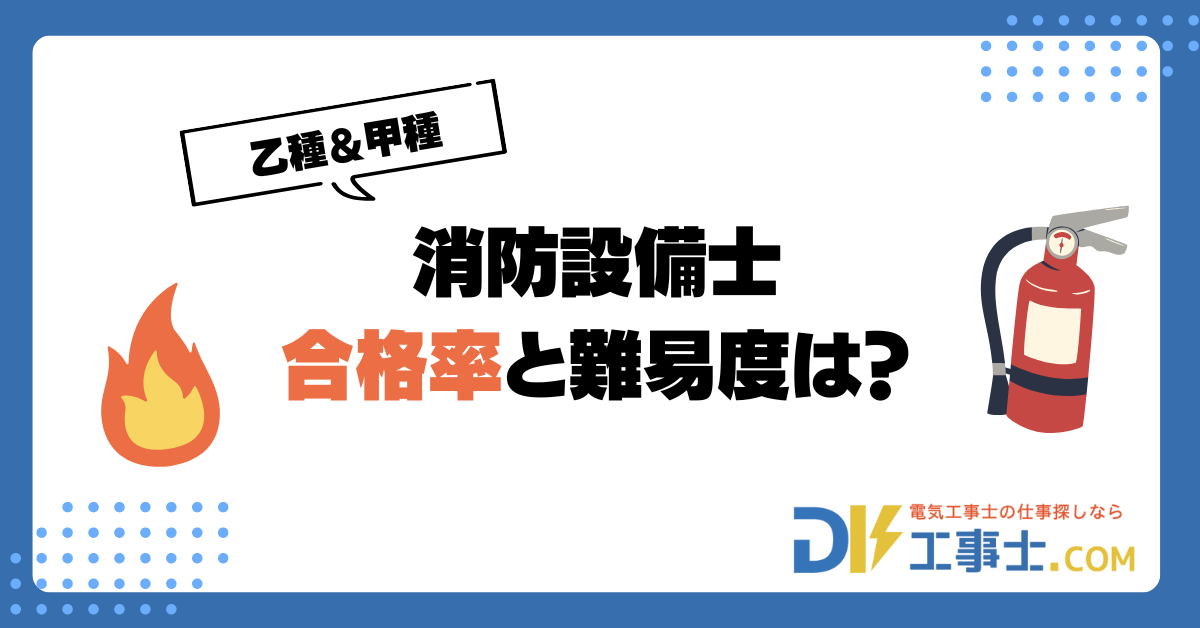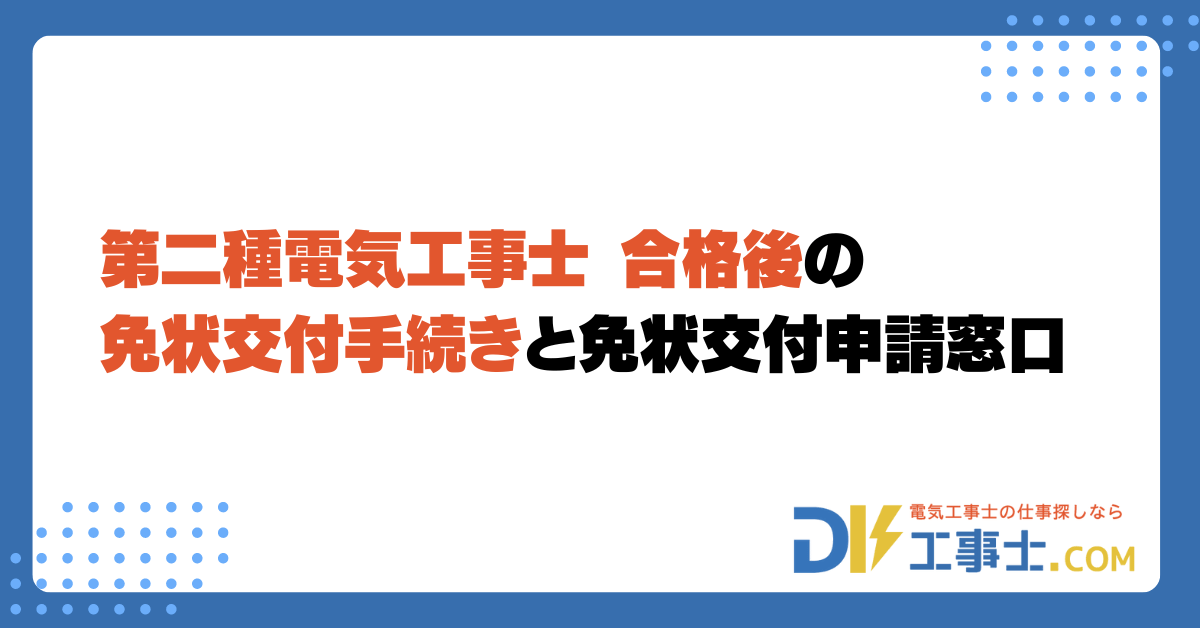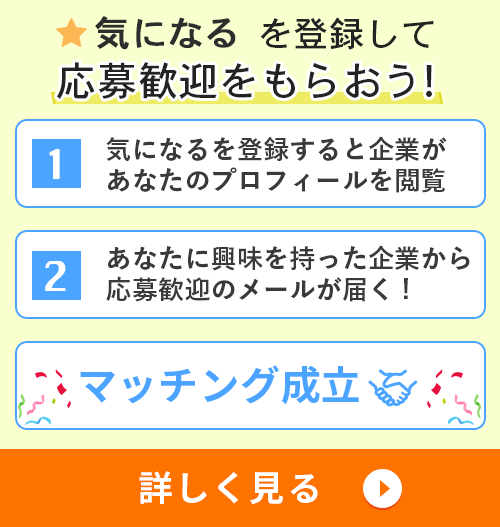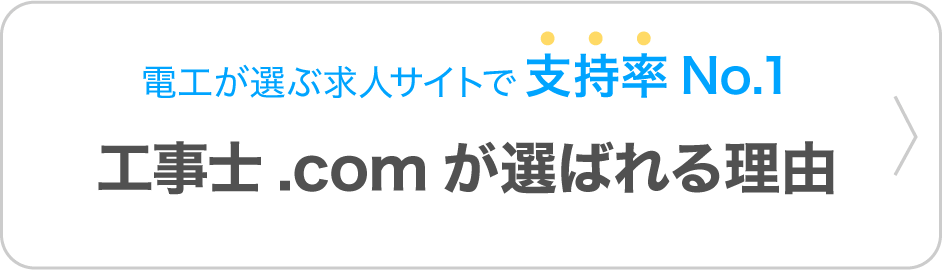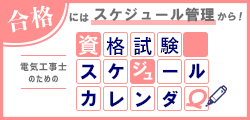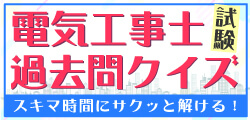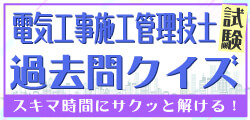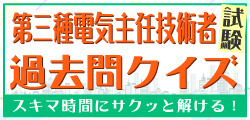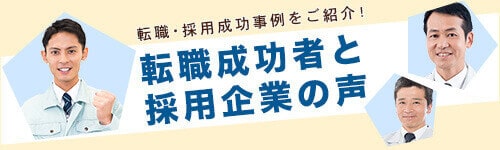電験二種の難易度や合格率を分析!難関試験と言われる理由を解説
電気主任技術者(電験)最終更新日:
電験二種(第二種電気主任技術者)の過去5年間(2019年〜2023年)の平均合格率は、一次試験が27.2%、二次試験が22.0%です。
電験二種は難易度が高い国家資格として知られています。
なぜかというと、電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の作業主任者として、電気設備の設計や運用、保守など幅広い高度な知識が必要だからです。
ただし、電験二種を保有していると、電力会社や大規模施設からの仕事を受注できるため、キャリアアップを考えている方には人気の資格となっています。
この記事では、電験二種の難易度や合格率を分析し、受験生が効率的に合格できるような情報を詳しく紹介します。また、資格受験以外の取得方法「認定取得」についても解説しています。
ぜひ最後までご覧下さい。
電験二種の難易度と合格率

電験二種は資格取得の難易度が高く、過去5年間(2019年〜2023年)の平均合格率は、一次試験が27.2%、二次試験が22.0%となっています。
2019年~2023年までの期間で、一次試験の平均合格率は以下のような結果です。
■1次試験合格率
| 合計 (2019~2023年度) |
過去5年の最高合格率 (2022年度) |
過去5年の最低合格率 (2019年度) |
|
|---|---|---|---|
| 受験者数 | 31,636人 | 6,189人 | 6,915人 |
| 合格者数 | 8,590人 | 2,178人 | 1,633人 |
| 合格率 | 27.2% | 35.2% | 23.6% |
※参考:第二種電気主任技術者試験(一般財団法人 電気技術試験センター)
2019年〜2023年までのデータを見る限り、一次試験の合格率は27.2%と低く、全体の4分の1程度にとどまっています。
次に、二次試験の合格率を見てみると、さらに厳しい状況が浮かび上がります。
■ 2次試験合格率
| 合計 (2019~2023年度) |
過去5年の最高合格率 (2020年度) |
過去5年の最低合格率 (2021年度) |
|
|---|---|---|---|
| 受験者数 | 13,018人 | 2,512人 | 2,407人 |
| 合格者数 | 2,860人 | 701人 | 413人 |
| 合格率 | 22.0% | 27.9% | 17.2% |
※参考:第二種電気主任技術者試験(一般財団法人 電気技術試験センター)
二次試験では、受験者のうち約78%が不合格となっています。
電験二種の難易度が高さは、それぞれ以下の理由が挙げられます。
| 項目 | 理由 |
|---|---|
| 出題範囲 | 電気理論、電力、機械、法規など多岐にわたる分野から出題される |
| 専門知識 | 単なる暗記ではなく、電気の原理や仕組みに関する深い理解が必要 |
| 記述式問題 | 二次試験では記述式の問題が出題され、知識を正確に文章化する能力が求められる |
| 合格基準 | 各科目で一定以上の得点が必要であり、全体の得点が高くても一科目でも合格基準を下回ると不合格となる(科目ごとの合格にはなる) |
ただし、電験二種には受験者をサポートしてくれる制度が用意されています。
科目合格留保制度は、一次試験の各科目(理論、電力、機械、法規)ごとに合否が決定され、合格した科目は翌年と翌々年の試験で免除されます。
さらに、一次試験免除制度は、一次試験に合格すれば翌年の一次試験が免除され、二次試験から受験できます。
これらの制度を活用することで、長期的な視点で合格を目指すこともできるでしょう。
電験二種の難易度は確かに高いですが、その分だけ資格の価値も高いです。電気設備の保安管理者として活躍できるだけでなく、キャリアアップの可能性も広がります。難関資格に挑戦する価値は十分にあるでしょう。
しかし、合格までには相当な努力と時間が必要となるため、計画的な学習と粘り強い取り組みが不可欠です。
電験二種の科目合格留保制度について

科目合格留保制度とは、一次試験の各科目(理論、電力、機械、法規)ごとに合否が決定され、合格した科目については翌年と翌々年の試験で免除される制度です。つまり、3年間で4科目全てに合格すればいいため、無理せず計画的に電験二種を取得できる仕組みとなっています。
この制度の詳細は以下の通りです。
■科目合格留保制度
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 適用範囲 | 一次試験のみ適用され、二次試験への適用はなし |
| 合格基準点 | 各科目で合格基準点を満たす必要がある 合格基準点は試験の難易度によって毎年変動する |
| 留保期間 | 合格した科目につき、翌年度および翌々年度の一次試験まで有効 |
| 免除申請 | 科目の免除を受けるためには、申請が必要 |
下記の条件をもとに、実際に科目合格留保制度を利用して、3年以内に合格することを想定してシミュレーションをしてみました。
■科目合格留保制度を利用した場合の一例
【条件】
1年目:『理論』・『法規』に合格 ※『機械』・『電力』は不合格
2年目:『機械」に合格 ※『電力』は不合格、『理論』・『法規』は免除
3年目:『電力』に合格 ※『理論』・『法規』・『機械』は免除
| 科目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 一次試験合格 |
|---|---|---|---|---|
| 理論 | 合格 | 免除 | 免除 | 合格 |
| 機械 | 不合格 | 合格 | 免除 | |
| 電力 | 不合格 | 不合格 | 合格 | |
| 法規 | 合格 | 免除 | 免除 |
上記の通り、科目合格留保制度を利用すれば、3年かけて一次試験の合格を目指すことも可能です。
しかし、科目合格の有効期限は翌々年度までです。したがって、3年以内に全科目合格しないと、一部の科目は再度受験する必要があります。
長期的に計画を立てて受験する場合は、有効期限にも注意しながら試験勉強に取り組みましょう。
なお、科目ごとに合格率は大きく異なります。以下、令和5年度の科目ごとの合格率をまとめました。
■令和5年度 科目別合格率
| 項目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 理論科目 | 5,123人 | 1,714人 | 33.5% |
| 電力科目 | 4,480人 | 1,702人 | 38.0% |
| 機械科目 | 3,953人 | 2,848人 | 72.0% |
| 法規科目 | 4,329人 | 3,892人 | 89.9% |
※参考:令和5年度第一種及び第二種電気主任技術者試験一次試験の結果について(一般財団法人 電気技術試験センター)
ご覧の通り、『理論』・『電力』の2科目の合格率が30%台で、他の2科目を大幅に下回っています。長期的に合格を目指すのであれば、科目ごとの難易度も考慮しながら、効率的に学習を進める必要があるでしょう。
なお、適用範囲でも説明した通り、二次試験での科目別合格制度はありません。しかし、二次試験では、一次試験に合格して二次試験で不合格になった場合につき、翌年度の一次試験が免除される「一次試験免除制度」があります。
1年度限りですが、一次試験を受ける必要がなくなるため、積極的に活用しましょう。
電験二種の認定取得について

電験二種(第二種電気主任技術者)の資格取得には、試験合格以外にも「認定制度」という方法があります。この認定制度は、一定の条件を満たす方に対して、試験を受けずに資格を与える仕組みです。
認定取得は、以下の3つのうちいずれかを満たしている必要があります。
■電験二種の認定取得条件
| 前提条件 | 認定条件 |
|---|---|
| 第三種電気主任技術者の免状取得者 | 5年以上の実務経験が必要 |
| 認定校の大学卒業者 | 3年以上の実務経験が必要 |
| 認定校の短大・高専卒業者 | 5年以上の実務経験が必要 |
※参考:第二種電気主任技術者の資格取得フロー(一般財団法人 電気技術試験センター)
これらのいずれかの条件を満たし、申請手続きを経て認定を受けると電験二種の資格を取得できます。
経済産業省が調査した「平成29年度電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査」によると、電気保安業界従事者の認定による資格取得比率が全体の55%、試験合格による資格取得比率が45%でした。つまり、試験合格よりも認定取得の方が多いのが現状です。
試験受験か認定取得どちらを選択して資格を取得するかは、認定取得のメリット・デメリットを把握した上で判断しましょう。
■認定取得のメリット
- 受験せず資格取得できる(試験勉強の負担がない)
- 働きながら資格取得ができる
- 実務経験が直接資格取得につながる
■認定取得のデメリット
- 一定の取得条件を満たす必要がある
(電験三種取得後5年以上の実務経験,認定校卒業後3~5年の実務経験 等) - 認定取得の手続きが煩雑
(各地の電力保安課に書類提出する,実務経歴書の記入条件が厳格である 等) - 面接が厳しい
(広範な知識と経験が必要となる)
以上のように、認定取得できるメリットは大きいのですが、取得条件や手続きなど取得までの条件も厳しいです。一般的に、認定取得までには約半年程度の期間が必要なので、すぐに資格が得られるわけでもありません。
実務経験を積みながら段階的に資格取得を目指すなら「認定取得」、短期間で資格を取得したい場合は「試験受験」の方が適している可能性があります。
どちらの方法を選択するにせよ、電験二種の資格取得には相応の努力と時間が必要です。自分に合った方法を選び、着実に目標に向かって進んでいくことが重要です。
電験二種の資格試験まとめ

電験二種は電気設備管理を担う、難易度の高い国家資格です。試験制度や科目、スケジュール、試験対策を理解することが合格への第一歩となります。
以下、電験二種の詳細を解説していきます。
電験二種とは?
電験二種(第二種電気主任技術者)は、電気事業法に基づいて定められた国家資格です。
| 詳細 | |
|---|---|
| 正式名称 | 第二種電気主任技術者 |
| 扱える設備の範囲 | 電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物 |
| 業務範囲 | 発電所、変電所、工場などの電気設備の工事・維持及び運用に関する保安・監督 |
電気主任技術者の業務内容は、独占業務として法律で定められているため、電気工事士では行えない範囲の業務を行うことも可能です。また、電験三種よりも高度な知識と技術が要求され、より広範囲の電気設備を扱うこともできます。
電験二種の資格者は、電気の安全性を確保する重要な役割を担うため、電力会社や大規模施設からの需要も高くなっています。また、将来的なキャリアアップを考えている人にとっては、価値のある資格として人気が高いです。
電験二種の試験科目
電験二種の試験は、一次試験と二次試験の2段階で実施されます。各試験の科目と内容は以下の通りです。
■一次試験(4科目)
| 科目 | 出題範囲 | 問題数 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 理論 |
|
A問題4問 B問題3問 |
90分 (9:15~10:45) |
| 電力 |
|
A問題4問 B問題3問 |
90分 (11:25~12:55) |
| 機械 |
|
A問題4問 B問題3問 |
90分 (14:15~15:45) |
| 法規 |
|
A問題4問 B問題3問 |
65分 (16:25~17:30) |
一次試験はマークシート方式で実施され、各科目100点満点で合計400点満点です。特に『理論』は、合格率が40%を下回る年度が多く、難易度が高いと言われています。
なお、CBT方式の試験は、電験三種では実施されていますが、電験二種および電験一種では行われないので注意してください。
■二次試験(2科目)
| 科目 | 出題範囲 | 問題数 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 電力・管理 |
|
6題中4題を選択 | 120分 (10:00~12:00) |
| 機械・制御 |
|
4題中2題を選択 | 60分 (13:20~14:20) |
二次試験は記述式で実施され、電力・管理から4問、機械・制御から2問を選択して解答します。一次試験が基礎的な知識を問われるのに対し、二次試験はより実戦的な知識や応用力が問われる問題が多いです。
なお、一次試験・二次試験については、各科目ごとに概ね60%以上の得点が必要とされていますが、合格基準は年度によって変動しますので注意が必要です。
電験二種の試験科目を詳しく知りたい方は、「令和6年度 第一種・第二種電気主任技術者試験(一般財団法人 電気技術試験センター)」をご確認ください。
電験二種の試験スケジュール
電験二種の試験は年1回実施され、一次試験と二次試験が別日程で行われます。
2024年度(令和6年度)の試験スケジュール等は以下の通りです。
なお、令和6年度の受け付けは既に終了しています。
■電験二種 試験実施スケジュール
| 項目 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 申し込み期間 | 2024年5月20日(月)~6月6日(木) | |
| 受験票の発送日(一次試験) | 2024年7月31日(水) | |
| 一次試験日 | 2024年8月18日(日) | |
| 受験票の発送日(二次試験) | 2024年9月30日(月) | |
| 二次試験日 | 2024年11月10日(日) | |
| 試験結果発表日 | 2025年1月24日(金) | |
| 受験手数料(非課税) | インターネット申し込み | 13,800円 |
| 郵便による書面申し込み | 14,200円 | |
参考:令和6年度電気主任技術者試験の実施日程等のご案内(一般財団法人 電気技術試験センター)
通常、一次試験は8月中旬から下旬に実施され、二次試験は11月上旬から中旬に行われます。合格発表は、一次試験が9月下旬、二次試験が翌年1月下旬頃に行われています。
また、前回の一次試験に合格し二次試験で不合格だった方は、今回の一次試験が免除されるため二次試験から受験することが可能です。
試験のスケジュールは年度によって多少の変動がありますので、最新の情報は「一般財団法人電気技術者試験センター」の公式サイトで確認するようにしましょう。
電験二種の試験対策・勉強方法
電験二種の試験に合格するためには、試験日程から逆算して学習スケジュールを計画し、効率的に勉強する必要があります。
試験勉強での学習ポイントを下記にまとめました。
| 項目 | 学習ポイント |
|---|---|
| 基礎知識の習得 |
|
| 過去問演習 |
|
| 計算問題の練習 |
|
| 記述力の向上 |
|
全ての項目について共通して言えることは、試験時間を意識しながら勉強することです。
また、一般的に600時間以上の学習時間が必要とされていることから、仕事と両立しながら計画的に勉強時間を確保する必要もあるでしょう。
まとめ
この記事では、電験二種(第二種電気主任技術者)の難易度について詳しく解説しました。主な内容は以下の通りです。
- 電験二種は平均合格率20%未満の難関試験
- 科目合格留保制度を使えば、合格した科目の試験が免除される
- 一定の条件を満たせば認定取得制度が利用できる
- 資格試験に合格するには効率的な学習が欠かせない
電験二種は、資格取得の難易度は相当高いものの、電気業界での需要が高く、キャリアアップや独立開業など仕事の幅を広げられるため、挑戦する価値が十分にあります。計画的かつ効率的に学習すれば、取得できない資格ではありません。
この記事が電験二種を目指す方のお力添えになれば幸いです。

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
電気主任技術者の求人を探す
電気主任技術者のおすすめ求人

株式会社日紅コンストラクション
昇給5万円の実績有◆経験の多さは武器になる。日本を股にかけよう!|太陽光発電の電気工事/資格経験不問..

株式会社モールス
【年休120日】需要高★通信設備の工事・保守点検など/資格・経験不問<家族手当・退職金あり>/正社員
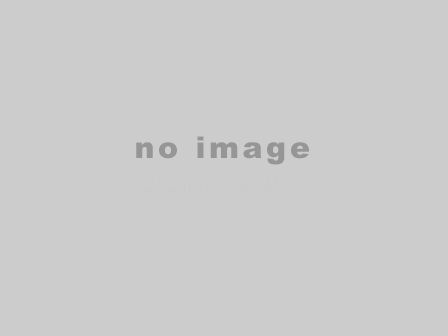
株式会社フルコー
太陽光発電システム設置に関する電気工事施工管理/正社員

高橋電業株式会社
【資格不問/未経験大歓迎!二種電工お持ちの方優遇◎】月給28.5万円~!<公共施設などの電気工事>/..

アルファ・テック合同会社
【残業月20h以下】展示会やイベント会場などの電気工事◆資格・経験不問《一人親方も募集中》/正社員・..
電気主任技術者の求人一覧
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする