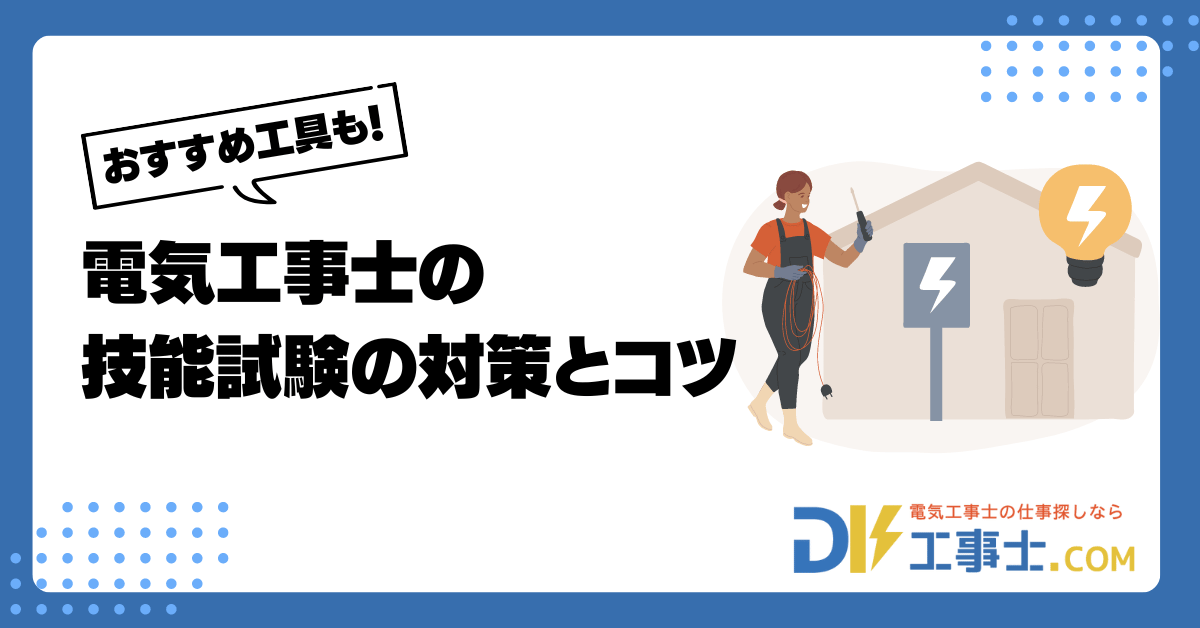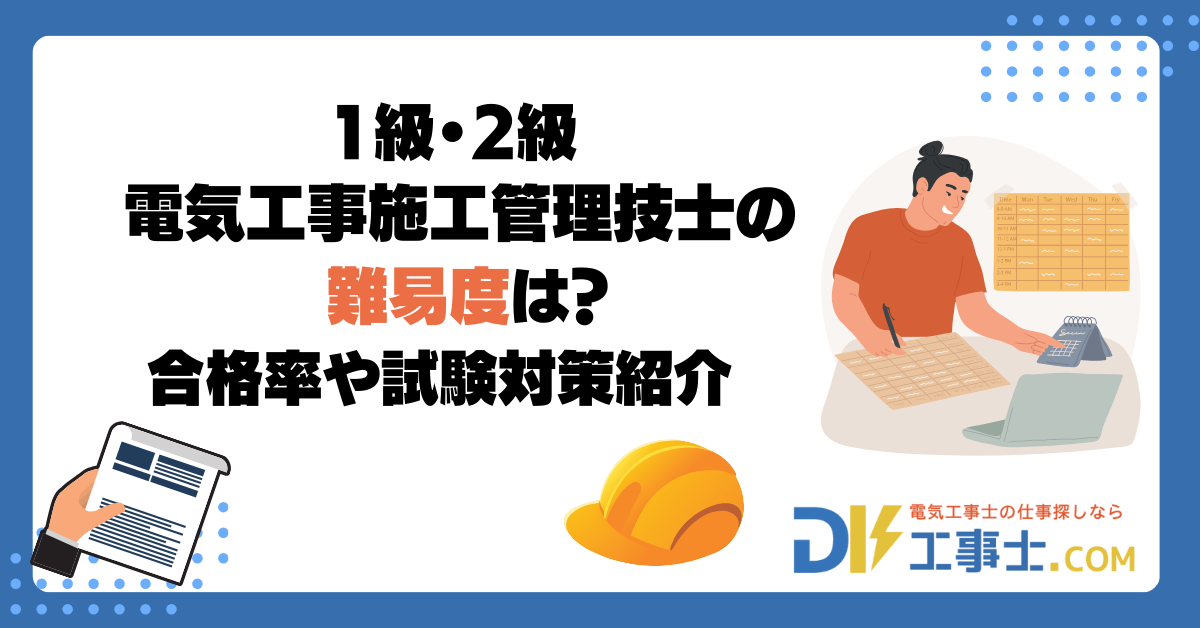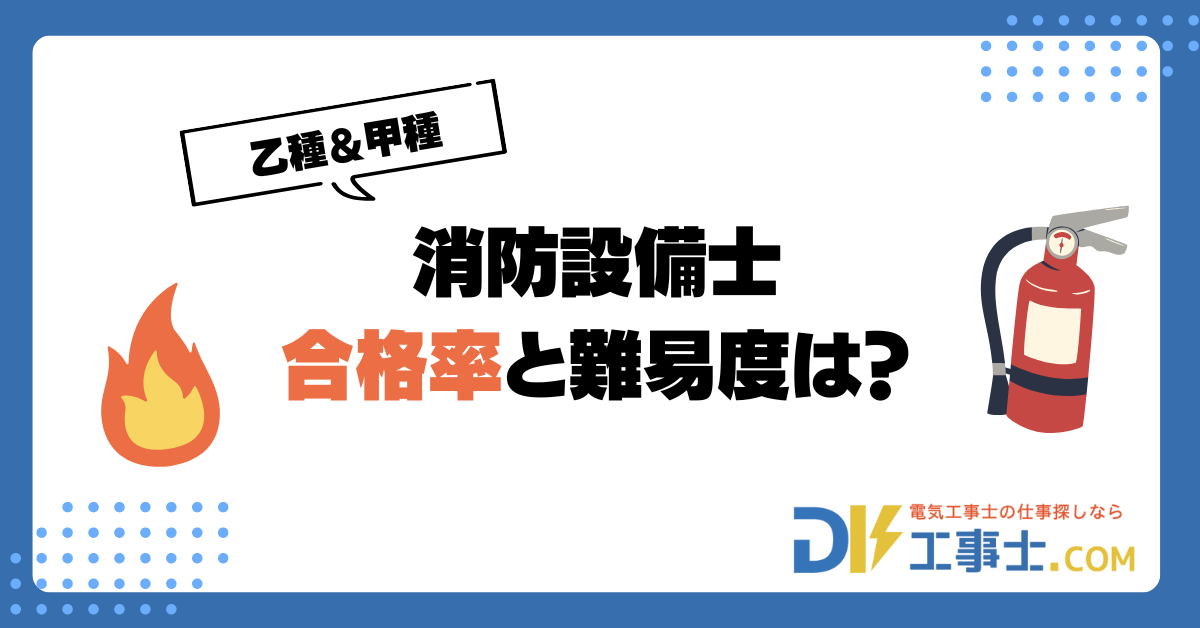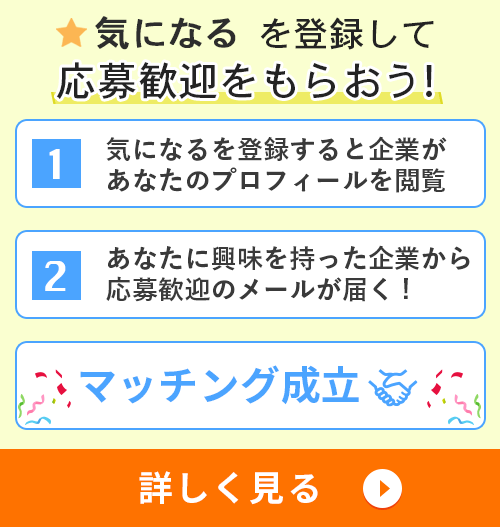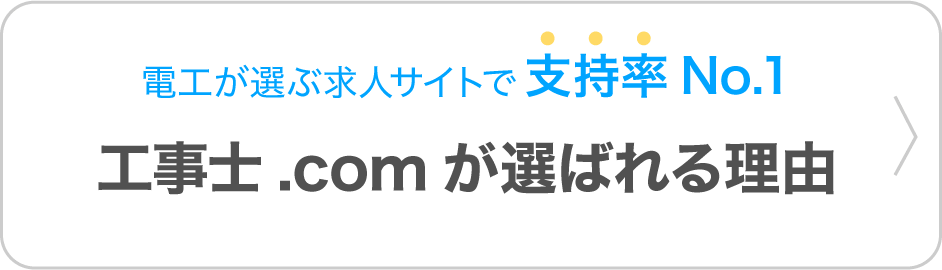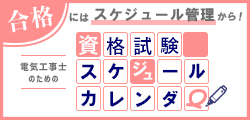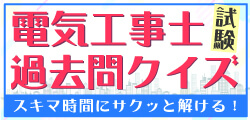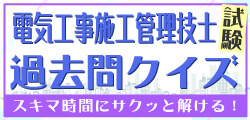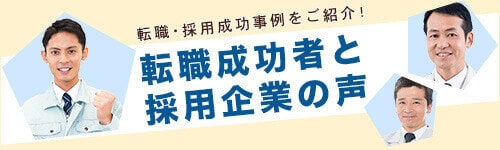第二種電気工事士の計算問題は捨てるべき?メリットデメリットや解くコツを紹介
電気工事士の資格・試験最終更新日:
第二種電気工事士の学科試験の計算問題は、「捨てるべきだ」という声も多く聞きますが、適切な対策を取ることで得点源にできます。
第二種電気工事士の学科試験の計算問題は、特に苦手としている受験者が多くいます。
しかしながら、計算問題をマスターすることで、第二種電気工事士学科試験合格の可能性を高めることができるでしょう。
本記事では、計算問題の特徴や種類、頻出公式から、具体的な解き方のコツまで、詳しく解説します。
第二種電気工事士学科試験の合格を目指す方は、本記事を参考にしてみてください。
■関連記事
第二種電気工事士学科試験の出題範囲ごとの勉強ポイントは下記記事で詳しく解説しています。
第二種電気工事士試験の計算問題は捨てるべき?
第二種電気工事士試験では、計算問題以外の科目で点数を取れれば、計算問題が解けなくても合格は可能です。しかし、計算問題も解けた方が学科試験の合格により近づくことができます。
そこで、計算問題がどのような特徴を持っているのかを理解し、計算問題を捨てるべきかどうかを考えましょう。
計算問題を捨てることのメリットとデメリットを把握しておくと、より最適な学習計画を立てられます。
計算問題の特徴
第二種電気工事士学科試験の計算問題には、以下のような特徴があります。
■ 第二種電気工事士学科試験 計算問題の特徴
- 出題範囲が限定されている
出題範囲は、「基礎理論」と「配電理論及び配線設計」に限られているため、基本的な計算問題(抵抗、電力、力率、電圧降下など)しか出題されません。そのため、高度な数学の知識はそこまで必要ありません。 - 過去問とほぼ同じ問題が出題されることがある
第二種電気工事士の学科試験は基本的な公式の理解を問う問題が中心であるため、過去問と類似した問題や答えまで全く同じ問題が出題されることがあります。 - シンプルな計算問題を中心に出題される
複雑な計算は出題されず、四則演算と基本的な公式(オームの法則など)を組み合わせれば解ける問題がほとんどです。
上記の特徴を理解して学習すれば、計算問題を得点源にすることも十分に可能です。
しかし、それでも計算問題に苦手意識のある方は、計算問題を捨てることも戦略の一つです。次は計算問題を捨てるメリットをご紹介します。
計算問題を捨てるメリット
第二種電気工事士学科試験の計算問題を捨てることには、以下のようなメリットがあります。
■ 第二種電気工事士学科試験 計算問題を捨てるメリット
- 計算問題を捨てても合格できる
学科試験は全50問中、計算問題が約10問出題されます。試験の合格ラインは30問以上(60点以上)とされており、計算問題以外で十分に合格点に達するため、計算問題を解かなくても合格できます。 - 学習時間を効率的に使える
計算問題を捨てて、電気の基礎知識、配線理論、法令など暗記すれば解ける分野の問題に集中すれば、計算問題に時間を使いすぎず合格ラインを目指せます。 - 配点が高い科目に注力できる
配線図問題は20問と出題数が特に多く、暗記要素が強いです。そのため、配線図問題を解くために必要な知識や記号などを集中的に学習することで、効率よく得点を重ね、合格できる可能性を高められます。
これらのメリットを考慮すると、計算問題が苦手な場合は、思い切って捨てるという戦略も有効です。
計算問題を捨てるデメリット
第二種電気工事士学科試験の計算問題を捨てることには、以下のようなデメリットがあります。
■ 第二種電気工事士学科試験 計算問題を捨てるデメリット
- 最初から10問分の配点を捨てなければならない
計算問題を捨てると、最初から10問分(20点分)の配点を諦めることになります。そのため、合格ラインである60点を取るためには、残りの40問で高い正答率が求められます。 - 計算問題以外を間違えられなくなる
計算問題を全て捨てると、他の問題で失点した場合、不合格になる可能性が高くなります。 - 電気工事士としての仕事に影響する
試験対策として計算問題を避けてしまうと、実務で苦労したり、上位資格を目指す際に改めて学習が必要になったりする可能性があります。
計算問題を捨てるかどうかは、メリット・デメリットを十分に考慮して判断しましょう。
第二種電気工事士試験の計算問題の種類
第二種電気工事士学科試験の主な計算問題は、「基礎理論」と「配電理論・配線設計」の2種類から出題されます。
基礎理論では、電気の基本的な法則や回路計算に関する問題が出題され、配電理論・配線設計では、より実践的な電気設備の設計や施工に関する問題が出題されます。
ここからは、それぞれの科目について詳しく見ていきましょう。
基礎理論
基礎理論は、電気工事士としてだけでなく、電気技術者を目指す全ての方が理解しておくべき電気の基本事項を問う科目です。
電気は社会生活に不可欠なエネルギーであると同時に、扱いを間違えると感電や火災などの危険性も伴います。そのため、電気を扱う専門家として、 オームの法則をはじめとする電気の基礎理論を十分に理解しておく必要があります。
電気理論は、主に以下の4つの項目に分類できます。
■ 基礎理論の種類
- 電流、電圧、電力、及び電気抵抗
- 導体及び絶縁体
- 交流電気の基礎概念(正弦波交流、周波数、RL直列回路など)
- 電気回路の計算(オームの法則、抵抗の直列接続など)
基礎理論は、他の分野を理解するための土台となるため、しっかりと学習しておきましょう。
特に、オームの法則、電力の計算、交流回路の基礎(RLC回路)、三相交流回路は頻繁に出題されます。過去問を参考に、それぞれの計算方法を確実にマスターすることが重要です。
配電理論・配線設計
配電理論・配線設計では、電気工事士が現場で実際に電気設備を設計・施工・管理する上で必要となる、より実践的な知識が問われます。
具体的には、以下の項目に分類できます。
■ 配電理論・配線設計の種類
- 配電方式(単相2線式、単相3線式、三相3線式など)
- 電線と配線(電線の許容電流、電圧降下など)
- 幹線の施設(幹線の許容電流、過電流遮断器の定格電流など)
- その他(需要率・負荷率、力率改善、接地抵抗など)
配電理論・配線設計は、電気工事の安全と品質に直結する重要な分野です。
過去問を繰り返し解き、計算問題に慣れるとともに、関連法規(電気設備技術基準など)も合わせて学習しましょう。
第二種電気工事士試験の計算問題の公式一覧
第二種電気工事士学科試験の計算問題は、基本的な公式を確実に覚えて使いこなせるようになることが重要です。
第二種電気工事士試験の計算問題の公式は、以下の4つに分類できます。
- 直流回路
- 交流回路
- 交流回路(三相)
- その他
それぞれの主な公式は下記のとおりです。
■ 直流回路の主な公式一覧
| 項目 | 公式 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 電圧 (オームの法則) |
|
V:電圧【ボルト(V)】 I:電流【アンペア(A)】 R:抵抗【オーム(Ω)】 |
| 電流 |
|
V:電圧【ボルト(V)】 R:抵抗【オーム(Ω)】 |
| 電力 |
または
|
P:電力【ワット(W)】 |
| 合成抵抗(直列) |
|
全ての抵抗を足した値 |
| 合成抵抗(並列) |
|
逆数を合成して計算 |
■ 交流回路の公式一覧
| 項目 | 公式 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 電線の抵抗 |
|
R:抵抗【オーム(Ω)】 ρ:導電率【抵抗率(Ω・m)】 L:電線の長さ(m) A:断面積(m²) |
| 誘導性リアクタンス |
|
f:周波数(Hz) L:インダクタンス(H) |
| 容量性リアクタンス |
|
f:周波数(Hz) C:静電容量(F) |
| インピーダンス |
|
R:抵抗【オーム(Ω)】 |
| 力率 |
|
P:有効電力(W) S:皮相電力(VA) |
■ 交流回路(三相)の公式一覧
| 項目 | 公式 | 補足事項 |
|---|---|---|
| Y結線 (相電圧と線間電圧の関係) |
|
VL:線間電圧(V) VP:相電圧(V) |
| Y結線 (相電流と線電流の関係) |
|
IL:線電流(A) IP:相電流(A) |
| Δ結線 (相電圧と線間電圧の関係) |
|
Δ結線では、相電圧と線間電圧は同じ |
| Δ結線 (相電流と線電流の関係) |
|
線電流は相電流の√3倍 |
■ その他の公式一覧
| 項目 | 公式 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 電力量 |
または
|
P:電力(W) t:時間(h) |
| 発熱量 |
|
Q:発熱量【ジュール(J)】 I:電流(A) R:抵抗(Ω) t:時間(s) |
| 電圧降下(単相2線式) |
|
I:電流(A) R:片道の電線抵抗(Ω) |
| 電圧降下(単相3線式、中性線電流0の場合) |
|
中性線電流が0の場合、片道のみの電線抵抗で計算 |
| 電圧降下(三相3線式) |
|
三相では、線間電圧の影響を考慮し、√3 倍になる |
| 電力損失(単相2線式) |
|
電圧降下の式 2IR を利用し、電力損失を計算 |
| 電力損失(単相3線式) |
|
中性線電流が0の場合、片道のみの電線抵抗で計算 |
| 電力損失(三相3線式) |
|
三相の場合、各相で電力損失が発生するため3倍する |
これらの公式を覚え、過去問を繰り返し練習し、計算問題をマスターしていきましょう。
第二種電気工事士試験の計算問題を解くコツ
第二種電気工事士学科試験の計算問題は、一見難しそうに思えますが、コツを押さえることで解けるようになります。
計算問題を解くコツは、以下のとおりです。
計算問題を闇雲に解くのではなく、効率よく攻略するためのポイントを理解しましょう。
過去問を解いて傾向を掴む
第二種電気工事士学科試験の計算問題を解くコツは、過去問を繰り返し解き、出題傾向を把握することです。
第二種電気工事士学科試験の計算問題は、出題パターンがある程度決まっているため、過去問を分析することで出題傾向がつかめます。
第二種電気工事士試験の出題傾向は、以下のとおりです。
■ 学科試験計算問題の出題傾向
- 頻繁に出題される問題
抵抗の直列・並列接続、オームの法則、電力の計算、電線の抵抗、電圧降下、三相交流回路などが頻繁に出題される。 - 同じ数値の問題
特定の数値や回路図のパターンが繰り返し使われることがある。
具体的には、最低でも過去5年分、できれば10年分の過去問を解くことをおすすめします。
解説を読みながら、「どのような手順で解くのか」「どの公式を使うのか」を確認し、徐々に解き方を覚えていきましょう。問題文を見ただけで「この問題はあのパターンだ」と瞬時に判断できるようになれば、解答スピードも格段にアップします。
電気設備業界に特化した求人サイト「工事士.com」では、第二種電気工事士学科試験をクイズ形式で勉強できる「過去問クイズ」を配信しています。
スキマ時間の勉強ツールとして活用してみましょう。
公式を暗記する
第二種電気工事士学科試験の計算問題を解くためには、基本的な公式を暗記することが重要です。
公式を暗記すれば、計算問題を効率的に解けるようになり、時間短縮につながります。
公式を効率的に暗記するコツは、以下のとおりです。
■ 学科試験計算問題を効率的に暗記するコツ
- 頻出公式をリストアップする
試験によく出る公式をリストアップし、ノートや単語帳にまとめ、繰り返し見返せるようにする。 - 公式の意味を理解する
ただ丸暗記するのではなく、それぞれの公式が何を表しているのか(例えば、オームの法則は電圧・電流・抵抗の関係を表している)、どのような場面で使うのかを理解する。 - 語呂合わせやイメージと関連付ける
覚えにくい公式は、語呂合わせを作ったり、具体的な回路図などのイメージと関連付けたりすると、記憶に残りやすくなる。 - 実際に問題を解いてみる
公式を覚えたら、実際に問題を解いてみて、公式をどのように使うのかを確認する。問題を解くことで、公式の理解が深まり、記憶にも定着しやすくなる。
上記のコツを参考にして公式を暗記すれば、計算問題への苦手意識を克服しやすくなるでしょう。
選択肢を見て目星を付ける
第二種電気工事士学科試験の計算問題の選択肢は、正解を推測するための大きなヒントになります。
なぜなら、計算問題は四肢択一式で、選択肢の中には明らかに間違っているものや、計算結果と大きく異なるものが含まれている場合があるからです。
例えば、抵抗値を求める問題で、選択肢が 「0.5Ω、1Ω、10Ω、100Ω」となっていた場合、回路の状況から考えて、極端に小さい値や大きい値は除外できる可能性があります。
また、問題文を読んだ段階で、ある程度答えの範囲を予測できる場合もあります。例えば、「電圧降下を求める問題で、電線の長さや電流の値が小さい場合、電圧降下もそれほど大きくならない」と予想できます。
自分の得意な問題を見つける
第二種電気工事士学科試験の計算問題の中で、自分が得意な問題パターンを見つけて、確実に正答できるようにすることも重要です。
限られた試験時間の中で、全ての問題に均等に時間をかけることは難しいです。また、得意な問題から先に解くことで、精神的な余裕も生まれ、他の問題にも落ち着いて取り組めます。
得意な問題はさらに演習を重ねて確実に得点できるようにし、苦手な問題は基本的な公式の復習や簡単な問題からステップアップしていくことで、徐々に克服していきましょう。
まとめ
本記事では、第二種電気工事士学科試験の計算問題を捨てるべきか、また、計算問題を解くコツなどをご紹介しました。
- 第二種電気工事士学科試験の計算問題は、解けなくても合格基準点に達することはできるが、その分、他の問題を確実に正解しなければならないというデメリットもある
- 第二種電気工事士学科試験の計算問題は、出題範囲が限られ、過去問と似た問題が多かったり、基本的な公式で解けたりする問題が中心に出題される
- 第二種電気工事士学科試験の計算問題は、基礎理論と配電理論・配線設計の2分野から出題され、それぞれ頻出公式がある
- 第二種電気工事士学科試験の計算問題攻略のカギは、「過去問の傾向をつかむ」「公式を暗記する」「選択肢を絞る」「得意問題を把握する」など
第二種電気工事士学科試験の計算問題に苦手意識を感じている方も多いですが、傾向や公式を覚えてしまえば意外と解ける問題も少なくありません。
何と言っても、計算問題で点数を稼げると、その分学科試験合格への可能性も高まります。
本記事を参考に、自分に合った学習計画を立て、計算問題にも取り組んでみてはいかがでしょうか。

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
おすすめ求人

タツミ電気工業株式会社
[浜松市中心◎商業施設・工場などの電気工事]資格・経験不問/直行直帰OK/残業ほぼなし/社用車貸与/..

株式会社電工石火
賞与年3回『計4.5ヶ月分』実績あり◎経験者は月給30万円~!山口市などの電気工事/資格・経験不問/..

栗林機工株式会社
【賞与約5ヶ月分】コンテナクレーンの保守点検における施工管理/一種電工&経験必須《年休114日》/正..

株式会社E&Eテクノロジー
≪即日勤務OK≫社員全員が未経験スタート★頑張り次第でグングン昇給も叶う!◇電気工事士/資格経験不問..

さくら電気株式会社
《年休125日◇新築マンション・ビルの電気工事》神奈川メインで出張なし*資格経験不問*残業少なめ/正..
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする

|
【第二種電気工事士とは?】できることや第一種との違い・資格取得メリットを解説
第二種電気工事士
資格
試験
対策
活躍
|
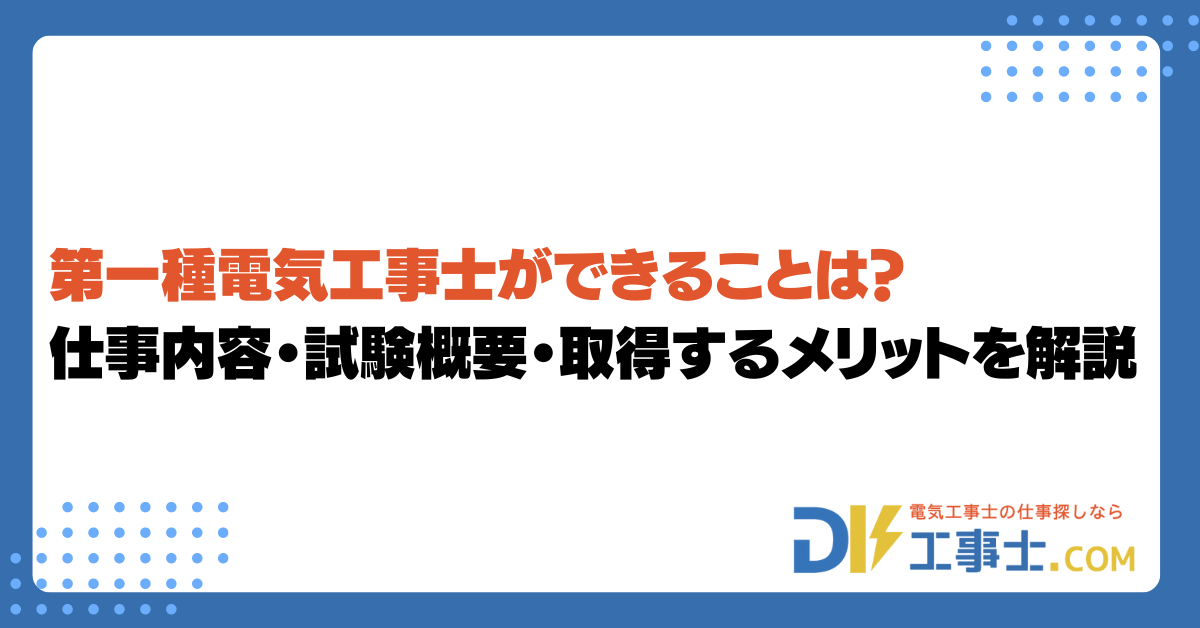
|
第一種電気工事士とは?仕事内容や第二種との違いから試験概要や勉強時間まで徹底解説
電気工事士
第一種電気工事士
資格
対策
仕事内容
|
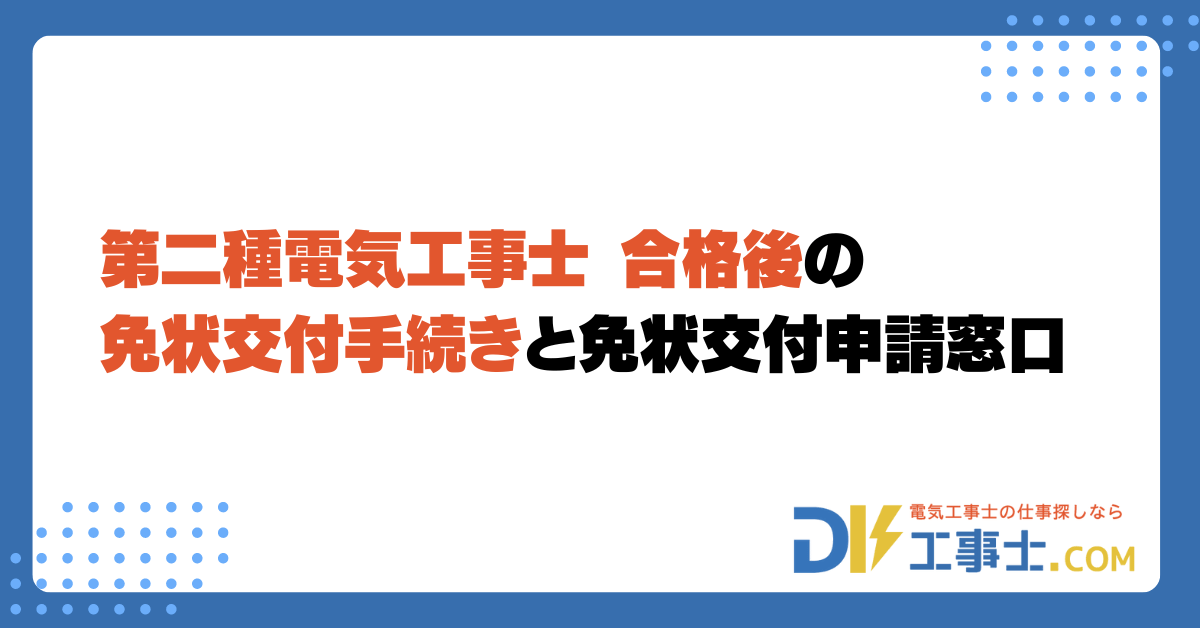
|
第二種電気工事士合格後の免状交付手続きを詳しく解説!申請期限や窓口情報まとめ
第二種電気工事士
資格
試験
|
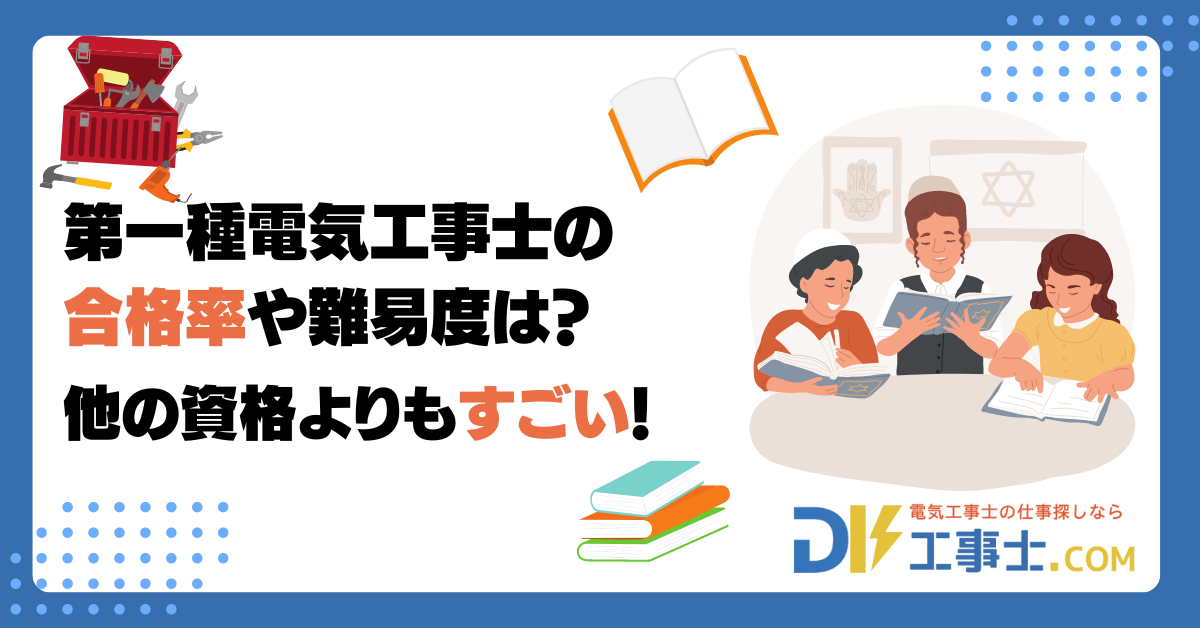
|
【実はすごい】第一種電気工事士の合格率は約56%!難易度を他資格と比較して解説
第一種電気工事士
資格
試験
|
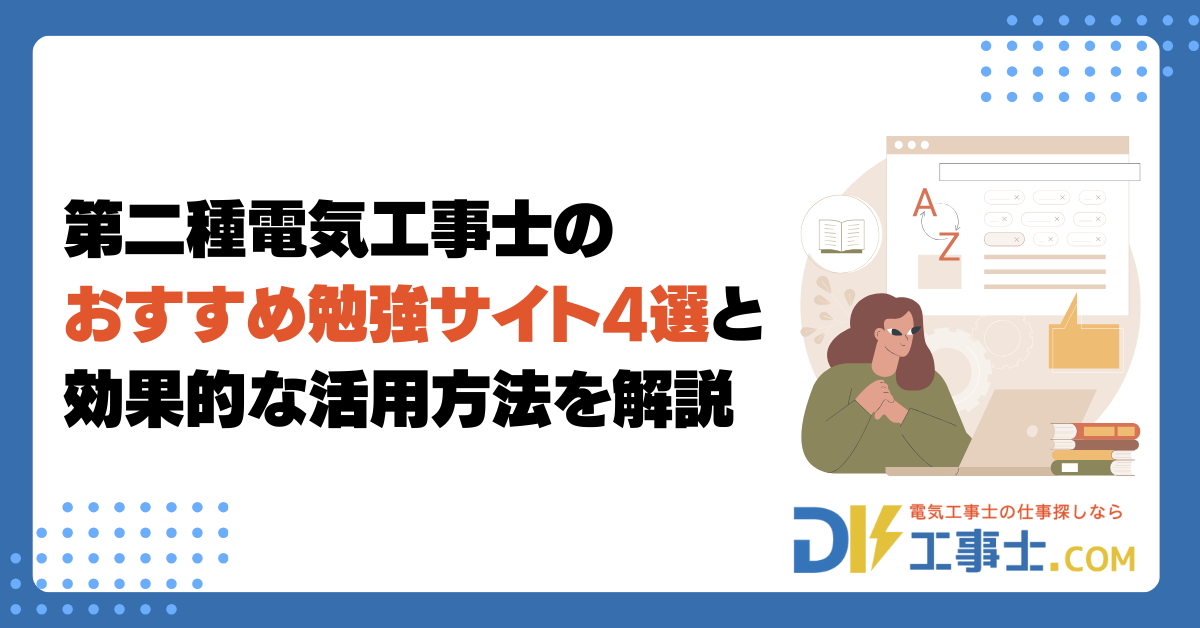
|
【無料】第二種電気工事士のおすすめ勉強サイト一覧!効果的な活用方法も解説
第二種電気工事士
試験
|