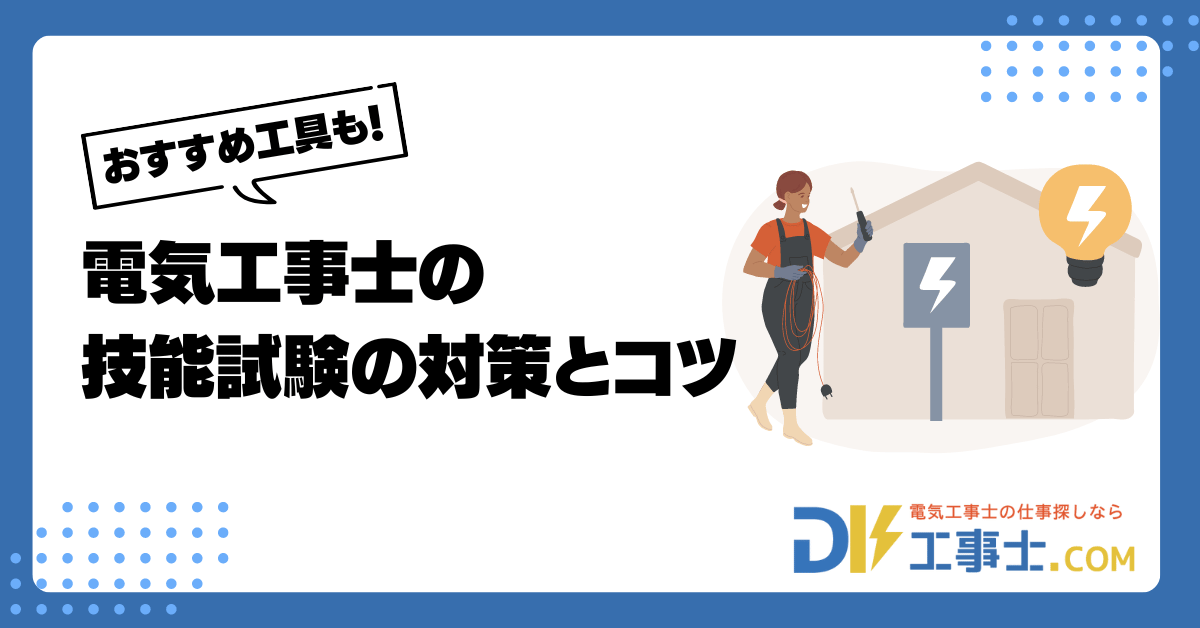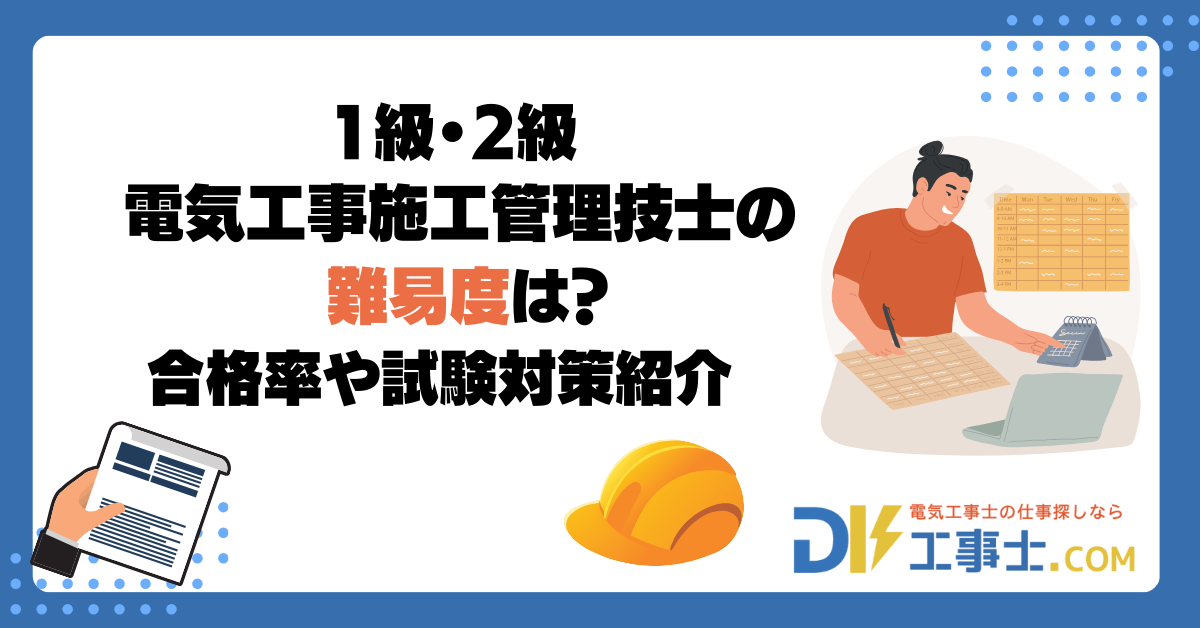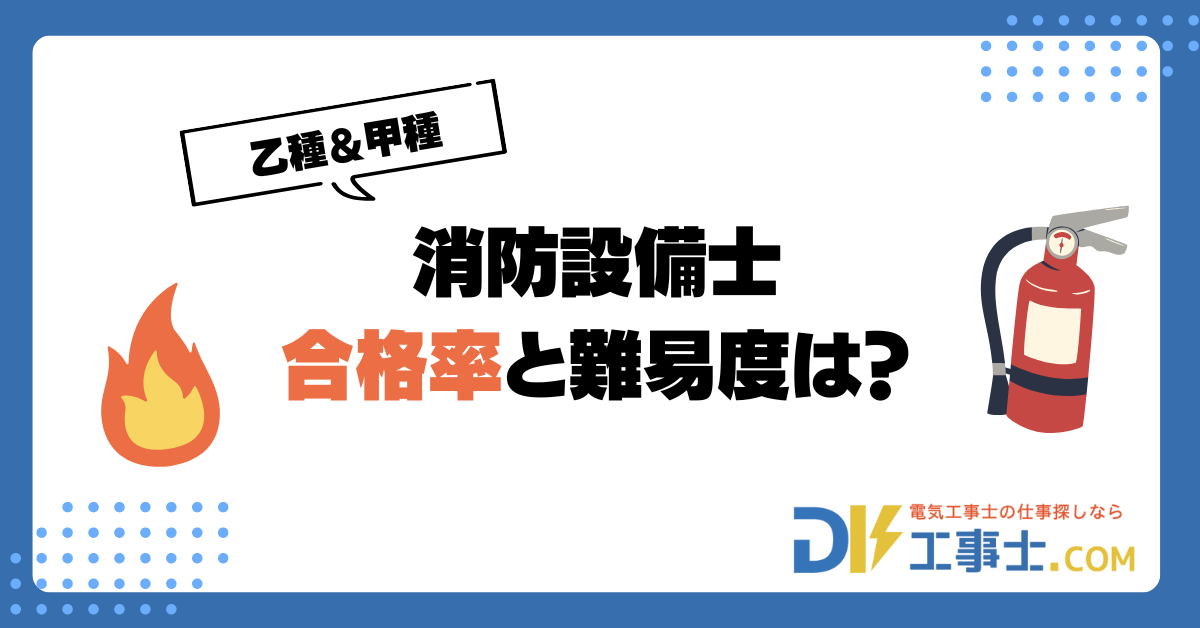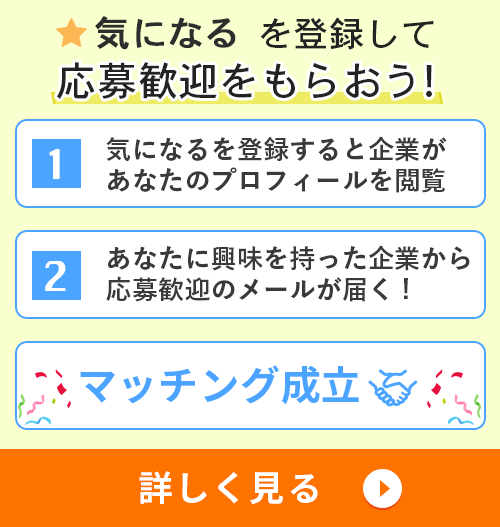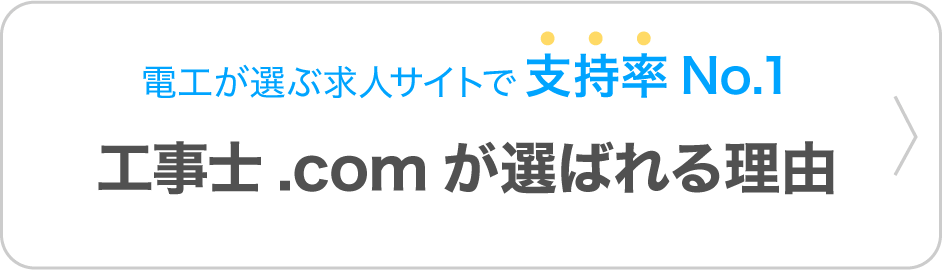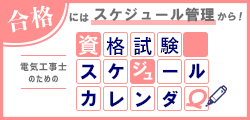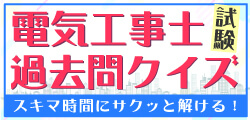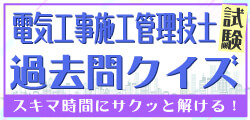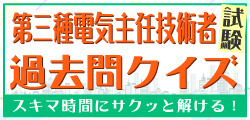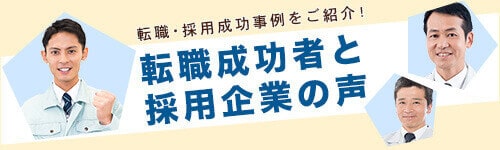第二種電気工事士の技能試験での欠陥とは?欠陥事例と対処法を解説!
電気工事士の資格・試験最終更新日:
「欠陥」とは電気工事の施工上の不備や誤りのことを指します。電線の接続ミスや損傷、器具の取り付け不良、電線の色別間違いなどが代表的です。
第二種電気工事士の技能試験では、欠陥が1つでも発生すると不合格となります。
この記事では、電気技術者試験センターが定める12項目の欠陥判断基準を詳しく解説します。
また、各器具の具体的な欠陥事例や防止方法、作業中に欠陥を発見した場合の対処法まで、実践的な内容を紹介していきますので、技能試験合格を目指す方は必見です。
第二種電気工事士の欠陥とは?
第二種電気工事士における「欠陥」とは、電気工事の施工上の不備や誤りを指します。
欠陥については、電気技術者試験センターが定める「欠陥の判断基準」に基づいて判定され、以下の12項目に分類されています。
- 未完成のもの
- 配置・寸法・接続方法等の相違
- 誤接続・誤結線
- 電線の色別や極性の相違
- 電線の損傷
- リングスリーブの圧着不良
- 差込形コネクタの接続不良
- 器具への結線不良
- 金属管工事の不備
- 合成樹脂製可とう電線管工事の不備
- 取付枠部分の不良
- その他の不適切な施工
以上の欠陥は、重大な事故につながる可能性があるため、実際の施工では細心の注意が必要です。
また、第二種電気工事士の技能試験では1つでも欠陥があると不合格となります。
第二種電気工事士の欠陥事例
電気工事の欠陥は、工事する箇所によって発生しやすいポイントが異なります。
- ランプレセプタクル
- 引っ掛けシーリング
- 露出型コンセント
- リングスリーブ
- 差し込みコネクタ
- 端子台
- 配線用遮断器
多くの受験生が苦戦しているのが、ランプレセプタクルでの作業ミス、コンセントの極性間違い、リングスリーブでの圧着不良などです。
いずれも実際の現場で行ってしまった場合は火災や感電の原因になりかねない重大な問題ですが、作業のコツを押さえればミスを防げます。
まずはランプレセプタクルでの欠陥事例から詳しく見ていきましょう。
ランプレセプタクルでよくある欠陥
ランプレセプタクルで最も注意が必要なのは、電線の接続方法です。
以下のよくある欠陥には注意しましょう。
- 結線の色別の欠陥

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p15」
- ねじから心線が5mm以上はみ出さない

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p29」
- 巻き付けによる処理が不適切

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p30」
- ケーブルは必ず台座の下から通す(上部からの配線は欠陥)

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p14」
以上の基本を押さえることで、欠陥のない施工ができます。
引掛シーリングで発生する欠陥
引掛シーリングは一見シンプルな器具ですが、細かい注意点は多いです。
代表的な欠陥として、以下の3つが挙げられます。
- 台座の下端から絶縁被覆が5mm以上はみ出すと欠陥

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p20」
- 差込口から心線が1mm以上見えると欠陥

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p32」
以上のミスを防ぐには、電線の被覆を剥く長さを正確に測ることが重要です。

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p44」
器具に表示されたストリップゲージを必ず参考にしましょう。
露出形コンセントの欠陥
露出形コンセントは、ランプレセプタクルと似た要領で施工しますが、独自の注意点があります。
主な欠陥ポイントは、以下の4つです。
- W表示側には必ず白色の電線を接続する
- ケーブルは必ず台座の下から通す(上部からの配線は欠陥)
- 右巻きで作り、ねじから5mm以上はみ出さない
- 配線が長すぎてカバーが閉まらない状態は欠陥

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p30」
特に心線の長さ調整は難しく、短すぎると接続が不十分になり、長すぎるとカバーが閉まりません。約1センチを目安に心線を剥くのがコツです。
リングスリーブでの圧着不良
リングスリーブでの圧着は、欠陥判定が最も厳しい作業の一つです。特に圧着マークの選択は、リングスリーブのサイズと電線の本数で決まるため注意してください。
よく見られる欠陥は、以下の3つです。
- 接続処理の欠陥

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p24」
- 被覆の噛み込み、スリーブ破損

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p23」
- 圧着マークの間違い

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p23」
圧着前には必ず電線の本数とリングスリーブのサイズを確認し、正しいダイスを選びましょう。圧着は確実に一発で決めることが大切です。
差し込みコネクタでの接続不良
差し込みコネクタは比較的簡単な作業に見えますが、意外な落とし穴があります。特に心線の露出は厳しくチェックされる部分です。
代表的な欠陥ポイントは、以下の3つです。
- コネクタの先端から心線が見えない

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p25」
- 下端から心線が飛び出している
- 被膜の剥きすぎ

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p26」
以上のミスを防止するには、コネクタを真横から見て確認することが大切です。一度挿入した電線を抜くときは、ペンチを使いねじるように引っ張ってください。
端子台で見られる欠陥
端子台での作業は、電圧の違いによって結線方法や注意点が異なります。見落としがちな部分も多いので、特に気をつけましょう。
主な欠陥のポイントは、以下の3つです。
- 結線図どおりに結線されていない

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p17」
- 端子台端から5mm以上の露出している
- 座金で絶縁被覆を挟んでしまっている

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p27」
特に200V回路では、R相に赤色、S相に白色、T相に黒色と電線の色を間違えないよう、施工条件をしっかり確認しましょう。
配線用遮断器(ブレーカー)での欠陥
配線用遮断器は、端子台同様に極性と結線方法に注意が必要です。作業は簡単に見えますが、細かな規定があります。
主な欠陥ポイントは、以下の4つです。
- N端子(接地側)には必ず白色電線を接続
- 器具の端から心線が5mm以上露出している

※引用元:電気技術者試験センター「技能試験の概要と注意すべきポイント p29」
- 端子への締め付けが弱く、心線がぬけてしまう
- 絶縁被膜を端子で挟んでいる
実際の施工では、必ず二次側(下側)の端子を使用し、一次側(上側)には接続しないよう注意しましょう。心線は約10mmを目安に被覆を剥くと、ちょうど良い長さで作業できます。
欠陥が発生する主な原因
電気工事の欠陥は、重大な事故につながりかねません。実際の現場でもよく見られる欠陥の原因は、大きく3つに分けられます。
- 誤った工具使用
- 施工手順の見落とし
- 電気器具や材料の選定ミス
以上の原因による欠陥は、技能試験でも多くの受験生が陥りがちです。
それでは、各原因について、具体的な事例を交えながら詳しく見ていきましょう。
①誤った工具使用
電気工事では、適切な工具を正しく使うことが欠陥防止の基本です。
特に以下の工具については注意しましょう。
| 工具 | 間違った使用方法 |
|---|---|
| リングスリーブ用圧着工具 |
|
| 電工ナイフ |
|
| VVFストリッパー |
|
工具は必ず使用方法を理解し、実際の作業前に練習を重ねることが大切です。
②施工手順の見落とし
電気工事で欠陥が発生する大きな原因の一つが、施工手順の見落としです。作業を急ぐあまり、基本的な手順を飛ばしてしまう場合があります。
例えば、ケーブルの外装を剥く前に長さを測り忘れたり、器具に結線する前に複線図の確認を怠ったりするケースが多く見られます。
現場や技能試験でよく起こる手順の見落とし例は、以下のとおりです。
■引っ掛けシーリング作業時
- ストリップゲージでの被覆剥きの長さの未確認
- 心線が露出するほど深く被覆を剥いてしまう
- 電線の極性(白・黒)の確認不足
■ランプレセプタクル取付時
- 台座下からのケーブル通し忘れ
- のの字曲げの向き確認漏れ
- カバーが閉まる長さの未確認
見落としを防ぐには、作業の前に手順を確認し、一つ一つチェックしながら進めることが重要です。慌てず、作業を行うことで確実な施工ができます。
③電気器具や材料の選定ミス
電気工事の欠陥で見落としがちなのが、器具や材料の選定ミスです。
その原因は、似たような形状の器具や材料を取り違えてしまうことにあります。例えば、リングスリーブのサイズを間違えたり、電線の太さや種類を取り違えたりするケースが多く見られます。
特にありがちな失敗例を見てみましょう。
■リングスリーブの選定ミス
- 電線2本なのに3本用を選ぶ
- 電線の太さに合っていないサイズを使用する
- 圧着工具のダイスを間違える
■電線の選定ミス
- VVFケーブルの太さを間違える
- 必要な心線数と異なる種類を選ぶ
- 色別の組み合わせを誤る
器具や材料の選定ミスを防止するには、作業前に施工図面や施工条件をよく確認し、必要な材料を正しく選定することが重要です。
一度取り付けてしまうと、やり直しに時間がかかってしまうので注意しましょう。
欠陥を防ぐためのコツとポイント
電気工事の欠陥を防ぐには、作業前の準備から作業後の確認まで、一連の流れを着実に行うことが大切です。
特に初心者は、基本的な部分で思わぬミスを起こしやすいです。
ここからは、多くの現場経験から得られた欠陥防止のコツを3つ紹介します。
まずは施工条件の読み込み方、次に適切な工具の使用方法、そして最後に見落としやすい確認ポイントについて、実践的なテクニックを交えながら解説していきます。
①施工条件をしっかり読み込む
欠陥を防ぐ第一歩は、施工条件をしっかり読み込むことです。
各候補問題には、施工条件が書かれているので必ず作業前に確認してください。

※引用元:電気技術者試験センター「令和6年度第二種電気工事士下期技能試験 公表問題№1」
施工条件を見落とすと、以下のような重大な欠陥につながります。
| 欠陥 | 内容 |
|---|---|
| 電線の色別を間違える |
|
| 接続方法の誤り |
|
そこで、注意すべき施工条件のチェックポイントをまとめました。
電線の色指定
- 電源の接地側:必ず白色
- 非接地側:必ず黒色
- 接地線:必ず緑色
器具の取付位置
- 取付枠の向き
- 器具の個数による取付位置
以上の条件を、必ず最初に確認してから複線図を作成し、作業に取り掛かりましょう。
②適切な工具を使用する
正しい工具の選択と使用方法は、欠陥のない施工の基本です。
以下の工具の使用では特に注意しましょう。
| 工具 | 使用方法 |
|---|---|
| リングスリーブ用圧着工具 |
|
| 電線ストリッパー |
|
| ペンチ・ニッパー |
|
誤った工具を持ち込んでしまうと作業に支障が出るため、自宅で必ず工具の再確認をしておきましょう。
③最終チェックで見落としをなくす
作業完了後の最終チェックは、欠陥を見つける最後のチャンスです。
よく見落とされる項目を機器別にまとめました。
| 器具 | チェック項目 |
|---|---|
| ランプレセプタクル |
|
| 引掛シーリング |
|
| リングスリーブ接続部 |
|
最終チェックのポイントは、以下のとおりです。
最終チェックのポイント
- 目視だけでなく、軽く引っ張って確認
- 真横からの確認で心線露出を確認
- 複線図と照らし合わせて確認
チェック項目を順番に確認して行けば、見落としを防げます。
ただし、最終チェックにかける時間を確保する必要があるため、最低でも終了時間の5分前までには作業を終了させておきましょう。
欠陥が発生した場合の対応方法
作業中に欠陥を見つけた場合の基本的な対応方法をまとめました。
欠陥を発見した場合は、落ち着いて対処することが重要です。
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 1、作業を中断する |
|
| 2、欠陥の状況を把握する |
■修正可能な欠陥
|
| 3、対処する |
■リングスリーブの場合
|
ただし、上記の対応方法は予備の部品がある場合に限られます。
技能試験では、時間との勝負になるため、練習時に欠陥への対処方法も含めて訓練しておくことが大切です。
欠陥に関するよくある質問(Q&A)
電気工事の欠陥について、よく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。実践的な内容を中心に解説します。
欠陥が発生する最も多い原因は何ですか?
欠陥が発生する最も多い原因は、作業を急ぐあまりに基本的な確認を怠ってしまうケースです。特に電線の色別や極性の確認不足が多く、白色の電線を接地側に接続するルールを守らなかったり、器具の極性表示(W、N、接地側)を見落としたりするミスが目立ちます。
また、焦りから複線図を誤って作成してしまい、電線の接続を間違えるケースも多く見られます。欠陥を防ぐには、施工条件をじっくり読み、複線図を正確に書いてから作業に取り掛かることが基本です。
第二種電気工事士実技試験で、欠陥は何個まで許されますか?
第二種電気工事士の技能試験では、1つでも欠陥があると不合格になります。以前は「重大欠陥」と「軽欠陥」の区別があり、軽欠陥は2つまで許容されていました。しかし、現在は全ての欠陥が同じ扱いとなり、1つでも欠陥があれば不合格となります。
その理由として、実際の電気工事では小さなミスでも重大な事故につながる可能性があるためです。例えば、電線の接続が少し緩いだけでも発熱や発火の原因となったり、被覆の傷から漏電が起きたりする危険があります。そのため、試験でも厳格な基準が設けられています。
欠陥が原因で不合格になった場合、再試験はできますか?
技能試験で不合格になった場合でも、次回の試験を再受験できます。第二種電気工事士試験は年2回(上期・下期)実施されており、どちらの回でも受験可能です。ただし、学科試験の合格は2年間だけ有効なので、その期間内に技能試験に合格する必要があります。
再受験のポイントは、前回の不合格だった原因をしっかり振り返ることです。多くの場合、同じような欠陥を繰り返してしまいがちです。苦手な作業を重点的に練習し、基本に立ち返って丁寧な作業を心がけることで、次回の合格につながるでしょう。
まとめ
今回は、第二種電気工事士試験における欠陥の定義や具体例、防止方法について詳しく解説しました。
- 欠陥は1つでも不合格になるため、施工条件の確認が重要
- 最も多い欠陥は電線の色別や極性の間違い
- 器具別の主な欠陥(ランプレセプタクル、引掛シーリングなど)を把握することが大切
- 欠陥防止には適切な工具の使用が不可欠
- 作業後の最終チェックで見落としを防ぐ
第二種電気工事士の技能試験合格には、欠陥のない施工が求められます。施工条件をしっかり読み、基本に忠実な作業を心がければ合格できます。
また、技能試験で出てくる知識は、実務においても重要な基礎となるため、しっかりと身につけておきましょう。

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
おすすめ求人

株式会社E&Eテクノロジー
≪即日勤務OK≫社員全員が未経験スタート★頑張り次第でグングン昇給も叶う!◇電気工事士/資格経験不問..

株式会社電工石火
賞与年3回『計4.5ヶ月分』実績あり◎経験者は月給30万円~!山口市などの電気工事/資格・経験不問/..

栗林機工株式会社
【賞与約5ヶ月分】コンテナクレーンの保守点検における施工管理/一種電工&経験必須《年休114日》/正..

さくら電気株式会社
《年休125日◇新築マンション・ビルの電気工事》神奈川メインで出張なし*資格経験不問*残業少なめ/正..

タツミ電気工業株式会社
[浜松市中心◎商業施設・工場などの電気工事]資格・経験不問/直行直帰OK/残業ほぼなし/社用車貸与/..
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする

|
【第二種電気工事士とは】できることは?仕事内容・メリット・試験内容を解説!
第二種電気工事士
資格
試験
対策
活躍
|
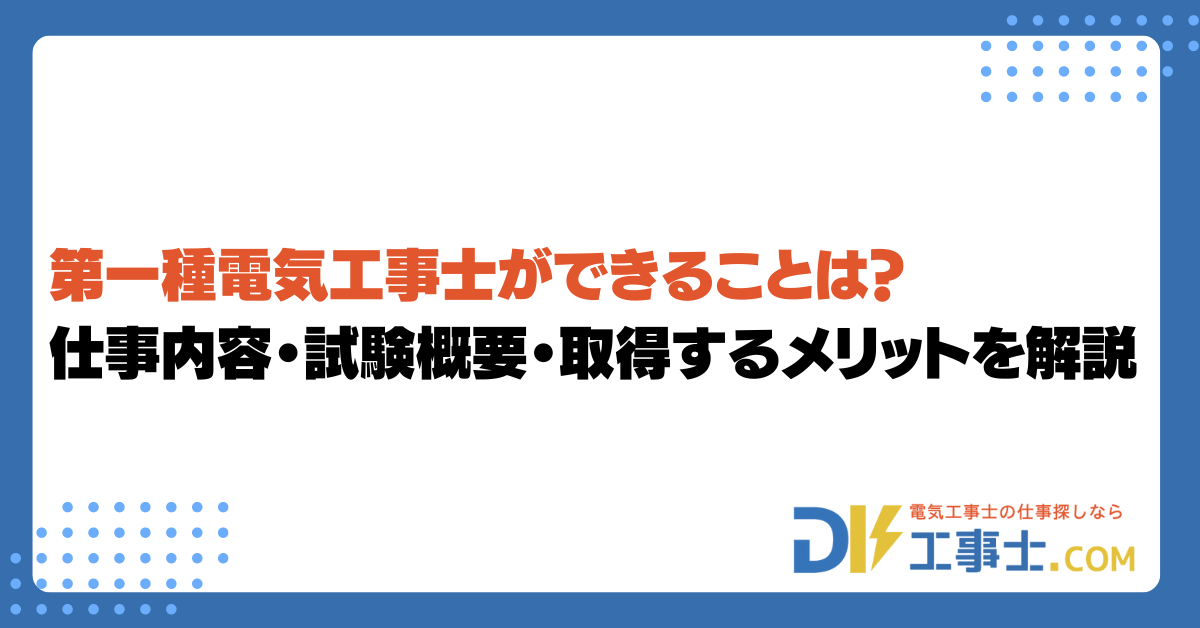
|
第一種電気工事士ができることは?仕事内容・試験概要・取得するメリットを解説
電気工事士
第一種電気工事士
資格
対策
仕事内容
|
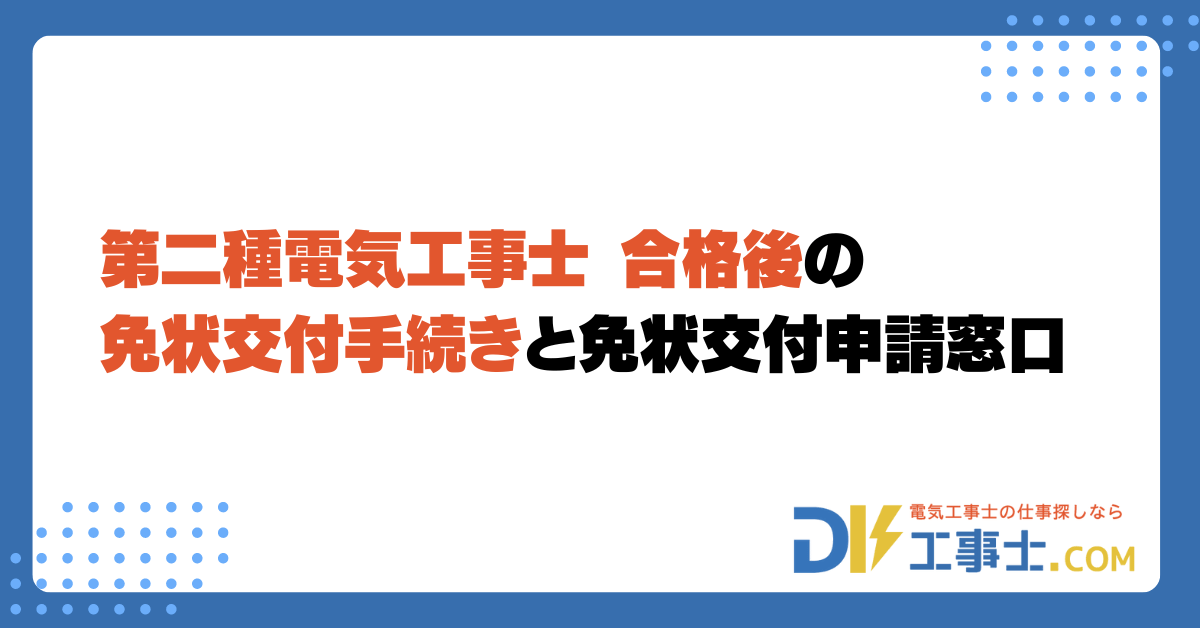
|
第二種電気工事士合格後の免状交付手続きを詳しく解説!申請期限や窓口情報まとめ
第二種電気工事士
資格
試験
|
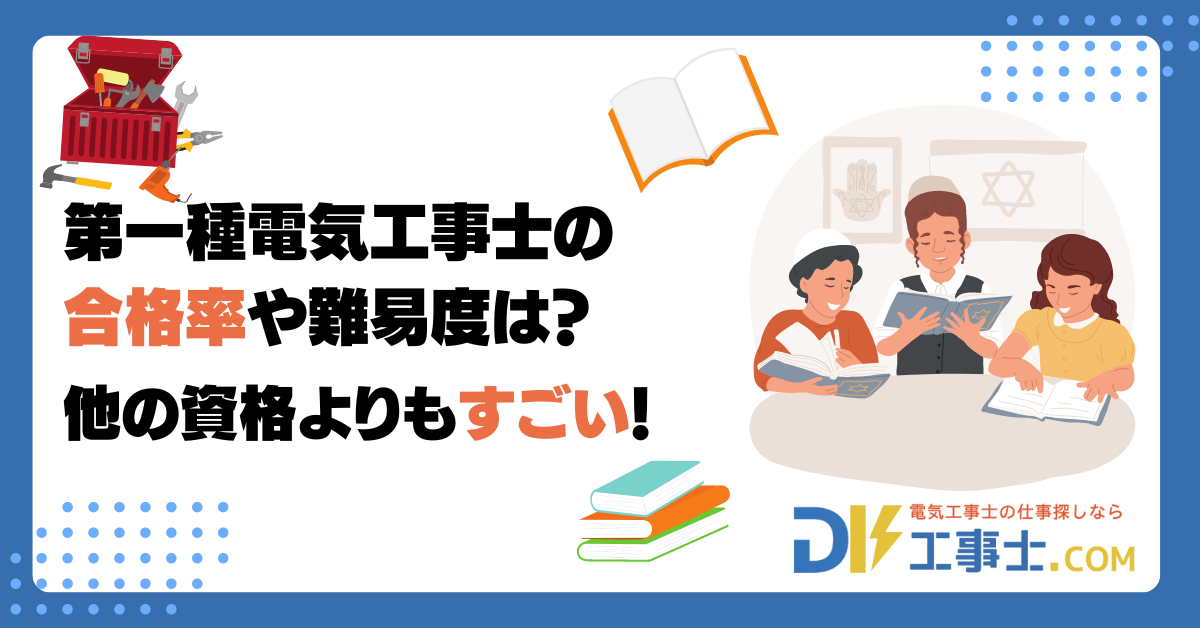
|
【実はすごい】第一種電気工事士の合格率は約56%!難易度を他資格と比較して解説
第一種電気工事士
資格
試験
|
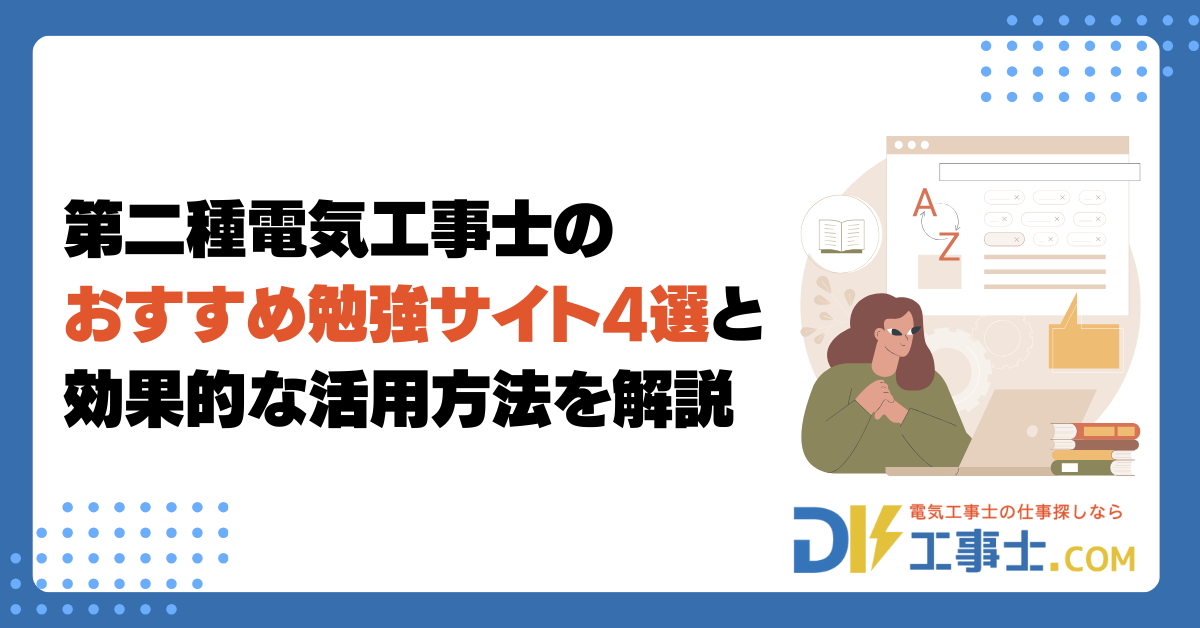
|
【無料】第二種電気工事士のおすすめ勉強サイト一覧!効果的な活用方法も解説
第二種電気工事士
試験
|