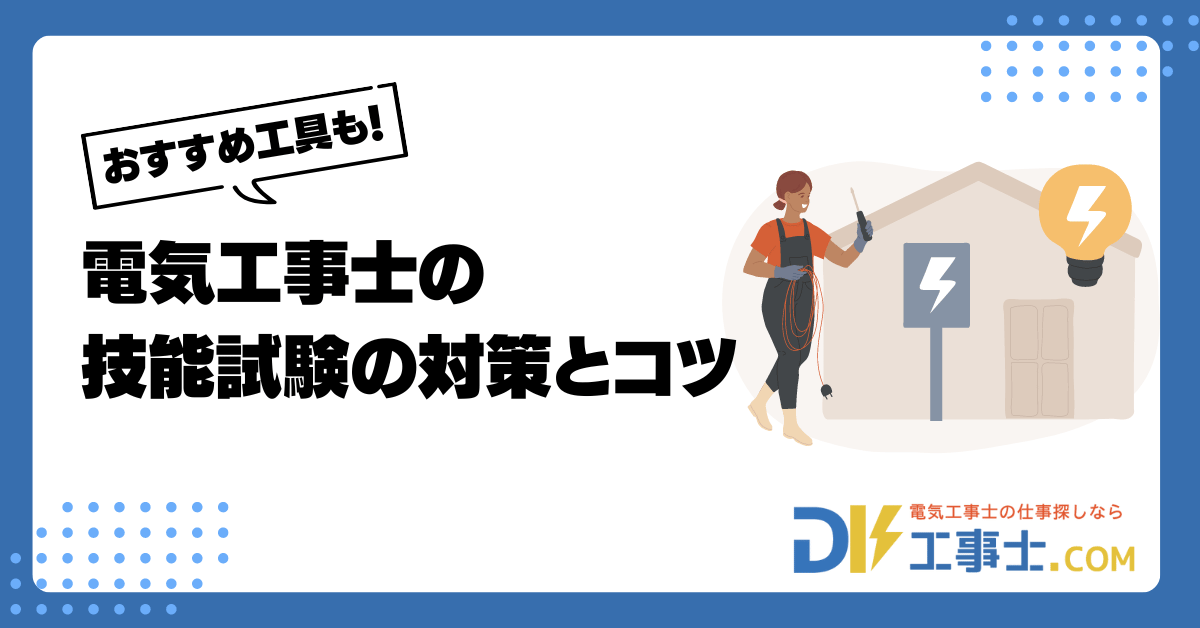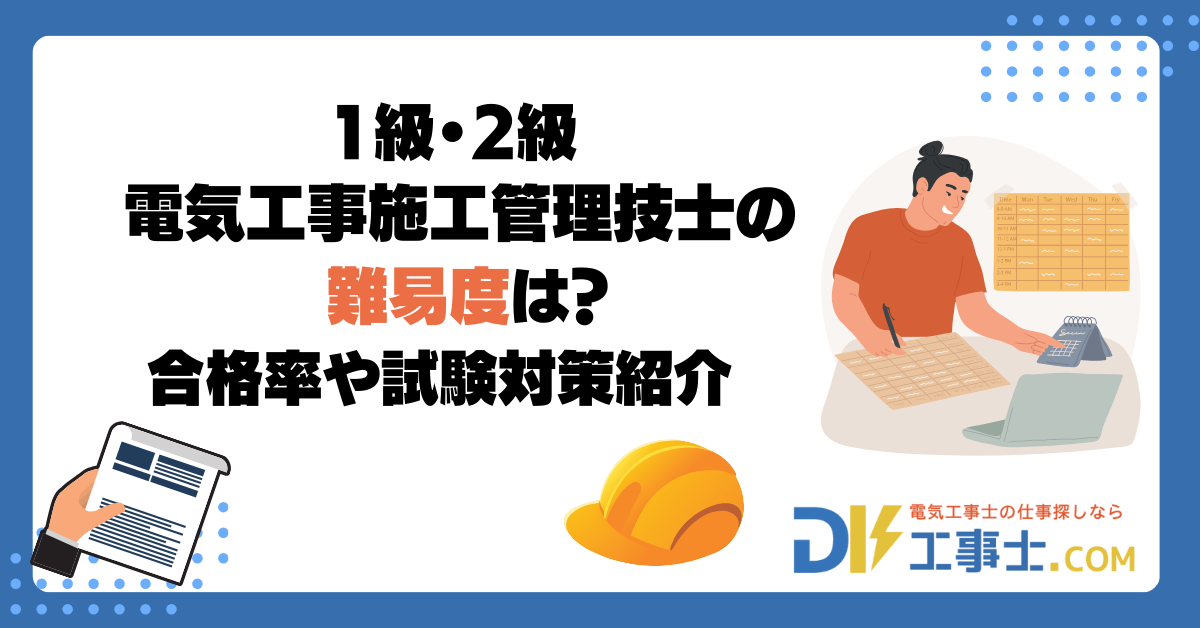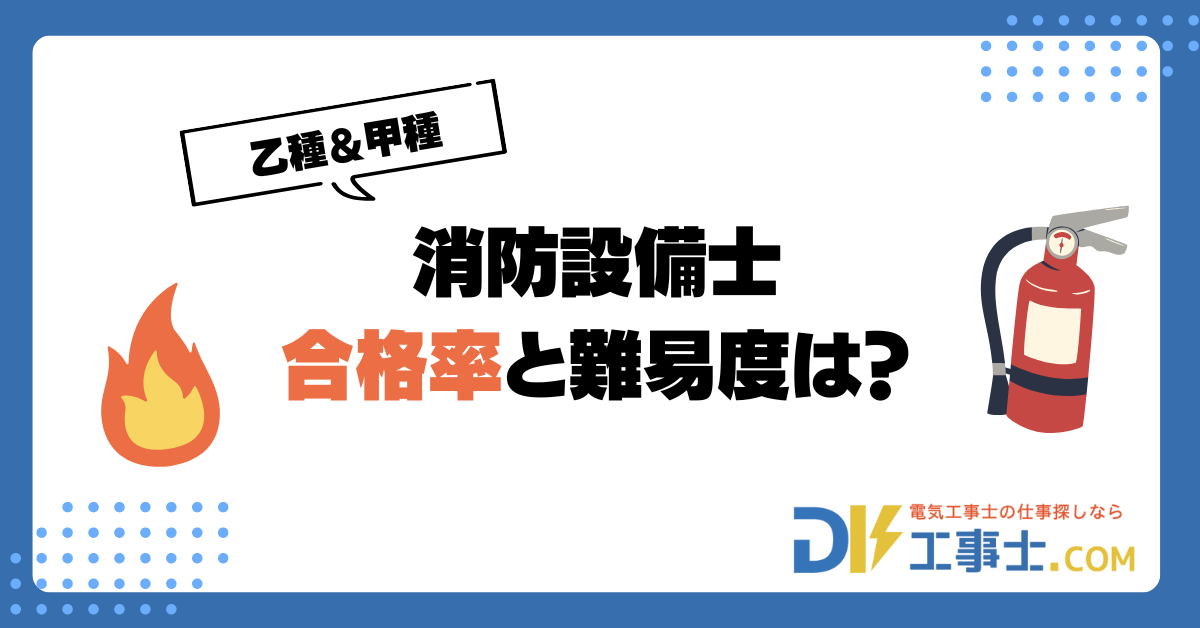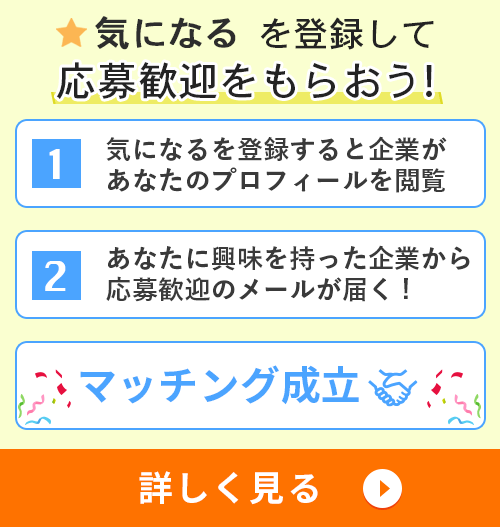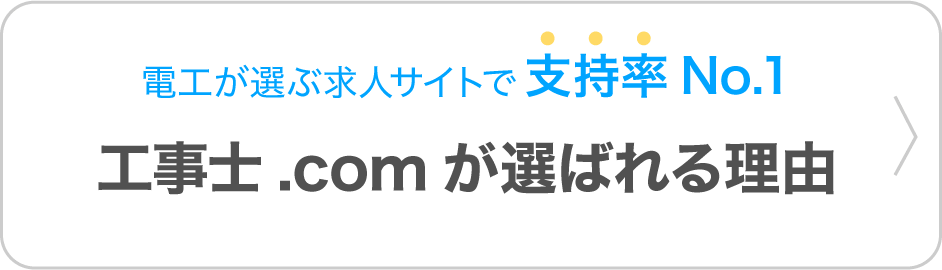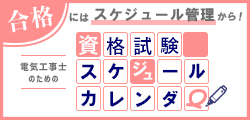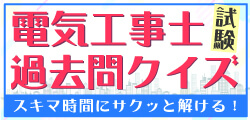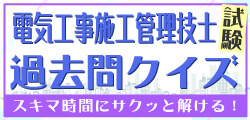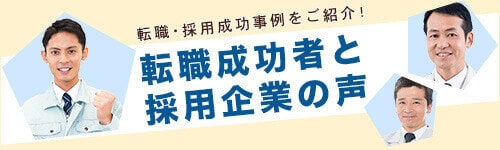第二種電気工事士の技能試験に落ちた原因は?よくある失敗や再試験への対策を解説!
電気工事士の資格・試験最終更新日:
第二種電気工事士の技能試験では、欠陥がたった1つでもあった場合、不合格となってしまいます。
また、不合格の場合でも具体的な欠陥箇所は公表されないため、次回の受験に向けた対策に悩む受験生が多いのが現状です。
この記事では、第二種電気工事士技能試験でよくある不合格の原因や、次回合格のための具体的な対策方法などを詳しく解説します。
第二種電気工事士の技能試験は、落ちてしまっても次回の学科試験を免除することができるため、もう一度技能試験の勉強をしっかり行えば合格しやすくなります。
この記事で、技能試験に落ちやすい原因と対策を確認して、第二種電気工事士の資格取得を目指しましょう。
第二種電気工事士技能試験の欠陥判定基準まとめ
第二種電気工事士の技能試験では、作品に1つでも欠陥があると不合格となります。
また、不合格となった場合でも具体的な欠陥箇所は公表されないため、「どこがダメだったのか分からない」という声も多いです。
次回の受験に向けた対策を立てるためにも、まずは合否の判断基準となる欠陥事項を把握しておきましょう。
第二種電気工事士技能試験の欠陥基準は、以下の12項目に分類されます。
■ 第二種電気工事士技能試験 主な欠陥判定基準
| 欠陥判定項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 1、未完成のもの |
|
| 2、配置・寸法・接続方法等の相違 |
|
| 3、誤接続・誤結線 |
|
| 4、電線の色別・極性の相違 |
|
| 5、電線の損傷 |
|
| 6、リングスリーブによる圧着接続不良 |
|
| 7、差込形コネクタによる接続不良 |
|
| 8、器具への結線不良 |
|
| 9、金属管工事の不良 |
|
| 10、合成樹脂製可とう電線管工事の不良 |
|
| 11、取付枠の不良 |
|
| 12、その他 |
|
以上のように、技能試験の合否は非常に細かい判断基準に基づいて決定されます。そのため、合格するためには、欠陥基準をしっかりと理解し、施工時に細心の注意を払わなければなりません。
また、完成作品が欠陥基準に該当していないかどうか、作業完了後の見直しも重要です。
なお、一部の欠陥(例:ランプレセプタクルなどの台座の欠けなど)については判定対象外になっています。ただし、基本的には1つでも欠陥があれば不合格となるため、慎重に作業しましょう。
第二種電気工事士技能試験に落ちた原因でよくある失敗10選!
第二種電気工事士の技能試験では、「練習では完璧だったのに」と感じながらも、不合格となってしまうことも珍しくありません。
「第二種電気工事士技能試験の欠陥判定基準まとめ」でご紹介したとおり、欠陥の判定基準は事前に公開されていますが、実際の試験では細かな部分での施工ミスが目立ちます。
ここからは、技能試験に落ちた原因の中でも特に起こりやすい失敗を10個ピックアップし、具体的な対策方法とともに解説していきます。
1.試験時間内に終わらなかった
第二種電気工事士技能試験で最も悔しい不合格の理由は、「施工が制限時間内に終わらなかった」ケースです。
第二種電気工事士技能試験の試験時間は40分ですが、慣れないうちはあっという間に過ぎてしまいます。
試験時間内に終わらない原因は、主に以下の3つが考えられます。
■ 技能試験が制限時間内に終わらない原因
- 1つ1つの作業が遅く、時間配分が上手くできていない
- 作業手順を考えずに施工を始めてしまう
- 途中で欠陥に気づいて作業をやり直してしまう
たとえ他の作業が完璧でも、未完成な部分が一ヶ所あれば即不合格となってしまいますので、制限時間は特に気をつけましょう。
2.器具の配置を間違えた
器具の配置の間違えも、欠陥基準に該当するため即不合格になる原因です。
よくある配置ミスの具体例を見てみましょう。
■ 技能試験で起こりやすい器具の配置ミスの具体例
- 取付枠を指定箇所以外に使用する
- スイッチの取付位置を間違える(2個用の場合は中央を空ける)
- 3路スイッチの入切の向きを間違える
特に多いのが取付枠の配置ミスです。スイッチは1個用、2個用、3個用で取付位置の基準が異なるため注意が必要です。
ミスを防ぐためには、問題用紙に記載されている施工条件をしっかり読み込み、施工前に配線図と器具の位置を複線図に書き込んでおくと良いでしょう。
3.ケーブルの寸法が指定よりも短くなっていた
ケーブルの寸法違いも見落としがちなポイントです。
第二種電気工事士技能試験では、ケーブルが指定寸法の50%以下になると欠陥と判定されてしまいます。
ケーブルの寸法が指定よりも短くなる原因は、主に以下のとおりです。
■ ケーブルの寸法が指定よりも短くなる原因
- 複線図に寸法を書き忘れる
- ケーブルを切断するときに目分量で切る
- 慌てて外装を多く剥きすぎる
- 器具の接続部分の長さを考慮していない
技能試験本番では、焦ってケーブルを短く切りすぎても追加支給はありません。
したがって、寸法違いを防ぐためには、複線図への長さ記入、スケールでの計測、接続部分の余裕、切断前の再確認を心がけましょう。
4.ケーブルが損傷している
技能試験では「ケーブルを剥く時に傷つけてしまった」といった失敗も多いです。
外装の損傷や心線の露出は重大な事故につながる可能性があるため、即不合格となってしまいます。
ケーブル損傷の具体例は下記のとおりです。
■ ケーブル損傷と判断される具体例
- 外装に20mm以上の縦割れがある
- ケーブルを折り曲げたときに絶縁被覆が見える
- 心線を折り曲げたときに折れそうな傷がある
- 電線被覆を剥く時に心線まで傷つけてしまう
特に注意が必要なのが、VVFケーブルの外装剥き作業です。力の入れ過ぎやカッターの刃の角度で思わぬ傷をつけてしまうこともあります。
損傷を防ぐには、電工ナイフやストリッパーで電線被膜を剥く作業を日ごろから練習しておきましょう。また、作業台への押し付けに気をつけながら、少しでも傷をつけたと感じたら直ちに確認することが大切です。
5.結線時にケーブルを剝き過ぎた
結線時のケーブル外装の剥き過ぎは、欠陥基準の中でも特に見落としがちな失敗のひとつです。
特に心線が露出してしまうと漏電や感電の危険があるため、不合格の対象となります。
ケーブルを剥きすぎた場合の不合格例は、以下のとおりです。
■ ケーブル外装の剥き過ぎの具体例
- 端子台の高圧側で20mm以上の心線露出
- 端子台の低圧側で5mm以上の心線露出
- ランプレセプタクルやコンセントでねじ端から5mm以上の露出
- 引掛シーリングで台座下端から5mm以上の絶縁被覆露出
施工時のポイントは、「外装を剥く長さは必ず器具の形状を確認してから決める」ことです。
また、心線被覆を剥く際はストリッパーのゲージマークを目安にし、迷ったらやや短めを心がけましょう。一度剥き過ぎてしまうと元には戻せないため、慎重に行う必要があります。
6.ランプレセプタクルの結線が間違っていた
ランプレセプタクルの結線ミスは、受験者が頭を悩ませるポイントの一つです。
ランプレセプタクルの結線は、一見簡単そうに見える作業ですが、細かい注意点が多く合否を分ける重要な作業となっています。
ランプレセプタクル結線の代表的な失敗パターンを見てみましょう。
■ ランプレセプタクルの結線ミスの具体例
- ケーブルを台座の引込口に通さなかった
- 心線の巻き付けが3/4周以下だった
- 左巻きで心線を巻いてしまった
- ねじの端から心線が5mm以上はみ出した
- カバーが閉まらなかった
特に多いのが、「心線の巻き付け不足」と「心線のはみ出し」です。試験中の焦りから、巻き付けが甘くなったり、心線を長く残してしまったりすることが多くあります。
ランプレセプタクルの結線では、まず心線を右巻きで時計回りに巻き付け、ねじの端から心線がはみ出ないように締め付けることが重要です。また、カバーが閉まるかどうかの確認も忘れずに行いましょう。
7.スイッチ・コンセントの渡り線を忘れた
渡り線はうっかり忘れてしまうことの多い作業で、「忘れ線」とも言われています。
たった1本の渡り線がなかっただけでも回路は正常に動作しないため、即不合格となります。
渡り線の典型的な失敗例は、以下のとおりです。
■ スイッチ・コンセントの渡り線のミス例
- 埋込連用タンブラスイッチの渡り線を忘れる
- 2個口コンセントの渡り線を忘れる
- 渡り線の色を間違える(非接地側は黒色)
- 渡り線が1本必要なのに2本入れてしまう
- 渡り線を後回しにして忘れてしまう
失敗例の中には、作業の後半で焦って渡り線を忘れてしまうケースも多いです。また、複線図で書いた線の中でも渡り線は見落としやすいです。
施工時は複線図を描く段階で渡り線の位置を赤丸でマークしておき、器具取り付け時に必ず確認するようにしましょう。
8.ねじなしボックスコネクタの止めねじをねじ切っていなかった
ねじなしボックスコネクタの止めねじ切りは、意外と見落としがちな欠陥ポイントです。
頭部がねじ切れるまで締め付けなければ接続強度が保てないため、ねじ切り作業を怠ると合格できません。
止めねじは、必ずウォーターポンププライヤーでしっかりと締め付け、ねじ頭部が切れて脱落したことを確認しましょう。
9.リングスリーブの圧着マークを間違えた
リングスリーブの圧着マークの間違いも、技能試験で失敗しやすい箇所です。
電線の太さと本数に応じた正しい刻印で圧着しないと、接続部の強度が保てないため即不合格となります。
第二種電気工事士技能試験で頻繁に発生している間違いをまとめました。
■ リングスリーブの圧着マークの失敗例
- 「○」刻印のところを「小」で圧着した
- 「小」刻印のところを「○」で圧着した
- 1つのリングスリーブに複数の圧着マークを付けた
- 圧着マークが端にかかり欠けている
- 圧着の向きが違って刻印が出ない
作業に慣れてくると仕上がりが雑になり、上記のようなミスが起きやすくなります。
圧着マークの間違いを防ぐには、電線の太さと本数を確認してから圧着工具を選び、圧着位置も慎重に決めることが重要です。また、圧着後は必ず刻印を目視確認し、間違いがあれば新しいリングスリーブを使い作業をやり直しましょう。
10.リングスリーブの圧着処理を間違えた
リングスリーブの圧着処理は、ただ圧着するだけではなく細かなルールが定められています。
正しい圧着処理ができていないと、接続不良による発熱や断線の原因となるなど電線の接続強度を左右する重要な作業のため、試験では厳しくチェックされます。
具体的な失敗例は、以下のとおりです。
■ リングスリーブの圧着処理の失敗例
- 絶縁被覆の上から圧着してしまう
- 心線が上端から5mm以上露出している
- 心線が下端から10mm以上露出している
- より線の素線が一部挿入されていない
- 心線の先端がリングスリーブの上から見えない
特に多い失敗が、絶縁被覆を噛んでしまうケースです。被覆を剥く長さが適切でないと、被覆まで圧着してしまいがちなので注意しましょう。圧着時は、心線が確実にリングスリーブに挿入されているかを確認し、被覆を噛まない位置で圧着することが大切です。
また、圧着後は心線の露出具合を上下両方から必ずチェックしましょう。一度失敗したら、躊躇せずに新しいリングスリーブで作業をやり直すこともおすすめです。
第二種電気工事士技能試験に落ちた時の対策法
第二種電気工事士技能試験に落ちてしまった場合は、次回の学科試験が免除されるため、技能試験の対策に集中できます。
ここでは、次回の技能試験合格に向けたおすすめの実戦的な対策法をご紹介します。
複線図を書いて練習する
技能試験で合格するための第一歩は、複線図を何度も書くことです。
複線図があいまいだと、配線や結線の間違いに直結します。
まずは、ミスを意識しながら何度も配線図を書く練習を行い、候補問題13問をそれぞれ5分以内には書けるようにしておきましょう。何度も配線図を書いているうちに、施工時の迷いや失敗を大幅に減らせます。
第二種電気工事士の複線図の書き方については「【図解でわかる】複線図の書き方5ステップ!第二種電気工事士試験に受かるコツまで」で詳しく解説しています。
試験時間を想定して練習する
計画的な時間配分と練習が、技能試験合格への近道です。 本番の40分を意識した練習を重ねることで、時間配分の感覚を掴めます。
理想的な時間配分は、複線図5分、施工30分、見直し5分です。
練習では毎回タイマーをセットし、各作業にかかる時間を計測しましょう。時間のかかっている作業が見つかれば、その部分だけを何度も練習することで、確実にスピードアップできます。ただし、焦って雑な作業になるのは禁物です。
練習の段階から欠陥のセルフチェックを行う
練習のうちから本番同様の厳しい目で欠陥をチェックする習慣をつけましょう。
施工が終わったら1つ1つの欠陥項目をチェックし、少しでも気になる箇所があれば修正します。
この習慣が身につけば、本番でも落ち着いて確認作業ができるはずです。
苦手な作業を集中的に練習する
技能試験の候補問題は13問もあるため、苦手意識を持つ作業が出てくるのは当然です。
しかし、苦手作業を克服しないと本番で焦って致命的なミスに繋がる可能性があるため、全体練習だけでなく苦手な作業の練習も徹底的に行いましょう。
■ 苦手克服のための重点練習ポイント
- ランプレセプタクルの輪作り
- リングスリーブの圧着
- VVFケーブルの外装剥き
- スイッチ類の渡り線接続
- コネクタへの差し込み
まずは候補問題13問の課題を一通り練習し、自分の苦手作業を洗い出すことから始めましょう。
苦手克服のポイントは、通し練習とは別に時間を設けて集中的に練習することです。
第二種電気工事士技能試験に落ちた後の流れは?
第二種電気工事士技能試験に落ちてしまっても、すぐに諦める必要はありません。
次回の試験では学科試験が免除されるため、技能試験の対策に集中できるからです。
第二種電気工事士技能試験に落ちた後の流れは、以下のとおりです。
1. 試験に落ちた原因を分析する
第二種電気工事士技能試験では、不合格の具体的な理由は公表されません。
そのため、試験時の作業を思い出しながら、何のミスがあったのか原因を探ることが重要です。
まずは、以下の項目を振り返ってみましょう。
■ 試験後の振り返りチェックリスト
- 制限時間内に完成できたか
- 複線図は正確に書けたか
- 作業手順に間違いはなかったか
- どの作業に時間がかかったか
- 見直しの時間は取れたか
例えば、練習では余裕があったのに本番で時間が足りなかった場合、作業の順番や工具の使い方に問題がある可能性があります。
冷静になって振り返ることで、次回の試験では同じ失敗を防げるでしょう。
2. 再受験の申し込みをする
次回の第二種電気工事士試験に向けて、申し込み手続きを行いましょう。
学科試験に合格していれば、次回の試験に限り学科試験が免除されます。
学科試験免除時の申し込みは、基本的に通常の受験申し込み手続きと同様に行います。試験区分で「学科試験 免除者」を選択すれば学科試験が免除できます。
第二種電気工事士の申し込み方法については、「第二種電気工事士の申し込みと試験日」にて詳しく解説しています。
3. 再受験に向けて練習する
再受験のための実技練習は、前回の技能試験に落ちた原因の工程を中心に何度も行いましょう。
技能試験に合格するポイントは、本番で緊張しても問題ないほど各作業をスムーズにこなせるようになることです。そのためには、どれだけ練習に時間を充てられるかが重要です。
第二種電気工事士の技能試験の合格に向けた対策法については、「第二種電気工事士の技能試験(実技)とは?対策方法5つや準備・よくあるミスを解説」で解説していますので、あわせてご覧ください。
まとめ
今回は、第二種電気工事士の技能試験に落ちた原因や対策について、詳しく解説しました。
- 第二種電気工事士技能試験は、欠陥事項が1つでもあると不合格になる
- 第二種電気工事士技能試験でよくある失敗は、「時間切れ」と「基本作業のミス」など
- 第二種電気工事士技能試験に落ちた場合、具体的な欠陥箇所は公表されないため分析する必要がある
- 第二種電気工事士技能試験に落ちてしまっても、次回は学科試験が免除されるため技能試験の勉強に専念できる
第二種電気工事士の技能試験は、たった1つの欠陥も許されない厳しい試験です。
しかし一度技能試験に落ちてしまっても、失敗の原因を分析し、基本作業の習得と時間配分の練習を重ねることで、もう一度合格を目指せます。諦めずに、1つ1つの作業を丁寧に見直していきましょう。

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
おすすめ求人

株式会社大電通
<未経験OK><残業月10h>電気通信設備工事・電気工事/資格経験不問【NTT関連の取引多数】/正社..

株式会社プログレス
《引越費用支援&借上社宅あり》電気工事・電気通信工事スタッフ/資格経験不問*残業月10h*/正社員
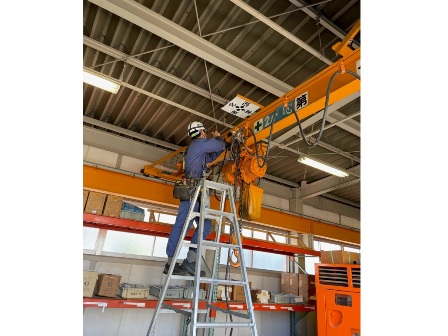
内藤工機株式会社
残業月平均10h以下★賞与実績計3ヶ月分★各種手当充実|クレーンなどのメンテナンス|資格経験不問/正..

KS電設株式会社
【最大15万円の入社祝金 or 社宅でサポート】電気・計装工事の施工や施工管理/経験資格不問/正社員

株式会社EAST B
【二種電工必須&経験不問】直流電源設備や蓄電池の電気工事◇年間休日120日程度◇努力を見逃さない環境..
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする

|
【第二種電気工事士とは?】できることや第一種との違い・資格取得メリットを解説
第二種電気工事士
資格
試験
対策
活躍
|
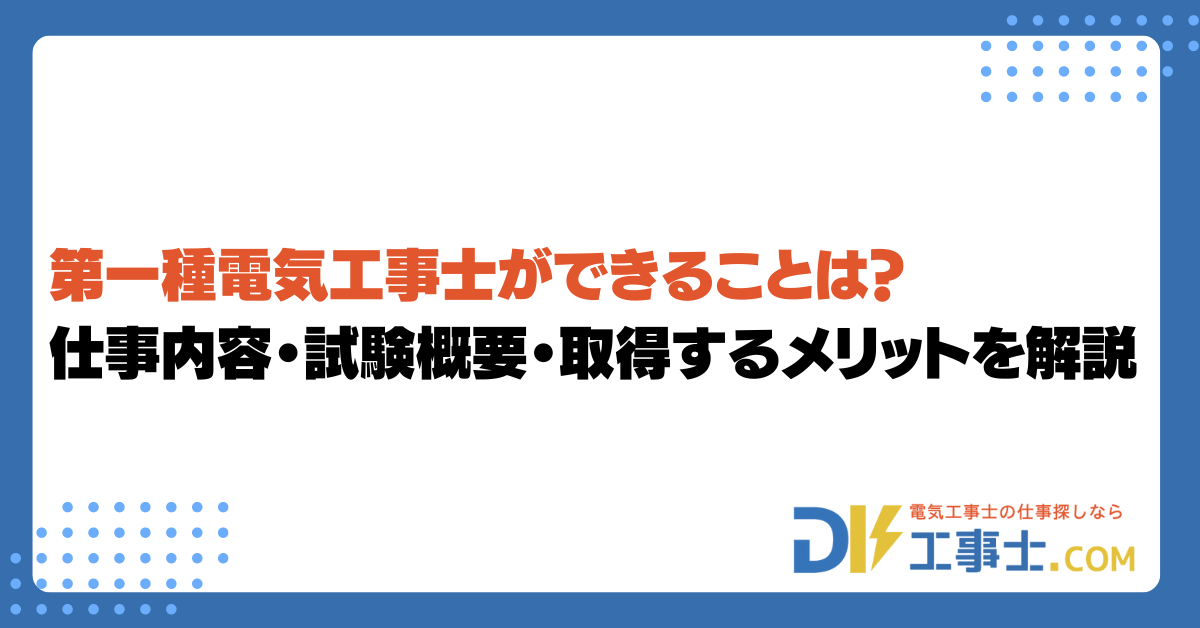
|
第一種電気工事士とは?仕事内容や第二種との違いから試験概要や勉強時間まで徹底解説
電気工事士
第一種電気工事士
資格
対策
仕事内容
|
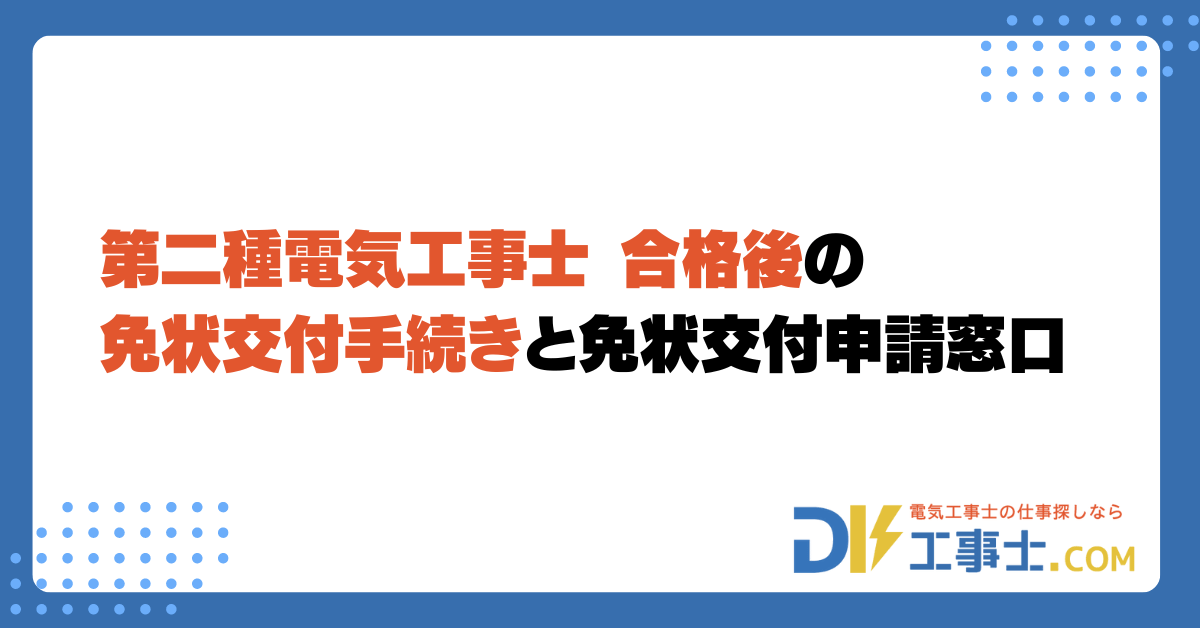
|
第二種電気工事士合格後の免状交付手続きを詳しく解説!申請期限や窓口情報まとめ
第二種電気工事士
資格
試験
|
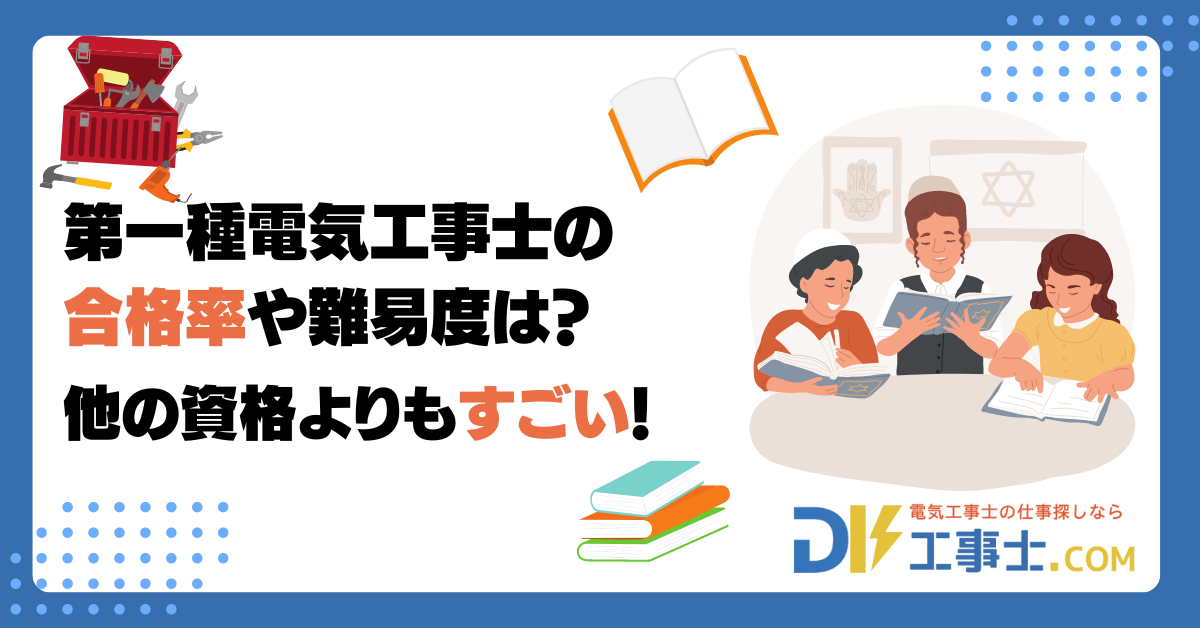
|
【実はすごい】第一種電気工事士の合格率は約56%!難易度を他資格と比較して解説
第一種電気工事士
資格
試験
|
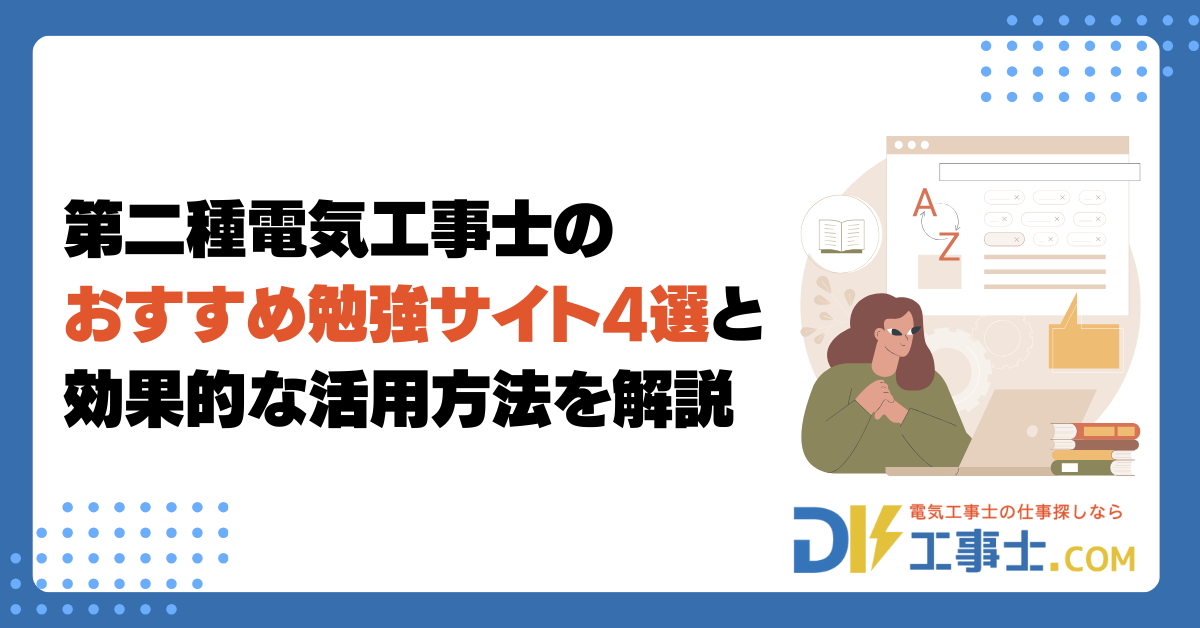
|
【無料】第二種電気工事士のおすすめ勉強サイト一覧!効果的な活用方法も解説
第二種電気工事士
試験
|