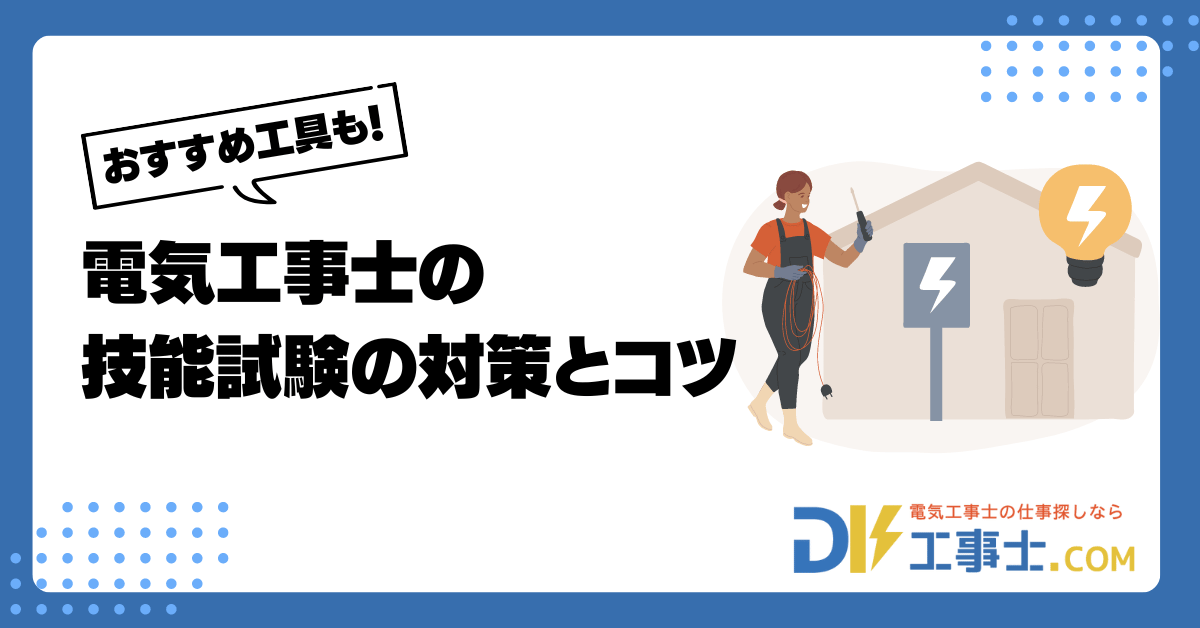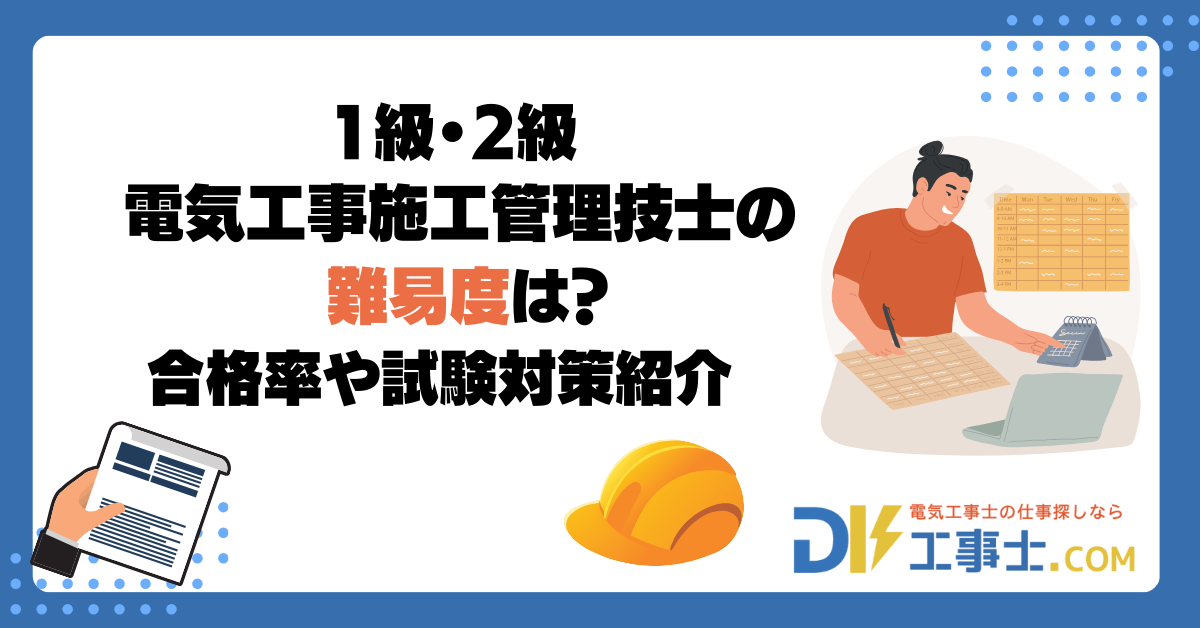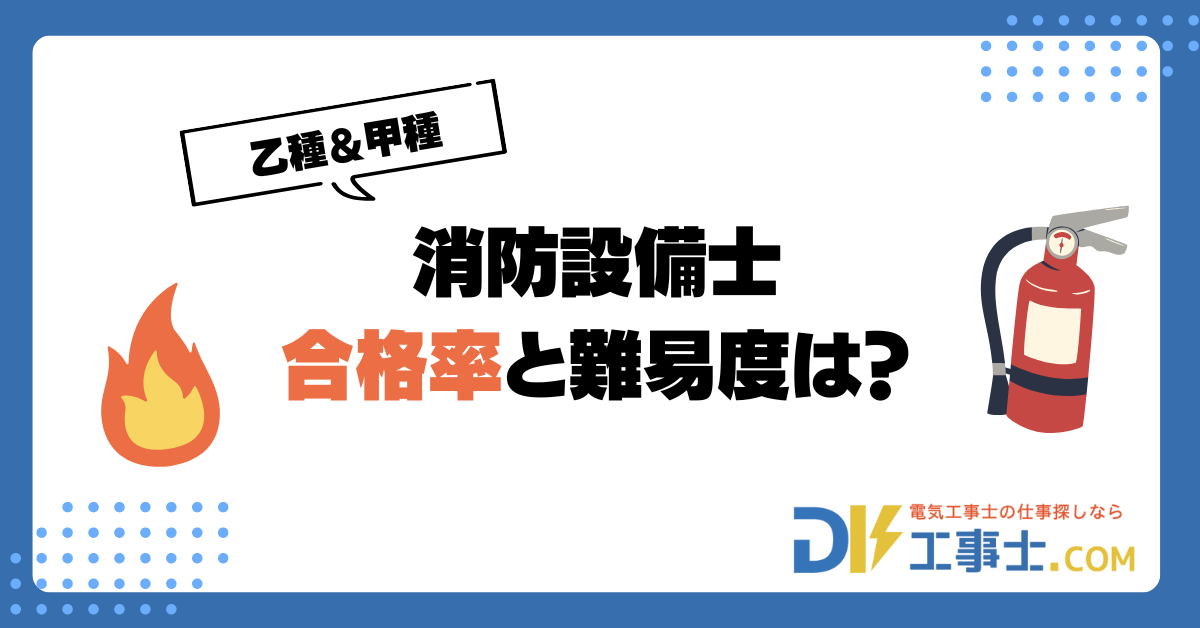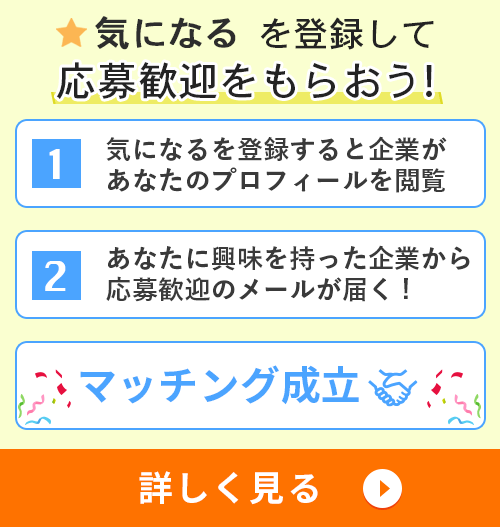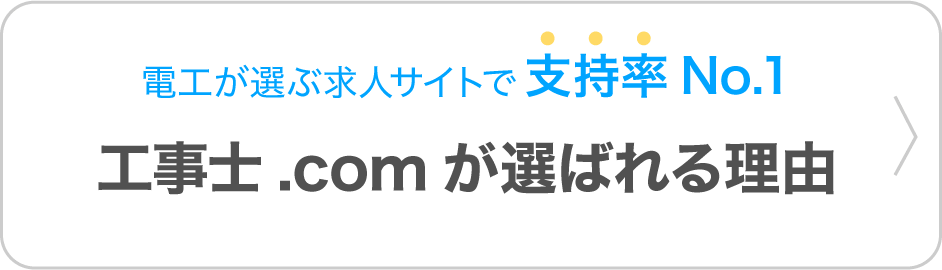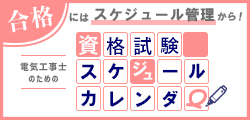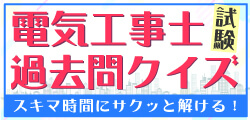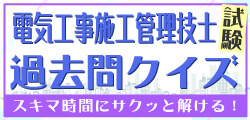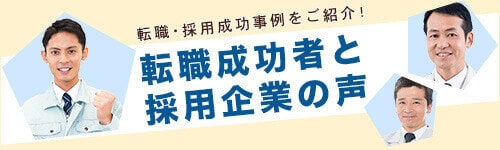【実例あり】複線図の書き方5ステップ!第二種電気工事士試験に受かるコツまで
電気工事士の資格・試験最終更新日:
第二種電気工事士の技能試験において、「電線と器具をどのように接続するか」が分かりやすいように、複数の線を使って詳細に表した配線図のことです。
1本の線で表された「単線図」と比べて複雑ですが、接続箇所が分かりやすく、作業ミスが起こりにくいという特徴があります。
この記事では、単線図から複線図への書き換え方を、基本的な5つのステップに分けて詳しく解説します。
また、複線図作成時の注意点やコツ、効率的な練習方法、おすすめの学習教材まで、技能試験合格に必要な情報をまとめています。
単線図の複線図化は技能試験の合否を分ける重要なポイントですが、基本的な手順を押さえれば、誰でも確実にマスターできます。
では最初に、試験で実際に出題される単線図と複線図の違いについて詳しく見ていきましょう。
電気工事士2種の試験に出題される単線図と複線図とは?
単線図は電気の通り道を1本の線で表した図面で、配線の全体像を把握するのに適しています。
一方、複線図は、電気の行き帰りの経路を複数の線で描いた詳細な図面で、どの電線同士を接続すればよいのかが分かりやすいという特徴があります。
第二種電気工事士の技能試験に合格するには、「単線図」を「複線図」に書き換えるスキルが必要です。
単線図のままでは、どのように接続すれば良いかが分かりにくいからです。
次の章からは、単線図と複線図の特徴を詳しく解説します。
単線図とは?
単線図とは、配線の全体像を1本の線で表した図面です。
第二種電気工事士の技能試験では単線図をもとに実際の作業を行います。
単線図には、メリットが2つあります。
- 配線の全体像が分かりやすい
- スイッチやコンセントなどの機器の配置場所が一目で把握できる
実際の工事現場でも、まずは単線図で配線の全体像を確認してから作業に入るため、単線図をしっかり読み解く力が必要です。
例えば、照明器具の配線では、スイッチの位置や電源からの配線ルートが単線図に示されています。単線図を見ることで、どこにどの器具を設置し、どのように配線するかが分かります。
ただし、単線図は大まかな図面なので、このままでは正確な工事はできません。
そこで次の章で説明する複線図への書き換えが重要になってきます。
複線図とは?
複線図とは、電線1本1本の接続関係をわかりやすく描いた図面です。単線図では1本で表現していた配線を、実際の工事で必要な往復2本の線で表現します。
複線図が必要な理由は、安全な電気工事を行うためです。電気は必ず往復の経路が必要で、黒線(非接地側)で電気を送り、白線(接地側)で電気を返すという決まりがあります。
例えば、照明器具の配線を黒線同士や白線同士で接続してしまうと、漏電や発火の原因になります。複線図化する際に、電線の色や接続方法を明確に示すことで、こうした事故を防げるでしょう。
つまり、複線図は電気工事の「設計図」とも言える重要な図面と言えます。
単線図を複線図にする基本的な書き方
単線図から複線図を書くときは、基本的な5つの手順に従えば誰でも簡単に行えます。
複線図を書く手順は、次の5ステップです。
- 器具と電源を単線図通りに配置する
- 各器具・電源に「+」「-」の記号を書き入れる
- スイッチとコンセントに電源から「+」線を引く
- スイッチの「-」から対象器具の「+」へ線を引く
- 各器具の「-」と電源の「-」をすべてつなぐ
この順序で書けば、電気の行き帰りの経路がスッキリして、配線ミスを防げます。特に重要なことは、電気は必ず「+」から「-」へ流れるという基本を意識することです。
5つの手順を意識して練習すれば、技能試験で出題される13問の候補問題すべてに対応できます。
では次に、実際の複線図の描き方を具体例を使って説明していきましょう。
【実例】複線図化のステップ
令和6年度の候補問題No.1を例に、複線図の具体的な書き方を解説します。
この問題には照明器具3台とスイッチ3個が含まれており、基本的な配線パターンを学ぶのに適しています。
ここからは、複線図化するための各ステップに分けてご紹介します。
ステップ①器具と電源の配置
まず、単線図と同じ位置に各器具を配置します。
問題No.1では、引掛シーリング(イ)、ランプレセプタクル(ロ)、照明器具(ハ)の3つの器具とそれぞれのスイッチを配置します。
また、電源とジョイントボックスの位置も書き入れてください。この段階では器具の記号だけを書き、まだ配線は行いません。

ステップ②「+」「-」の記入
次に、各器具と電源に「+」「-」の記号を書き入れます。
電源の黒線側を「+」、白線側を「-」とし、各器具にも同様に記号を付けていきます。
この作業で電気の行き帰りの経路が明確になります。

ステップ③電源からの配線
続いて、電源の「+」(黒線)からスイッチへの配線を行います。
ジョイントボックスを経由して3つのスイッチに配線します。
この時点では、まだスイッチから照明器具への配線は行いません。

ステップ④スイッチと器具の接続
スイッチの「-」から対応する器具の「+」へ配線していきます。
- スイッチ(イ)→引掛シーリング
- スイッチ(ロ)→ランプレセプタクル
- スイッチ(ハ)→照明器具
の順番で接続します。

ステップ⑤帰りの経路の完成
最後に、すべての器具の「-」(白線)を電源の「-」につなぎます。ジョイントボックスで接続する箇所には必ず接続記号を付け、見落としのないようにします。

これで基本的な複線図は完成ですが、実際の試験では施工条件に従って電線の色や接続方法も書き加える必要があります。この例では、電源からの接地側(白線)、非接地側(黒線)の指定や、ジョイントボックスでの接続方法などを追記しておきましょう。

※引用元:令和6年度第二種電気工事士上期技能試験「公表問題№1」
また、配線の経路は必ず水平・垂直に引き、斜めの線は使わないようにしましょう。線が交差する箇所では接続の有無を明確にするため、接続する場合は黒点をつけてください。
段階を追って丁寧に書いていけば、複雑な配線図も正確に描くことができます。
複線図でミスしないために注意するポイント・コツ
複線図を書くときに気を付けるべきポイントは3つあります。書き方を意識するだけで配線ミスを防げます。
作図で守るべきポイントは、以下のとおりです。
- 配線は必ず水平・垂直に引く
- 線が交差する箇所では接続の有無を明確にする
- 電線の色や接続方法を正確に記入する
例えば、斜めの線を使うと図面が分かりにくくなったり、接続箇所が不明確だと配線ミスの原因になったりします。
特に多いミスが、スイッチと照明器具の接続です。スイッチには電源から黒線を接続し、スイッチから照明器具へは線を接続します。この順序を間違えると、回路が正しく動作しません。
また、複線図は時間をかけすぎないことも大切です。
試験では5分程度で書き上げることを目標に、少しでも実技の作業時間に充てましょう。
第二種電気工事士の技能試験で不合格になってしまう原因については「第二種電気工事士の技能試験に落ちた原因は?よくある失敗や再試験への対策を解説!」で詳しく解説しています。
過去問を使った複線図の練習法
複線図の練習は、13問の技能試験の候補問題を使って、少しずつ進めていくのが効果的です。
練習の手順は、以下の3ステップで行います。
- 時間を気にせず、1問ずつ正確な複線図が描けるように練習する
- 5分以内に書き終えることを意識しながら、13問すべての複線図を2〜3周描く
- 実際の試験を想定し、複線図を描いてから施工作業まで通しで行う
最初から時間を気にすると焦って間違えやすくなります。まずは正確さを重視し、徐々にスピードを上げていく方が上達スピードは早いです。
また、複線図を書く場合は、難易度が低いとされている問題から始めて、徐々に難しい問題に取り組むとよいでしょう。
| 難易度 | 特徴 |
|---|---|
| 難易度の低い問題 |
|
| 難易度の高い問題 |
|
練習をすればするほど、複線図を書く時間は短縮できます。
複線図をマスターするためのおすすめ教材・ツール
複線図を効率的に学ぶには、教材やツールを上手く利用することをおすすめします。
①2024年版 ぜんぶ絵で見て覚える第2種電気工事士 技能試験すい~っと合格:入門講習DVD付

(出典:Amazon)
このテキストでは、合格に必要な要点を効率的に学べます。
■主な特徴
- 2024年度の候補問題13問の解答と作業手順を写真付きで解説
- 合否のポイントを書き込んだ詳細複線図とカラー完成写真を収録
- 基本作業が学べるDVDと切り離して使える複線図練習帳が付属
初心者の方にとっては、写真やイラストで丁寧に解説されているため分かりやすく、DVDと練習帳を活用することで独学でも実技試験の対策を進められるテキストです。
②電工試験の虎_ホーザン

(※引用元:電工試験の虎_ホーザン)
「電工試験の虎_ホーザン」のYouTubeチャンネルは、第二種電気工事士試験の合格に必要な情報を無料で学べる動画教材です。
■主な特徴
- 候補問題13問の詳細な解説動画を見られる
- 材料確認から複線図、施工完了までをフル解説
- 配線のミス修正方法など実践的なコツも紹介
初心者の方にとっては、過去問を解きながら分からない部分を何度も繰り返し視聴できるため、自分のペースで確実に理解を深められる学習ツールと言えます。このチャンネルを利用している合格者は多いです。
まとめ
今回は、第二種電気工事士の技能試験で必ず覚えなければならない「複線図」について、詳しく解説しました。
- 単線図は配線の全体像を1本の線で表現し、機器の配置や配線経路を把握するのに適している
- 複線図は電気の行き帰りを複数の線で表現し、実際の施工に必要な接続関係を示している
- 複線図は5つの基本ステップで効率的に作成できる
- 練習は難易度の低い問題から始め、段階的にレベルアップするのが効果的
第二種電気工事士の技能試験では、単線図を複線図に正確に書き換える力が合否を分けるポイントです。
特に初心者の方は、テキストやDVD教材で作図の基本を学び、練習帳で繰り返し練習することをおすすめします。
また、YouTubeなどの動画教材も併用することで、より理解を深めることができます。
複線図は実際の作業でも重要なスキルなので、確実にマスターしておきましょう。

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
おすすめ求人

株式会社EAST B
【二種電工必須&経験不問】直流電源設備や蓄電池の電気工事◇年間休日120日程度◇努力を見逃さない環境..
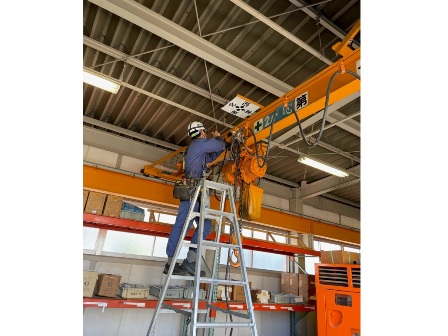
内藤工機株式会社
残業月平均10h以下★賞与実績計3ヶ月分★各種手当充実|クレーンなどのメンテナンス|資格経験不問/正..

株式会社プログレス
《引越費用支援&借上社宅あり》電気工事・電気通信工事スタッフ/資格経験不問*残業月10h*/正社員

柏崎協電株式会社
残業月3h◆引込線工事で地域のライフラインを守る!資格経験不問<育成環境が充実><講習費用支援あり>..

KS電設株式会社
【最大15万円の入社祝金 or 社宅でサポート】電気・計装工事の施工や施工管理/経験資格不問/正社員
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする

|
【第二種電気工事士とは?】できることや第一種との違い・資格取得メリットを解説
第二種電気工事士
資格
試験
対策
活躍
|
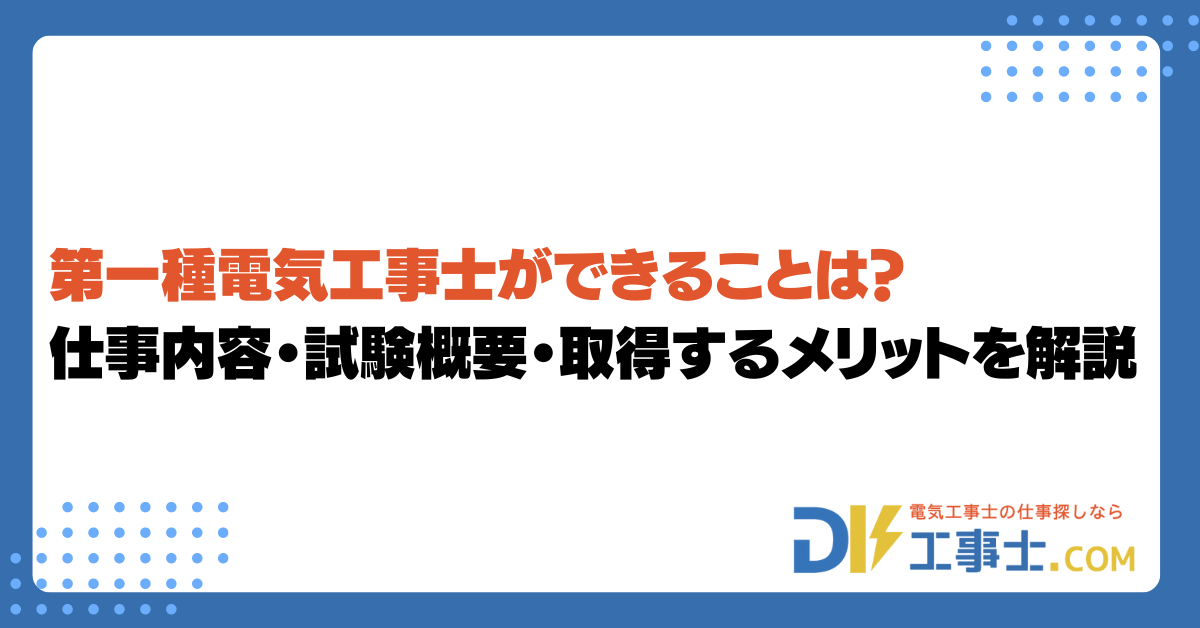
|
第一種電気工事士とは?仕事内容や第二種との違いから試験概要や勉強時間まで徹底解説
電気工事士
第一種電気工事士
資格
対策
仕事内容
|
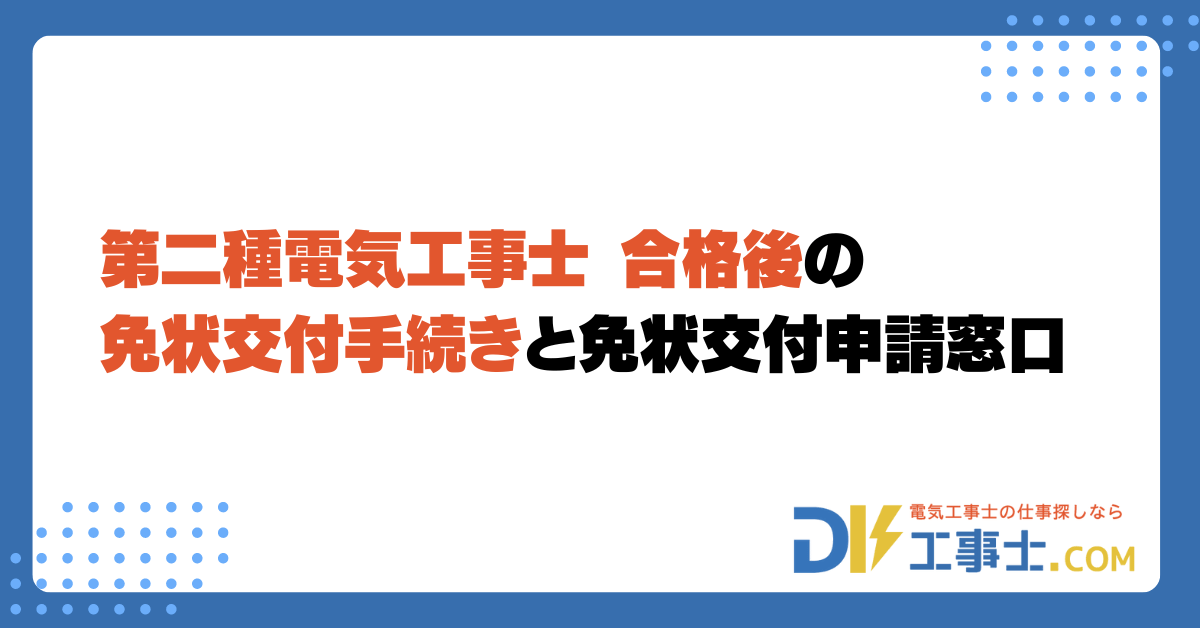
|
第二種電気工事士合格後の免状交付手続きを詳しく解説!申請期限や窓口情報まとめ
第二種電気工事士
資格
試験
|
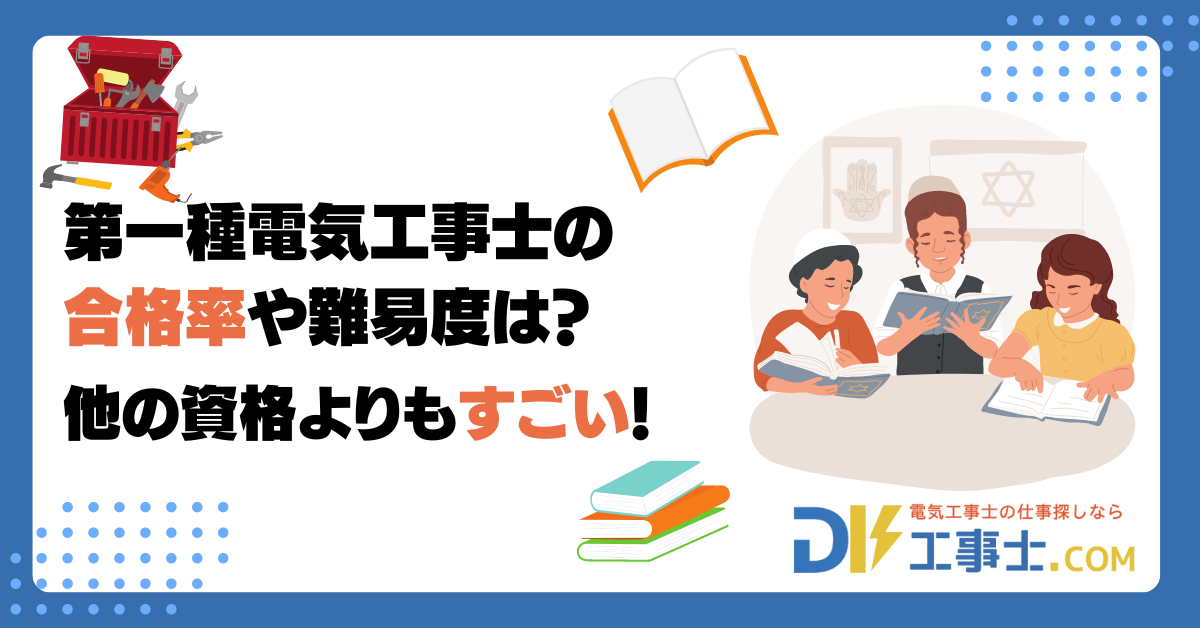
|
【実はすごい】第一種電気工事士の合格率は約56%!難易度を他資格と比較して解説
第一種電気工事士
資格
試験
|
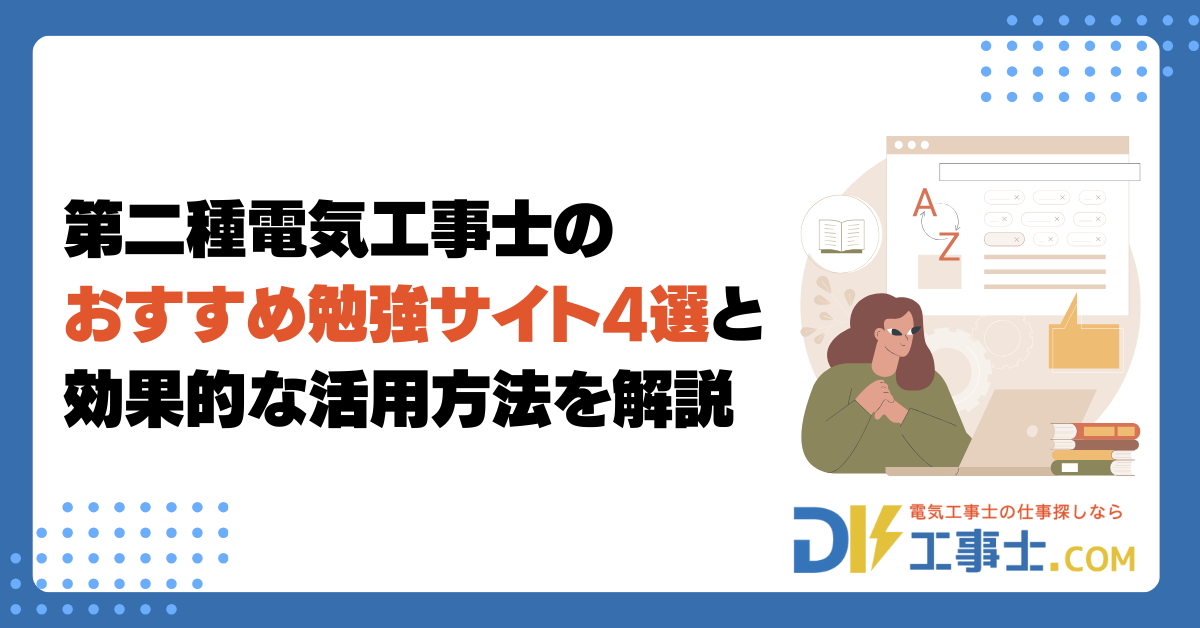
|
【無料】第二種電気工事士のおすすめ勉強サイト一覧!効果的な活用方法も解説
第二種電気工事士
試験
|