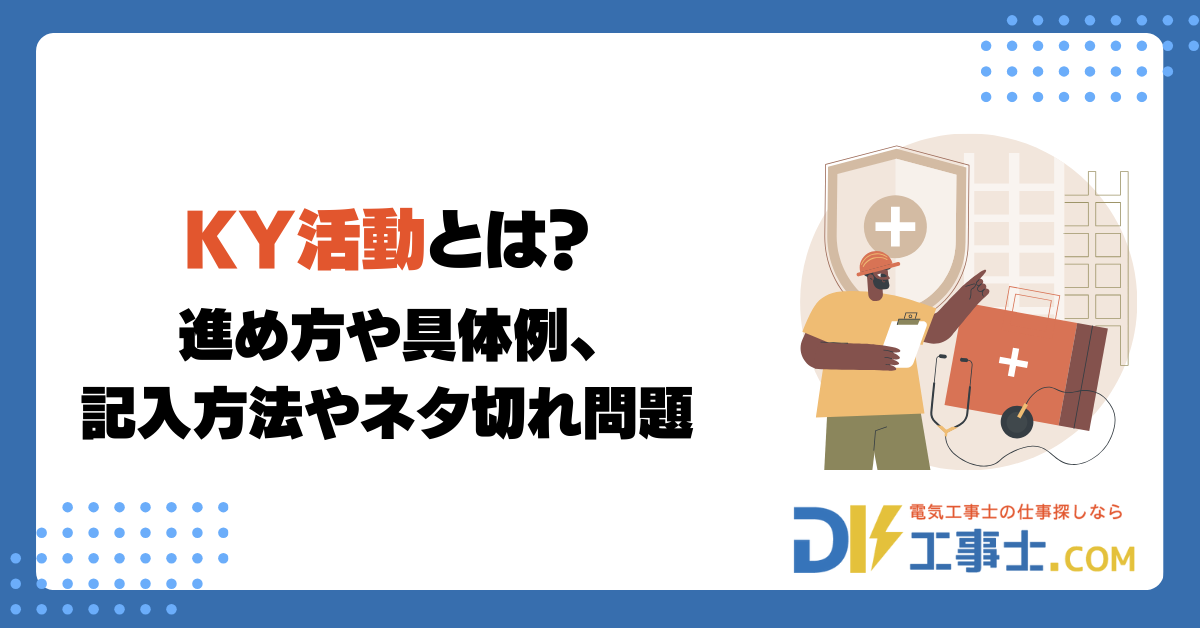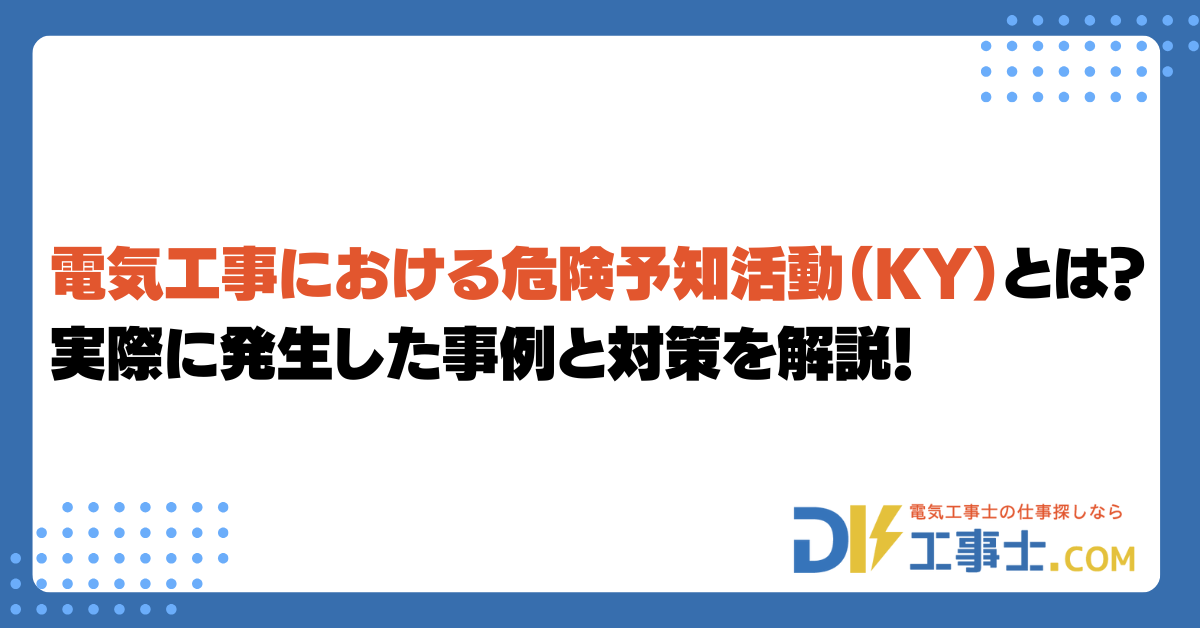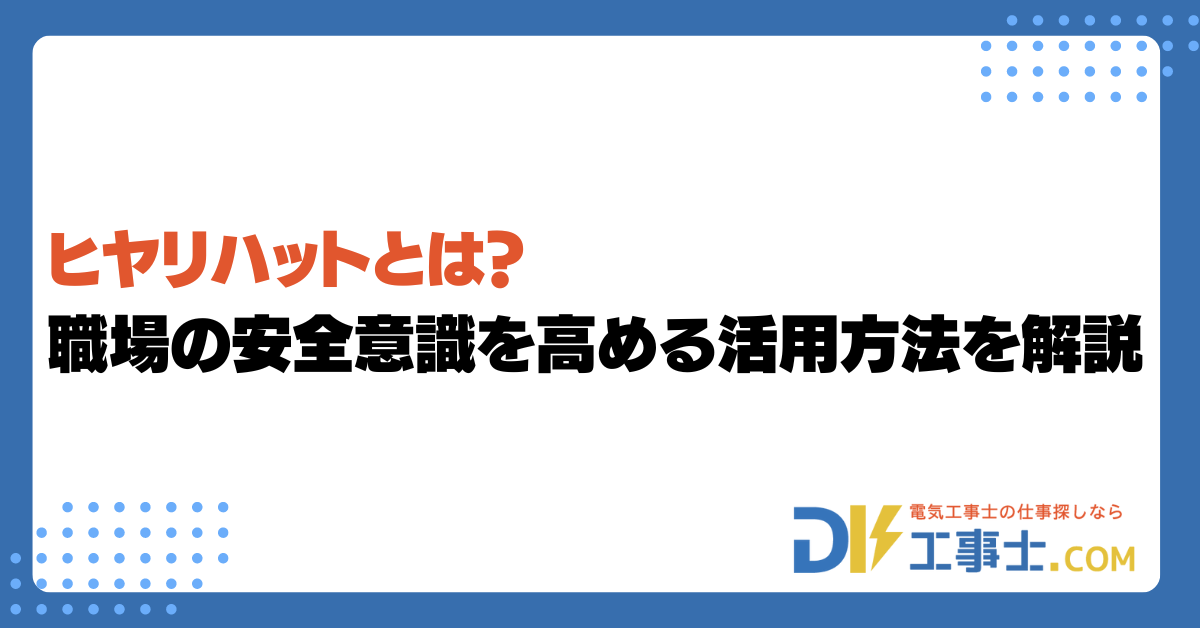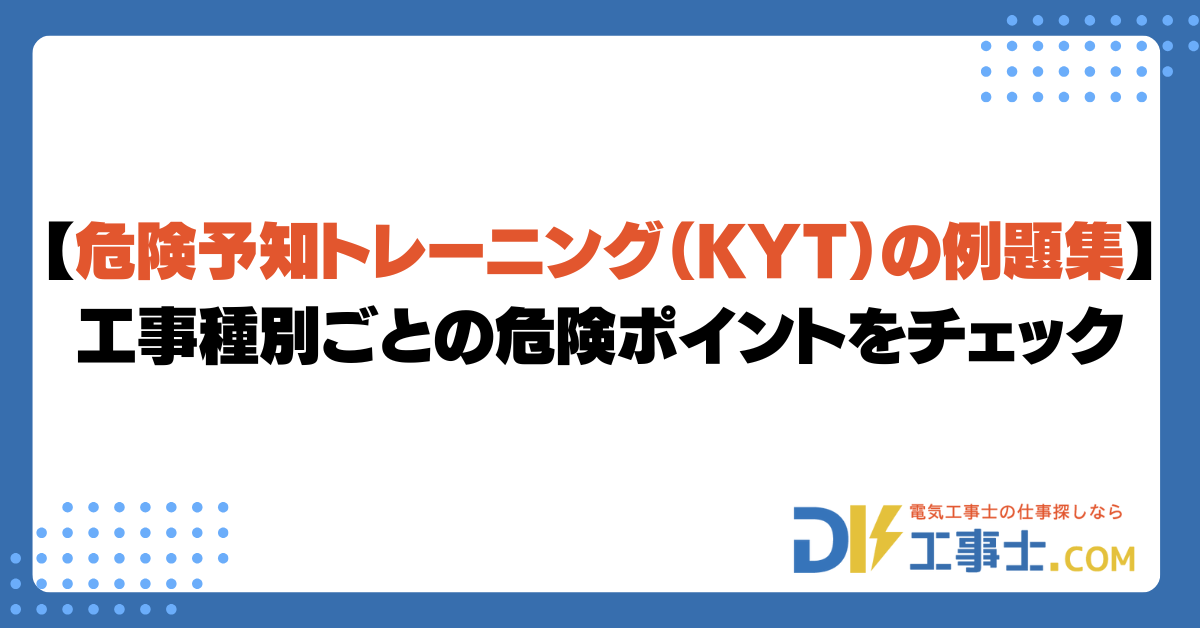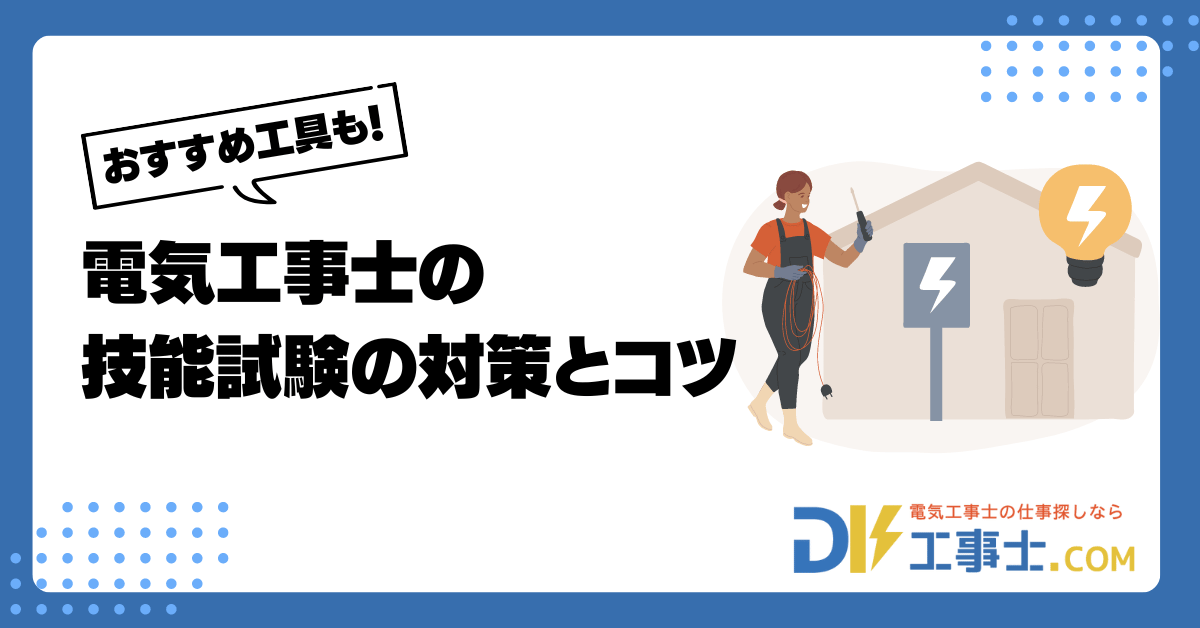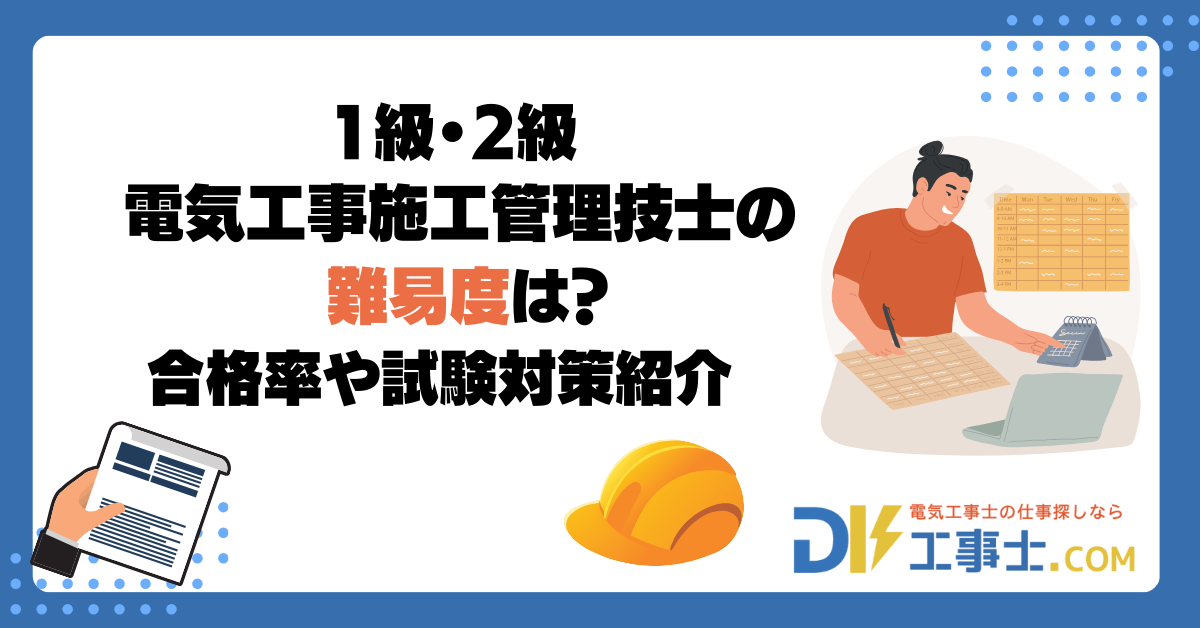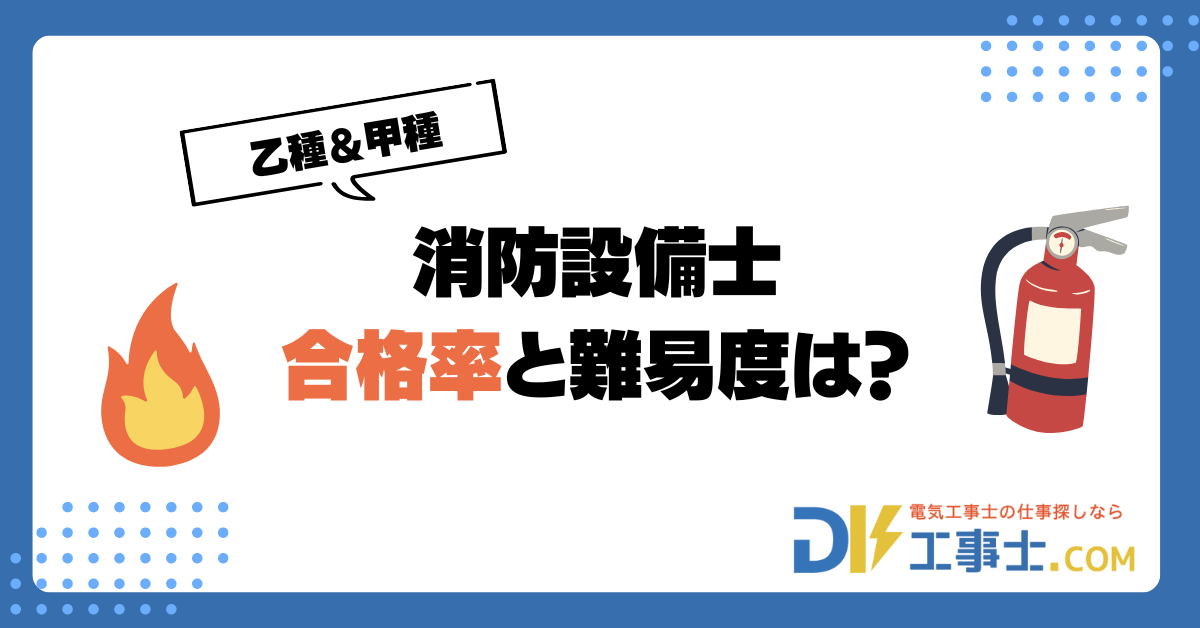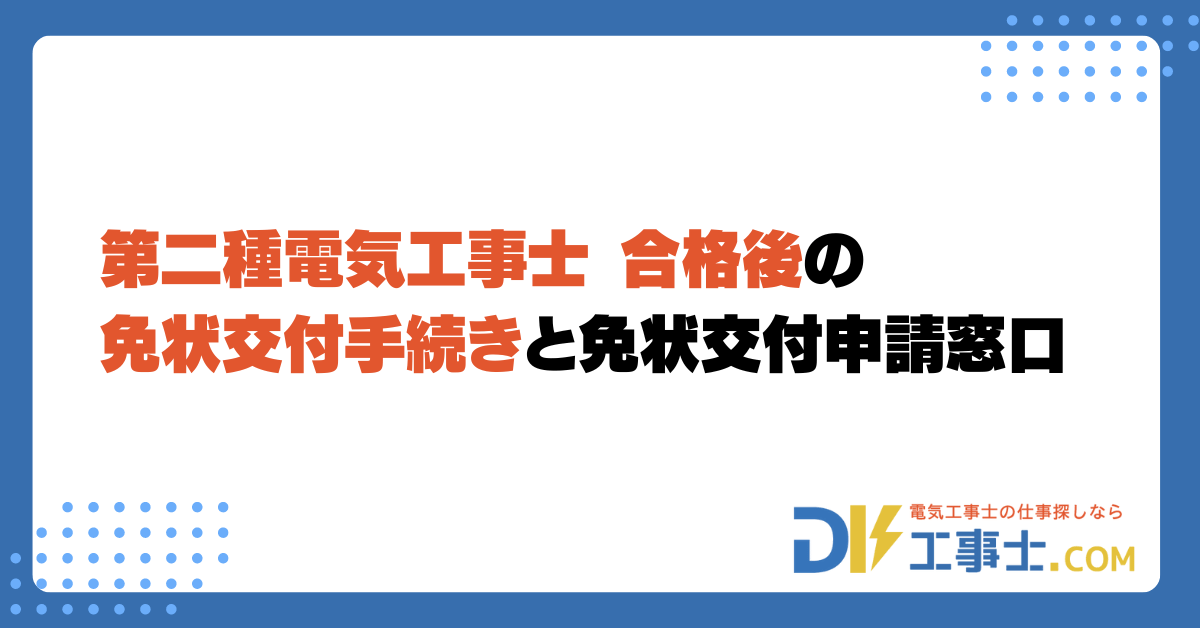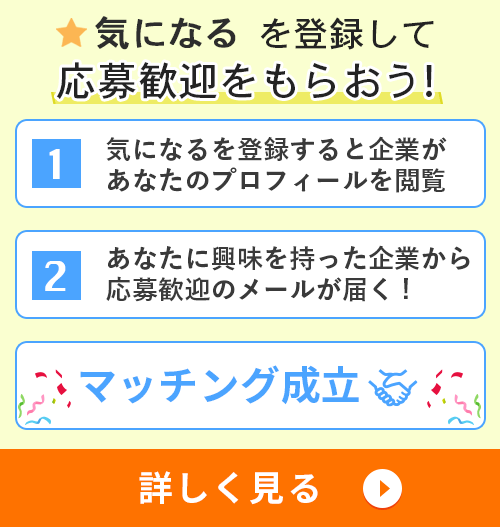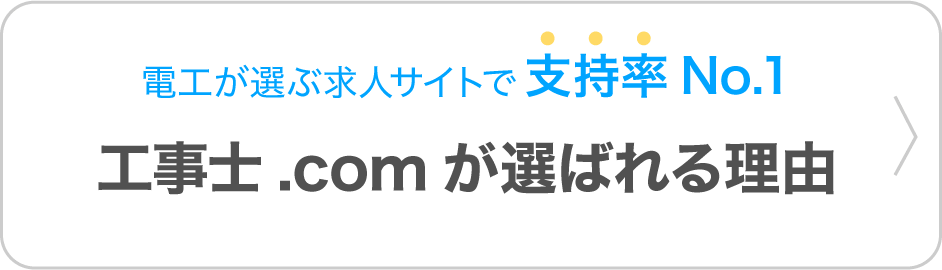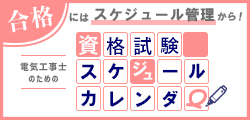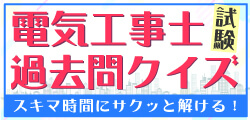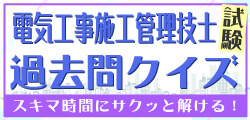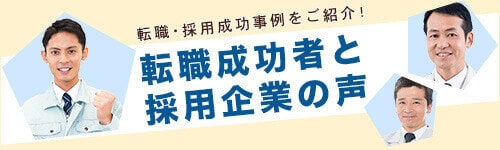ヒヤリハットのネタ切れが起きる原因は?解決ポイントと使える事例も紹介
安全衛生最終更新日:
ヒヤリハット報告のネタ切れは、「長期間事故が発生していない」「報告手続きが煩雑」などといった安全意識の低下や、教育・共有の不十分といった理由から起こりやすい傾向にあります。
ヒヤリハットの「ネタ切れ」に悩む職場は少なくありません。
しかし、ヒヤリハットの形骸化は、重大事故の前触れを見逃すことにつながりかねません。ハインリッヒの法則によると、1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットが存在するとされています。
本記事では、ヒヤリハットのネタ切れが起きる原因から、それを解消するための具体的な対策まで、詳しく解説していきます。
職場や現場でヒヤリハットの「ネタ切れ」にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
ヒヤリハットのネタ切れが起きる原因とは
ヒヤリハット報告の現場で「ネタ切れ」が起きる主な原因は2つあります。「安全意識の低下」「教育・共有不足」です。
それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
安全意識の低下による形骸化
ヒヤリハットのネタ切れの大きな原因は、「事故やトラブルが長期間発生していないことで、職場全体の安全意識が低下してしまうこと」です。
事故やトラブルが長期間発生していない職場では、「いつも通り」という慣れが生じ、危険に対する感度が鈍くなります。特に経験豊富な従業員ほど「これまで問題なかったから大丈夫」という過信に陥りやすく、潜在的な危険性を見過ごしてしまいがちです。
例えば、製造現場で毎日使用している機械設備に対して「不具合が出たことがないから安全」と思い込み、異音や振動の変化を報告しないケースがあります。また、建設現場では「この程度の高さなら転落しない」という慣れから、安全帯の着用を省略してしまうといった事例も見られます。
安全意識の低下を防ぐためには、定期的な研修や事例共有を通じて、ヒヤリハットの重要性を繰り返し従業員に意識づけることが大切です。また、「当たり前」と思っている作業にこそ危険が潜んでいる可能性があることを、組織全体で認識する必要があります。
情報が共有できていない
ヒヤリハットの目的や重要性に関する教育不足、他部署との情報共有の不足などが、ネタ切れの原因となっています。
従業員がヒヤリハットの本質を理解していないと、何を報告すべきか判断できません。また、部署間や他社との事例共有が不足していると、視野が狭くなり、新たな気づきを得る機会が減少してしまいます。
例えば、製造現場では「機械の不具合は報告するべきだが、通路でつまずきそうになった程度では報告する必要がない」と考える従業員がいます。また、営業部門では「事務作業にはヒヤリハットは関係ない」と誤解している場合もあるでしょう。
さらに、他部署で発生した「情報漏洩につながりそうだった」といった事例が共有されないために、同様のリスクに気づけないケースも見られます。
ヒヤリハット活動を活性化させるためには、定期的な安全教育の実施と、部署を超えた事例共有の仕組みづくりが重要です。些細な気づきでも報告する価値があることを理解してもらい、他部署の事例から学ぶ機会を増やすことで、新たな視点でのヒヤリハット発見につながるでしょう。
ヒヤリハットのネタ切れを解消するためのポイント
ヒヤリハットのネタ切れを解消するには、3つの重要なポイントがあります。「報告の仕組み改善」「教育・意識改革の実施」「情報共有の活性化」です。
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
報告の仕組み改善
ヒヤリハット報告を活性化させるには、報告手続きの簡素化と報告しやすい環境づくりが不可欠です。
従来の紙ベースの報告や複雑な手続きは、従業員の報告意欲を低下させる要因となることがあります。また、業務の合間に報告する時間を確保することも難しく、気づきが埋もれてしまいがちです。
具体的な改善策として、スマートフォンやタブレットでの報告システムの導入や、チェックリスト形式の採用が効果的です。また、毎週決まった日時に報告タイムを設けるなど、定期的な報告時間の確保も効果があります。
報告の仕組みを改善し、従業員が「手軽に」「すぐに」報告できる環境を整えることで、日々の気づきを確実に収集できるようになるでしょう。
教育・意識改革の実施
ヒヤリハット活動を形骸化させないためには、定期的な安全教育と組織全体の意識改革が重要です。
ヒヤリハットの本質的な意義が理解されていないと、重要な気づきが報告されないまま放置されてしまいます。また、報告することへの心理的な抵抗感が、有効な情報収集の妨げとなるでしょう。
例えば、月1回の安全ミーティングで実際のヒヤリハット事例を共有したり、「廊下でつまずいた」「書類の確認を忘れた」といった些細な事例も報告対象となることを説明したりします。また、報告者を非難せず、むしろ積極的に評価する姿勢を示すことで、報告への抵抗感を軽減できます。
継続的な教育と意識改革により、「失敗から学ぶ」という組織文化を根付かせ、全従業員が自発的にヒヤリハット報告に取り組む環境を作ることが大切です。
情報共有の活性化
部署を超えた事例共有と、他社の優良事例から学ぶ機会を増やすことも、ヒヤリハットのネタ切れを解消するためのポイントになります。
なぜなら、一つの部署だけでは気づきの視点が限定されがちなため、似たような報告が続くと新たな危険に対する感度が低下してしまう傾向にあるからです。
月1回の部門横断ミーティングで各部署の事例を共有したり、他社の事故事例を基にした検討会を開催したりしましょう。また、報告件数や内容の質が優れた部署を表彰する制度を設けることで、従業員の意欲向上にもつながるでしょう。
ネタ切れ時に使えるヒヤリハット事例
ヒヤリハットのネタ切れに悩んでいる方のために、業種別の具体的な事例をご紹介します。
これからお伝えする事例は、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」や各業界団体が公開している情報を参考にしています。
それぞれのヒヤリハット事例は、実際の現場で起きた出来事を基にしており、どの職場でも起こりうる可能性のある内容です。自社の業務と照らし合わせながら、類似の危険がないかを確認してみましょう。
製造業のヒヤリハット
製造業の現場では、機械設備や重量物を扱うことが多く、危険も多く存在します。
ここからは、製造業で実際に報告された代表的なヒヤリハット事例を、危険の種類別に分けて紹介します。
手袋がスクリューに巻き込まれそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
樹脂混練機での作業には、回転部への巻き込まれによる重大事故のリスクがあります。
■発生状況
工場内で混錬機に樹脂原料を投入しているとき、うっかりして混錬機の投入口にゴム手袋をはめた状態で手を少し入れてしまい、手袋がスクリューに巻き込まれそうになった。
■ 原因
- 運転中の混練機投入口への手挿入
- 回転部近くでのゴム手袋の着用
- 安全カバーの未設置
- 作業手順の無視
- 危険性に対する認識不足
■ 対策
- 回転部への接触防止カバーの設置
- 作業時の手袋着用禁止の徹底
- 投入口への安全柵の設置
- 作業手順の再教育実施
- 安全な投入方法の確立
高温物を素手で触って火傷しそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
調理作業場では、高温の器具や調理器具による火傷のリスクが常に存在します。
■発生状況
スーパーの食品調理作業場で調理用鉄板を別の作業台に移そうとした際、オーブンから取り出した直後で100℃以上の高温であることに気づかず素手で触れ、咄嗟に手を離した。瞬時の判断で大きな火傷は免れた。
■ 原因
- 温度確認を怠っていた
- 作業手順の軽視
- 高温物であることの認識不足
- 保護具未使用
- 作業者間の情報共有不足
■ 対策
- 耐熱手袋の常時着用の徹底
- 温度確認の習慣化
- 高温物取扱い時の声掛けルール化
- 作業者間の情報共有強化
- 温度表示シールの活用
建設業のヒヤリハット
建設業の現場では、足場作業や重量物の運搬など、様々な危険が潜んでいます。
ここからは、建設業で実際に報告されたヒヤリハット事例を、作業別に紹介します。
足場板の破損により転落しそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
建設現場での足場作業には、転落や墜落のリスクが潜んでいます。
■発生状況
建築工事の現場で足場組立工事をしていて高さ5mの足場上を歩行中、突然足場板のツメがちぎれて乗っていた足場板が傾き、バランスを崩して転落しそうになった。幸い安全帯を着用していたので5m下には墜落せず、右ひざの軽い擦り傷ですんだ。
■ 原因
- 足場板の事前の点検が不十分で、ツメ取付け部の劣化に気づかなかった
- 定期的な足場点検の未実施
- 足場材の経年劣化に対する意識不足
■ 対策
- 作業開始前の足場板の目視点検徹底
- 足場材の定期的な点検と記録の実施
- 劣化した部材の即時交換
- 安全帯の確実な使用の徹底
- 足場の点検チェックリストの活用
足場材が落下し、歩行者にぶつかりそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
建設現場での足場解体作業には、資材の落下による重大事故のリスクがあります。
■発生状況
工事現場の足場の解体作業中、足場材(腕木材)を取り外そうとしたところ、地上に落下してしまった。落下防止ネットの一端が固定されていなかったため、足場材は道路まで落下し、通行人に危険が及ぶところだった。
■ 原因
- 腕木材の固定状態の確認不足
- 落下防止ネットの不適切な設置
- 作業手順の確認不足
- 安全設備の点検漏れ
■ 対策
- 作業開始前の足場材固定状態の確認徹底
- 落下防止ネットの設置状態の定期点検実施
- 作業手順の再確認と教育の実施
- 歩行者通路の適切な区分け
- 監視員の配置による安全確認の強化
事務所・オフィスのヒヤリハット
事務所やオフィスは、製造現場や建設現場と比べると比較的安全に思われがちですが、意外にも多くのヒヤリハットが発生しています。
ここからは、実際にオフィスで報告された代表的なヒヤリハット事例を、場面ごとに分けて紹介します。
デスクの引き出しにつまずき転倒しそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
オフィスでの日常的な移動時には、転倒のリスクが潜んでいます。
■発生状況
事務所内で、机の席からFAXを送信しようと立ち上がり振り向いたところ、移動式袖机の引き出しが開いたままになっていたためつまずき、転倒しそうになった。すぐに近くの机につかまり、大事には至らなかった。
■ 原因
- 引き出しの開放状態の放置
- 作業スペースの整理整頓不足
- 急な動作による周囲確認の不足
- 通路確保の意識不足
- 5S活動の不徹底
■ 対策
- 引き出しを使用後すぐに閉める習慣づけ
- 机周りの定期的な整理整頓
- 通路スペースの確保
- 動作前の周囲確認の徹底
- 5S活動の推進
足がすべり転倒しそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
書類や備品の運搬作業には、階段での転倒・転落のリスクが潜んでいます。
■発生状況
事務室の完結書類をダンボールに入れ、地下書庫に運搬する途中、階段を降りるとき前がよく見えなかったため足を滑らせよろめいて転落しそうになった。手すりをつかんでいたため、大事故は免れた。
■ 原因
- 一度に運ぶ量が多すぎた
- 視界が確保できない状態での作業
- 一人での無理な作業実施
- 運搬用具の未使用
- 作業手順の不徹底
■ 対策
- 台車やキャリーの活用
- 二人以上での作業実施
- 一度の運搬量の制限
- 階段での手すり使用の徹底
- エレベーターがある場合はその活用
介護のヒヤリハット
介護現場では、利用者の安全と介護者自身の安全、両者に関わるヒヤリハットが発生しやすいです。
ここからは、介護施設で実際に報告された代表的なヒヤリハット事例を、場面ごとに分けて紹介します。
介護現場特有の人的リスクと、施設・設備に関わる物的リスクの両面から、事例を見ていきましょう。
患者の体位を直そうとして腰をひねった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
介護現場での体位交換作業には、介護者の腰痛リスクが常に存在します。
■発生状況
午前2時頃、病室で患者さんの体位を直そうとベッドの縁に腰掛けて作業を行い、ベッドから降りる際に腰をひねってしまった。幸い一時的な痛みで済んだが、重度の腰痛につながる可能性があった。
■ 原因
- 不適切な姿勢での作業実施
- 一人での無理な体位交換
- 夜間の人員不足
- 介助技術の不足
- 補助具の未使用
■ 対策
- ボディメカニクスを活用した作業姿勢の徹底
- 二人以上での介助の実施
- スライディングシートなどの補助具の活用
- 定期的な介助技術研修の実施
- 夜間の応援体制の整備
荷物を持って階段を上っている際に、転倒しそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
電動車椅子の移動介助には、転倒や転落による重大事故のリスクが潜んでいます。
■発生状況
訪問介護の利用者の電動車椅子を運ぶため、一人で電動車椅子を持ち上げて階段を上がっているときに、電動車椅子が介助者の足の上に載り、バランスを崩して転倒しそうになった。咄嗟の判断で手すりをつかみ、大事故は免れた。
■ 原因
- 一人での重量物の運搬
- 階段での無理な移動
- 作業手順の未確認
- エレベーター未使用
- リスクアセスメント不足
■ 対策
- エレベーターの優先使用
- 複数名での介助実施の徹底
- 作業手順の明確化
- 代替ルートの事前確認
- 介助者の適正配置
日常生活のヒヤリハット
日常生活の中にも、思いがけない危険が潜んでいます。普段何気なく行っている動作や、日常的に使用している道具・設備にも危険は多いです。
ここからは、一般家庭や日常生活で実際に報告されたヒヤリハット事例を、状況別に分けて紹介します。
自分の生活を振り返りながら、安全対策の参考にしてください。
エプロンに火が付きそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
火周りの清掃作業には、火気による火傷や着衣着火のリスクが潜んでいます。
■発生状況
火周りにおいて鍋で湯を沸かして麦茶を作りながら、鍋の上方にある換気扇の清掃をしていたところ、エプロンの裾に火がつき、火傷しそうになった。咄嗟に払い落としたため、大事には至らなかった。
■ 原因
- 火気使用中の清掃作業実施
- 危険予知の不足
- 清掃手順の未確認
■ 対策
- 火気使用時の清掃作業禁止
- 作業前の安全確認徹底
- 清掃手順の見直し
ピーラーで指先を切りそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
調理の下処理作業には、刃物による切創事故のリスクが常に存在します。
■発生状況
右手でピーラーを持ち、左手で持った人参の皮をむいている最中に、他のスタッフに話しかけられて振り返った際、指先を切りそうになった。とっさに動作を止めたため、大きな怪我は免れた。
■ 原因
- 作業中の注意力分散
- 複数作業の同時進行
- 作業に対する慣れ
- 危険意識の低下
- 作業環境の管理不足
■ 対策
- 刃物使用時の作業への専念
- 声掛け時のルール化
- 作業の一時中断の徹底
- 集中できる環境の整備
- 定期的な安全教育の実施
通勤時(交通関係)のヒヤリハット
通勤時は、時間に追われがちで注意力が低下しやすい時間帯です。「いつもの道だから大丈夫」という過信が、思わぬ事故につながる可能性があります。自身の通勤経路を振り返りながら、潜在的な危険がないか確認してみましょう。
冬道でタイヤが滑り雪山に突っ込んでしまった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
冬季の道路走行には、路面凍結による重大な交通事故のリスクが潜んでいます。
■発生状況
打合せのため事務所より現場に社有車で向かう途中、除雪した雪だまりのあるT字路で右折しようとブレーキを掛けたが、アイスバーンのため車は止まらず、そのまま1回転して雪山に突っ込んだ。幸い周囲に車両や歩行者がおらず、大事故には至らなかった。
■ 原因
- 路面状況の確認不足
- 速度超過での右折
- 冬道での急ブレーキ
- 気象条件への対応不足
- 危険予測の甘さ
■ 対策
- 交差点手前での十分な減速
- 路面状況に応じた運転速度の調整
- 急ハンドル・急ブレーキの回避
- 冬用タイヤの早期装着
- 気象情報の事前確認
車から降りた際、自転車とぶつかりそうになった

※引用元:厚生労働省「ヒヤリ・ハット事例」
車と車の間からの道路横断には、自転車や車両との衝突事故のリスクが潜んでいます。
■発生状況
会社の向かい側にあるポストに郵便物を投函するため、駐車中の車と車の間から道路を横断しようとしたところ、走行してきた自転車と衝突しそうになった。咄嗟の判断で立ち止まったため、大事故は免れた。
■ 原因
- 横断歩道を使用しない危険行動
- 見通しの悪い場所からの横断
- 安全確認の不徹底
- 時間に追われた焦り
- 交通ルールの軽視
■ 対策
- 横断歩道の確実な使用徹底
- 左右の安全確認の習慣化
- 余裕を持った行動計画
- 駐車車両間からの横断禁止
- 交通安全教育の実施
ヒヤリハットの事例を集めたサイト
ヒヤリハット対策をより効果的に進めるため、参考となる2つの代表的なサイトを紹介します。
業種や目的に応じてこれらのサイトを活用することで、幅広い事例から学ぶことができます。
職場における安全衛生の総合情報サイトとして、400件を超えるヒヤリハット事例を掲載しています。
製造業、建設業、介護など、業種別に整理された事例を確認でき、各事例の具体的な対策は社内教育用の資料としても活用可能です。
また、すべての情報が無料で閲覧でき、必要な資料はPDFでダウンロードすることもできます。
380件以上のヒヤリハット事例を、実際のドライブレコーダー映像とともに公開しています。
車両事故の事例を中心に、多様な事故発生状況を扱っています。
映像による視覚的な学習が可能で、各事例に対する具体的な対策も示されています。
こちらも無料で閲覧可能です。
以上のサイトは一例であり、各業界団体が運営する専門的なサイトも多数存在します。
自社の業務内容や必要性に合わせて、最適な情報源を選択し、効果的な安全教育に活用することをおすすめします。
まとめ
本記事では、職場でのヒヤリハット報告における「ネタ切れ」の問題について、原因から対策まで詳しく解説してきました。
- ヒヤリハットのネタ切れは、「安全意識の低下」や「教育不足」が主な原因
- ヒヤリハットのネタ切れを解消するには、「報告の仕組み改善」や「情報共有の活性化」が重要
- ヒヤリハットのネタ切れを防ぐためには、製造業、建設業、事務所、介護職など、業種別の具体的な事例を把握しておくことが効果的
ヒヤリハット報告のネタ切れは、職場の安全管理における重要な課題です。 報告手続きの簡素化や定期的な教育、部署を超えた情報共有など、適切な対策を講じることで解決できます。
また、本記事で紹介した業種別の事例を参考に、自社の業務環境に潜む新たな危険に気づくきっかけとしてください。
ヒヤリハットの報告・分析を継続的に行うことで、より安全な職場づくりを実現できます。

執筆者・監修者
工事士.com 編集部
株式会社H&Companyが運営する電気工事業界専門の転職サイト「工事士.com」の編集部です。
◆工事士.comについて
- 電気工事業界専門の求人サイトとして2012年にサービス開始
- 転職活動支援実績は10,000社以上
- 「電気工事士が選ぶ求人サイト」として「使いやすさ」「信頼度」「支持率」の三冠を獲得※
※調査元:ゼネラルリサーチ
「ITとアイデアと情熱で日本の生活インフラを守る」をミッションに掲げ、建設業界で働く方々を支援するサービスを提供しています。
◆運営会社ホームページ
◆運営サービス
└ 施工管理求人.com(建設業界求人に特化した転職エージェント)
◆SNSアカウント
◆メディア掲載実績
└ 建設専門紙「建通新聞」 / jobdaマガジン / メタバース総研 / TOKYO MX「ええじゃないか」 等
おすすめ求人

株式会社大電通
<未経験OK><残業月10h>電気通信設備工事・電気工事/資格経験不問【NTT関連の取引多数】/正社..

一條電気工業株式会社
未経験でも月給28.5万~★残業月5h【新築メイン!ビル・マンション等の電気工事・資格経験不問】/正..

株式会社プログレス
《引越費用支援&借上社宅あり》電気工事・電気通信工事スタッフ/資格経験不問*残業月10h*/正社員

KS電設株式会社
【最大15万円の入社祝金 or 社宅でサポート】電気・計装工事の施工や施工管理/経験資格不問/正社員

株式会社武藤電気商会
【工場・マンション・官公庁関係等の現場代理人】賞与4.5ヶ月分★年収800万円も叶う!/資格経験不問..
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする