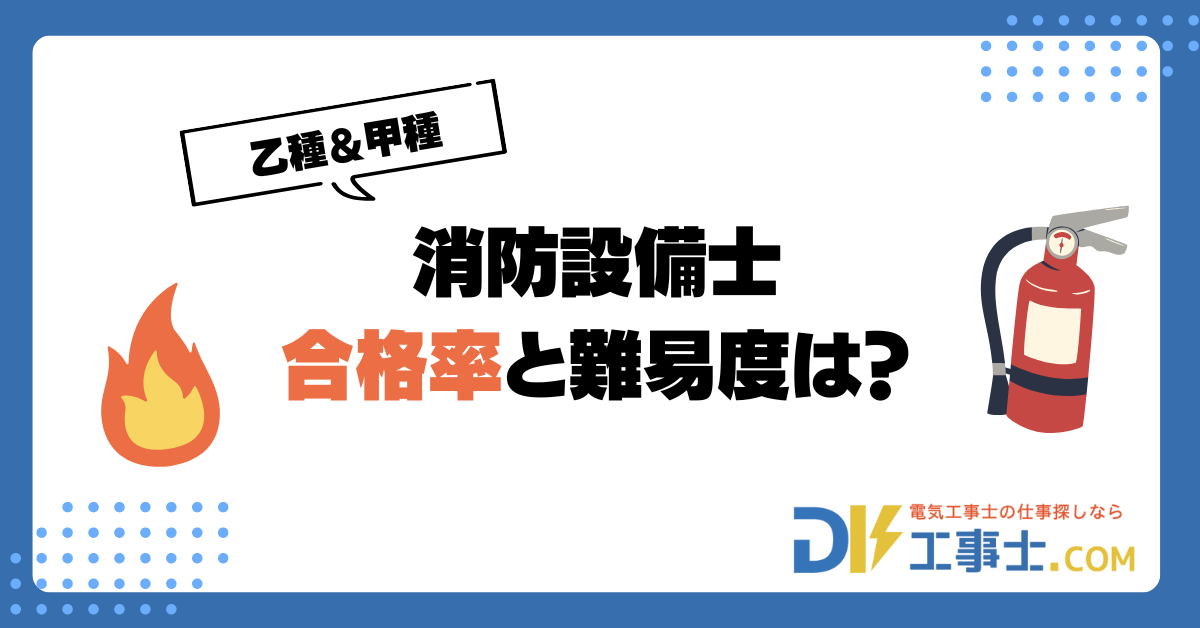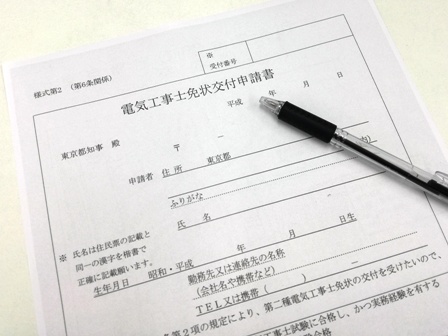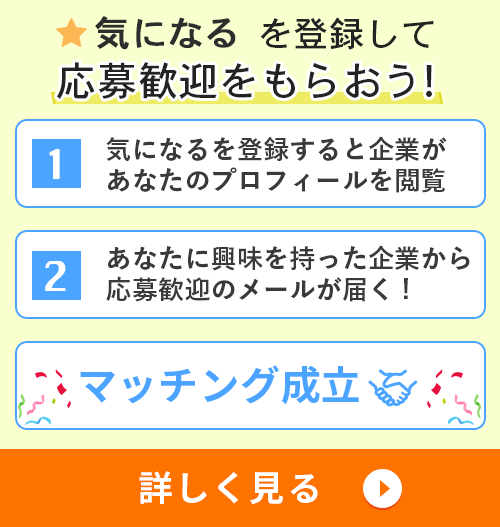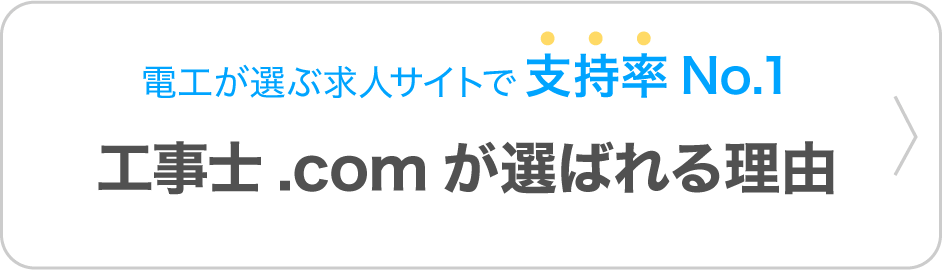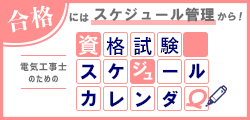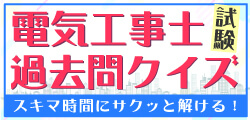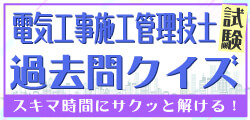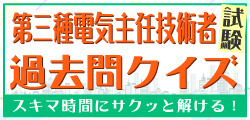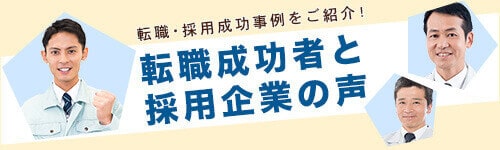第二種電気工事士 筆記試験合格に必要な勉強方法とコツを徹底解説!
電気工事士の資格・試験第二種電気工事士の筆記試験で合格するためには、勉強方法とコツを押さえることが大切です。
より短い時間で確実な合格のために、例年の出題内容や傾向、効率的な勉強方法、申し込み〜試験当日までの流れなどを解説していきます。是非参考にしてください。
第二種電気工事士筆記試験とは
第二種電気工事士の試験は、筆記試験と技能試験の2部構成です。まずは筆記試験に合格し、その後技能試験に合格することで、免状の取得が可能となります。
以下3つの観点から、第二種電気工事士の筆記試験について詳しく解説します。
第二種電気工事士の「申し込み〜免状取得まで」の流れについて、詳しくは以下の記事も参考にしてください。
>>第二種電気工事士試験の申し込み
>>第二種電気工事士の免状交付
筆記試験の概要
第二種電気工事士の資格試験として、筆記試験と技能試験の両方を受験します。まずは筆記試験を受け、合格した方のみ技能試験を受験するという流れです。例年、技能試験は筆記試験のおよそ1〜2ヶ月後に実施されています。
筆記試験と技能試験の違いは、以下の表を参考にしてください。
| 筆記試験 | 技能試験 | ||
|---|---|---|---|
|
実施期間
|
上期 | 筆記方式:2024年5月26日(日) CBT方式:2024年4月22日(月)~5月9日(木) |
2024年7月20日(土) または 2024年7月21日(日) |
| 下期 | 筆記方式:2024年10月27日(日) CBT方式:2024年9月20日(金)~10月7日(月) |
2024年12月14日(土) または 2024年12月15日(日) |
|
| 出題内容 | 電気工事士の基本知識 | 電気工事士の基本作業 | |
| 所要時間 | 120分 | 40分 | |
| 出題数 | 全50問 | 1問 | |
※試験時間・出題数は変更される場合あり
問題形式と合格点
第二種電気工事士の筆記試験は、電気工事の基礎知識や、配線図に関する問題が中心です。全50問に、四択形式で回答します。
筆記試験の2つの受験方法
筆記方式もしくはCBT方式を選択して受験してください。
| 筆記方式 | CBT方式 |
|---|---|
| 問題用紙とマークシートを用いて行う試験方式 | 指定会場に準備されたパソコンの画面上で行う試験方式 |

出題内容
電気技術者試験センターは筆記試験の出題内容を次のように説明しています。
筆記試験
| 解答方法 | マークシート式(4択) |
| 問題数 | 50問(一般問題30問程度/配線図問題20問程度) |
| 配点 | 2点/問(全問共通) |
| 試験時間 | 120分 |
| 満点 | 100点 |
| 合格点 | 60点 |
*試験時間、出題数は変更される場合があります。
第二種電気工事士の筆記試験は、1問2点のマークシート方式で全50問が出題されます。1問あたり2点配点、全50問で、100点満点です。
例年、60点が合格ラインと言われています。4択のマークシート方式で30問正解すれば良いのですから、それほどハードルが高い試験ではないと言えるでしょう。ただし、合格点は年度によって異なるため注意してください。
出題される問題の詳細
筆記試験の出題内容と問題数の傾向は以下の通りです。
■ 第二種電気工事士の筆記試験問題
| 問題 | 問題の種類 | 問題数 |
|---|---|---|
| (1)電気に関する基礎理論 | 計算 | 約5問 |
| (2)配電理論および配線設計 | 計算 | 約5~6問 |
| (3)電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 | 覚える | 約7問 |
| (4)電気工事の施工方法 | 覚える | 約5~6問 |
| (5)一般用電気工作物の検査方法 | 覚える | 約4問 |
| (6)配線図 | 覚える | 約20問 |
| (7)一般用電気工作物の保安に関する法令 | 覚える | 約3問 |
参考:電気技術者試験センター
問題が出題される順番や分野ごとの出題数は例年おおよそ同じです。電気に関する理論や計算を必要とする問題もありますが、全体の中では一部となっています。
「覚えてしまえば正解できる問題」の方が多いです。この分野の問題を正解することができれば、計算問題を抜きにしても、合格ラインである60点に近づけます。
工事士.comでは、移動中にスマホからでもサクサク使えるような、第二種電気工事士の過去問クイズを公開しています。筆記試験でどのような問題が出るのか、ぜひ一度覗いてみてください。
第二種電気工事士筆記試験の勉強方法
第二種電気工事士の筆記試験対策には、主に以下5つのステップが必要です。
- 受験案内の確認をする
- スケジュールを立てる
- テキストを選ぶ
- 過去問を解く
- 試験前の準備をする
1.受験案内の確認をする
まずは電気技術者試験センターが公開する第二種電気工事士の受験案内を確認しましょう。出題内容や試験形式などを理解します。
2.スケジュールを立てる
合格までの期間を考慮して学習のスケジュールを立てます。各科目ごとに対策期間を割り振り、定期的にスケジュールを見直します。
3.テキストを選ぶ
試験範囲に沿った信頼性の高いテキストを選びます。詳細な解説や豊富な例題が含まれているテキストを選ぶことで、効率的な学習が可能です。
4.過去問を解く
過去の試験問題に解答し、試験の傾向や出題形式を理解します。苦手な科目があれば後で復習できるようにしておきましょう。通常、過去問による練習は数年分行います。
5.試験前の準備をする
試験当日に備えます。忘れ物がないように持ち物をチェックしてください。試験前日はしっかりと休んで、最善の状態で試験に臨みましょう!
第二種電気工事士 合格率と勉強時間
第二種電気工事士の合格率は、筆記試験で50%〜60%、技能試験で60%〜70%程度です。第二種電気工事士は、国家資格の中でも比較的易しい部類と言われています。
難易度はそれほど高くないため、電気工事関連の資格としてまず初めに挑戦するには、最適な資格の1つと言えるでしょう。たとえ専門学校の卒業者や電気工事経験者でなかったとしても、合格できる可能性は十分にあります。とはいえ、油断は禁物です。しっかりと対策を行いましょう。
工事士.comが行った第二種電気工事士合格者を対象とした調査によると、試験対策に要した勉強時間はおよそ50〜150時間でした。
仮に1日あたり1時間の勉強時間を取れたとしたら、50時間の勉強におよそ2ヶ月程度かかる計算となります。ご自身で確保できる勉強時間を考慮しながら、計画的に学習を進めましょう。
例; 1時間 × 31日 × 2ヶ月 = 62時間
第二種電気工事士の筆記試験にかかる勉強時間について、さらに詳しく知りたい方は「第二種電気工事士の難易度と必要な勉強時間」を参考にしてください。
効率的な学習方法と勉強時間の配分
効率良く学習を進めるために、以下5つのポイントを抑えておきましょう。
- 具体的な目標設定をする
- 優先順位をつける
- 週次・日次スケジュールを立てる
- 学習方法を選択する
- 効果的な休息を入れる
1.具体的な目標設定をする
学習計画を立てる前に、具体的な目標を設定します。例えば、試験日までにどの科目をどれだけの理解度で学習するかを定めます。
2.優先順位をつける
試験範囲を確認して、学習する科目を整理します。重要度や難易度に応じて優先順位をつけます。
3.学習スケジュールを立てる
週ごとや日ごとに学習のスケジュールを立てます。各科目ごとに割り当てられる学習時間や目標を設定しましょう。予定外の出来事や状況の変化に対応できるように、柔軟性を持たせるのがポイントです。必要に応じてスケジュールの調整を行ってください。
4.学習方法を選択する
ご自身の勉強時間や各科目に適した学習方法を選択します。例えば、教科書の読み込み、問題集の解答、ネット上の動画や資料の活用などです。このセクションで説明する、「使用テキスト・過去問集の選び方」も参考にしてください。
5.効果的な休息を入れる
学習計画には、十分な休息も含めることが大切です。疲れたりモチベーションが下がったりした場合に、休息を取ることも計画に組み込みましょう。
筆記試験勉強のコツ2つ
第二種電気工事士の筆記試験勉強のコツを2つ紹介します。
- 配点の大きいところから勉強する
- 過去問を繰り返し解く
■ コツ1「配点の大きいところから勉強する」
「覚えれば正解できる問題」から始めると、合格ラインに早く近づきます。毎年、筆記試験の出題構成は、次のような傾向です。
▽第二種電気工事士の筆記試験問題
| 問題 | 主な種類 | 問題数 |
|---|---|---|
| (1)電気に関する基礎理論 | 計算 | 約5問 |
| (2)配電理論および配線設計 | 計算 | 約5~6問 |
| (3)電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 | 覚える | 約7問 |
| (4)電気工事の施工方法 | 覚える | 約5~6問 |
| (5)一般用電気工作物の検査方法 | 覚える | 約4問 |
| (6)配線図 | 覚える | 約20問 |
| (7)一般用電気工作物の保安に関する法令 | 覚える | 約3問 |
問題の始めに登場する「(1)電気に関する基礎理論」「(2)配電理論および配線設計」は、計算問題です。勉強する際には、攻略しやすく配点が高い「(3)」~「(7)」から始めると効率的でしょう。
■ コツ2「過去問を繰り返し解く」
電気工事士の筆記試験対策では過去問を解くことが重要です。過去問を解くことで、次のようなメリットがあります。
- 問題の番号と出題分野はほぼ同じなので、本番同様の流れを理解できる。
- 同じような問題が出題されるので、消去法も使っていけば、正解に近づける。
- 工具などの写真を使った問題は、同じ写真が使われることもある。
移動時間などでスマホを使って、電気工事士の過去問クイズを解くこともできます。コツコツと繰り返し過去問を解くことがポイントです。
使用テキスト・過去問集の選び方
適切なテキストや過去問集を選ぶ際のポイントは以下の5つです。
- 信頼性の高い出版社から出ている
- 試験範囲を網羅している
- 解説がわかりやすい
- 豊富な例題や問題集が含まれている
- 最新版である
1.信頼性の高い出版社から出ている
レビューや評判を調べ、信頼できる出版社の教材を選択しましょう。試験対策の教材を提供している有名な出版社や電気分野専門の出版社を選ぶと安心です。
2.試験範囲を網羅している
教材の目次やカバーなどから、試験範囲に沿った内容が含まれていることを確認しましょう。
3.解説がわかりやすい
教材の一部をサンプルで確認し、解説がわかりやすいかどうかをチェックしましょう。レビューや口コミも参考になります。
4.豊富な例題や問題集が含まれている
教材の中には、豊富な例題や問題集が含まれていることがあります。これにより、理解度を確認しながら学習できます。
5.最新版である
出版日が最新の版数を選ぶことで、試験内容や傾向に最も近い情報を得ることができます。ここ数年、第二種電気工事士の試験内容は大きく変わることはありませんが、出来るだけ最新のものを選ぶようにしましょう。
上記のポイントを考慮しながら、自分に最適なテキストや過去問集を選択しましょう。
参考ブログ
過去に第二種電気工事士の資格試験を受験した方のブログをご紹介します。
おすすめはこちら。
>>『青山OLが独学で受ける第二種電気工事士筆記試験』(全13話)
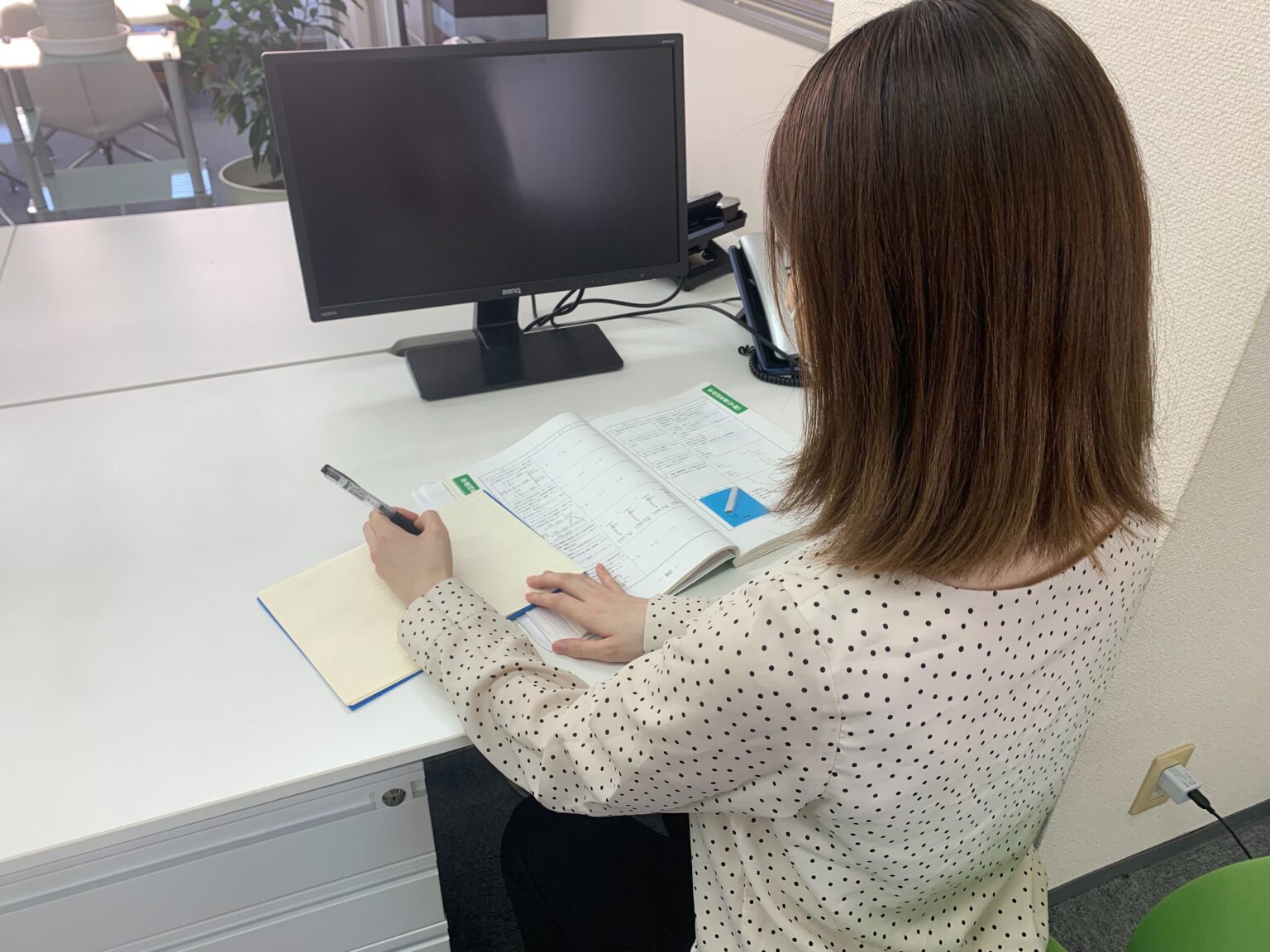
申し込み・教材選び〜試験当日までに行うプロセスが分かりやすく、写真からリアルな様子が伝わってきます。ぜひ参考にしてください。
日々の様子はX(旧ツイッター)でも公開されています。(ハッシュタグは #電工魂受験記録)
勉強サポートツール
第二種電気工事士の筆記試験勉強に役立つアプリやウェブサイトをご紹介します。対策したいポイントや学習スタイルに合わせて活用してみてください。
編集部おすすめの勉強アプリ(iPhone・Android対応)
工事士.com編集部が実際に使用してみて「これは良い!」と感じたアプリをご紹介します。
1.『全問解説付 第2種電気工事士 筆記 一問一答問題集』(Apple版)
出典:App Store
このアプリは一問一答の問題集で、230問の問題が用意されています。 他のアプリと比較すると問題数がちょっと少ないという印象を受けますが、1つ1つに解説がついているので、 単に回答を暗記するだけではなく、「なぜその回答になるのか」しっかりと学びたい方には良いアプリだと思います。
2.『俺の電工2種 - 第二種電気工事士の筆記試験アプリ』(Apple版)
出典:App Store
このアプリの特徴は、過去問題テストのほか、基礎理論や配線図などのカテゴリ別で勉強を行うことが出来ます。 自分の苦手な分野を徹底攻略したい方にはぴったりでしょう。アプリを使用した方からも好評! ただし解説がついていないため、初心者の方より、ある程度勉強している方向けにおすすめできるアプリです。
3.『第二種電気工事士試験 過去問チャレンジ』(Google Play版)
出典:google Play
このアプリの特徴は、3つの出題モードがあること。 時間のある時にじっくり問題を解きたい場合は「実践形式!50問」、通勤時間や休憩中などのスキマ時間を有効活用したい時は「気軽にチャレンジ!10問」、寝る前にサクッと勉強したい時は「おやすみ前のちょっと5問」。このように人それぞれで生活リズムに合わせた勉強を行えるのが大きな特徴です。
4.『第二種電気工事士 筆記試験対策(過去問ドリル)解説付』(Apple版/Google Play版)
出典:google Play
このアプリには20年分の過去問が収録されています。試験別、単元別、模試コースを含む3つの学習モードがあり、自分の苦手を克服するのに最適です。さらに、ノーマルからシャッフル、未実施、ミスまで、様々な出題モードがあるのが非常に便利。問題ごとに直接メモを取れるふせん機能もあります。弱点を重点的に克服したい方におすすめです。
登録不要の過去問サイト(無料)
登録不要で気軽に使える便利な勉強サイトとして、『工事士.comの過去問クイズ』もおすすめです。
ウェブサイトなのでPCやタブレット、スマートフォンなど、インターネットに接続できるあらゆるデバイスからアクセス可能です。
アプリの場合、ダウンロードが必要で使用できるデバイスが限られることがありますが、ウェブサイトならそのような制限がありません。特に、デバイスの容量に余裕がない方には、ウェブサイトの方が向いているでしょう。
過去15年分の試験問題をカバーしていますので、腕試しにもぜひご活用ください。

試験直前!1カ月前にとるべき対策は?
試験1カ月前は、合格に向けての最終調整を行うための重要な期間です。
第二種電気工事士の筆記試験直前対策には、以下の3つがおすすめです。
- 過去問を繰り返し解く
- 重要用語と法規を確実に暗記する
- 時間を計りながら模擬試験を行う
1.過去問を繰り返し解く
第二種電気工事士の試験では、過去の問題が繰り返し出題される傾向にあります。過去問を分析することで出題パターンや頻出分野を把握し、効率的に学習を進めることができます。 過去問を解き、試験の傾向や出題形式を把握し、不足している部分を補強することで、合格への自信を高めることができます。
2.重要用語と法規を確実に暗記する
電気工事士試験は、電気工事に関連する法規や安全管理についての知識を問われることが多いです。これらの領域は、事前に暗記しておくことで高得点を狙えます。
3.時間を計りながら模擬試験を行う
試験時間である40分を計り、時間配分の練習を行います。実際の試験に少しでも近い環境で問題を解くことで、本番での心理的プレッシャーに慣れることができます。
参考:筆記試験合格者の声
私が受験した際、過去5年間の問題集を繰り返し解き、その中で特に出題頻度の高かった電気回路や法規に関する問題に焦点を当てました。これにより、試験当日には見覚えのある問題が多数出題され、自信を持って解答することができました。
電気工事士の試験準備として、電気工事士法や電気事業法など、頻出の法規をフラッシュカードで暗記しました。試験には多くの法規に関する直接問題が含まれており、この暗記作業が大きな助けとなりました。
試験の2週間前からは、毎日少なくとも一回は模擬試験を解き、試験時間内で解答する訓練を行いました。これにより、実際の試験での時間配分に慌てることがなくなりました。
最後の手段!一夜漬けの方法
結論として、第二種電気工事士の筆記試験を一夜漬けで行うのはおすすめできません。一夜漬けがおすすめできない理由と、どうしても一夜漬けで行わなければならなくなった際の対策について解説します。
一夜漬けでの合格は難しい
第二種電気工事士の筆記試験は、電気に関する基礎理論、電気工事の施工方法、電気を扱う上での法律など、幅広い知識を要求されるため、一夜漬けでの合格は非常に困難です。
筆記試験は、基本的な理論から応用問題までを網羅し、法規や技術基準に関する詳細な知識が求められるため、短期間での詰め込みよりも、長期にわたる計画的な学習が重要とされています。
また、試験の理解と記憶を深めるためには、繰り返し学習と実践的な問題演習が効果的です。一夜漬けで合格を目指すよりも、適切な学習計画を立て、定期的に学習内容を見直し、過去問題を解いて試験に備える方がより現実的なアプローチと言えるでしょう。
それでも一夜漬けで望む場合
一夜漬けで試験に臨む際には、過去問集や重要ポイントの確認、睡眠の確保などが重要です。
まず前日の夜に十分な睡眠を確保します。睡眠不足は学習効率を下げるだけでなく、試験当日のパフォーマンスにも影響を与えます。
睡眠を取った後は、試験範囲の大まかな把握や重要ポイントの確認を行います。過去問集を解いたり、重要な公式や法則を暗記したりすることで、短時間で効果的な学習が可能です。
焦らずに計画的に学習を進め、試験当日に自信を持って臨みましょう。
筆記試験合格後のステップ
筆記試験合格後も気を抜くことはできません。事前に筆記試験合格後のステップについても把握し、免状取得まで確実に進めましょう。
筆記試験合格後に必要なステップは以下の通りです。
- 筆記試験の合格通知を受け取る
- 技能試験対策を始める
- 技能試験を受験する
- 免状取得の申請手続きを行う
1.筆記試験の合格通知を受け取る
筆記試験の合格通知を受け取りましょう。2024年度(令和6年度)上期の場合、試験結果通知書は、7月5日(金)に発送予定です。
また、通常、筆記試験の結果は受験日のおよそ2週間後に発表されます。試験センターホームページ(CBT方式の場合はマイページ)で確認してください。
2024年度(令和6年度)上期の筆記試験結果の発表期間は以下の通りです。
| 筆記方式 | CBT方式 |
|---|---|
| 2024年6月10日(月)~7月21日(日) | 受験日から2週間後の正午より公開 |
※詳しくは第二種電気工事士の受験案内の40ページ目をご確認ください。
2.技能試験対策を始める
技能試験の対策として、試験内容の確認、工具や材料の準備、実践練習などが必要です。筆記試験の合格が分かり次第すぐに始めましょう。
詳しくはこの記事の「技能試験対策の始め方」で解説します。
3.技能試験を受験する
技能試験を申し込み、受験しましょう。試験会場名・住所・交通手段は、送付される受験票及びマイページに記載されます。
筆記方式で受験して合格した場合は、試験結果通知書と一緒に技能試験の受験票が添付されています。試験当日に受験票を忘れずに持参してください。CBT方式の場合、受験票の発送はありません。試験当日に顔写真付きの公的証明書の提示が必要になるので覚えておきましょう。
4.免状取得の申請手続きを行う
技能試験に合格したら、免状の取得申請手続きを行いましょう。必要書類や手数料を提出します。免状が発行されたら、晴れて第二種電気工事士としての資格が正式に取得されます。
詳しくは「第二種電気工事士の免状交付」をご確認ください。
技能試験対策の始め方
第二種電気工事士の技能試験対策には主に以下3つのステップが必要です。
- 試験案内の確認
- 適切な工具や材料の準備
- 時間を計りながらの実践練習
上記のほか、YouTubeの解説動画も非常に役に立ちます。必要に応じて視聴するようにしましょう。
詳しくは「第二種電気工事士 技能試験対策」と「独学で第二種電気工事士にチャレンジ」をご覧ください。
第二種電気工事士 申し込み方法と試験日
2024年度(令和6年度)上期の第二種電気工事士試験の受験申し込み期間は、2024年3月18日(月)~4月12日(金)です。
これから第二種電気工事士試験を受験される方は「第二種電気工事士試験の申し込み方法」を参考に、早めに申し込みを済ませましょう。
■2024年度 試験スケジュール
| 日程 | 上期 | 下期 |
|---|---|---|
| 申込期間 | 2024年3月18日(月) ~2024年4月12日(金) |
2024年8月19日(月) ~2024年9月5日(木) |
| 筆記試験日 (筆記方式) |
2024年5月26日(日) | 2024年10月27日(日) |
| 筆記試験日 (CBT方式) |
2024年4月22日(月) ~2024年5月9日(木) |
2024年9月20日(金) ~2024年10月7日(月) |
| 技能試験日 | 2024年7月20日(土) または 2024年7月21日(日) |
2024年12月14日(土) または 2024年12月15日(日) |
よくある質問(Q&A)
「第二種電気工事士」に関するよくある質問をまとめました。
筆記試験の合格率はどのくらいですか?
- 合格率は年度や試験の難易度によって変動します。詳しい合格率はこの記事の「第二種電気工事士 合格率と勉強時間」を確認してください。一般的には、しっかり準備をすれば合格は十分に可能です。
筆記試験によく出る科目は?
- 電気理論、法規、電気機器、配線設計などが中心となります。これらの科目からの出題が多いため、特に重点を置いて勉強することがおすすめです。
詳しくはこの記事の「出題される問題の詳細」をご覧ください。
筆記試験のためのおすすめテキストや参考書は?
- 本人のレベルや学習スタイルに合ったテキスト選びが重要です。基礎からしっかり学びたい人には詳細な解説書が、短期間で効率的に学びたい人には要点をまとめた参考書が適しています。アプリやウェブサイト、YouTubeでの解説も参考になります。
この記事の「勉強サポートツール」も参考にしてください。
筆記試験の前日にすべきことは?
- 前日は過度な詰め込み勉強を避け、重要ポイントの軽い復習にとどめるのが良いでしょう。早めに就寝して十分な休息を取り、試験当日のコンディションを整えることが大切です。
まとめ|正しい勉強方法で一発合格を目指そう!
この記事では第二種電気工事の筆記試験における勉強方法ついて解説しました。
- 第二種電気工事士の筆記試験は難しくない
- 勉強方法のポイントは試験内容の理解・学習計画・過去問の反復練習
- アプリやサイトを使ってスキマ時間を活用する
- 筆記試験の1ヶ月前は詰め込みよりも復習に時間を使う
- 試験の申し込みや、筆記試験合格後のステップもお忘れなく
合格のためには、試験の流れを理解し、効率的な学習計画を立て、過去問を解くことが不可欠です。また、重要用語と法規の暗記、模擬試験も効果的です。
一夜漬けではなく、計画的な準備を行い、一発合格を目指しましょう。
第二種電気工事士の求人を探す
第二種電気工事士のおすすめ求人

株式会社マトイ防災
\連続・増収増益/早期昇進・昇給のチャンスも!将来も無くならない、消防設備の保守点検<資格経験不問>..

有限会社アドバンス
【監視カメラなどの設置・メンテナンス】二種電工以上&3年以上の経験必須/家族手当*退職金あり◎/正社..

株式会社日紅コンストラクション
昇給5万円の実績有◆経験の多さは武器になる。日本を股にかけよう!|太陽光発電の電気工事/資格経験不問..

有限会社レジェンズ
【資格経験不問/ゼネコン現場や商業施設の電気工事】朝・昼食現物支給◎残業月10h以下◎経験者歓迎!/..

大洋興業株式会社
★賞与年2回・過去5年間の平均支給実績は「計6ヶ月分」です!【二種電工以上・経験不問/施工管理】/正..
第二種電気工事士の求人一覧
その他の条件で電気工事士の求人を探す
エリアから電気工事士求人を探す
経験・スキルから電気工事士求人を探す
資格が活きる仕事が見つかる!
無料会員登録をする
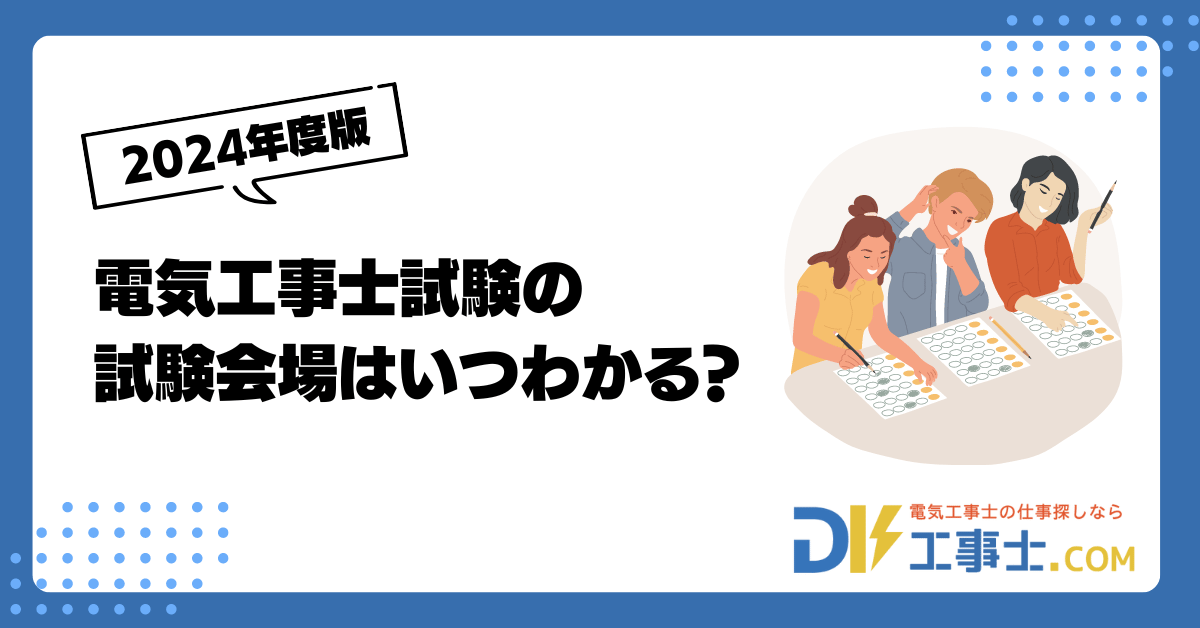
|
第一種・第二種電気工事士の試験会場はいつわかる?確認方法と過去の試験会場一覧
電気工事士
第二種電気工事士
第一種電気工事士
資格
試験
|
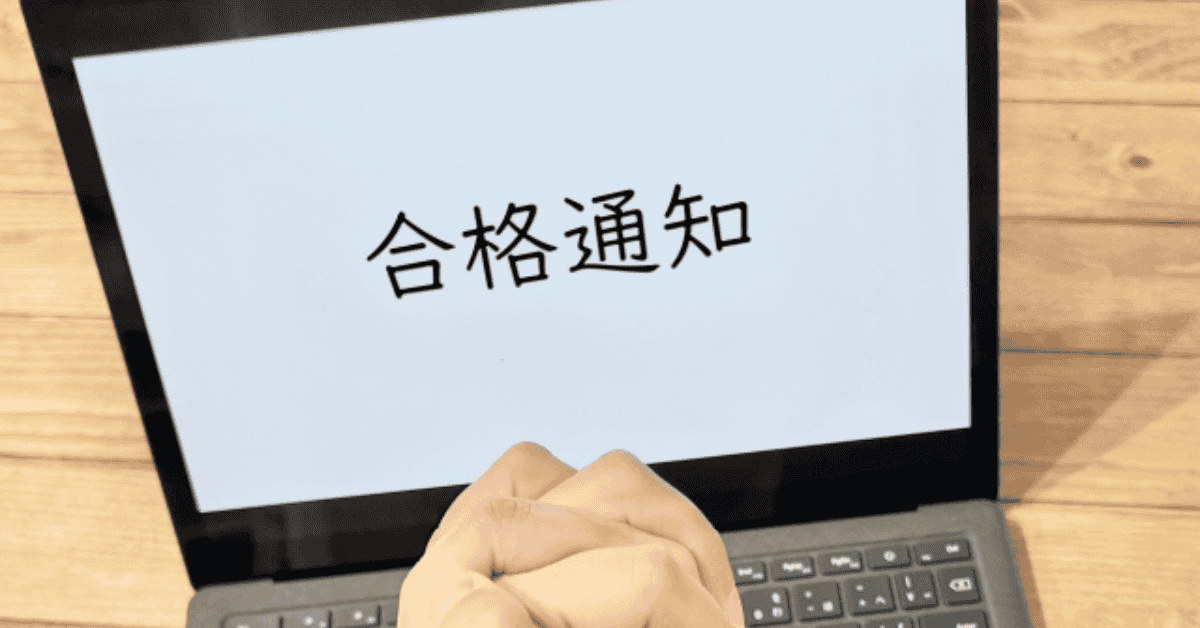
|
合格率でわかる!第二種電気工事士の難易度と必要な勉強時間
第二種電気工事士
資格
試験
対策
|
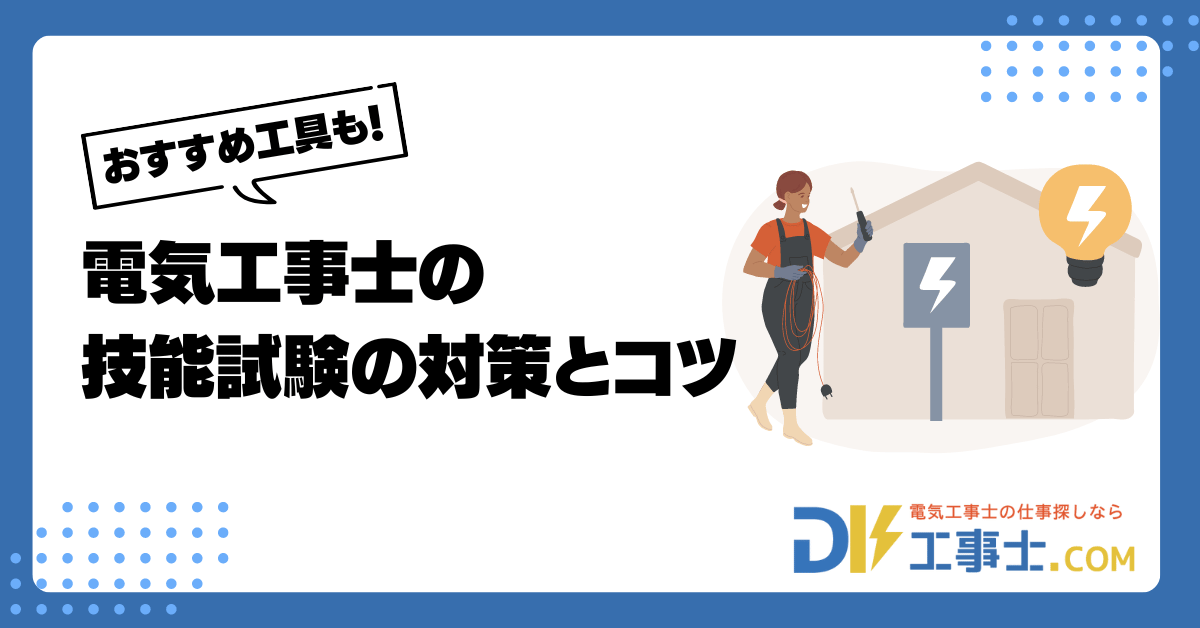
|
第二種電気工事士の技能試験(実技)対策の5つのコツと注意ポイント
第二種電気工事士
資格
試験
対策
|
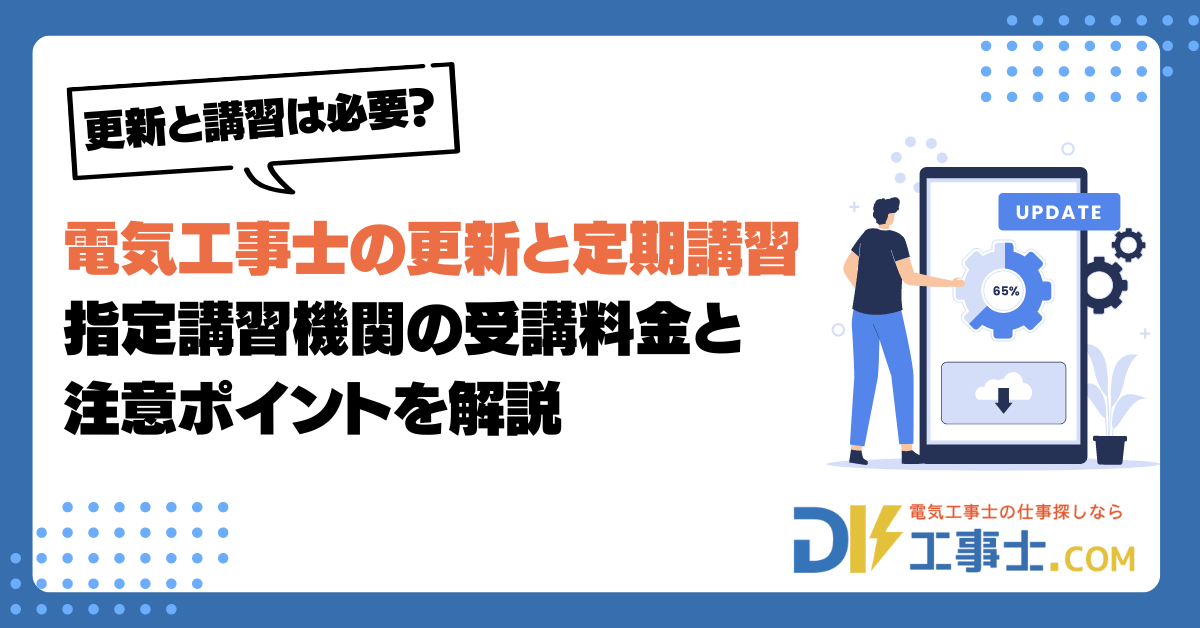
|
第一種・第二種電気工事士に更新と定期講習は必要?指定の講習機関と受講料金も解説
第二種電気工事士
第一種電気工事士
資格
|

|
2024年(令和6年)第二種電気工事士の申込方法と試験日|必須手続きと受験の流れを詳しく解説
第二種電気工事士
試験
|